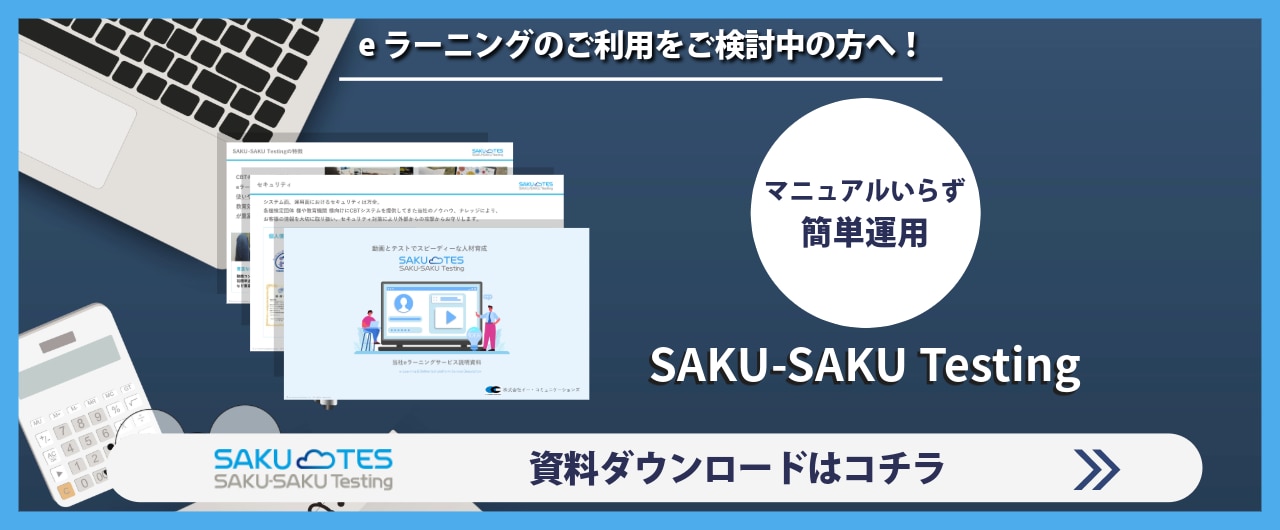ハイブリッド研修とは?メリット・デメリットから具体的な行い方まで解説

ハイブリッド研修とは、対面で行う集合研修とオンライン研修を組み合わせた研修手法のことです。この研修のやり方は多様化する働き方に対応し、教育機会の均等化と学習効果の向上を両立させる方法として注目されています。
本記事では、ハイブリッド研修の基本的な知識からメリット・デメリット、そして具体的な開催手順や成功のポイントまで、企業の研修担当者が知りたい情報を網羅的に解説します。
目次[非表示]
- 1.そもそもハイブリッド研修とは?2つの学習形式を組み合わせた手法
- 2.ハイブリッド研修で用いられる3つの主な形式
- 3.ハイブリッド研修を導入する4つのメリット
- 3.1.全国どこからでも参加可能になり受講率が向上する
- 3.2.一度に多くの従業員が研修を受けられる
- 3.3.オンラインと対面の利点を活かして学習効果を高める
- 3.4.受講者の状況に応じた柔軟なプログラム設計ができる
- 4.ハイブリッド研修で注意すべき3つのデメリット
- 5.ハイブリッド研修の開催準備から実施後までの7ステップ
- 5.1.①研修の目的と達成目標を明確にする
- 5.2.②研修全体のプログラムを設計する
- 5.3.③対面とオンラインの役割を具体的に決める
- 5.4.④必要な機材、ツール、会場を準備する
- 5.5.⑤参加者へ事前に詳細を案内する
- 5.6.⑥当日の進行管理とトラブル対応を行う
- 5.7.⑦研修後のフォローアップで効果を測定する
- 6.ハイブリッド研修の効果を最大化させる3つのポイント
- 7.まとめ
- 8.ハイブリッド研修をお考えの担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
そもそもハイブリッド研修とは?2つの学習形式を組み合わせた手法
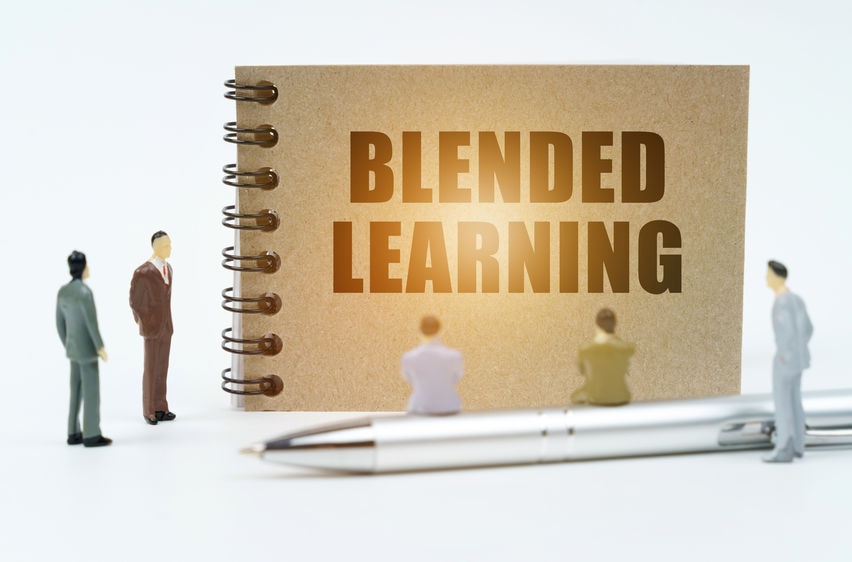
ハイブリッド研修とは、参加者が一堂に会する「対面研修(集合研修)」と、時間や場所に縛られない「オンライン研修」の2つの学習形式を組み合わせた研修手法です。
このハイブリッド方式は、両者の長所を活かし短所を補い合うことで、より高い学習効果を目指します。
例えば、知識のインプットはオンラインで効率的に行い、実践的なグループワークは対面で深く行うといった設計が可能です。
働き方の多様化に伴い、全従業員に質の高い教育機会を提供するためのハイブリッド型の研修が多くの企業で導入されています。
ハイブリッド研修で用いられる3つの主な形式

ハイブリッド研修の実施形式には、目的や内容に応じていくつかの種類が存在します。
それぞれの形式は、オンラインと対面の組み合わせ方や受講者の参加形態によって特徴が異なります。
代表的な型としては、事前学習と対面研修を組み合わせる形式や、受講者が場所を自由に選べる形式、複数の拠点をつないで行う形式などが挙げられます。
研修の目標を達成するために、どの実施方式が最も適しているかを見極めることが重要です。
ブレンド型:事前学習と集合研修で知識の定着を図る
ブレンド型は、eラーニングなどで事前に基礎知識をインプットし、その後の集合研修ではディスカッションやロールプレイングといったアウトプット中心の活動に取り組む方法です。
この手法は「反転学習」とも呼ばれ、知識のインプットとアウトプットのフェーズを明確に分けることで、学習内容の深い理解と定着を促します。
集合研修の時間をより実践的でインタラクティブな活動に充てられるため、受講者のスキル向上に直結しやすい点が特徴です。
研修全体の学習効果を高めるための有効な方法として広く採用されています。
▶関連記事:ブレンディッドラーニングとは?企業研修で成果を出す仕組みと導入・設計のポイントを徹底解説
ハイフレックス型:参加者が受講場所を自由に選択できる
ハイフレックス型は、同じ研修を対面の会場とオンラインで同時に開催し、参加者が自身の都合に合わせてどちらの形式で受講するかを自由に選択できる研修スタイルです。
この型は「Hybrid-Flexible」の略称であり、受講者の柔軟な参加を可能にします。
例えば、遠隔地に住んでいる従業員はオンラインで、都心部の従業員は対面で参加するといった選択ができます。
多様な働き方に対応できる一方で、運営側は対面とオンライン両方の参加者に配慮した進行や設備準備が求められるため、比較的難易度の高い形式といえます。
分散型:各拠点をつなぎグループワークを活性化させる
分散型は、全国の各支社や営業所などの拠点ごとに対面で参加者が集まり、それらの複数拠点をWeb会議システムでつないで実施する研修形式です。
各拠点では集合しているため、拠点内での一体感を醸成しやすく、グループワークもスムーズに行えます。
さらに、拠点間をオンラインでつなぐことで、他拠点の従業員とのディスカッションや情報交換も可能となり、組織全体のコミュニケーション活性化にも貢献します。
全社的なプロジェクトや複数部署が連携して行う研修に適した形式です。
▼参考記事
研修の種類や目的や階層別に合わせた選び方、実施方法を紹介します!
ハイブリッド研修を導入する4つのメリット

ハイブリッド研修の導入は、企業と従業員の双方に多くのメリットをもたらします。
場所の制約を超えて参加機会を拡大できるだけでなく、オンラインと対面の長所を組み合わせることで、従来の研修よりも高い学習効果が期待できます。
また、一度に多くの従業員を対象にできる効率性や、個々の状況に合わせた柔軟なプログラム設計が可能になる点も大きな利点です。
これらのメリットを理解し、自社の課題解決に活かすことが重要です。
全国どこからでも参加可能になり受講率が向上する
ハイブリッド研修はオンラインでの参加が可能なため、勤務地や居住地に関わらず、全国の従業員が研修に参加する機会を得られます。
これにより、従来は移動時間やコストが障壁となって参加が難しかった遠隔地の従業員も、気軽に参加できるようになります。
また、在宅勤務者や育児・介護中の従業員にとっても参加のハードルが下がります。
結果として、より多くの従業員が研修を受けられるようになり、企業全体の受講率向上が期待できます。
研修の開催頻度や対象者を広げる上でも有効です。
一度に多くの従業員が研修を受けられる
対面のみの研修では、会場の収容人数によって一度に参加できる人数に上限がありました。
しかし、ハイブリッド研修ではオンラインでの参加枠を設けることで、物理的な制約を超えてより多くの従業員を対象にすることが可能です。
特に、全社的に実施するコンプライアンス研修や新制度に関する説明会など、大規模な研修会においてその効果を発揮します。
会場のキャパシティを気にすることなく研修を計画できるため、運営の効率化にもつながります。
オンラインと対面の利点を活かして学習効果を高める
このように、学習内容や目的に応じて最適な形式を使い分けることで、一方的な知識伝達に留まらない、能動的で深い学びを促進します。
結果として、研修内容の理解度やスキルの定着率を高める効果が期待できます。ハイブリッド研修の大きなメリットは、オンラインと対面それぞれの長所を組み合わせられる点にあります。
例えば、知識のインプットは各自のペースで進められるオンラインの事前学習で行い、対面では実践的な演習や受講者同士の深い対話に時間を集中させるといった設計が可能です。
▼参考記事
社内研修をオンライン化するメリットは?効果の出る進め方も解説
受講者の状況に応じた柔軟なプログラム設計ができる
ハイブリッド研修は、従業員一人ひとりの状況に合わせた柔軟な学びの機会を提供できる方法です。
例えば、育児や介護といった家庭の事情で長時間の外出が難しい従業員や、多忙な業務の合間に学習したい従業員も、オンライン参加という選択肢があることで研修を受けやすくなります。
企業側は、従業員の多様なライフスタイルや働き方に対応した教育プログラムを設計でき、学習意欲の向上やキャリア形成支援につながります。
個々のニーズに応える教育方法を取り入れることで、エンゲージメントの向上も期待できます。
▼参考記事
階層別研修とは?目的・メリット・カリキュラム例までわかりやすく解説
ハイブリッド研修で注意すべき3つのデメリット
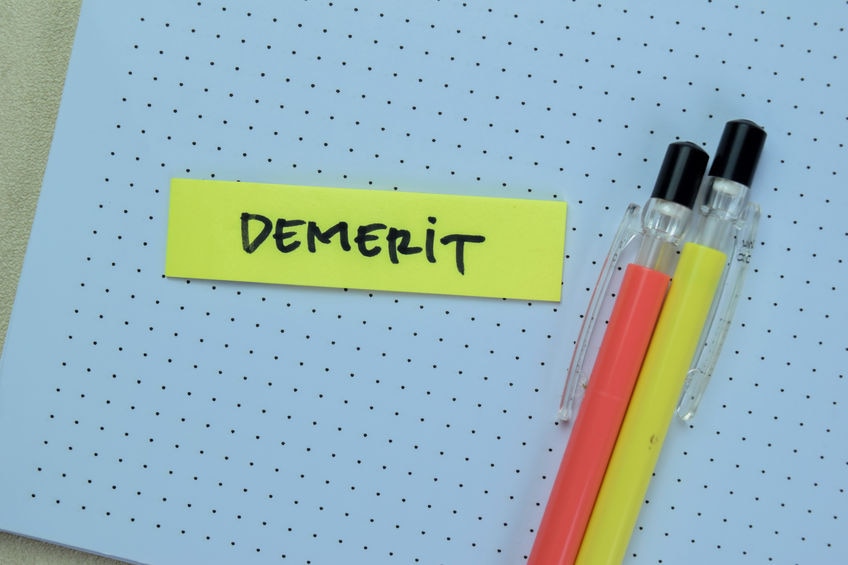
ハイブリッド研修は多くのメリットがある一方、導入にあたってはいくつかのデメリットも考慮する必要があります。
対面とオンライン両方の準備が必要となるため運営側の負担が増加するほか、配信用の機材導入などでコストが割高になる可能性も否めません。
また、参加形式の違いから、受講者間のコミュニケーションに差が生まれやすいという課題もあります。これらの注意点を事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。
対面とオンライン両方の準備で運営側の負担が増える
ハイブリッド研修の実施には、対面研修とオンライン研修の両方の準備と運営ノウハウが求められます。
具体的には、対面会場の設営や参加者対応に加え、オンライン配信のための機材セッティング、通信環境の確認、配信中のトラブル対応など、運営担当者の業務は多岐にわたります。
また、当日は両方の参加者に気を配りながら進行する必要があるため、司会者やファシリテーターのスキルも重要です。
これらの業務を円滑に進めるためには、役割分担を明確にし、入念なリハーサルを行うなど、通常よりも手厚い運営体制を整える必要があります。
会場費や機材導入でコストが割高になる可能性がある
ハイブリッド研修は、コスト面で割高になる可能性があります。
対面研修のための会場費や講師の交通費に加え、オンライン配信を円滑に行うための高品質なカメラ、マイク、スイッチャーといった専門的な機材の導入費用が必要になるためです。
また、安定した配信環境を確保するためのインターネット回線の増強や、配信サポートを外部に委託する場合はその費用も発生します。
交通費や宿泊費の削減効果と比較し、導入する機材のスペックや研修規模を慎重に検討して、費用対効果を見極めることが求められます。
参加者間のコミュニケーションや一体感に差が出やすい
ハイブリッド研修では、対面参加者とオンライン参加者の間でコミュニケーションの質や量に差が生まれやすい点が課題です。
会場の対面参加者同士の議論が盛り上がると、オンライン参加者が会話に入りづらくなったり、発言のタイミングを逃したりして疎外感を抱くことがあります。
また、休憩時間中の雑談など、非公式なコミュニケーションの機会は対面参加者に偏りがちです。
こうした環境の違いが、研修全体としての一体感を損なう要因にもなり得ます。
研修会を成功させるには、この差を埋めるための工夫が必要です。
ハイブリッド研修の開催準備から実施後までの7ステップ
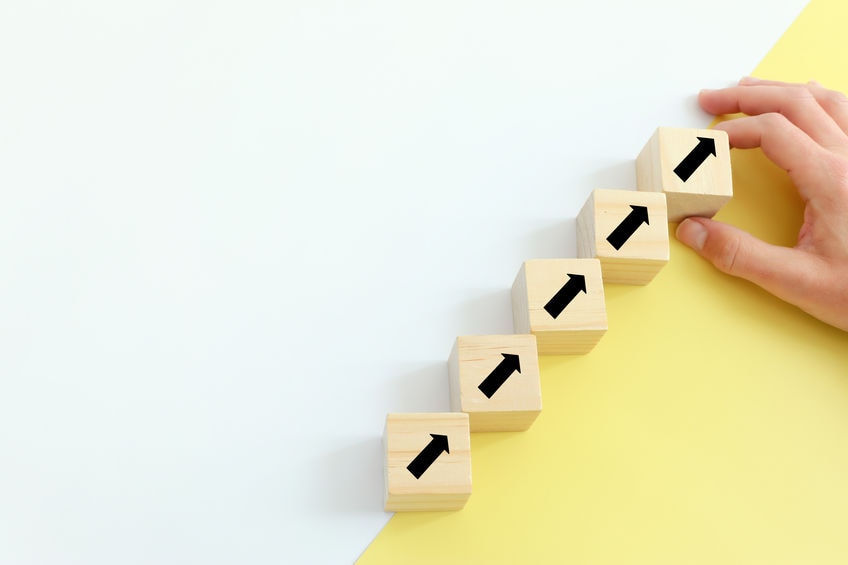
ハイブリッド研修を成功させるためには、計画的かつ体系的な準備が不可欠です。
目的設定から始まり、プログラム設計、機材準備、参加者への案内、当日の運営、そして研修後のフォローアップまで、一連のやり方をステップごとに丁寧に進める必要があります。
このプロセスを確実に実行することで、ハイブリッド開催のメリットを最大限に引き出し、質の高い研修を実現できます。
ここでは、具体的な7つのステップに分けてその流れを解説します。
①研修の目的と達成目標を明確にする
研修を成功させるための最初のステップは、その目的と達成目標を具体的に定義することです。
まず「なぜこの研修を行うのか」「研修後に受講者にどのような知識・スキルを身につけてほしいのか」を明確にします。
その上で「なぜハイブリッドという方法を選択するのか」を問い直し、ハイブリッド形式でなければならない理由を言語化します。
例えば「全国の拠点のナレッジを共有し、一体感を醸成する」といった目的があれば、それに沿ったプログラム設計が可能になります。目的が明確であれば、後の工程での判断基準がぶれません。
②研修全体のプログラムを設計する
目的と目標が定まったら、次はその達成に向けた研修全体のプログラムを設計します。
まず、研修のテーマに沿ったコンテンツを洗い出し、それらをどのような順序で、どのくらいの時間をかけて実施するかを計画します。
講義、グループワーク、個人ワーク、質疑応答などの各要素を効果的に組み合わせ、受講者が集中力を保ちながら学べるタイムスケジュールを作成します。
この段階で、対面とオンライン、それぞれの形式にどのコンテンツを割り当てるか、大まかな方針を立てておくと、その後の設計がスムーズに進むでしょう。
学習効果を最大化する時間配分と形式を検討します。
▼参考記事
研修プログラムの作り方とは?プログラムの例も目的別・階級別に紹介
③対面とオンラインの役割を具体的に決める
プログラムの全体像が見えたら、対面とオンラインの役割分担を具体的に決定します。
それぞれの形式の特性を最大限に活かすことが重要です。
例えば、知識や情報のインプットは、各自が繰り返し学習できるオンラインの事前動画コンテンツで済ませ、対面の時間ではより実践的なロールプレイングや深い議論に集中させるといった役割分担が考えられます。
逆に、オンラインではチャット機能を使って意見を広く集め、対面ではその意見を基に議論を深めるなど、相互に連携させる設計も有効です。
役割を明確にすることで、研修の質が向上します。
④必要な機材、ツール、会場を準備する
プログラムと役割分担が決まったら、それを実現するための物理的な準備を進めます。
対面会場の選定と予約はもちろんのこと、オンライン配信に不可欠な機材の準備が重要です。
具体的には、会場全体を映すカメラ、講師の声をクリアに拾うマイク、映像を切り替えるスイッチャーなどが必要です。
また、Web会議システムはZoomなどが一般的ですが、研修の目的に合わせてブレイクアウトルーム機能や投票機能が充実しているツールを選定します。
事前にすべての機材を接続し、正常に作動するかリハーサルを行うことが不可欠です。
⑤参加者へ事前に詳細を案内する
研修の成功は、参加者の準備状況にも大きく左右されるため、事前の詳細な案内が欠かせません。
研修日時、目的、プログラム内容はもちろん、対面参加者には会場の地図、オンライン参加者には参加用URLやツールの使用方法を明記します。
特にオンライン参加者に対しては、推奨される通信環境や、必要に応じて事前の接続テストの案内を行うと当日のトラブルを減らせます。
また、事前課題がある場合はその内容と提出方法も明確に伝えます。
丁寧な事前案内は、参加者の不安を解消し、学習意欲を高める効果があります。
⑥当日の進行管理とトラブル対応を行う
研修当日は、入念な準備の上で円滑な進行管理が求められます。
司会進行役、オンライン参加者のサポート役、機材管理役など、運営チーム内での役割分担を明確にしておきます。進行役は、対面参加者とオンライン参加者の両方にバランスよく話を振り、一体感を醸成するよう努めます。
同時に、音声が聞こえない、映像が映らないといった技術的なトラブルはつきものであるため、迅速に対応できる体制を整えておくことが重要です。
トラブル発生時の対応手順を事前にシミュレーションしておくことで、研修開催中の混乱を最小限に抑えます。
⑦研修後のフォローアップで効果を測定する
研修は実施して終わりではなく、その効果を測定し、次につなげるためのフォローアップが不可欠です。
研修直後にアンケートを実施し、内容の理解度や満足度、運営方法に関するフィードバックを収集します。これにより、今回の研修の成果と課題を客観的に把握できます。
また、数週間後や数か月後に、研修で学んだ内容が実務でどのように活かされているかをヒアリングしたり、レポートを提出させたりする方法も有効です。
これらの結果を分析し、次回の研修プログラムの改善に役立てるサイクルを確立します。
▼参考記事
社内研修の効果測定に有効な方法は?効果測定の課題とポイントを解説
【質問例あり】研修後アンケートで何を聞く?実施のポイントも紹介
下記に7つのステップをまとめました。
ステップ | 主なポイント |
1. 研修の目的と達成目標を明確にする | ・目的、目標を具体化 |
2. 研修全体のプログラムを設計する | ・コンテンツを整理 |
3. 対面とオンラインの役割を具体的に決める | ・オンライン=知識インプット |
4. 必要な機材・ツール・会場を準備する | ・会場・機材(カメラ・マイク等)の準備 |
5. 参加者へ事前に詳細を案内する | ・日時・目的・内容の明示 |
6. 当日の進行管理とトラブル対応を行う | ・司会・サポート |
7. 研修後のフォローアップで効果を測定する | ・アンケート、ヒアリング実施 |
ハイブリッド研修の効果を最大化させる3つのポイント
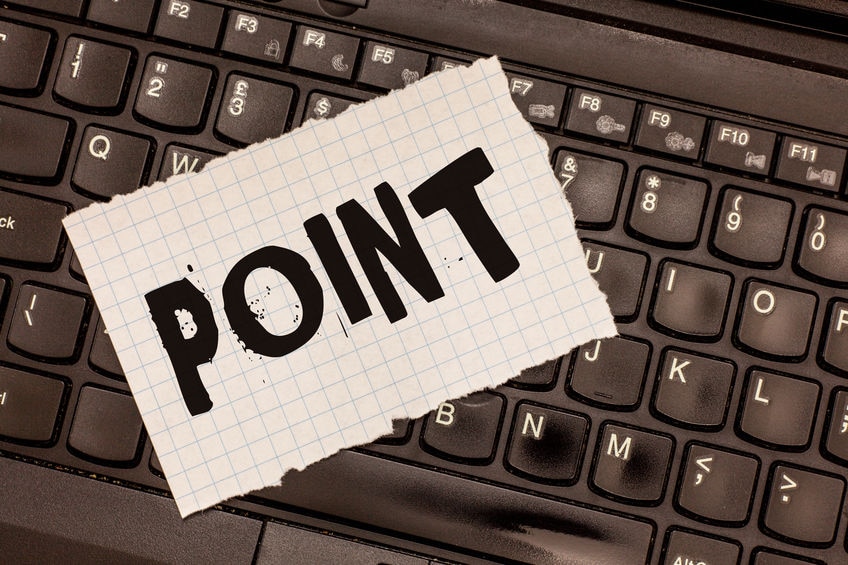
ハイブリッド研修を単なる形式の組み合わせで終わらせず、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。
特に、オンライン参加者が孤立しないような配慮や、技術的なトラブルへの備えは不可欠です。
また、参加者全員が受け身にならず、主体的に関われるような双方向のコミュニケーション設計が、研修会全体の満足度と学習効果を大きく左右します。
これらの点を意識して計画・運営することが成功への道筋となります。
オンライン参加者が疎外感を感じないような配慮をする
ハイブリッド研修で最も注意すべき点の一つが、オンライン参加者の疎外感です。
これを防ぐためには、意識的な配慮と仕組みづくりが求められます。
例えば、ファシリテーターはオンライン参加者にも名指しで意見を求めたり、チャットでの質問やコメントを積極的に拾い上げて紹介したりすることが有効です。
また、グループワークを行う際は、オンライン参加者のみのグループだけでなく、対面とオンラインの混合グループを作るなど、交流を促す工夫も考えられます。
研修全体で、すべての参加者が平等な当事者であるという雰囲気を作ることが重要です。
起こりうる機材や通信のトラブル対策を講じておく
オンライン配信を伴うハイブリッド研修では、機材や通信のトラブルが起こる可能性を常に想定しておく必要があります。
音声が途切れる、映像が固まるといった事態は、研修の流れを止め、参加者の集中力を削いでしまいます。
こうしたリスクを最小限に抑えるため、本番前に必ずリハーサルを行い、すべての機材の動作確認と通信環境のテストを徹底します。
また、マイクやカメラ、LANケーブルなどの予備機材を準備しておくことや、トラブル発生時の対応手順を運営スタッフ間で共有しておくことも有効な対策です。
参加者全員が主体的に関われる双方向のコミュニケーションを促す
研修効果を高めるには、参加者が受け身で講義を聞くだけでなく、主体的に関わることが重要です。
ハイブリッド研修では、対面・オンラインを問わず、全員が参加できる双方向のコミュニケーションを設計することが求められます。
具体的には、Web会議ツールの投票機能やアンケート機能を使ってリアルタイムで意見を収集したり、オンラインのホワイトボードツールを活用してブレインストーミングを行ったりする方法があります。
講師からの一方的な情報提供だけでなく、参加者同士が意見を交わし、学び合う場を意図的に作り出すことが学習の深化につながります。
まとめ

ハイブリッド研修は、対面研修とオンライン研修の利点を融合させた効果的な教育手法です。
このハイブリッド方式を採用することで、企業は多様な働き方に対応しながら、全従業員に対して均等かつ質の高い学習機会を提供できます。
一方で、その導入と運営には、綿密な計画と準備が不可欠です。
運営側の負担増加やコスト、参加者間の一体感の醸成といった課題を克服するための工夫が求められます。
本記事で解説したメリット・デメリットや具体的な手順、成功のポイントを踏まえ、自社の目的や状況に最も適した形でハイブリッド研修を設計・実施することが重要です。
ハイブリッド研修をお考えの担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
記事のように、研修の「事前学習はオンライン、実践は対面で」という ハイブリッド型も増えています。ハイブリッド型は、事前にオンラインで基本知識を習得 →対面研修でグループワークやロールプレイという形式をとることで時間もコストも抑えつつ、実践と交流の場も確保できるというメリットがあります。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、自社の動画を搭載したオリジナル研修が簡単に実施できます。
ぜひ動画研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。
また、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新人社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。