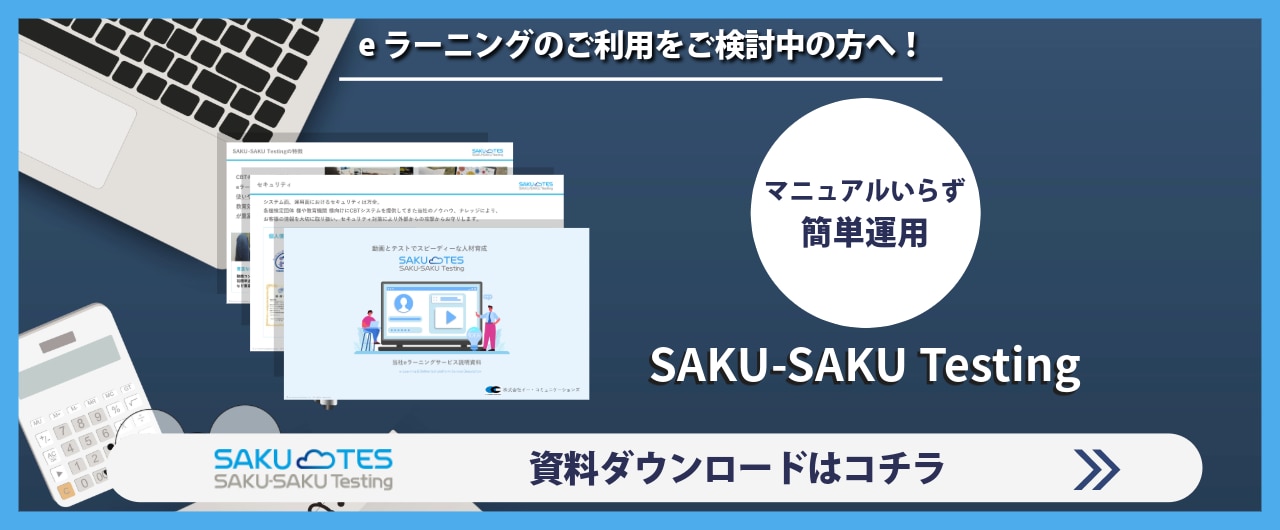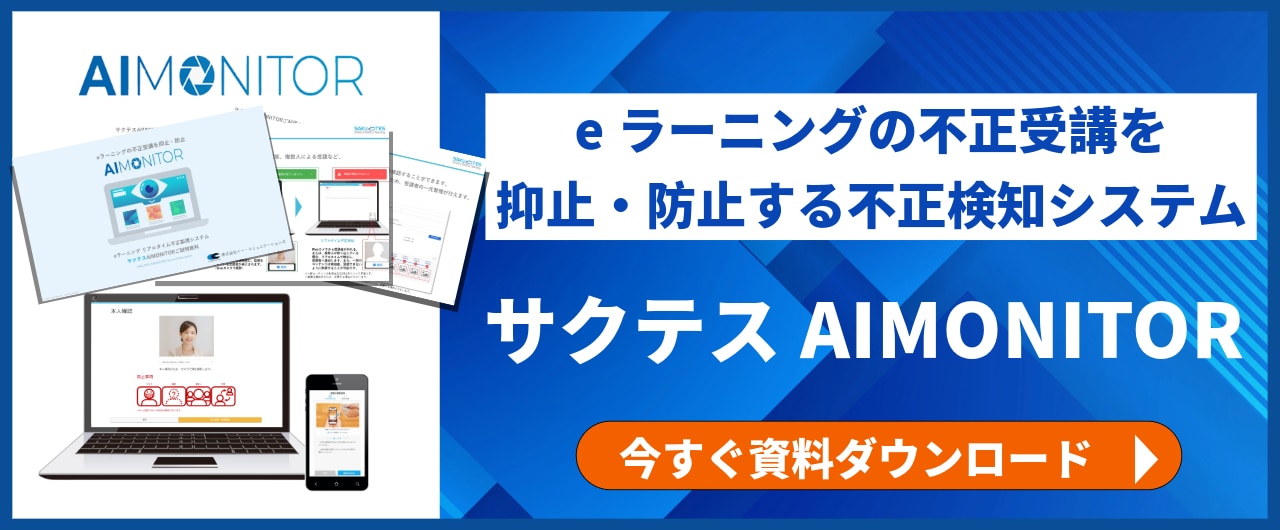階層別研修とは?目的・メリット・カリキュラム例までわかりやすく解説

社員育成のために社内研修は欠かせませんが、どうしても研修対象者が偏ってしまいお困りの担当者もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここでは階層別研修の目的やメリット、カリキュラム例について、社内の研修企画をしている人事・総務担当者向けに解説していきます。
目次[非表示]
- 1.階層別研修とは
- 2.階層別研修を行う目的
- 2.1.企業が望む役割の理解
- 2.2.知識や技術の向上と組織全体の底上げ
- 3.階層別研修のメリット
- 4.階層別研修のデメリットと課題
- 5.階層別研修の企画・実施ステップ
- 5.1.研修企画のステップ
- 5.2.階層別研修体系図の概要と作成のポイント
- 5.2.1.体系図の主な構成要素
- 5.2.2. 作成の流れ
- 5.3.階層別研修の適切な実施タイミング
- 5.4.実施方法の選択(内製研修と外部委託)
- 6.階層別研修の効果を高めるための留意点
- 6.1.定期的に研修内容をアップデートする
- 6.2.積極的にアウトプットを行う
- 6.3.求める役割や人物像を明確化する
- 6.4.記憶量定着のための復習の機会を設ける
- 7.階層別のカリキュラム例
- 7.1.新入社員研修のカリキュラム例
- 7.2.若手社員研修のカリキュラム例
- 7.3.中堅社員研修のカリキュラム例
- 7.4.管理職研修のカリキュラム例
- 7.5.役員研修のカリキュラム例
- 8.eラーニングを活用した階層別研修なら「サクテス学びホーダイ」「SAKU-SAKU Testing」
階層別研修とは

階層別研修とは、社員を勤続年数や役職、等級、習得スキルなどの階層に分けて実施する研修です。
一般的に階層は「新入社員」「若手社員」「中堅社員」「管理職」といった役職や立場を指し、「役員」まで分類されることもあります。この研修の目的は、それぞれの階層で求められる役割に応じた知識やスキルを習得することにあります。階層が上がるにつれて求められる役割が変化するため、階層ごとに異なるテーマやプログラムが設定されます。
階層別研修の大きな特徴は、特定の優秀な人材の「引き上げ」を目的とする選抜研修とは異なり、組織全体の能力を底上げすることにあります。
対象は階層に属する社員全員で、企業主導で必須参加となるケースが多いのもポイントです。体系的に設計されたプログラムは、研修の重複や無駄を省き、効率的に社員の成長を促します。
また、階層が上がると求められる知識やスキルが格段に増え、複雑化するため、OJTや個人の努力だけでは対応に限界があります。特に中堅社員の育成は企業成長のカギとなる一方で、研修機会が不足しがちです。
こうした背景からも、社員が社内での役職や立場が変わる節目で、その役割に特化した研修を行うことが必要になります。
目的 | 対象者 | |
階層別研修 | 底上げ | その階層になった社員全員 |
選抜研修 | 引き上げ | 企業に選ばれた優秀な社員 |
階層別研修を行う目的

階層別研修を行う目的には「企業が望む役割の理解」と「社員の知識や技術の向上」の2つがあります。それぞれ詳しく解説していきます。
企業が望む役割の理解
階層別研修の大きな目的のひとつは、社員が自分の階層で果たすべき役割を正しく理解することです。
新入社員には業務の基礎、管理職にはマネジメントや経営的視点といったように、企業が社員に期待する役割は階層によって異なります。
研修を通じて「今の階層で求められるスキル」や「どのような役割を担うべきか」が明確になれば、社員は自身のキャリア目標を描きやすくなります。逆に役割の理解が不十分だと、独断的な行動や組織の方向性の乱れにつながるおそれがあります。
階層別研修の実施により、こうしたリスクを防ぎ、全社員が同じベクトルで成果を発揮できるようになります。
知識や技術の向上と組織全体の底上げ
もう一つの目的は、階層が変わった直後の社員が、短期間で必要な知識やスキルを習得し、スムーズにその役割を果たせるようにすることです。
階層が上がると、業務を遂行するために必要な知識やスキルは複雑で多岐にわたりますが、OJTや自己啓発だけではスキルアップに限界があります。研修は、この不足している知識やスキルのレベルアップを図り、より早くその階層で活躍できるように導く役割を果たします。
このように階層別研修は「底上げ教育」としての役割をもち、同じ階層の全社員のスキルを一定水準まで引き上げる効果があります。
階層別研修のメリット

階層ごとに合ったスキルを効率的に身に付けられる
階層別研修のメリットの一つは、それぞれの役割やタイミングに応じたスキルや知識を効率的に習得できる点です。
研修内容が階層に特化しているため、受講者は必要な情報に集中でき、スムーズなスキルアップにつながりやすくなります。
また、同じ階層の社員が共通して学ぶことで、スキルレベルを一定水準に揃えられる点も企業にとって有益です。たとえば、若手社員が研修を通じてビジネス文書や業務効率化のスキルを習得すれば、誰に業務を任せても一定のクオリティが見込めるようになります。
さらに、研修の場では普段の業務で得にくい専門知識や問題解決の思考法を体系的に学ぶ機会があり、他の受講者との議論を通じて理解を深めることも可能です。
社員のモチベーションや自主性の向上につながる
階層別研修は、社員のモチベーションアップに大きくつながります。
研修を通じて「自分の階層にどのような役割が求められているか」を理解できると、業務や自己研鑽に取り組む目的意識が明確になり、主体的な行動につながりやすくなります。役割が整理されることで「今、何を学ぶべきか」が分かり、挑戦意欲が高まる効果も期待されます。
さらに、同期や役職が近い社員と交流する場にもなるため、互いに刺激し合いながら学べる点もモチベーション向上につながります。基礎的なスキルや知識を得ることで業務が円滑になれば、働きやすさが増し、そのこと自体が意欲向上の好循環を生み出します。
離職率低下への効果が期待できる
特に新人や若手社員にとって、階層別研修は同期と集まれる数少ない機会です。この場で日常の悩みを共有し、解決のヒントを得られることは心理的な支えになりやすいでしょう。
同期同士のつながりが強まることで帰属意識が育ち、結果として離職率の低下や定着率の向上につながる可能性があります。社員の定着は企業にとって採用・教育コストの削減にも直結するため、若年層向けの階層別研修は組織づくりの観点からも大切な役割を担います。
時代や環境に応じたスキルを習得できる
変化の激しい現代では、過去に得たスキルが現在のニーズに合わなくなることも少なくありません。企業が競争力を保つには、社員が継続的に新しい知識を学び、環境の変化に対応できるようにすることが重要です。
階層別研修は、AIやDXといった最新テーマを取り入れる場としても活用できます。プログラムを定期的に見直すことで、業界動向を反映した学びを提供でき、組織全体の対応力維持にもつながります。
さらに、研修は新しいスキルを学ぶだけでなく、自分の強みや課題を振り返り、キャリアビジョンを整理する機会としても活かせます。
階層別研修のデメリットと課題
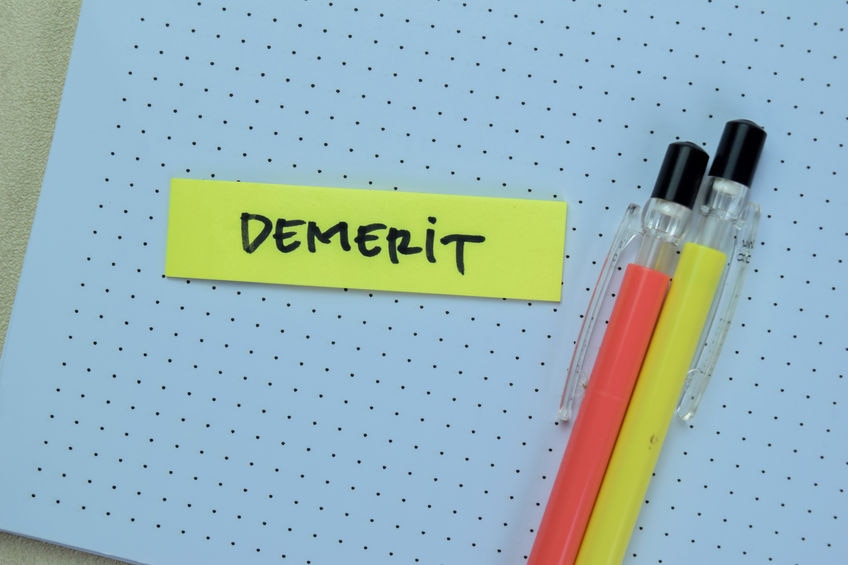
階層別研修のデメリット
階層別研修を導入する際には、いくつかの運営上のデメリットも考慮が必要です。
まず、対象が階層に属する全社員となるため、義務感から受け身になりやすく、「やらされ感」が生じる可能性があります。受講者自身が研修の意義やメリットを理解できていないと、前向きな参加が難しくなる場合があります。
また、対象人数が多いため、日程や会場の調整が難しい点も課題です。特に管理職以上は業務が流動的であるため、全員を集めることは人事担当者にとって大きな負担となり得ます。ただし、オンライン実施や録画受講などの仕組みを取り入れることで、この負担を軽減できる可能性があります。
さらに、外部業者に委託する場合はコストがかかるほか、パッケージ化されたプログラムでは自社の文化や課題に十分対応できず、効果が限定的になるおそれもあります。
形骸化しやすい・効果が見えにくいといった課題
階層別研修がもつ大きな課題の一つは、研修自体が形骸化しやすいことです。
目的が曖昧なまま「昇格したから受ける」「時間を過ごすだけ」といった形式的なものになると、実質的な効果を得にくくなります。こうした形骸化を防ぐには、研修の目的を事前に周知し、受講者の目的意識を高める工夫が重要です。
また、「学んだ内容が業務に活かされているか分からない」といった効果の見えにくさも課題です。研修の目的は実施そのものではなく、受講後の行動変容にあります。そのため、アンケートやレポート提出に加え、直属の上長や同僚からのフィードバックを取り入れることで、受講者の行動や成長の変化を確認する方法が有効と考えられます。
こうした検証を通じて、研修で育成すべきポイントが適切かどうかを見極めることができます。
階層別研修の企画・実施ステップ
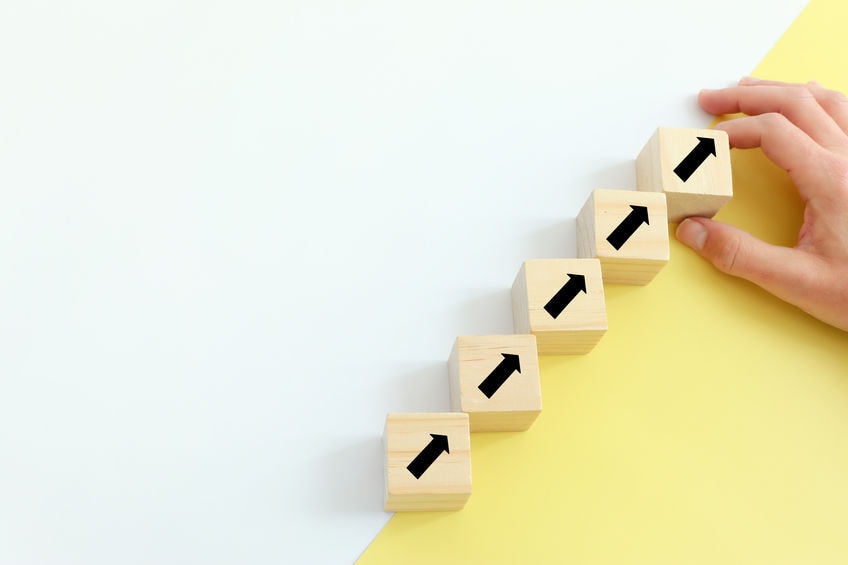
研修企画のステップ
効果的な階層別研修を行うには、自社の経営戦略を踏まえた体系的な企画が欠かせません。
- 自社の事業環境を捉える:人材育成は経営戦略と密接に結びつくため、外部環境や組織戦略・組織構造を踏まえ、自社の経営課題を明確化します。
- あるべき姿を設定する:階層ごとに期待する役割(ロールモデル)を定義し、それを果たすための行動や必要なスキル・マインドを整理します。
- 現状とのギャップを把握する:ヒアリングやアセスメントを通じて、現状とあるべき姿の差を特定し、研修で重点的に取り組むべき課題を明らかにします。
- 研修テーマを決める:解消すべきギャップに基づき、研修のゴールを設定し、テーマに落とし込みます。
階層別研修体系図の概要と作成のポイント
階層別研修を効果的に企画するには、「どの階層に、どのような知識やスキルを習得させるか」を一目で把握できる 研修体系図 を作成しておくことが有効です。
体系図の主な構成要素
- 階層ごとの役割定義:新入社員、若手、中堅、管理職など、各階層で期待される役割を明確にする
- 必要なスキル・知識の整理:役割を果たすために必要なスキルやマインドを具体化する
- 研修内容のマッピング:それぞれのスキルを習得するために、どの研修を実施するのかを配置する
作成の流れ
- 経営戦略に基づいて人材育成方針を整理する
- 階層ごとに「あるべき人物像」「期待される役割」を定義する
- 現状とのギャップを踏まえて、研修テーマを設定する
- 階層ごとの研修内容を体系図として一覧化し、全体像を見える化する
体系図は一度作って終わりではなく、経営環境や社員の状況に応じて定期的に見直すことが重要です。研修が形骸化するのを防ぎ、常に「今の組織に必要な研修体系」を維持することができます。
階層別研修の適切な実施タイミング
実施時期に明確なルールはなく、各社の階層の分け方や状況に応じて柔軟に設定されます分類方法としては、
- 役職(若手・中堅・管理職など)
- 年次(3年目・5年目など)
- スキル(営業・経理など)
の3つが一般的です。役職で分ける場合は昇格時、年次で分ける場合は年度切り替えのタイミングで行われることが多いです。
特に、新しい役職や役割に就いた直後はモチベーションが高まりやすく、研修を通じて役割理解やスキル定着を促す効果が期待できます。
ただし、他の研修施策と重なると負担が増えるため、全体のスケジュールを見ながら実施時期を調整することが望ましいです。。
実施方法の選択(内製研修と外部委託)
階層別研修は大きく分けて「内製」と「外部委託」の2つの方法があります。
- 内製研修:社内リソースで企画・運営する方法。自社の文化や理念を反映しやすく、コストを抑えられる点が利点です。特に、自社のルールや理念を浸透させたい場合に向いています。一方、準備負担が大きく、専門的なノウハウが不足している分野では成果が出にくい点が課題です。
- 外部委託:専門機関に依頼する方法。高度な専門知識やスキルを学べるほか、設計から運営まで任せられるため社内負担を軽減できます。ただし、コストやスケジュール調整の難しさがデメリットとなります。
両者のメリットを活かすために「理念やルールは内製」「専門知識は外部委託」といったハイブリッド型で進める企業も多く見られます。
外部委託を選ぶ場合は、自社の課題を理解しカスタマイズ対応してくれる企業を選定することが重要です。
階層別研修の効果を高めるための留意点

定期的に研修内容をアップデートする
企業を取り巻く環境が変化する中で、階層ごとに求められる役割や能力も移り変わります。そのため、研修内容は一度設計して終わりではなく、定期的な見直しが欠かせません。
同じ内容を繰り返すと準備は簡単になりますが、形骸化の恐れがあります。
アンケートや意見を取り入れて改善を重ねることで、受講者にとって有意義な内容に保てます。経営戦略や事業方針に合わせて「変わらず伝えたいこと(例:理念・マインド)」と「変化させるべきこと(例:DXや最新知識)」を整理し、常に時代に即した更新を行うことが重要です。
積極的にアウトプットを行う
研修の効果を高めるには、学んだ知識を実際に使う「アウトプット」が重要です。
ケーススタディや発表、ロールプレイングといった形式を取り入れることで、理解が深まり定着につながります。
アウトプットの方法には「書く」「話す」「行動する」があり、研修後の行動目標シートや実施報告書もその一環です。繰り返し実践することでスキルが習慣化し、仕事の質や自信の向上にも結びつきます。
求める役割や人物像を明確化する
研修を効果的にするには、階層ごとに期待する役割や人物像を明確にすることが大切です。求められる人材像と必要なスキルを定義することで、研修の方向性が定まり、社員の理解や納得感も高まります。
また、受講者にとってのメリットを丁寧に説明し「今の自分に必要な研修だ」と感じてもらうことが、積極的な参加を促す要因となります。役割が曖昧なままではモチベーション低下につながるため、この明確化は育成課題の特定においても欠かせません。
記憶量定着のための復習の機会を設ける
研修効果を長期的に持続させるためには、学んだ知識が定着するように、復習の機会を設けることが不可欠です。人間の記憶は時間が経過すると忘却するため、研修後すぐに業務で実践したり、復習の機会を設けたりすることが効果的です。
具体的には、研修後に1on1やミーティングで学んだことを他者に説明したり、簡易的なテストを実施したりする方法があります。eラーニングシステムを活用したテストエデュケーションは、知識の習得度や定着度を測る上で効果的な方法です。
復習を通じて知識の習得度を確認し、業務で使う場面を設けることが効果的です。
階層別のカリキュラム例

新入社員研修のカリキュラム例
新入社員研修の主な目的は、学生から社会人への意識転換と、基本的なビジネスマナーの習得です。入社直後に「受ける側」から「提供する側」への意識を切り替える機会となります。
近年では、情報管理の重要性の高まりから、SNS利用の注意点などネットリテラシーに関する研修を行っている企業も増えています。
【主なカリキュラム例】
- ビジネスマナーの習得(敬語、名刺交換、報連相など)
- 会社の理念やビジョンの理解、企業のルール
- コンプライアンス・ビジネスモラル
- 基礎的なビジネススキル研修(ExcelやWordなどのOAスキル)
若手社員研修のカリキュラム例
主に入社2年目から5年目程度の若手社員が対象であり、目的は、一人で業務をこなせる力を身につけさせ、さらなる土台の強化につなげることです。戦力として必要なビジネススキルや指導力の習得が求められ、業務遂行や業務改善に必要な知識・スキルをテーマとする傾向があります。
【主なカリキュラム例】
- ロジカルシンキング(論理的思考力)や問題解決と論理的思考
- コミュニケーション力強化、プレゼンテーション
- 指導力習得(後輩指導、OJT指導者としての部下育成など)
- キャリアデザイン、モチベーションアップ研修
- セルフケア・ストレスマネジメント
中堅社員研修のカリキュラム例
主に5年目以上で管理職ではない社員(入社10年目までが目安)が対象です。この階層はチームリーダーやサブリーダーを務めることが多く、自分だけでなくチーム全体の成果拡大に貢献する意識が求められます。
【主なカリキュラム例】
- リーダーシップ、フォロワーシップ、オーナーシップ
- 課題発見・問題解決
- 高度なコミュニケーションスキル(ネゴシエーション、ファシリテーションなど)
- セルフマネジメント(アンガーマネジメント、アサーティブ)
- コンプライアンス(機密情報管理)
管理職研修のカリキュラム例
新任管理職や昇格予定者を対象とし、管理職としての役割理解や心構えを中心に学びます。組織運営やリスクマネジメントのノウハウが要求され、内容は経験値に応じて変化します。
【主なカリキュラム例】
- 管理職の役割と組織マネジメント
- リスクマネジメント(ハラスメント、メンタルヘルスなど)
- 部下育成とチームビルディング、コーチング
- 経営知識(財務、マーケティングなど)
- 評価者・内部統制
役員研修のカリキュラム例
企業の舵取りを担う役員が対象で、事業戦略・方針の策定、グローバル対応といった高度な役割が期待されます。法律、経営分析、財務戦略など、極めて高度な専門的知識を必要とする内容が多く、多忙なため、計画的かつ長期的に研修計画を立てることが重要です。
【主なカリキュラム例】
- 経営戦略立案
- リスクマネジメント
- 競合・同業他社の分析
- 持続可能なビジネスモデルの策定
- マネジメント能力、経営の知識、海外の文化や法律の違いを知る研修
eラーニングを活用した階層別研修なら「サクテス学びホーダイ」「SAKU-SAKU Testing」
階層別研修にeラーニングを導入することは、研修効果を高め、運用を効率化する上で非常に有効な手段です。
eラーニングの大きな効果の一つは、スケジュール調整の難しさといったデメリットを解消できる点です。社員が自身のスケジュールに合わせて好きな時間に受講できるため、業務との両立が容易になり、受講者の負担軽減につながります。
また、階層別研修は立場によって行う内容が異なるため、eラーニングを活用することで、役職や所属ごとに必要なコンテンツを柔軟に提供できます。
eラーニングの導入をお考えであれば、ぜひ「サクテス学びホーダイ」をご検討ください。簡単に運用ができるeラーニングシステム「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
内定者教育向けのコンテンツから、入社3年目までのビジネススキルをアップさせるコンテンツと、さらに管理職候補から管理職向けのコンテンツなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っており、階層別研修に最適です。
「研修効果をさらに高めたい」「運用負担を軽減したい」とお考えでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。