
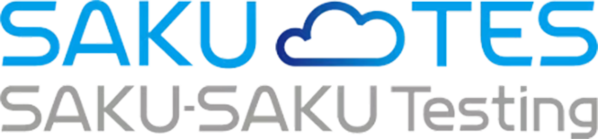

SAKU-SAKU Testing導入事例
求めていた各種機能が、サクテスにはデフォルトで装備されていた

病院の経営支援をはじめ、医療業界のDXを推進するメディカル・データ・ビジョン株式会社では、各種研修におけるeラーニングプラットフォームとして「SAKU-SAKU Testing」を活用しています。ここでは、導入した経緯や今後の活用に関して、リスク・コンプライアンス部 部門長 渡邉幸広氏、築井未佳氏にお話を伺いました。
導入の目的
多様化するeラーニングの充実と、センシティブな研修に対する専門家の知見をいれた研修にしたい。
導入前の課題
多様化する問題に対し、理解してほしい研修科目を増やしたり、センシティブな内容に関してどのように設問を作成・改良したりしたら良いか難しくなった。
導入の成果
コンテンツの質の向上はもちろん、受講者への事前リマインドによる受講率向上や、受講状況・結果を容易に把握できるようになったことで、次の施策への展開が容易になった。













