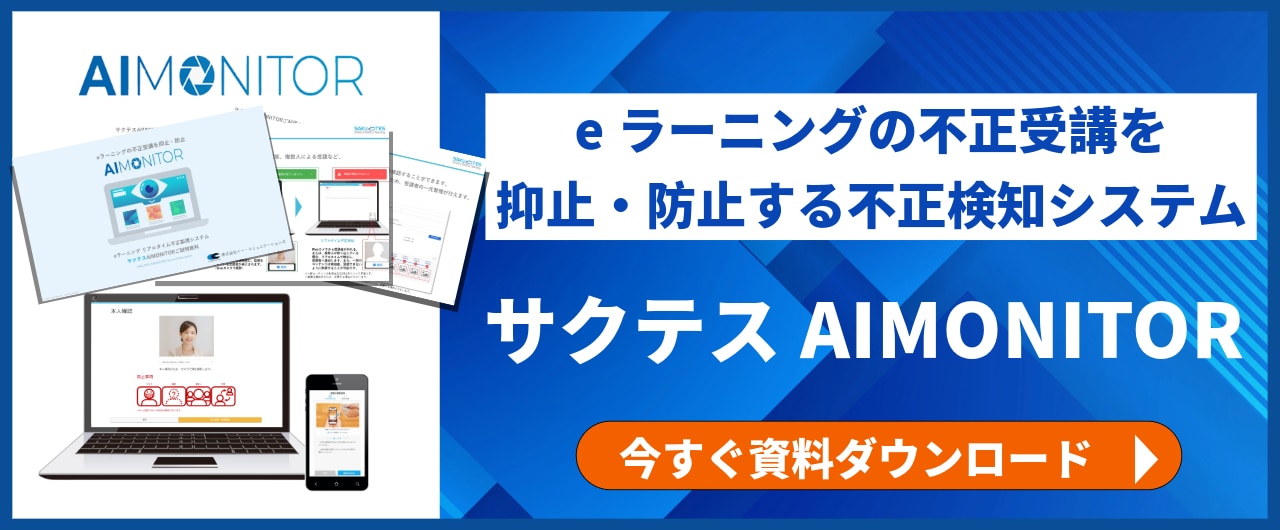【企業の義務】労働安全衛生法の「特別教育」とは?対象業務・時間・罰則まで徹底解説

建設業や製造業、電気工事など、特定の危険または有害な業務に労働者を就かせる際、企業に課せられる法的義務があります。それが、労働安全衛生法に基づく「特別教育」です。これを怠れば、重大な労働災害につながるだけでなく、企業は厳しい罰則や多額の損害賠償責任を負うことになります。企業の安全配慮義務の根幹でありながら、「対象業務が多い」「実施方法が複雑」といった理由で、対応が後手に回ってしまうケースも少なくありません。
本記事では、この特別教育の法的定義から、対象となる具体的な業務の種類、法令で定められた教育時間、企業が取るべき実施方法、そして未実施の場合に科せられる重大な罰則リスクまでを、実務的な視点から徹底解説します。
目次[非表示]
- 1.なぜ今、「特別教育」が必要なのか?
- 2.労働安全衛生法における「特別教育」の基本
- 2.1.特別教育の定義と法律上の位置づけ
- 2.2.特別教育の対象業務とは
- 2.3.教育の実施者と時間の基準
- 2.3.1.教育の実施者(主体)
- 2.3.2.法令で定められた教育時間
- 3.特別教育の具体的な事例と実施方法
- 3.1.足場の組立て等特別教育のポイント(建設業の例)
- 3.1.1.事故防止に直結するカリキュラム内容
- 3.1.2.実務経験者向けの省略規定の活用
- 3.2.代表的な危険業務と特別教育(一覧)
- 3.3.効果的な教育の実施方法
- 3.3.1.外部講習を利用する場合のメリット・デメリット
- 3.3.2.オンライン学習(eラーニング)の活用可能性
- 4.特別教育を怠った場合の重大なリスク
- 4.1.事業者への法的罰則と責任
- 4.1.1.労働安全衛生法に基づく罰則(行政罰)
- 4.1.2.安全配慮義務違反による民事訴訟
- 4.2.労働災害発生が企業に与える影響
- 4.2.1.企業イメージの失墜と信用の低下
- 4.2.2.安全意識の低下が引き起こす連鎖的な事故
- 5.まとめ:安全な現場をつくるためのチェックリスト
- 6.特別教育のオンライン化に「サクテスAIMONITOR」をご活用ください
なぜ今、「特別教育」が必要なのか?


製造業、建設業をはじめとする多くの産業において、労働者の安全確保は企業の存続に直結する最重要課題です。どれだけ優れた安全マニュアルや設備を導入しても、それを扱う労働者の知識とスキルが不足していれば、事故のリスクは常にゼロにはなりません。
労働安全衛生法に定められた「特別教育」は、まさにその「知識とスキル」のギャップを埋め、危険な業務から労働者を守るための「最後の砦」として機能します。これは単なる「講習」ではありません。特定の危険・有害な業務に就く労働者に対して、その業務特有の危険性と安全対策を徹底的に教育することを企業に義務付けたものです。
労働災害ゼロを目指す企業の責務
近年、労働安全衛生に対する社会の目は厳しくなっており、一度重大な労働災害が発生すれば、企業の信用失墜、巨額の賠償責任、そして何よりも大切な人材の喪失という、計り知れない損失を招きます。
特別教育は、企業が負う安全配慮義務を具体的に履行するための核心的な要素であり、「安全は自己責任」という考え方が通用しない現代において、企業が法的責任と倫理的責任を果たすための第一歩となります。
一般の安全衛生教育と「特別教育」の違い
労働安全衛生法に基づく教育には、大きく分けて3つの区分があります。
- 雇入れ時の教育・作業内容変更時の教育:すべての労働者に対し、職場の一般的な危険性や安全ルールを教えるもの。
- 職長等の安全衛生教育:現場の責任者(職長など)に対し、作業指揮や部下への指導方法を教えるもの。
- 特別教育:特定の危険・有害業務に限定して行う専門教育。
特別教育が他の安全衛生教育と異なるのは、その「業務の危険性」の高さと、教育の「専門性」にあります。足場の組立て、電気の充電部を扱う作業、危険物取扱など、一歩間違えば重大な事故につながる業務に対し、その業務の特性に合わせた専門知識(作業方法、機材の構造、災害事例など)を、法令で定められた時間と内容で確実に習得させることが求められます。
特別教育は、特定の業務を行うための必須教育であり、これを欠く労働者はその業務に就くことが禁じられています。
労働安全衛生法における「特別教育」の基本

特別教育の重要性を理解するためには、その法的根拠と対象範囲を正しく把握することが不可欠です。
特別教育の定義と法律上の位置づけ
特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づいています。この条文は、事業者が労働者を「危険又は有害な業務」に就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないと定めています。
この「行わなければならない」という表現は、事業者の法的義務を示しています。特別教育は任意ではなく、業務を行うための前提条件です。
この教育を省略したり、不十分な内容で実施したりすることは、直ちに法令違反となり、後に労働災害が発生した場合は、企業の過失責任を問われることになります。
特別教育の対象業務とは
特別教育の対象となる「危険又は有害な業務」は、労働安全衛生規則の第36条に定められています。その業務は多岐にわたり、足場の組立て等、高所作業車運転、フォークリフト運転、アーク溶接、低圧電気取扱、特定化学物質の取扱、エックス線作業など49の業務が指定されています。
事業者は、自社の業務内容が該当するかどうかを厳密にチェックし、該当する場合は必ず特別教育を実施しなければなりません。特に建設業では足場や玉掛け、製造業では低圧電気やフォークリフト、サービス業でもビル管理等で高所作業が関わる場合があり、幅広い業種で適用されます。
教育の実施者と時間の基準
特別教育の実施方法についても、法令で明確なルールが定められています。
教育の実施者(主体)
原則として、特別教育を実施する義務は、労働者を雇用する事業者(企業)にあります。事業者は、自社で教育を行うか、または外部の教育機関に委託することができます。
- 自社で実施する場合: 講師は、その業務に関する十分な知識と経験をもつ者(例:作業主任者、有資格者、安全衛生推進者など)を選任する必要があります。
- 外部機関に委託する場合: 外部の教習機関や協会などが開催する講習を利用します。この場合、企業は労働者が確実に受講し、修了証を取得したことを確認・保管する義務があります。
法令で定められた教育時間
特別教育のカリキュラムと時間は、各業務の危険度に応じて細かく定められています。例えば、主要な業務の教育時間は以下の通りです。
業務の種類 | 学科時間 | 実技時間 | 合計時間(目安) |
足場の組立て等作業 | 6時間 | 3時間 | 9時間 |
低圧電気取扱業務 | 7時間 | 1時間 | 8時間 |
アーク溶接等作業 | 10時間 | 10時間 | 20時間 |
フォークリフト運転 | 11時間 | 4時間 | 15時間 |
この教育時間は最低基準であり、企業は自社の作業環境や危険特性に合わせて、これらの時間を超えて教育を行うことが推奨されています。教育時間と内容を厳守しなければ、法令で求められる「特別教育」を実施したとは認められません。
特別教育の具体的な事例と実施方法

特別教育の中で、特に多くの事業者が関わり、かつ事故のリスクが高い業務について、具体的な教育内容と実施のポイントを解説します。
足場の組立て等特別教育のポイント(建設業の例)
足場からの墜落・転落事故は、建設業における死亡災害の主要な原因の一つです。そのため、足場の組立て、解体または変更の作業(地上での準備作業、資材の運搬等を除く)に従事するすべての労働者に対して、特別教育が義務付けられています。
事故防止に直結するカリキュラム内容
足場の組立て等特別教育(9時間)は、以下の要素を網羅します。
区分 | 主な内容 |
学科 (6時間) | 足場の構造及び組立て等の方法に関する知識、 |
実技 (3時間) | 足場の組立て、解体及び変更に関する実技 |
この教育では、単に「手順」を教えるだけでなく、なぜその手順が必要なのか、足場の各部材(建地、布板、手すり先行工法など)が果たす安全上の役割を理解させることが重要です。特に、手すり先行工法など、最新の安全基準に基づいた作業方法を教えることが、墜落制止用器具の適切な使用と合わせて、事故防止に直結します。
実務経験者向けの省略規定の活用
特別教育には、すでに相当の知識や経験がある労働者に対して、教育時間の一部を省略できる規定があります。例えば、「足場の組立て等作業主任者」の資格をもつ者や、特定の作業経験をもつ者に対しては、教育の一部(労働災害の防止に関する知識など)の学科時間が短縮されます。ただし、これは必須の教育時間を無条件で免除するものではないため、適用する際は法令を厳密に確認する必要があります。
代表的な危険業務と特別教育(一覧)
業務名 | 関連する危険 | 教育時間(例) | 実施のポイント |
低圧電気取扱業務 | 感電・火災 | 8時間(学科7h, 実技1h) | 「充電部に近接する作業」も対象となる点に注意。活線作業用保護具の使用方法が必須。 |
アーク溶接等作業 | 感電・アーク光による眼の障害(電光性眼炎)・有害ガス発生 | 20時間(学科10h, 実技10h) | 適切な保護具(溶接面、防護服)の選定と使用、換気方法の指導が重要。 |
フォークリフト等の運転 | 荷崩れ・転倒・挟まれ | 15時間(学科11h, 実技4h) | 構内での走行に関する知識、荷の安定性の確保、作業開始前の点検方法を徹底。 |
効果的な教育の実施方法
事業者は、教育の質を高め、労働者の定着率と理解度を向上させるために、実施方法を工夫する必要があります。
外部講習を利用する場合のメリット・デメリット
外部講習を利用する場合のメリット・デメリットを表にまとめると下記のとおりです。
実施方法 | メリット | デメリット |
外部機関(教習所など) | 法令で定められた内容を確実に網羅できる。講師の質が高い。修了証の発行がスムーズ。 | コスト(受講料)と時間の調整が必要。自社の現場固有のリスクに対応できない。 |
自社内での実施 | 労働者の勤務時間内に柔軟に対応可能。自社の設備や災害事例に即した教育が可能。 | 講師の確保と教育資料の作成に手間がかかる。教育記録の管理が煩雑になりやすい。 |
オンライン学習(eラーニング)の活用可能性
学科教育については、現在、eラーニングなどの遠隔教育も認められつつあります。これは、時間と場所の制約を減らし、業務の合間に学習できるという大きなメリットがあります。しかし、実技教育は必ず対面で行う必要があります。事業者は、eラーニングを活用する場合でも、実技教育が完全に法令の要件を満たしているかを厳しくチェックしなければなりません。
特別教育のオンライン化に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
↓
特別教育はオンライン化でここまで変わる!法令対応と効率化を同時に実現させる方法を解説
▼参考資料:特別教育のオンライン化 実践ガイド
特別教育を怠った場合の重大なリスク
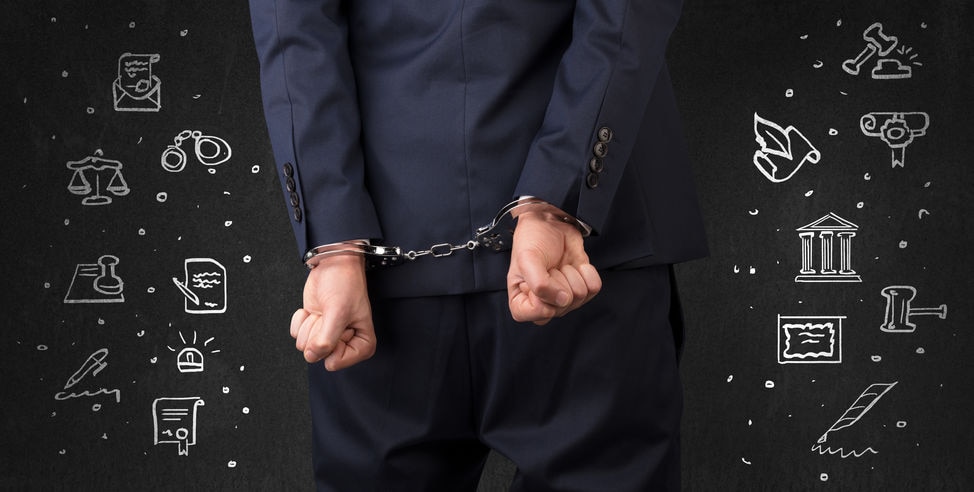
特別教育は「義務」です。これを怠った場合、企業が負うリスクは、単なる罰金で済まされるものではありません。
事業者への法的罰則と責任
特別教育の未実施は、労働安全衛生法の違反となります。
労働安全衛生法に基づく罰則(行政罰)
労働安全衛生法では、特別教育を実施しなかった事業者は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります(労働安全衛生法第119条)。この罰則は、両罰規定(法人と行為者の双方を罰する)が適用されるため、法人そのものも罰則の対象となります。
安全配慮義務違反による民事訴訟
行政罰以上に深刻なのが、労働災害が発生した場合の民事責任です。企業は労働契約に基づき、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する安全配慮義務を負っています(民法第415条、労働契約法第5条)。
特別教育の未実施は、この安全配慮義務を怠ったと判断される最大の根拠となります。裁判で過失が認められた場合、企業は、治療費、休業補償、逸失利益、慰謝料など、数千万円から数億円に及ぶ損害賠償金を支払う義務を負うことになります。
労働災害発生が企業に与える影響
特別教育を怠った結果、労働災害が発生した場合、企業の受けるダメージは金銭的なものだけに留まりません。
企業イメージの失墜と信用の低下
重大災害が発生すると、行政(労働基準監督署)による立ち入り検査や業務停止命令を受ける可能性があります。ニュースや業界紙で報道されれば、取引先や顧客からの信用は地に落ち、企業ブランドは大きく毀損します。特に安全を重視する発注元からは、新規の受注停止や契約解除につながる可能性が高まります。
安全意識の低下が引き起こす連鎖的な事故
特別教育を受けていない労働者は、自身の危険を察知する能力や、緊急時の対応能力が低くなります。その結果、その労働者が事故に遭うだけでなく、周囲の作業員を巻き込む連鎖的な事故を引き起こすリスクが高まります。安全教育を軽視する企業風土は、組織全体のモラル低下と生産性の悪化を招き、結果的に長期的な競争力の低下につながります。
まとめ:安全な現場をつくるためのチェックリスト

特別教育は、企業の「安全文化」を構築するための礎です。以下のチェックリストを参考に、自社の安全体制を見直してください。
企業の特別教育対象者リストの作成・管理
- 業務の棚卸し: 労働安全衛生規則第36条に記載された49業務と、自社の業務を照合する。
- 対象者の特定: 特別教育が必要な業務に現在従事している、または今後従事させる予定の労働者全員を特定する。
- 教育記録の管理: 誰に、いつ、どのような内容で、何時間教育を実施したかを記した記録簿と修了証の写しを法令に従って保管する(教育実施日から5年間の保管が推奨される業務もある)。
特別教育は「コスト」ではなく「未来への投資」
教育費用や受講中の人件費は、一時的には「コスト」にみえるかもしれません。しかし、特別教育を通じて労働災害を未然に防ぐことは、以下の「投資効果」を生み出します。
- 労働災害による損失コスト(治療費、休業補償、遅延損害など)の回避
- 安全意識の高い労働者による作業効率の向上
- 企業の信用力の向上と優良な人材の定着
法令遵守を超えた、真の安全文化の構築に向けて
特別教育は、単なる法令遵守(コンプライアンス)の達成で終わるべきではありません。重要なのは、教育内容を現場で実践させることです。企業は、教育後のOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や、定期的な安全ミーティングを通じて、労働者が学んだ知識を定着させ、安全作業を習慣化させる仕組みを構築する必要があります。
「法令で定められたからやる」のではなく、「社員の命と企業の未来を守るためにやる」という強い意志こそが、真の安全文化を築き上げます。
特別教育のオンライン化に「サクテスAIMONITOR」をご活用ください
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」と連携して使用する「サクテスAIMONITOR」は、eラーニング受講前に本人認証、登録を行い、受講中、Webカメラやスマホのカメラでリモート監視をし続けることで、不正受講を検知するAI × クラウドサービスです。
スマートフォンによる本人認証(eKYC)が行えます。スマートフォンのカメラで顔写真・身分証明証を撮影し、撮影された画像を照合します。照合NGの場合は、eラーニングコンテンツの受講ができません。
eラーニング受講中に、離席や複数人による受講を検知した場合、受験者への通知や、受講コンテンツの停止など、制御を行います。居眠りや、受講画面とは異なる他のアプリケーションを起動している、受講画面とは違うところを見ているといった挙動も検知し、受講者にアラートを出したり、受講中の動画を停止させます。
また、検知したデータを管理者サイトから確認することができます。
サクテスAIMONITORは安全衛生教育・特別教育での導入実績があるサービスです。ご興味がおありの場合は、お気軽にお問い合わせください。