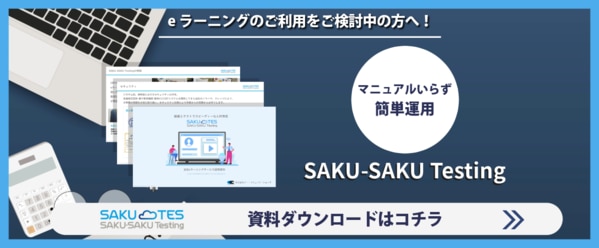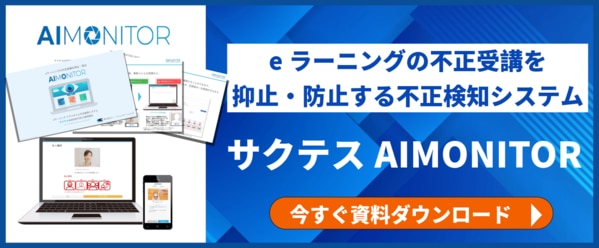特別教育はオンライン化でここまで変わる!法令対応と効率化を同時に実現させる方法を解説

法令で義務づけられている安全衛生教育や特別教育――。
「会場手配や講師確保、紙のテキスト発送が毎回大きな負担になっている」と感じていませんか?
2023 年の eラーニング通達改正により、学科部分はオンライン化が正式に認められ、受講率・コスト・監査対応のすべてを一気に改善できる環境が整いました。
本記事では、安全衛生教育と特別教育の法的ポイントをおさらいし、対面講習の課題と eラーニング化による具体的なメリット、そして導入ステップまでを徹底解説します。
▼あわせて読みたい:特別教育のオンライン化 実践ガイド
目次[非表示]
- 1.安全衛生教育とは
- 1.1.1. 安全衛生教育の法的根拠と目的
- 1.2.2. 教育内容
- 1.2.1.1 雇い入れ時、作業内容変更時の教育
- 1.2.2.2 特別教育
- 1.2.3.3 職長等に対する教育
- 1.3.4. 安全衛生教育等のeラーニング化
- 2.特別教育とは
- 2.1.1.特別教育の位置づけ
- 2.2.2. 特別教育の対象業務
- 2.3.3. 学科+実技の二本立て
- 2.4.4. 特別教育はオンライン化できる?
- 3.なぜ「特別教育」が必要なのか
- 3.1.1. 重大災害はいまも“ゼロ”になっていない
- 3.2.2. ハイリスク作業は小さなミスが大事故に直結
- 3.3.3. 法令違反は罰則+事業停止リスク
- 3.4.4. 事故コストは教育コストの数十倍
- 3.5.5. 取引継続のかなめ
- 4.対面で実施する特別教育の課題とオンライン化で解消できるポイント
- 5.特別教育をオンライン化するメリット
- 5.1.コスト削減ができる
- 5.2.好きな時間・好きな場所で受講できるのでキャンセルが減る
- 5.3.受講状況をモニタリングできる
- 5.4.記録を残せる
- 5.5.講義の質を担保できる
- 5.6.講師リソースを“高付加価値業務”へ再配分
- 5.7.教材のアップデートが簡単
- 6.特別教育をオンライン化する手順
- 6.1.ステップ1 法令・通達の最新版を確認
- 6.2.ステップ2 既存教材のデジタル化
- 6.3.ステップ3 プラットフォーム(LMS)の選定
- 6.4.ステップ4 プラットフォーム(LMS)の初期設定・搭載
- 6.5.ステップ5 進捗状況の管理
- 7.まとめ
- 8.特別教育のオンライン化に「サクテスAIMONITOR」をご活用ください
安全衛生教育とは

まずは安全衛生教育の概要について解説します。
1. 安全衛生教育の法的根拠と目的
労働安全衛生法第59条1・2項および労働安全衛生規則第35条は、事業者に対し「労働者を雇い入れたとき、または作業内容を変更したとき」に安全衛生教育を実施する義務を課しています。目的は「危険有害要因の理解と事故予防」です。雇用形態(常用・臨時・派遣・日雇い)を問いません。
参考:職場のあんぜんサイト
2. 教育内容
1 雇い入れ時、作業内容変更時の教育
事業者は、労働者を雇い入れたときや労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行う必要があります(労働安全衛生法第59条1項、2項)。
教育の具体的な内容は、以下のとおりです(労働安全衛生規則第35条)。
業種によっては、一部の教育を省略することができます。
(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3)作業手順に関すること。
(4)作業開始時の点検に関すること。
(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6)整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(7)事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8)前各号に掲げるものの他、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
2 特別教育
事業者は、危険または有害な一定の業務に労働者を従事させるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別の教育(特別教育)を実施しなければいけません。(労働安全衛生法第59条3項)。
特別教育に関しては、後ほど詳しく解説します。
3 職長等に対する教育
建設業、製造業(一部業種を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業において、事業者は新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、以下の事項についての安全または衛生のための教育を行う必要があります(労働安全衛生法第60条)。
(1)作業方法の決定および労働者の配置に関すること。
(2)労働者に対する指導または監督の方法に関すること。
(3)その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
4. 安全衛生教育等のeラーニング化
2023 年12 月の厚生労働省の「インターネット等を介したeラーニング等により行われる 労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(以下、「eラーニング通達」という)」改正で、申込~受講~修了証交付までのデジタル化が認められました。
eラーニング等での安全衛生教育等を実施することへのニーズの高まりが背景にあります。
e ラーニング等により安全衛生教育等を行う場合であっても、法定の科目の範囲、教育時間及び講師の要件を満たした上で、教本等必要な教材を用いて行うとともに、受講者が受講した事実を適切に確認する必要があります。
詳しい留意事項は「eラーニング通達」で示されています。
参考:インターネット等を介したeラーニング等により行われる 労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について
特別教育とは

1.特別教育の位置づけ
同じく労働安全衛生法第59条3項に基づき、“危険または有害性の程度が著しい特定業務” に就く前に追加で行う法定教育が特別教育です。通常の安全衛生教育よりも深い知識と実技技能の習得が義務づけられています。
2. 特別教育の対象業務
特別教育を必要とする業務は、労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転などの業務です。
特別教育の対象となる業務の一部を以下に表でまとめます。
分野 | 法令名称例 |
|---|---|
荷役・運搬 | フォークリフト運転、玉掛け、床上操作式クレーン |
高所 | 高所作業車(10m未満)、足場組立て |
切削・伐倒 | チェーンソー伐木、刈払機取扱い |
有害物 | 有機溶剤、特定化学物質、石綿作業 |
酸欠・圧力 | 酸素欠乏危険作業、ボイラー取扱い |
3. 学科+実技の二本立て
特別教育は、基本的には学科教育と実技教育の二本立てになっています。内容と最小時間は「安全衛生特別教育規程」で業務ごとに細かく規定されています。
例えばフォークリフト(最大荷重1トン未満)の運転の業務では、「学科6h+実技6h」となっています。
学科と実技の両方を修了して、はじめて「受講済み」となります。
また、事業者は、特別教育を行なったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければいけません(労働安全衛生規則第38条)。
4. 特別教育はオンライン化できる?
2023 年改正の「eラーニング通達」で、特別教育の学科部分のオンライン化が原則認められました。e ラーニング等により安全衛生教育等を行う場合であっても、法定の科目の範囲、教育時間及び講師の要件を満たした上で、教本等必要な教材を用いて行うとともに、受講者が受講した事実を適切に確認する必要があります。
さらに、eラーニングで実施する場合の要件が下記のように定められています。
【eラーニング等の内容】 | 教育内容が各特別教育規程に定める範囲を満たすこと |
【eラーニング等の教材の閲覧・視聴等の時間の担保】 | 教育時間が、各特別教育規程に定める時間以上であることが担保できること |
【使用されている映像教材又はウェブサイト動画等に出演する講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び監修する者】 | いずれも十分な知識又は経験を有することが確認できること |
【実技、修了試験等】 | 特別教育のうち、実技教育について、講師と同一場所で対面により実施していること |
【実施場所、質問対応 】 | 受講者からの質問があった際に受付け回答できる体制があること |
なぜ「特別教育」が必要なのか

特別教育は労働安全衛生法で定められているものですが、それ以外の側面においても重要です。
ここでは、なぜ特別教育が必要なのかについて、5つの視点で解説します。
1. 重大災害はいまも“ゼロ”になっていない
厚生労働省が公表した 2023 年(令和5年)の労働災害統計によると、死亡者は755人、休業4日以上の死傷者は13万5,371人と依然高水準です。死亡者数は過去最少を更新した一方で、死傷者は3年連続で増加しており、「数は減っているから大丈夫」とは決して言えない現状があります。
2. ハイリスク作業は小さなミスが大事故に直結
フォークリフトや高所作業車などの運搬・高所作業機械は、重量物の落下や機体転倒が起きると、作業者本人だけでなく周囲に甚大な被害を与えます。実際、一般社団法人日本産業車両協会の2024年の調査では、フォークリフト由来の死傷者数が2年連続で増加 していると報告されています。
こうした“重大リスク”を抱える業務では、操作方法を「わかったつもり」で始めること自体が危険行為になります。
3. 法令違反は罰則+事業停止リスク
労働安全衛生法第59条の違反が発覚した場合、50万円以下の罰金(第120条) に加え、労働基準監督署からの是正勧告や改善命令、最悪の場合は事業停止命令が科されることもあります。
一度の違反で行政処分、メディアによる報道、取引停止などが連鎖し、企業の信用は大きく揺らぎます。
4. 事故コストは教育コストの数十倍
労災1件あたりの平均損失額(休業補償・代替人員・設備破損・訴訟対応など)は、専門機関のシミュレーションで数百万円規模といわれます。特別教育にかかる受講料は、その10~30%程度に収まるケースがほとんどです。予防投資としての費用対効果は明らかです。
5. 取引継続のかなめ
建設・製造業の大手企業では、協力会社や下請けに対して「特別教育修了証の提出」を義務づける動きが広がっています。
安全教育が不十分だと取引そのものができなくなるリスクがあり、特別教育の修了は取引を継続させるためにも必要不可欠です。
対面で実施する特別教育の課題とオンライン化で解消できるポイント

特別教育を対面で実施する場合には、いくつかの課題があります。
ここでは、対面実施の場合の課題とオンライン化で解消できるポイントを表にまとめます。
課題カテゴリ | 対面実施の具体的な課題 | オンライン化で解消できるポイント |
|---|---|---|
コスト | ・会場・機材レンタル・講師の拘束・交通費・受講者の移動・宿泊費 | 画面越しで学科を完結 ▶ 会場・旅費ゼロ/講師は在宅実施可 |
スケジュール調整 | ・複数拠点を同日に集められない | 受講者の空き時間にオンデマンド受講 ▶ 開催待ちが消滅 |
受講率・修了率 | ・急な現場応援や悪天候でキャンセル | eラーニングは24h×365日受講▶ 受講率アップ |
講師リソース不足 | ・経験講師が高齢化/兼務で確保困難 | 1本の動画を全国に配信▶ リソースを他業務へ再配分 |
コンテンツ更新の遅れ | ・法改正や新事例を反映するたびにテキスト修正・印刷が必要 | デジタル教材は差し替え即日反映 ▶ 最新状態を保てる |
紙ベースの記録管理 | ・出席簿・試験答案を3年間保管・検索・提出に工数かかる | LMSで電子保存▶ 検索・提出が簡単 |
学習効果のばらつき | ・講師ごとに説明品質が一定しない ・受講中に寝てしまう | 同一の動画で品質担保、居眠り検知機能▶ 定着率向上 |
安全衛生リスク | ・感染症流行や災害時は中止必至 | オンラインなら“集まらない”▶ 中断リスクを最小化 |
環境負荷・ESG | ・移動でCO₂排出、紙大量印刷 | デジタル完結▶ ペーパーレス&移動ゼロ |
スケーラビリティ | ・受講枠は会場定員が上限 | ID追加が簡単 ▶ 需要変動に即応 |
特別教育をオンライン化するメリット

「eラーニング通達」により、特別教育の学科部分のオンライン化が認められていますが、オンライン化するとさまざまなメリットがあります。
ここでは、オンライン化のメリットをご紹介します。
コスト削減ができる
特別教育の学科をeラーニング化すれば、会場費、講師代、講師交通費、テキスト印刷代、テキスト郵送費などのコストが削減できます。
ご参考に、6時間の学科講習を400名に対して行う場合、対面実施の場合とeラーニングで実施する場合の費用の一例を以下にまとめます。
【対面講習の場合】 | 【eラーニングの場合】 |
約230万円 |
約85万円 |
これは一例ではありますが、特別教育をeラーニング化することで約65%のコスト削減が可能です。これ以外にも、受講記録の管理が楽になったり、研修の際の移動時間がなくなったり、対面研修実施の際にかかる人件費も削減することができます。
好きな時間・好きな場所で受講できるのでキャンセルが減る
24 時間 365 日、受講者の好きな時間に学習できるため、受講者の利便性はもちろんのこと、繁忙期や突発業務での延期・キャンセル、気候や災害による開催中止が起きにくくなるため、主催者側のメリットも大きいです。
自由度の高い受講形式のため、受講率・修了率のアップにつながります。
受講状況をモニタリングできる
LMSを活用すれば、受講者の進捗が簡単にわかるため、受講が進んでいない人に対して、リマインドメールを送るなどが可能です。
記録を残せる
システムを使用することで、厳格な本人確認・不正対策が可能になり、受講中に不正な挙動があれば、webカメラを通じて記録して残しておくことが可能です。
法令で定められている「特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存」にも対応できるため、主催者側の負担が軽減されます。
講義の質を担保できる
対面講習の場合、その日の講師のコンディションや受講者の反応により、講義の内容や質にばらつきが出る可能性があります。日によってばらつきが生じてしまうと、講義の質の均一化が難しくなります。
一方、eラーニングは、同じ動画を受講者全員が視聴するため、コンディションによるブレがなく、質の担保がはかれます。
講師リソースを“高付加価値業務”へ再配分
教材の作成を1回行えば、同じ講義動画を一律で配信することができます。そのため、講師の時間や負荷を大幅に削減することができ、削減できた分の時間を他の業務へ充てることが可能です。
講師業務以外の付加価値の高い業務にリソースをさくことができます。
教材のアップデートが簡単
コンテンツのアップデートが簡単かつ迅速に行えます。新しい情報や資料の追加、既存コンテンツの修正が簡単で、常に最新の情報を受講者に提供できます。
法改正や最新の事例を盛り込むなども簡単に行えます。
特別教育をオンライン化する手順

ここまで、特別教育の重要性と、オンライン化の必要性やメリットをお伝えしてきました。
オンライン化には、Web会議ツール等を活用して、オンラインで決まった時間に講義を行う方法と、eラーニング等で好きな時間に視聴する方法があります。
ここではより利便性の高いeラーニングを活用する方法において特別教育をオンライン化する手順を解説します。
ステップ1 法令・通達の最新版を確認
まず、特別教育をオンライン化する場合の条件を確認します。法令・通達等が改正されている場合がありますので、都度確認することが大切です。
労働安全衛生法や「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の通達等を確認してください。
ステップ2 既存教材のデジタル化
すでに対面などで研修を行っている場合は、使用している資料を元にオンライン教材を作成します。
「安全衛生特別教育規程」で定められている教育時間に従い、研修動画等を作成します。
eラーニングでの学習は集中力の観点やスキマ時間で学べるという点から、なるべく1つひとつの動画時間を短くすることがおすすめです。1動画を15分以内で設計していくと、学習効率が上がります。法改正や内容のアップデートを行う必要があった場合も、1動画が短いほうが編集が簡単に行えます。
対面研修でテキスト等を用いて講義をしている場合は、動画の中で資料を共有しながら話をする等、テキストの情報を組み込むのがおすすめです。
紙のテキストをなくすことで、テキストにかかる印刷代や配送料のコストを削減することができます。
ステップ3 プラットフォーム(LMS)の選定
教材を搭載するプラットフォーム(LMS:学習管理システム)を選定します。
以下の項目を参考にプラットフォームを選定してください。
□目的に合った機能が揃っているか
– 例)動画配信、理解度テスト、進捗ダッシュボード、本人確認機能、不正抑止機能など。
□受講者・管理者ともに操作しやすいか
– UI/UX が直感的で、マニュアルを読まなくても使えるレベルか。
□サポート体制は十分か
– 導入後の操作問い合わせや法改正対応のアップデート支援など。
□価格は妥当か
– 他社同等製品との比較、ID 単価の継続負担まで試算。
□自社と同業種の導入実績があるか
– 同じ業務・業界で効果が出ている事例があると社内説得材料になる。
▼参考資料:LMS選定のポイントを資料にまとめていますので、ご参考にしてみてください。
特別教育のオンライン化について示されている「eラーニング通達」では、受講者が受講した事実を適切に確認する必要があるとしているため、受講者の本人認証ができ、きちんと受講していることが証明できるシステムを導入する必要があります。
そこでおすすめなのが、イー・コミュニケーションズの「サクテスAIMONITOR」です。
サクテスAIMONITORはeラーニング受講前に本人認証、登録を行い、受講中、Webカメラやスマホのカメラでリモート監視をし続けることで、不正受講を検知するAI × クラウドサービスです。
安全衛生教育、特別教育のオンライン化での導入実績があり、さまざまな教育実施団体様から反響をいただいているサービスです。
▼参考資料:サクテスAIMONITORのサービスはこちらからダウンロードできます。
ステップ4 プラットフォーム(LMS)の初期設定・搭載
プラットフォームが決定し導入がすんだら、初期設定や教材の搭載を行います。
実際に使用する教材を搭載し、受講者の登録などを行っていきます。
最初は手間取ることも多いと思いますので、適宜サポート窓口に相談しながら準備を進めます。
ステップ5 進捗状況の管理
教材や受講者登録の準備が完了したら、該当者にコンテンツを配信し、研修を実施します。
システムの使い方などで、受講者から問い合わせなどがある場合が考えられますので、質問が来た場合のサポート体制を整えておきましょう。
また、管理者画面から受講者の進捗状況を確認し、状況に応じて受講を促すメールを送るなどの取り組みが必要です。
LMSの導入に関してはこちらの記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
↓
社員研修をスムーズにeラーニング化! LMS(学習管理システム)導入の手順を徹底解説
まとめ
安全衛生教育・特別教育は、いずれも労働安全衛生法が定めている必須研修です。
対面方式のみで運営を続ける場合、会場費や講師旅費、紙媒体の配布・保管コストが累積し、受講率の低下や記録不備による法令違反リスクも看過できません。2023 年の厚生労働省通達改正により、特別教育の学科部分のオンライン実施が正式に容認されたいま、学科を eラーニング化し実技を対面で行うハイブリッド方式へ移行することは、法令順守を強化しつつ運営効率と教育品質を高める最も確実な手段と言えます。
本記事を参考に、法令に対応したオンラインでの安全衛生教育・特別教育を実施し、負担軽減や研修業務の効率化を実現させてください。
▼あわせて読みたい:特別教育のオンライン化 実践ガイド
特別教育のオンライン化に「サクテスAIMONITOR」をご活用ください
「サクテスAIMONITOR」は、eラーニング受講前に本人認証、登録を行い、受講中、Webカメラやスマホのカメラでリモート監視をし続けることで、不正受講を検知するAI × クラウドサービスです。
スマートフォンによる本人認証(eKYC)が行えます。スマートフォンのカメラで顔写真・身分証明証を撮影し、撮影された画像を照合します。照合NGの場合は、eラーニングコンテンツの受講ができません。
eラーニング受講中に、離席や複数人による受講を検知した場合、受験者への通知や、受講コンテンツの停止など、制御を行います。居眠りや、受講画面とは異なる他のアプリケーションを起動している、受講画面とは違うところを見ているといった挙動も検知し、受講者にアラートを出したり、受講中の動画を停止させます。
また、検知したデータを管理者サイトから確認することができます。
サクテスAIMONITORは安全衛生教育・特別教育での導入実績があるサービスです。ご興味がおありの場合は、お気軽にお問い合わせください。