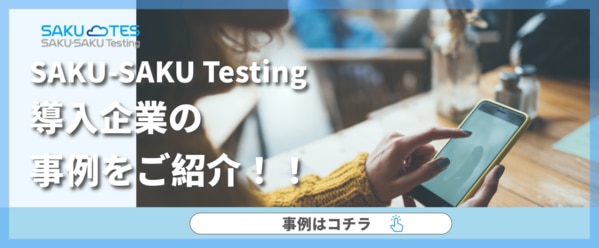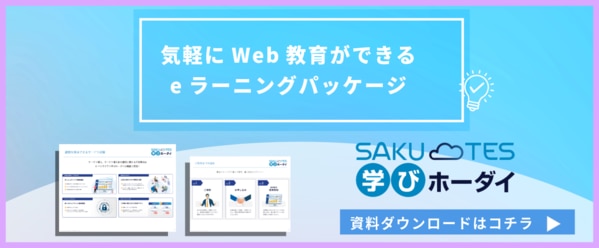eラーニングの作り方を解説!自作方法やおすすめ作成ツールも紹介

eラーニングは、企業や教育機関で効率的な学びの手段として注目されています。eラーニングを効果的に活用するためには、カリキュラムや教材内容を計画的に設計し、受講者の理解を深めるためにわかりやすく整理されたコンテンツを用意する必要があります。
本記事ではeラーニング作成の基本や方法の種類、自作の際の注意点などを解説します。
目次[非表示]
- 1.eラーニングを作る基本ステップ
- 1.1.学習目標と対象者の設定
- 1.2.教材の構成と設計
- 1.3.コンテンツの制作・作成
- 1.4.教材の実施と評価
- 2.eラーニングの作り方の種類
- 2.1.動画教材の特徴と作成のポイント
- 2.2.作成ソフトを使った自作
- 2.3.外部への制作委託
- 2.4.目的別eラーニング教材作成方法まとめ
- 3.eラーニング教材を自作する際の注意点
- 3.1.教材作成のわかりやすさ
- 3.2.学習効果を高める工夫
- 3.3.コンテンツの更新・管理のしやすさ
- 3.4.著作権に対する適切な対応
- 4.eラーニング作成のパターン例
- 4.1.スタジオ収録型
- 4.2.ライブ配信型
- 4.3.スタジオ収録型・ライブ配信型・ハイブリット型の特徴
- 5.eラーニング作成ツール
- 6.eラーニングシステムの利用
- 6.1.eラー二ングシステムの機能
- 7.eラーニングを用いた社内教育に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
eラーニングを作る基本ステップ

eラーニング教材を作る際の第一歩は、全体の計画を立てることです。作成方法を順序立てて実践することが、効果的なeラーニング構築のポイントとなります。計画を進めるためのステップについて、順を追って説明します。
学習目標と対象者の設定
教材を作る際には、誰に向けてどのような知識やスキルを身につけてもらいたいのか明確に設定することが肝心です。学習目標は、具体的かつ測定可能な内容にすることで、教材を作る過程やその後の評価がしやすくなります。また、教材を作る前に対象者の年齢層や職務経験、学習背景を正確に把握することで、用いる言葉や説明の深さを適切に調整できます。
たとえば、新人社員向けに教材を作る場合は、基礎を重視し、わかりやすい解説が必要です。一方、管理職向けに教材を作成する際には応用的なテーマや実践的な内容を中心に作ることで、対象者のニーズに合った構成になります。こうした配慮が、学習者の理解度向上やモチベーション維持に大きく影響します。
教材の構成と設計
教材設計とは、受講者が学びやすく、しっかり理解できるように、学習内容を順を追って分かりやすく整理することです。まずは全体の構成を決定し、教材ごとの目的や学習の流れを明確にまとめます。詳しい設計書を作っておくことで、関係する人たちと情報をしっかり共有でき、認識のズレや行き違いを防ぐことができます。設計段階で学習時間や評価方法、具体的な作成方法を計画しておくと、後の制作や運用もスムーズに進行します。教材構成では、重要なポイントを的確に絞り込み、必要な知識やスキルを過不足なく伝えるバランスが求められます。また、教材の作成方法や構成を工夫し、将来的な更新や改訂が柔軟にできる仕組みにしておくことで、長期間にわたって教材を効果的に活用することが可能になります。
コンテンツの制作・作成
具体的な教材の制作は、設計段階で決めた仕様に従って進めます。教材を作成する際には、テキストはシンプルでわかりやすい表現を用い、専門用語や難しい表現には丁寧な補足説明を加えます。
また、文章だけでなく、イラストや写真を適切に使用して視覚的な理解を深める工夫も重要です。動画コンテンツの制作においては、画質や音声のクリアさに配慮し、要点を押さえた編集を心がけることで、学習者にとって快適で理解しやすい動画を作成できます。
さらに、クイズやアンケートなどの操作しながら学べる箇所も取り入れ、学習内容の定着を促す方法も効果的です。教材の完成後に、別の人の目で内容を確認してもらうことで、誤字脱字やわかりにくい表現を防ぎ、より質の高い教材に仕上げることができます。最終的には、学習者がストレスを感じることなく自然に知識を吸収できるような制作・作成を目指すことが大切です。
教材の実施と評価
教材を配信したあとは、受講者がどれくらい学習を進めているかや成果を把握し、学びの効果をしっかりと確認することが大切です。学習管理システムを活用すると履歴の把握や成績の集計が容易で、効果測定が客観的に行えます。
受講者からのフィードバックやアンケートを参考にしながら、内容の見直し点や改善点を抽出していきます。評価を基に教材を適切に修正し、学習者にとってより効果的な学習環境を整備することが重要です。また、学習効果が続くように、スキルが実際の仕事でどれだけ活かされているかを確認し、必要に応じてサポートやフォローアップを行います。こうした一連のプロセスによって、教材の質を持続的に向上させることが可能となります。
eラーニングの作り方の種類

eラーニング教材を作成する方法には、多様な手段がありそれぞれに特徴があります。効果的にeラーニングを導入するには、予算や目的、社内の体制など、自社の状況に合った方法を選ぶことが大切です。方法や特徴について、詳しくご説明いたします。
動画教材の特徴と作成のポイント
動画教材動画教材は、講義や操作手順などを映像でわかりやすく伝えられるのが大きな特長です。
作成する際は、まずシナリオや全体構成を考え、必要な資料や機材をそろえます。制作工程には撮影・編集・ナレーションなどが含まれ、初めての場合は準備に時間がかかることもあります。
高品質な教材を目指すなら、撮影時に専用スタジオを使うと画質や音声が向上し、より見やすい仕上がりになります。撮影後は編集ソフトで不要な部分をカットしたり、テロップを入れたりして、学びやすい動画に整えます。
動画は繰り返し再生できるため、受講者が自分のペースで学べるという利点があります。効果的な動画教材にするには、内容や長さを適切に調整し、視聴者の集中を維持できる工夫をすることが重要です。
作成ソフトを使った自作
作成ソフトを活用した自作は、専門的な知識やスキルがなくても教育コンテンツの作成や教材の内製が手軽に始められる方法です。PowerPointをはじめ、市販や無料のeラーニング作成ツールが豊富に提供されており、学習者がクリック・選択・入力などで参加できる要素を簡単に組み込むことができます。これらのツールを利用すれば、文章や資料を効率よくまとめることに加えて、動画や音声も組み合わせた、より深みのある教材コンテンツを自社で制作できます。また、現在のパソコン環境をそのまま活かせるため、新たな設備投資を抑えながら、自分たちのペースで無理なく教材作成を行えるのが魅力です。
また、最新の教材作成ソフトでは、同期機能やクラウド対応が進んでおり、複数人での同時編集や進行状況の共有がしやすくなっています。
外部への制作委託
制作を外部に委託することは、社内に十分なノウハウがない場合や、多数の教材を短期間で作成したい場合に有効です。制作会社には、教材づくり全般にわたる幅広い経験があり、動画編集や構成の工夫に加え、オリジナルのイラストやアニメーションを組み合わせた魅力的な教材を作成できます。プロが制作するeラーニング教材は、学習効果を高める工夫や最新のトレンドを取り入れつつ、受講者のニーズに合わせた内容に仕上げることができます。
ただし、外部委託にはコストがかかるため、予算管理が重要です。また、円滑に制作を進めるには、納期や要件の伝達、スケジュール調整を慎重に行うことが必要です。自社のリソースや期間、予算をしっかりと比較・検討し、外部委託を活用すれば、効率的に高品質な教材作成が可能になります。
目的別eラーニング教材作成方法まとめ
目的別のeラーニング教材作成方法を表にまとめると以下のとおりです。
目的 | 適した作成方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |
社内ルールの共有・理解 | PowerPoint +音声/動画 | 手軽で社内にノウハウがある | 短期間で作成可能、コスト低め | デザイン・操作性に限界がある |
専門知識の体系的な教育 | 専門ベンダーへの外注 | 教育設計から開発まで一括対応 | 高品質で学習効果も高い | 費用が高くなる傾向、納期がかかる |
操作マニュアルや業務手順の習得 | シミュレーション教材(e.g. Adobe Captivate, STORM Xe) | 実際の画面を模した操作体験が可能 | 実務に直結、習得効果が高い | 専門ソフトの知識や環境が必要 |
自発的な学び・知識定着 | マイクロラーニング(短時間・分割) | 1コンテンツが短く集中しやすい | モバイル対応も◎、継続しやすい | 教材数が多くなりがち、設計が重要 |
全国展開・拠点教育 | LMS(学習管理システム)と連携した教材 | 進捗・成績の一元管理が可能 | 配信・運用・管理がしやすい | LMS選定や導入にコスト・時間が必要 |
eラーニング教材を自作する際の注意点

自作でeラーニング教材を作成する際には、単にコンテンツを準備するだけでなく、全体の構成や流れに細心の注意を払うことが大切です。ここでは、注意すべき重要な点についてご説明いたします。
教材作成のわかりやすさ
教材のわかりやすさは、受講者が内容をしっかり理解できるかどうかに大きな影響を与えます。教材を作成する際には、専門用語の使用は必要最小限にとどめ、難しい言い回しは避けて簡潔に説明しましょう。具体的な例や事例を使うことで、抽象的な内容をわかりやすくし、理解を深めることができます。また、イラストや図表、動画といった視覚的な要素を積極的に取り入れることで、よりわかりやすい教材になります。フォントの大きさや色使いを工夫して、見やすいデザインにすることで、受講者がより集中しやすく、理解もしやすくなります。こうした工夫が盛り込まれた教材は、学習中のストレスを減らし、知識を効率よく吸収できる役割を果たします。
学習効果を高める工夫
学習効果の向上には、単に情報を伝えるだけではなく、受講者が積極的に教材と関わる仕組みを取り入れることが重要です。たとえば、理解度を測るためにクイズや演習問題を作ることで、受講者が自ら考えながら学習に参加しやすくなります。インタラクティブな要素を作ることで、受講者自身の参加意欲も高まり、記憶の定着が促されやすくなります。また、進捗管理機能を活用し、自己学習のペースを把握できる環境を作ることはモチベーションの維持に役立ちます。さらに、講師や仲間とのコミュニケーション機会を作ることで疑問点の解消や意欲向上にも効果的です。これらの取り組みを組み合わせて作ることで、効果的な学びの機会が提供されます。
コンテンツの更新・管理のしやすさ
eラーニング教材は、環境や業務内容の変化に応じて内容の見直しが必要になるため、更新や管理のしやすさが重要なポイントとなります。教材の作成方法を工夫し、自社制作することで、急な変更や修正にも迅速に対応できます。教材の構成を柔軟にし、テキストや動画を個別に編集できるようにすると、修正がしやすくなります。また、複数の担当者で編集や更新を分担できる体制を整えることで、作業効率が向上します。クラウドベースでバージョン管理や更新履歴の記録を徹底することにより、どの部分がどのように変更されたかを明確にし、運用上の問題を防ぐことができます。適切な管理体制と作成方法を確立することで、長期的に安定して活用できる教材を作り上げることができます。
著作権に対する適切な対応
eラーニング教材に用いる画像、動画、音声、テキストなどの多くには著作権が関係しているため、適切に権利を確認・処理することが重要です。市販やインターネット上の素材を無断で利用することは法律違反となり、後からトラブルに発展する恐れがあります。素材の利用許諾を事前に確認し、必要に応じて使用権を取得することが求められます。オリジナルで作成したコンテンツはもちろん安全ですが、他者の著作権を尊重する姿勢も重要です。スタジオ撮影などの場合は、出演者の同意書や権利関係を明確にする手続きを徹底すると、将来のリスクを回避できます。著作権を考慮した運用は、信頼性のある教材制作につながります。
eラーニング作成のパターン例

eラーニング教材の作成や制作にはいくつかのパターンがあり、それぞれの作り方にはメリットや特徴があります。ここでは代表的なパターンをご紹介します。
スタジオ収録型
スタジオで講義を録画して、あとから受講者が見るタイプのeラーニングです。
- 高画質・高音質できれいな動画
- いつでも何回でも見られる
- 編集されていて分かりやすい
スタジオ収録型はこれら3つの特長を持ち、「あとから見る録画授業」のような位置づけです。
ライブ配信型
Zoomなどでリアルタイムに講義を配信するeラーニングです。
- 講師とリアルタイムでやり取りできる
- 質問やディスカッションがその場でできる
- 決まった時間に参加する必要がある
ライブ配信型は受講者と講師が双方向でやりとりでき、「その場で参加する生授業」といった形式です。
スタジオ収録型・ライブ配信型・ハイブリット型の特徴
スタジオ収録型・ライブ配信型・ハイブリット型の特徴を以下に表でまとめます。
パターン名 | 概要 | 特徴・メリット | 向いている用途 |
スタジオ収録型 | 専用スタジオや静かな環境で、講師・ナレーション・スライドなどを事前に録画・編集したコンテンツ | ✔ 品質の高い映像が作れる | 基礎講座や専門知識の体系的な解説・長期間使える教材 |
ライブ配信型 | ZoomやTeamsなどを使い、リアルタイムで受講者と双方向にやり取りする形式 | ✔ 質問対応やディスカッションが可能 | 社内研修やウェビナー・参加型ワークショップ |
ハイブリッド型 | 収録済みの教材を事前配信し、後日ライブセッションで質疑応答や演習を行う形式 | ✔ 学習効率と柔軟性の両立 | 新入社員研修や技術トレーニング・反転学習 |
eラーニング作成ツール

オンライン教育を成功させるためには、eラーニング作成ツールの活用が不可欠です。eラーニング作成ツールは、受講者にとってわかりやすく、理解しやすい教材やテストを制作する手助けとなります。ここでは代表的なeラーニング作成ツールをご紹介します。
eラーニング教材作成に特化したツールについての解説
eラーニング教材を作成するツールにはさまざまな種類がありますが、ここでは教材作成に特化したツールをご紹介します。
たとえば、Articulate Storylineはスライド形式でクイズや分岐シナリオなど、インタラクティブな教材を作るのに適しています。Adobe Captivateはソフトの操作説明などをシミュレーション形式で作れる、高機能なツールです。iSpring SuiteはPowerPointと連携して簡単に教材を作れるので、初心者にも扱いやすいのが特徴です。
動画中心の教材を作るなら、Camtasiaがおすすめで、画面録画やナレーション付きの動画を手軽に編集できます。Lectoraは大規模で複雑な教材を作成するのに向いており、柔軟なカスタマイズが可能です。H5Pはブラウザ上で使える無料ツールで、インタラクティブなコンテンツが簡単に作れます。
このように、それぞれのツールには得意分野があるため、目的やスキルレベルに応じて選ぶことがポイントです。
eラーニング作成ツールの特徴と選定ポイント
eラーニング作成ツールの特徴と選定ポイントを表でまとめると以下のとおりです。
ツール名 | 主な特徴 | 向いている用途 | 操作の難易度 | 選ぶ際のポイント |
Articulate Storyline | スライド型・クイズ・分岐シナリオが作成可 | インタラクティブ教材、研修教材 | 中〜上級 | 複雑なシナリオやクイズを作りたい場合に適している |
Adobe Captivate | シミュレーション・レスポンシブ対応 | ソフト操作解説、多言語対応教材 | 上級 | 高度な操作や多機能性を求める場合におすすめ |
iSpring Suite | PowerPointと連携、簡単操作 | スライド教材、ナレーション付き教材 | 初〜中級 | PPTに慣れている人に最適。短期間で教材化可能 |
Camtasia | 画面録画+動画編集が可能 | 動画教材、操作説明動画 | 初〜中級 | 動画中心の教材を作成したいときに便利 |
Lectora | 大規模教材向き、高度な制御が可能 | 大企業の研修、多ページ教材 | 中〜上級 | 柔軟性・拡張性を重視する場合に適している |
H5P | 無料で使える、対話型コンテンツが豊富 | クイズやミニ教材、Web教材 | 初級 | 無料で手軽にインタラクティブ教材を作りたい場合 |
eラーニングシステムの利用

eラーニング教材を作成したら、学習進捗を管理できるシステムに搭載して利用するのがおすすめです。
ここでは、eラーニングシステムの利用について解説します。
eラー二ングシステムの機能
eラーニングシステムの機能と特徴を表でまとめます。自社で必要な機能を確認し、システムを導入する際の参考にしてください。
機能カテゴリ | 主な内容 |
教材配信 | 動画、PDF、クイズ、スライドなどの配信 |
受講者管理 | 受講者の登録・グループ分け |
進捗・成績の確認 | 学習状況・テスト結果の自動集計 |
テスト・クイズ作成 | 理解度確認テストの作成と実施 |
レポート出力 | 学習データをCSVやグラフで出力 |
eラーニングを用いた社内教育に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
本記事では、eラーニングの作成方法やおすすめツールをご紹介いたしました。
「SAKU-SAKU Testing」は多くの機能が充実しているeラーニングシステムです。
自社オリジナルの研修内容や問題を搭載し、受講者に応じてコンテンツの出し分けができるので、簡単に受講者のニーズにあった研修を実施することが可能です。
ぜひLMSとして「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。
さらに、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新人社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ぜひ「サクテス学びホーダイ」をご活用ください。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。