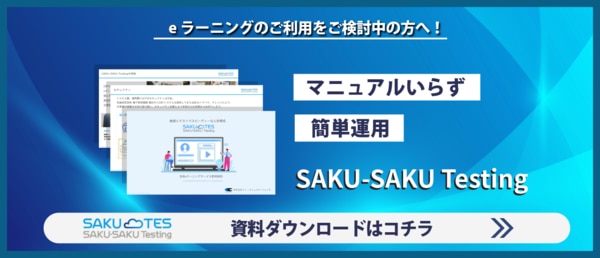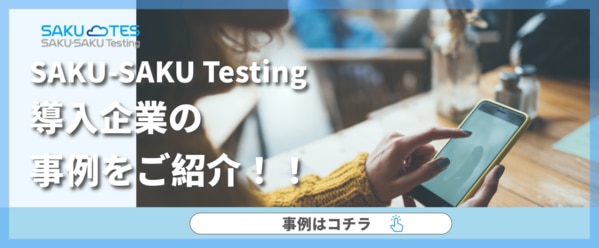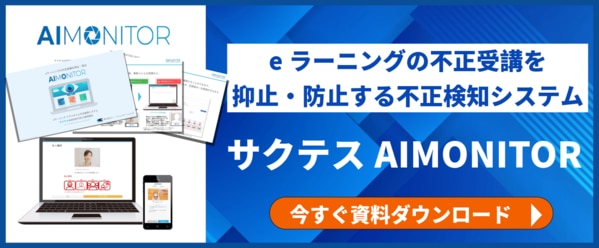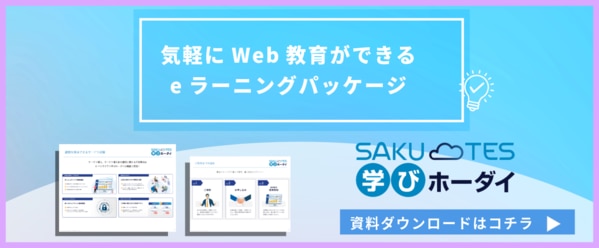定量評価とは?活用方法と部門別の具体例、定性評価との違いを解説

定量評価とは、業績を数値に基づいて評価する方法であり、特に客観性を重視する手法です。この方法を導入することで、企業は明確な基準を設けられ、従業員の成果を具体的に把握することができます。
定量評価は、数値による透明性が高いため、評価結果に対する納得感が得られやすく、モチベーションの向上にもつながります。さらに、定量評価は組織全体のパフォーマンスを分析する際にも役立ち、どこに課題があるのかを明確に把握する手段としても機能します。このように、定量評価は人事評価の中で重要な役割を果たす手法です。目標達成を効率的に促進するための効果的な活用方法について、本記事で詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.定量評価の基本
- 2.定量評価の具体例
- 2.1.1. 教育・研修分野の定量評価
- 2.2.2. マーケティング活動の定量評価
- 2.3.3. 業務改善・生産性評価
- 2.4.4. 顧客満足度(CS)
- 2.5.5. 品質管理
- 3.定性評価の基本
- 3.1.定性とは
- 3.2.定性評価とは
- 3.3.定性評価の評価基準と特徴
- 4.定性評価の具体例
- 4.1.1. 教育・研修における定性評価
- 4.2.2. マーケティング・商品開発での定性評価
- 4.3.3. 人事・採用評価での定性評価
- 4.4.4. UX・UIデザイン評価(ユーザー体験)
- 4.5.5. カスタマーサポート・顧客対応の定性評価
- 5.定量評価と定性評価の違い
- 5.1.評価基準の違い
- 5.2.定量評価と定性評価の使い分け
- 5.3.定量と定性が混在する場合の対策
- 6.定量評価のメリット
- 6.1.メリット①評価基準の明確化
- 6.2.メリット②公平性のある評価ができる
- 6.3.メリット③目標設定がしやすい
- 7.定量評価のデメリット
- 8.定量評価を効果的に活用する方法
- 8.1.適切な目標数値の設定
- 8.2.評価後のフィードバック
- 8.3.目標管理を行う
- 9.定量評価を導入する際のポイント
- 9.1.SMARTの法則を活用した目標設定
- 9.2.短期間での目標見直し
- 9.3.KPIとKGIを活用した評価体制
- 10.部門別活用の具体例
- 10.1.営業部門
- 10.2.開発・エンジニア部門
- 10.3.カスタマーサポート部門
- 10.4.マーケティング部門
- 10.5.管理部門(人事・経理・法務など)
- 11.効果的・効率的に社員の育成を行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
定量評価の基本

ここでは、そもそも「定量」とは何か、「定量評価」とは何かについて解説します。
定量とは
定量とは、ものごとを数値で測れる形にしたものを意味します。数量や割合、スコア、時間などの客観的に測定可能な情報を扱うのが特徴です。
反対の概念は「定性」で、こちらは感情・意見・印象など数値化しにくい主観的情報を扱います。
定量の特徴
定量の特徴を表にまとめると以下のとおりです。
特徴 | 内容 |
測定可能 | 数字や記録として表現できる |
客観性がある | 誰が見ても同じように判断できる |
比較ができる | 時間や他のデータと比較して効果を検証できる |
分析しやすい | 統計処理やグラフ化などが可能 |
定量評価とは
定量評価とは、業績や成果を数値で表現し、客観的に評価する手法のことです。
この手法では、売上や業務の進捗状況といった具体的な数値データを活用するため、従業員のパフォーマンスや組織全体の成果を明確に把握することが可能です。
例えば、売上成績や目標達成率などの指標を基に評価を行うことで、主観的な感情や偏りを排除し、より公平で透明性の高い評価を実現します。定量評価とは、データに基づいた評価体系を構築することで、従業員が納得しやすい基準を提供すると同時に、組織全体の業務状況を可視化し、改善点を明確にするための重要な手段です。
定量評価の具体例
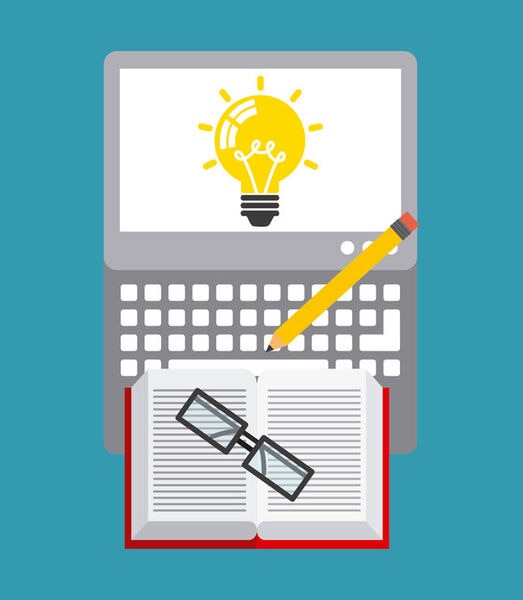
ここでは、分野別における定量評価の具体例について解説します。
1. 教育・研修分野の定量評価
テストの得点:研修前後のテストの平均点、正答率の向上率。
例:事前テスト平均点60点 → 事後テスト平均点85点(+25点)
受講完了率:指定されたコースを完了した受講者の割合。
例:全100人中90人が完了 → 完了率90%
理解度アンケートのスコア:5段階評価の平均点など。
例:理解度「非常に高い」〜「低い」の平均スコアが4.3/5
2. マーケティング活動の定量評価
クリック率(CTR):広告表示回数に対するクリック数の割合。
例:表示1,000回中100クリック → CTR = 10%
コンバージョン率:サイト訪問から成果(購入や登録)に至る割合。
例:訪問500人中25人が購入 → CVR = 5%
3. 業務改善・生産性評価
作業時間短縮率:業務効率化による作業時間の減少。
例:作業時間 10時間 → 6時間 → 短縮率40%
エラー発生件数の推移:
例:月間エラー数 30件 → 10件(-20件、66%減)
4. 顧客満足度(CS)
NPS(ネット・プロモーター・スコア):顧客ロイヤルティを測るための指標。顧客が企業の製品やサービスを友人や同僚にどの程度強く推薦したいと思うか、という推奨度
例:「あなたはこのサービスを他人にすすめますか?」のスコアが+42
CSアンケートの平均スコア:顧客満足度のアンケートなど。
例:5点満点中、4.5点
5. 品質管理
不良率:製品やサービスの中で不良と判定されたものの割合。
例:生産数1,000個中、不良品20個 → 不良率2%
定性評価の基本

ここでは、定性とは何か、定性評価とは何かについて解説します。
定性とは
定性とは、ものごとを数値ではなく「質的」な特徴や性質として捉える評価方法です。つまり、感想・意見・印象・態度・考え方などの、人の主観や背景を含む情報を扱います。
反対は「定量」で、数値で表せる客観的な情報を扱います。
定性評価とは
定性評価とは、数値化が難しい特性や能力を評価するための手法です。この評価方法は、一般的に従業員のコミュニケーション能力やリーダーシップ、創造力など、幅広い側面を把握することを目的としています。定性とは、具体的な数値では示せない意味や特性を評価する点に特徴があります。数値化されない情報は、主に面接やフィードバックセッション、同僚からの推薦状などから収集され、これらのデータを活用して対象となる個々の特性やスキルを浮き彫りにします。定性評価を通じて得られる深い洞察により、より適切で効果的な人材育成や業務配置が可能となります。
このように、定性評価の意味は、単なる数値分析では捉えきれない要素を理解し、組織全体の成長につなげる重要なプロセスであると言えます。
定性評価の評価基準と特徴
定性評価の基準は、具体的な数値ではなく、観察やフィードバックを通じて形成されることが一般的です。この評価では、従業員の態度、問題解決力、協調性など、数値化が難しい要素が重視されます。そのため、評価基準の設定においては、長期的なパフォーマンスの向上を見据えることが重要です。特徴として、評価者の主観的な判断が影響を与える可能性があるため、信頼性の高い評価者を選定する必要があります。また、この評価方式では、他者との比較ではなく、従業員一人ひとりの成長や改善に焦点を当てることが特徴的です。信頼性の高い基準を設けることで、公平かつ正確な評価が可能となり、企業全体の成長に寄与することが期待されます。
定性評価の具体例

定性評価の具体例を以下に分野別にわかりやすく紹介します。
1. 教育・研修における定性評価
具体例:
「教材の内容が現場に即していて理解しやすかった」
「講師の説明が丁寧で、質問しやすい雰囲気だった」
「グループワークが印象に残り、学んだ内容を実践で使えそう」
➡ 数値にはしづらい「学びの質」や「実用性」、「感情的な印象」などを捉えるために使います。
2. マーケティング・商品開発での定性評価
具体例:
「デザインがスタイリッシュで高級感がある」
「操作が直感的で初めてでも迷わなかった」
「広告のコピーが共感できたので、使ってみようと思った」
➡ 消費者の「感覚」「動機」「感情」を分析することで、購買行動の背景が見えてきます。
3. 人事・採用評価での定性評価
具体例:
「プレゼン時の受け答えが誠実で信頼感がある」
「課題に対する論理的思考力が高く、柔軟な発想も見られた」
「面接中に自己理解が深いと感じられる発言が多かった」
➡ 面接の印象や人物像の評価など、定量的には測れない部分を補完します。
4. UX・UIデザイン評価(ユーザー体験)
具体例:
「ボタンの位置が自然で、迷わず操作できた」
「色使いが落ち着いていて、長時間使っても疲れない」
「フォーム入力が簡単で、ストレスを感じなかった」
➡ ユーザーの直感的な使用感や心理的な快・不快など、数値化できないリアルな声を重視します。
5. カスタマーサポート・顧客対応の定性評価
具体例:
「オペレーターの対応が親身で安心感があった」
「こちらの話をしっかり聞いてくれて丁寧だった」
「対応が早く、必要な情報を的確に案内してくれた」
➡ 単なる応答時間や件数だけでなく、感情的な満足度を把握するのに効果的です。
定量評価と定性評価の違い

定量評価、定性評価についてそれぞれ解説してきました。ここでは、両者の違いについて解説します。
両者はそれぞれ異なる強みをもっており、役立つ場面が異なるため、状況に応じて活用するのが重要です。
評価基準の違い
評価基準においては、定量評価が数値を基準として重視するのに対し、定性評価は観察やフィードバックを基準として中心に据えています。具体的には、定量評価では、売上高や達成率など、数値化できる具体的な結果が評価の基準となります。一方で、定性評価では、職場でのコミュニケーションの質、チームワークの強さ、業務に対する主体的な姿勢や意欲など、数値には表しにくい要素が重視されます。このように、評価基準の違いによって注目するポイントや得られる洞察の種類も大きく変わるのが一般的です。したがって、適切な評価基準の選定が、評価結果の有用性を左右する重要な要素となっています。
定量評価と定性評価の使い分け
定量評価と定性評価を適切に使い分けることは、効果的な人事管理において非常に重要です。特に、営業職や生産部門のように成果が数値で把握しやすい業務では、定量的な評価が効果的に機能します。
一方で、クリエイティブなプロジェクトやチームの協力が鍵となる職種においては、業務の質やコミュニケーション能力を重視した定性評価が適しています。それぞれの業務特性や目指す結果に応じて、定量評価と定性評価を組み合わせることで、よりバランスの取れた評価方法を実現できます。こうしたアプローチにより、個人の成果だけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上につながる可能性が高まります。
定量評価と定性評価を表にまとめると以下の通りです。
項目 | 定量評価(Quantitative) | 定性評価(Qualitative) |
評価対象 | 数値で表せる成果・行動・実績 | 数値では測れない態度・姿勢・人柄・ポテンシャル |
表現形式 | スコア(点数)、件数、割合、目標達成率など | 言葉による記述、フィードバックコメント |
データ例 | - 売上額、達成率 - 業務処理件数 - 出勤率- 提案数 | 「チームワークが良い」- 「顧客との信頼関係が強い」- 「積極的に学ぶ姿勢がある」 |
手法 | - OKR/KPI達成度 - 業績指標評価 - 評価シートの点数 | 上司や同僚による記述式評価- 360度評価の自由記述欄 |
特徴 | 客観性が高く、比較・数値管理に適している | 主観が含まれるが、人間性や将来性の把握に有効 |
評価しやすさ | 評価が明確でしやすい | 評価者のスキルや視点に左右されやすい |
課題・注意点 | 数字だけでは背景やプロセスが評価されにくい | 評価基準があいまいになりやすく、評価者間のバラつきが出る |
活用シーン例 | - インセンティブ計算 - 業績評価 | キャリア面談- 適性配置検討- 育成方針の策定 |
定量と定性が混在する場合の対策
定量評価と定性評価が混在する場面では、それぞれの特徴を正しく理解し、バランスを考慮した上で目的に合った指標を選ぶことが求められます。具体的には、数値を基に定量的に評価する方法を活用しつつ、現場での観察やフィードバックを通じた定性評価も取り入れることで、多角的な視点を維持することが重要です。特に、定量評価で使用する指標やデータは定期的に見直し、適用性や精度をチェックすることで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
一方で、定性評価は日常的なコミュニケーションや現場での観察を通じて、柔軟かつ包括的に行うべきです。これらの結果をチーム全体と共有し、透明性を高めることで、従業員の理解を深め、評価プロセスへの信頼感を醸成することができます。このように、多角的で透明性のある評価を通じて、公平性の確保や評価の精度向上を図り、組織全体の一体感とパフォーマンス向上に貢献することが期待されます。
定量評価のメリット

定量評価には、多くのメリットがあります。
ここでは、定量評価のメリットについて解説します。
メリット①評価基準の明確化
定量評価の最大の利点の一つは、評価基準が明確であることです。
具体的な数値目標や指標が設定されることで、各従業員が自身の評価がどのような基準で行われるのかを直感的に理解しやすくなります。
例えば、売上目標やプロジェクトの達成率といった数値で表される指標を通じて、何を達成すれば高く評価されるのかが明確に把握できます。このような評価基準の明確さは、従業員にとってモチベーションを高めるだけでなく、組織全体としての目標達成への方向性も共有されやすくなり、より良い成果を追求する土台を形成します。
メリット②公平性のある評価ができる
定量評価は、公平な評価を実現するための強力な道具となります。主観的な判断が介在しにくく、数値に基づいた結果により、評価が一貫して行われるため、公平性を保つことが可能です。
また、定量的なデータを活用した評価システムを導入することで、さらなる効率化と透明性が実現され、評価プロセスに対する不満や疑念が軽減されます。これにより、従業員全体が感じる公平感が高まり、社内での信頼関係の構築にも大きく貢献します。特に、成果によって報酬が左右される業種では、公平性のある評価システムの重要性が一層際立ちます。
メリット③目標設定がしやすい
目標設定が容易である点は、定量評価の重要な特徴の一つです。具体的な数値が示されることで、従業員は目標達成に向けたやり方を具体的に理解し、どのような努力が必要かを明確に把握できます。数値化された目標があると、進捗を定期的に確認しやすくなるだけでなく、必要に応じてやり方を調整することも可能です。さらに、この仕組みにより、短期的な目標と長期的な目標を連動させることが簡単になり、各フェーズでの進捗を効果的に管理することができます。結果として、明確な数値目標を設定することが、目標達成への効果的なやり方を導き出し、それを支える道筋を築く重要な役割を果たします。
定量評価のデメリット

定量評価には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
ここでは、定量評価のデメリットについて解説します。
デメリット①プロセスが評価されにくい
定量評価では、数字に表れた成果に重きが置かれるため、成果を達成するまでのプロセスが評価されにくい傾向があります。
例えば、チームでの協力や問題解決に向けた努力が成果には直結しない場合、それらの重要な要素が無視されることがあります。業務における苦労や挑戦が数値で表現されないため、評価対象とならず結果的に不公平感を生じることも考えられます。プロセスの評価を軽視することは、従業員の成長や改善意欲を損なう恐れもあります。
デメリット②職種や業務による公平性の課題
職種や業務内容によっては、定量評価を適用することが難しい場合があります。
特に、クリエイティブな業務やサービス業では、数値化できる評価基準が乏しく、評価を行う際に公平性が損なわれるリスクが存在します。同様に、エンジニアのような専門性の高い職種においても、単に生産性や作業スピードといった指標だけでは業務の重要性や複雑さを正しく評価するのが難しい場合があります。たとえば、営業職では明確な売上や契約数を基に評価を行うことが可能ですが、カスタマーサポートやクリエイティブチーム、さらにはエンジニア業務では、客観的な数値だけで業務の本質を把握することは困難です。結果として、そのような状況では従業員が正当に評価されないと感じることがあり、モチベーションの低下やパフォーマンスの減少といったリスクを伴う場合があります。
このような問題を解決するためには、業務ごとの特性を十分に理解した上で、数値と質的評価をバランス良く組み合わせた適切な評価制度を構築することが重要です。
定量評価を効果的に活用する方法

定量評価を効果的に活用するためには、適切な手法や方法を取り入れつつ、いくつかの重要なポイントを押さえることが必要です。
ここでは、定量評価の活用方法について解説します。
適切な目標数値の設定
目標数値の設定は、定量評価を成功させるためにとても重要です。適切な目標を設定することにより、従業員は具体的な成果を目指して効果的に行動することができます。
目標数値の設定では、SMARTの法則を活用することが特に有効です。
目標は「具体的(Specific)」「測定可能(Measurable)」「達成可能(Achievable)」「関連性(Relevant)」「期限付き(Time-bound)」であるべきであり、このフレームワークを基にした目標の設定により、達成度合いが明確になります。
その結果、従業員は自分の役割や方向性を明確に把握し、無駄のない効率的な行動が可能になります。目標を戦略的に設定することで、個人やチーム全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
評価後のフィードバック
評価後のフィードバックは、定量評価を効果的に活用し、組織全体のパフォーマンスを向上させるための不可欠な要素です。
適切なフィードバックを通じて、従業員は自らの成果を正確に理解し、改善すべきポイントを明確に把握できます。フィードバックの際、単に評価結果を通知するだけでなく、その結果がどのようなプロセスを経て導かれたのかを詳細に話し合うことが重要です。このような双方向のコミュニケーションは、従業員が納得感を持ちやすくするだけでなく、さらなる成長に向けた主体的な行動を促します。また、改善点の指摘だけでなく、ポジティブなフィードバックを積極的に取り入れることは、従業員の自己効力感を高め、モチベーションの向上にも寄与します。質の高いフィードバックと良好なコミュニケーションの実現が、組織の持続的な成功を支える鍵となります。
目標管理を行う
目標管理には、いくつかの具体的な手法が存在します。
例えば、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に進捗をレビューする方法が一般的です。これにより、目標達成までの進捗を管理部門を含めた関係者全体で可視化し、必要に応じて計画を修正することが可能です。また、月次や四半期ごとに目標の見直しを行う手法も有効であり、これによって変化する環境に対して柔軟に対応しながら効果的に目標へと近づけます。
加えて、管理部門が主導となる形で、管理者と従業員が密にコミュニケーションを取ることで、各メンバーの目標に対する理解とコミットメントを向上させることが期待されます。これらの手法を活用することで、組織全体が一丸となり、目標の達成に向けた効率的な取り組みを進めることができるでしょう。
定量評価を導入する際のポイント

定量評価を導入するためには、いくつかの重要なポイントをおさえることが必要です。
ここでは、定量評価導入時のポイントについて解説します。
SMARTの法則を活用した目標設定
SMARTの法則を活用することで、目標設定の手法がより効果的になります。
Sは「Specific」(具体的)、Mは「Measurable」(測定可能)、Aは「Achievable」(達成可能)、Rは「Relevant」(関連性)、Tは「Time-bound」(期限付き)を表します。
この5つの要素を踏まえた目標設定を行うことで、実現可能な目標を明確に定義でき、具体性や達成基準を持った計画を立てることが可能となります。この手法により、従業員が何を目指すべきかを明確に理解し、進捗の測定や評価を効率的に行うことができます。また、実際に達成された成功例を共有することで、モチベーション向上にもつなげやすくなります。
短期間での目標見直し
短期間での目標見直しは、目標の達成度を定量的に評価し、業務効率を向上させるために重要です。
市場環境や業務状況が常に変化している中では、最初に設定した目標が適切でない場合もあるため、柔軟に対応することが求められます。
例えば、四半期ごとや月次で目標の達成状況を確認すると、現状に即した具体的な目標を再設定しやすくなります。このような定期的な見直しを行うことで、従業員には明確な方向性が示されるだけでなく、建設的なフィードバックを受ける機会が増え、モチベーションの向上や自己成長の促進にもつながります。さらに、業務の柔軟性や適応力を高めるために、こうした見直し作業は欠かせない要素といえます。目標の設定や修正を計画的に行うことで、個人と企業全体のパフォーマンス向上を期待できるでしょう。
KPIとKGIを活用した評価体制
KPI(重要業績評価指標)とKGI(重要目標達成指標)を活用することで、評価体制を効果的に整備することが可能です。KGIは最終的な目標の達成度を測定するための指標であり、組織が目指すべき最終的な成果を明確に定義します。一方、KPIはその達成に向けた進捗を可視化する中間指標として機能し、目標に向けた具体的な行動や成果を示します。
これらの指標を適切に設定し運用することで、組織全体の目標と個々の業績を明確に結びつけることができます。これにより、従業員は自身の業務が組織の成果にどのように寄与しているかを理解しやすくなります。また、進捗状況が明確に見えることで、業務に対するモチベーションが向上し、効率的な働き方を促進します。
さらに、これらの指標を定期的に見直し、必要に応じて調整することで、組織の環境や目標の変化に柔軟に対応できる評価体制を構築することが可能です。このようにKPIとKGIを適切に活用した評価体制は、組織全体の成長と目標達成を力強くサポートします。
部門別活用の具体例
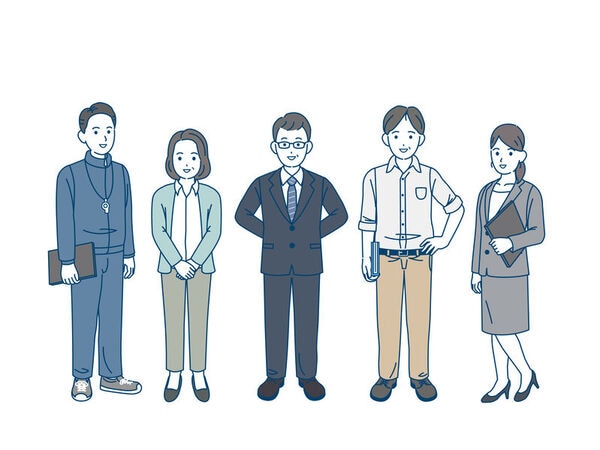
ここでは、人事評価における「定量評価」の活用を部門別にまとめた具体例をご紹介します。部門によって評価対象や目的が異なるため、それに合わせて指標設計や活用方法が変わります。ご参考にしてみてください。
営業部門
営業部門は、売上や活動量が数値化しやすく、目標管理(MBO/KPI)と連携しやすいです。
成果だけでなく、行動量や効率性の評価も組み込むことで育成につなげやすくなります。
評価項目 | 定量指標例 |
売上実績 | 月間売上金額、契約数、利益率 |
顧客対応 | 顧客訪問件数、提案書提出数 |
効率性 | 1契約あたりの平均商談回数 |
開発・エンジニア部門
開発分は、単なるアウトプット量だけでなく、品質や協働の指標も取り入れるのが重要です。
定性評価(技術的な工夫、知識共有、コードの読みやすさなど)と合わせて運用するのがおすすめです。
評価項目 | 定量指標例 |
生産性 | リリース数、完了タスク数、コード量 |
品質 | バグ件数、レビュー修正回数、テスト通過率 |
対応スピード | インシデント対応時間、リードタイム |
カスタマーサポート部門
顧客対応の質が問われるため、スピードと満足度のバランスが重要です。
定性面では「丁寧な対応」「感謝の声」などを評価コメントで補完するといいでしょう。
評価項目 | 定量指標例 |
対応件数 | 1日あたりの対応数、処理時間 |
顧客満足度 | アンケートスコア、NPSなど |
応答速度 | 初回応答時間、平均対応時間 |
マーケティング部門
効果測定がしにくい業務もあるため、中間成果(KGI/KPI)を明確化するのがポイントです。
チーム貢献度や創造性などは定性評価で補完するといいでしょう。
評価項目 | 定量指標例 |
施策の成果 | リード獲得数、CV率、PV数 |
企画実施件数 | キャンペーン数、資料作成数 |
業務効率 | タスク処理数、納期遵守率 |
管理部門(人事・経理・法務など)
サポート部門の成果は「信頼性」「安定性」「正確性」で数値化します。
組織への貢献やリスク管理意識などは定性コメントを活用するのがおすすめです。
評価項目 | 定量指標例 |
処理件数 | 給与計算件数、契約書チェック数 |
正確性 | ミス率、修正依頼数 |
期限遵守 | 締切遵守率、対応リードタイム |
効果的・効率的に社員の育成を行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」は、社員教育に活用することができるLMSです。
自社で作成した教材を簡単に搭載できるため、自社作成の研修教材を用いた社員教育が可能です。
さらに、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新入社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ぜひ「サクテス学びホーダイ」をご活用ください。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・新入社員側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。