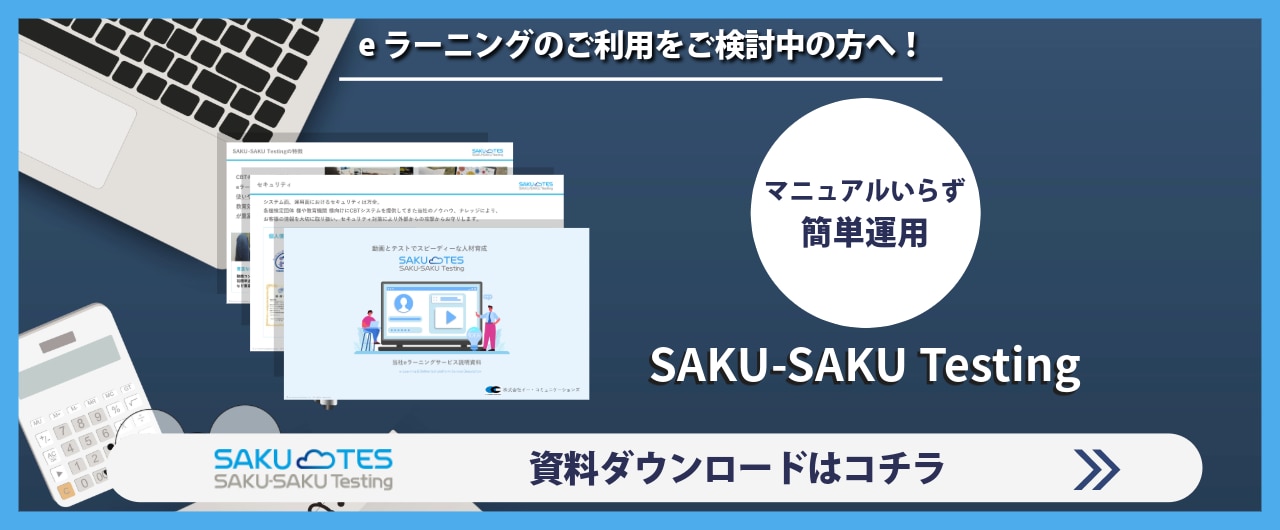モラルハラスメント(モラハラ)とは?パワハラとの違いや具体例・対処法を解説

モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度で相手の尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める行為を指します。その本質を理解することは、健全で安心できる職場環境を維持するうえで欠かせません。
本記事では、しばしば混同されるパワーハラスメントとの違いを整理し、職場や家庭で実際に起こり得る具体例を紹介します。
あわせて、企業が取り組むべき予防策や、問題が発生した際の対応方法についても解説し、日々の職場づくりに役立つ知識をお届けします。
目次[非表示]
- 1.モラルハラスメント(モラハラ)とは言葉や態度による精神的な暴力のこと
- 2.パワハラとの違いは?3つの観点から比較解説
- 2.1.違い①:優越的な関係性の有無
- 2.2.違い②:身体的な攻撃を含むかどうか
- 2.3.違い③:行為が行われる場所や関係性
- 3.モラルハラスメントの具体的な言動例
- 3.1.人格を否定するような言動
- 3.2.意図的に孤立させる行動
- 3.3.業務上の不当な扱い
- 3.4.プライベートへの過剰な干渉
- 4.モラルハラスメントの加害者に見られがちな4つの特徴
- 5.モラルハラスメントを放置するリスク
- 6.職場におけるモラルハラスメントを予防するための対策
- 6.1.ポリシー・ガイドラインの整備
- 6.2.相談・対応体制の整備
- 6.3.教育・啓発の導入
- 6.4.職場環境の改善
- 7.モラルハラスメントが発生したときの対応プロセス
- 7.1.初動対応(記録収集、ヒアリング、事実確認)
- 7.2.被害者ケアと支援制度(休職、配置転換、相談支援など)
- 7.3.加害者に対する処分・改善措置
- 7.4.再発防止策とフォローアップ(モニタリング、職場風土改善)
- 8.まとめ
- 9.eラーニングを活用したハラスメント防止・コンプライアンス研修なら「SAKU-SAKU Testing」
モラルハラスメント(モラハラ)とは言葉や態度による精神的な暴力のこと

モラルハラスメント、通称モラハラは、言葉や態度、身振りなどによって、相手の人格や尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為全般を意味します。
この概念はフランスの精神科医であるマリー=フランス・イルゴイエンヌによって提唱されました。
日本の厚生労働省による直接的な定義はありませんが、精神的な攻撃が中心となる点で、パワーハラスメントの一類型とも考えられます。
平易な言葉で言い換えれば「精神的な暴力やいじめ」であり、身体的な暴力とは異なり目に見える形で証拠が残りにくいのが特徴です。
パワハラとの違いは?3つの観点から比較解説

モラルハラスメントとパワーハラスメントは、どちらも精神的苦痛を与える点で共通しますが、成立要件や対象範囲には違いがあります。
両者は混同されがちですが、法律上の扱いも異なるため理解が必要です。ここでは「優越的関係の有無」「身体的攻撃の有無」「発生する場面や関係性」という3つの観点で整理します。
違い①:優越的な関係性の有無
パワーハラスメントには、上司と部下のように職務上「優越的な関係」が前提となります。
一方、モラルハラスメントはその前提を必要とせず、同僚同士、部下から上司、顧客や取引先から従業員へなど、立場に関係なく成立します。対等または被害者側が優位に見える関係性でも成立しうる点で、より広い範囲を対象としています。
違い②:身体的な攻撃を含むかどうか
パワーハラスメントの概念には、精神的な攻撃に加え、殴る、蹴るといった直接的な身体的攻撃も含まれます。労働施策総合推進法(パワハラ防止法)におけるパワーハラスメントの6類型のうちの一つとして「身体的な攻撃」が明記されています。
これに対して、モラルハラスメントは、主に精神的な攻撃に特化した概念です。ただし精神的ダメージは身体的暴力に匹敵する場合もあります。
違い③:行為が行われる場所や関係性
パワーハラスメントは、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)で規制されている通り、主に会社などの「職場」において、業務との関連性の中で発生するものが対象となります。
一方で、モラルハラスメントという概念は、職場に限定されず、夫婦や親子、友人関係など私生活でも発生します。職場内外を問わず広く適用される点が大きな違いです。
モラルハラスメントの具体的な言動例

モラハラは、言動によって相手を精神的に追い詰める行為です。職場でどのような行為が該当しうるのかを知ることは、早期発見や予防のために重要です。以下に代表的なケースを紹介します。
人格を否定するような言動
「こんなこともできないのか」など能力を軽視する発言
社員全員の前で執拗に叱責する
本人のいない場で悪口や陰口を繰り返す
意図的に孤立させる行動
挨拶を無視する
業務連絡のメールを送らない、会議に呼ばない
特定の社員を意図的に雑談や飲み会から外す
業務上の不当な扱い
実現困難な目標を押し付ける
達成できないことを理由に侮辱する
明らかに業務と関係のない雑務ばかりを割り当てる
プライベートへの過剰な干渉
私生活や家族のことをしつこく詮索する
本人の同意なくプライベートな情報を周囲に言いふらす
モラルハラスメントの加害者に見られがちな4つの特徴

モラハラを行う人には、共通する心理や行動パターンが見られます。多くの場合、本人は自覚せずに行っていることも少なくありません。加害者の特徴を理解しておくことは、問題を早期に察知し、適切な対応につなげる上で重要です。ここでは代表的な4つの特徴を紹介します。
特徴①:自分が常に正しいと思っている
モラハラを行う人は自分の考えや価値観が常に正しいと信じているため、他者の意見を受け入れることが難しく、自分の意見に従わない相手を攻撃することがあります。相手の感情や状況を考慮せず、自分の正当性を主張する傾向があります。
特徴②:自尊心が高く他人を見下す傾向がある
モラハラを行う人は高すぎる自尊心と不安定な内面を抱えています。そのため、自分の優位性を保とうとし、他者の欠点や失敗を執拗に攻撃したり見下したりする傾向が見られます。他人の成功を妬み、相手を貶めることで自己肯定感を得ようとすることも、モラハラの動機となる場合があります。
特徴③:自分の非を認めず他人のせいにする
モラハラを行う人は問題発生時に自身の非を認めず、責任を他者に転嫁しがちです。自分が常に正しいと考え、相手に責任を押し付けることで自己を正当化します。そのため、心から反省して謝罪することはほとんどなく、被害者をさらに精神的に追い詰める要因となります。
特徴④:ささいなことで機嫌が変わりやすい
モラハラを行う人は、感情の起伏が激しく、ささいなことで機嫌が急変する傾向があります。周囲は顔色をうかがうことになり、強いストレスを感じます。予測不能な態度は、被害者に罪悪感を植え付け、心理的に支配しやすく、安定した人間関係を困難にします。
モラルハラスメントを放置するリスク

職場でモラハラを放置すると、企業にとってさまざまなリスクを招く可能性があります。
まず、被害を受けた従業員は強いストレスからメンタルヘルス不調に陥りやすく、業務パフォーマンスの低下や休職、場合によっては離職につながることがあります。その結果、企業が大切な人材を失う危険性があります。
また、ハラスメントが見過ごされる環境では、従業員全体の士気が下がり、チームワークが損なわれ、生産性の低下を招く可能性があります。
さらに、企業は従業員への安全配慮義務を負っているため、適切に対応しなければ法的責任を問われ、損害賠償に発展するリスクも否定できません。社会的信用やブランドイメージが損なわれる可能性もあるため、早期の対策が求められます。
職場におけるモラルハラスメントを予防するための対策

モラハラを未然に防ぐためには、企業が組織全体で取り組む姿勢を示すことが重要です。個人の資質に責任を押し付けるのではなく、組織的な課題として対策を講じる必要があります。
予防のための重要な軸は、以下の3つです。
明確な方針の策定と周知徹底
安心して利用できる相談窓口の設置
迅速かつ公正に対応できる体制の整備
ここでは、これら3つの軸に基づいて、具体的な取り組みの方法を解説します。
ポリシー・ガイドラインの整備
モラハラを含むハラスメント防止の第一歩は、会社として許さないという明確な方針を策定し、それを就業規則などの社内規程に具体的に落とし込むことです。
例えば、ハラスメントの定義や禁止される言動の具体例を明記し、違反した場合には懲戒処分の対象となることを明確にします。
この方針や対処内容は、社内報やイントラネットなどを活用して全従業員に周知し、組織の共通認識としなければなりません。
また、定期的にハラスメント防止に関する研修を実施し、研修資料などを通じて管理職や一般従業員の理解を深めることも有効です。
厳正な対応を行うという会社の姿勢を示すことが、強力な抑止力として機能します。
相談・対応体制の整備
モラハラ被害者が一人で抱え込まずに済むよう、実効性のある相談窓口の設置が極めて重要です。
相談窓口は、人事部門などが担当する社内窓口のほか、プライバシー保護の観点から外部の専門機関に委託することも有効な選択肢となります。
相談担当者には高度な専門性が求められるため、守秘義務の遵守や傾聴スキル、中立的な立場での事実確認の方法などについて、定期的な研修を実施する必要があります。
相談受付から事実調査、解決に至るまでの対応フローをマニュアルとして整備し、どのような相談にも迅速かつ適切に対処できる社内体制を構築しておくことが求められます。
教育・啓発の導入
ハラスメントを許さない組織文化を醸成するためには、全従業員に対する継続的な教育と啓発活動が不可欠です。
例えば、新入社員研修や階層別研修のプログラムにハラスメント防止研修を組み込み、定期的に実施します。
研修の内容は、どのような言動がモラハラに該当するかの具体例、被害者や会社に与える深刻な影響、関連する社内規程の解説などを含むべきです。
特に管理職に対しては、部下からの相談を受けた際の適切な対応方法や、自身のマネジメントがハラスメントと受け取られないための指導も重要です。
これにより、従業員一人ひとりの意識を高め、ハラスメントの発生を未然に防ぎます。
職場環境の改善
モラルハラスメントは、特定の個人の資質だけでなく、職場環境に起因して発生することも少なくありません。
特に、コミュニケーションが希薄で、過度な業務負荷や長時間労働が常態化している職場は、ハラスメントの温床となりやすい傾向があります。
これを改善するため、定期的に従業員満足度調査やストレスチェックを実施し、職場の問題点を客観的に把握することが有効です。
その上で、上司と部下が定期的に1対1で対話する機会を設ける、業務量の偏りを是正して適正な人員配置を行うなど、風通しの良いコミュニケーションと健全な労働環境を整備することが、根本的な予防策となります。
関連リンク:大企業のコンプライアンス教育に関する実態調査
モラルハラスメントが発生したときの対応プロセス

モラルハラスメントに関する相談が寄せられた場合、企業は迅速かつ慎重な対応を求められます。初期対応の誤りは問題の複雑化を招き、企業の法的責任を問われる事態にもつながりかねません。
そのため、相談受付から事実確認、被害者・加害者への対応、そして再発防止策の実施に至るまで、一貫した対応プロセスをあらかじめ定めておくことが極めて重要です。
初動対応(記録収集、ヒアリング、事実確認)
相談を受けた際の初動対応は、その後のプロセス全体を左右する重要なステップです。
まず、相談者のプライバシー保護を徹底し、安心して話せる環境を確保した上で、具体的な事実関係を丁寧に聴取します。
いつ、どこで、誰から、どのような言動があったのかを5W1Hに沿って整理し、関連するメールや録音などの客観的な証拠があれば提出を求めます。
次に、相談者の了解を得た上で、行為者とされる人物や、状況を知りうる第三者からも中立的な立場でヒアリングを実施します。
関係者の主張が食い違うことも多いため、一方的な情報のみで判断せず、客観的な事実確認を慎重に進める必要があります。
被害者ケアと支援制度(休職、配置転換、相談支援など)
事実確認のプロセスと並行して、被害を受けている従業員の心身の安全確保を最優先に考えなければなりません。被害者の精神的負担を軽減するため、産業医や社外カウンセラーによるメンタルヘルスサポートを提供します。
また、加害者と物理的に距離を置くことが必要と判断される場合には、本人の意向を確認した上で、一時的な配置転換や在宅勤務への切り替え、あるいは安心して療養に専念できるよう休職制度の利用を促すなどの措置を検討します。
相談窓口が継続的にフォローアップを行い、被害者が社内で孤立することのないよう、組織として支える体制を整えることが企業の責務です。
加害者に対する処分・改善措置
事実調査の結果、モラルハラスメント行為が客観的に確認された場合、企業は就業規則の定めに従い、加害者に対して厳正な措置を講じる必要があります。
処分の内容は、行為の悪質性、継続性、被害の深刻さ、加害者の反省の度合いなどを総合的に考慮して決定します。
具体的には、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇といった懲戒処分が考えられます。
処分と同時に、加害者自身の問題行動を認識させ、改善を促すための指導や研修、カウンセリングの受講を命じることも重要です。
再発防止策とフォローアップ(モニタリング、職場風土改善)
個別のハラスメント事案への対応が完了した後、最も重要なのは同様の問題を二度と発生させないための再発防止策を組織全体で講じることです。
処分や配置転換が行われた後も、当事者やその周囲の従業員の状況を定期的にモニタリングし、問題が再燃していないかを確認します。
また、発生した事案を教訓として、全社的にハラスメント防止研修を再度実施したり、経営トップから強いメッセージを発信したりすることで、組織の意識改革を図ります。
アンケート調査などを通じて職場環境の課題を洗い出し、コミュニケーションの活性化策や業務プロセスの見直しなど、より根本的な職場風土の改善に取り組むことが求められます。
まとめ
モラルハラスメントは、被害者の尊厳を深く傷つける行為であり、企業はこれを防止し、適切に対処する法的責任を負っています。
問題を放置した場合、安全配慮義務違反として、被害者から慰謝料請求や損害賠償を求める民事訴訟に発展するリスクがあります。
過去の判例でも企業の責任は厳しく問われており、関連する法律や法令の遵守は必須です。
企業は、就業規則などの社内規程にハラスメントの禁止と懲戒処分に関する規定を明確に設け、研修資料などを用いて全従業員に周知徹底しなければなりません。
予防策の実施から、問題発生時の公正な調査、加害者への厳正な処分、そして再発防止までの一貫した体制を構築し、全ての従業員が安心して働ける職場環境を実現する責務があります。
eラーニングを活用したハラスメント防止・コンプライアンス研修なら「SAKU-SAKU Testing」
イー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」は、知識の定着を重視した「テストエデュケーション」方式により、学んだ内容をしっかり理解・定着させることが可能です。シンプルで直感的な操作性を備えているため、研修の準備から受講・進捗管理まで効率的に運用できます。
さらに、すぐに研修を始めたい方には、ハラスメント防止をはじめ社員教育に必要な教材があらかじめパッケージ化された「サクテス学びホーダイ」をご用意しております。自社で教材を準備する時間やコストを削減し、スムーズな研修実施をサポートいたします。
健全な職場づくりの第一歩として、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ハラスメント防止・コンプライアンス研修に関するコンテンツ
コンプライアンス・ハラスメント・情報セキュリティベーシック
「自社の従業員のハラスメント意識レベルを把握したい」「まずは情報セキュリティに関する知識のベースを揃えたい」といったニーズにこたえ、スピーディーで効果的な教育を実現できるコンテンツパッケージ「弁護士が解説 よくわかる企業のコンプライアンス講座」
動画で学ぶ従業員向けコンプライアンス教育のスタンダード教材。自社のニーズにあったコンプライアンスコンテンツを選びたいというご担当者におススメ
関連サービス
サクテス学びホーダイ:100本を超える動画と3,000問以上のビジネス問題を含むコンテンツパッケージで、すぐにWeb教育をスタートできます。
サクテスAIMONITOR:受講中の不正行為をリアルタイムで検知・防止するリモート監視ツールです。