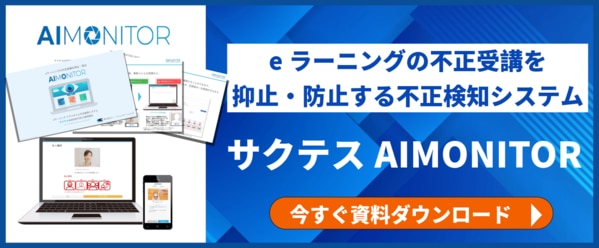研修スケジュールの作り方|テンプレートや作成ポイントをご紹介

研修の企画運営に携わる担当者にとって、研修スケジュール作成は重要な業務の一つです。効率的かつ効果的なスケジュールは、研修の成功を左右するだけでなく、受講者の学習意欲や成果にも大きく影響します。しかし、研修目標の設定から費用管理、内容検討、日程調整、そして最終的なスケジュール表への落とし込みまで、多岐にわたる工程には多くの課題が伴います。本記事では、研修スケジュールを効率的かつ効果的に作成するための具体的な手順、ポイント、そして実践的なテンプレートやツールについて解説します。
目次[非表示]
- 1.研修スケジュール作成の流れ
- 1.1.研修の目標を設定する
- 1.2.研修にかけられる費用を確定する
- 1.3.研修内容と実施形式を検討する
- 1.4.担当者の日程を調整する
- 1.5.日程を表にまとめる
- 1.5.1.研修の具体的な時間配分例
- 2.研修スケジュール作成時の注意点
- 2.1.詰め込みすぎず余裕をもたせる
- 2.2.社外研修の日程を優先的に確保する
- 2.3.基礎的な内容の研修を優先する
- 2.4.振り返りの機会を設ける
- 3.研修スケジュールのテンプレート作成方法
- 3.1.Excelを活用して作成する
- 3.2.ガントチャートを用いて作成する
- 3.3.Googleスプレッドシートで管理する
- 4.研修スケジュールのテンプレ例
- 5.社内研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
研修スケジュール作成の流れ

研修スケジュールを作成する際は、いくつかのステップを踏むことで効率的かつ効果的な計画を立てることができます。まず、研修の目的と目標を明確に設定し、その後、予算を確定します。次に、研修の内容と実施形式を検討し、関係者の日程調整を行った上で、最終的にスケジュールを表にまとめます。
ここでは、これらのステップを順番に解説していきます。
研修の目標を設定する
研修スケジュール作成の最初のステップとして、研修の目標を明確に設定することが不可欠です。目標を具体的にすることで、研修全体の方向性が定まり、受講者や関係者全員が共通の目的意識をもって取り組めます。たとえば、新人研修であれば、「新入社員のビジネスマナーや企業文化への理解を深める」「入社3ヶ月までに基本的な社会人スキルを習得し、円滑なコミュニケーションが取れるようになる」といった具体的な目標を設定することが考えられます。目標が曖昧なままだと、研修内容や形式の選定が難しくなり、結果として研修の学びの効果が薄れてしまう可能性があります。目標設定にあたっては、「いつまでに、何を、どのくらいできるようになるか」という具体的な基準を設けることが重要です。
研修にかけられる費用を確定する
研修の目標設定後、次に重要となるのが、研修にかけられる費用の確定です。研修費用を事前に明確にすることで、適切な内容や形式を選定し、予算内で効果的な研修を実施することが可能になります。
研修の実施形式は、社内研修、外部研修、eラーニングなど多岐にわたりますが、外部講師を招く場合や外部機関の研修を利用する場合には、高額な費用が発生する可能性があり、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
また、会場費や教材費、講師への謝礼など、研修に必要なすべての費用項目を洗い出し、それぞれの概算を立てて総費用を確定させましょう。予算が確定すれば、その範囲内で最適な研修計画を立てることができ、予期せぬ費用超過を防ぐことにもつながります。費用を考慮した上で、参加者が最大限の学びを得られるような質の高い研修を企画することが求められます。
研修内容と実施形式を検討する
研修にかけられる費用が確定したら、次に研修内容と実施形式を具体的に検討します。研修内容は、設定した目標や対象者のニーズに応じて適切に設計することが重要です。優先度の高い内容を中心に据え、参加者が本当に必要とする知識やスキルを習得できるカリキュラムを構成しましょう。新入社員にはビジネスマナーやコミュニケーションスキル、文書作成技術などの基礎的な能力を組み込むのが一般的です。実施形式には、自社のリソースを活用する社内研修、専門家や外部リソースを利用する外部研修、そしてオンラインで学習するeラーニングなどがあります。社内研修は、企業独自のニーズに即した内容を柔軟に設計できるメリットがありますが、講師の確保やカリキュラム作成に手間がかかる場合があります。一方、外部研修は高度な知識や最新スキルを効率的に学べますが、費用がかかるため、費用対効果の検討が不可欠です。eラーニングは、個々人が自身のペースで学習を進められるため、集合研修のタイムスケジュールが組みにくい場合や、地理的に分散している受講者がいる場合に有効な選択肢となります。各形式のメリット・デメリットを比較検討し、予算や研修目標、受講者の状況に最も適した組み合わせを選ぶことで、効果的な研修を実現できるでしょう。
担当者の日程を調整する
研修内容と実施形式の検討が済んだら、次に研修に関わる担当者、特に講師や関係者の日程調整を進めます。研修をスムーズに進行させるためには、講師や研修担当者のスケジュール確保が非常に重要です。特に、外部講師を招く場合や、社外研修を組み込む場合は、講師の予定が既に埋まっている可能性が高いため、早めに調整を行うことが求められます。社内研修の場合でも、講師となる社員の通常業務との兼ね合いや、複数の部署から集まる受講者の業務状況も考慮し、無理のないタイムスケジュールを組む必要があります。関係者全員のスケジュールを効率的に調整するためには、各担当者の空き時間を確認し、複数の候補日を提示することが有効です。また、調整が難しい場合は、オンラインでの実施やeラーニングの活用も検討し、柔軟に対応することで、円滑な日程調整が可能になります。
日程を表にまとめる
担当者の日程調整が完了したら、研修の日程を表にまとめます。スケジュール表は、研修の具体的な流れを視覚的に把握できるため、関係者や受講者全員に研修の全体像をわかりやすく共有するために重要です。
表を作成する際には、日付、時間、研修内容、講師名、場所などの項目を明確に記載しましょう。特に、一日単位の研修であれば、分刻みのタイムスケジュールを記載することで、研修が計画通りに進行しやすくなります。
例えば、9:00~9:30にオリエンテーション、9:30~10:30にビジネスマナー講習(座学)といった具体的な時間配分を明記します。複数の研修が並行して進む場合や、長期にわたる研修の場合は、ガントチャート形式を用いると、各研修項目やタスクの開始日、終了日、期間を一目で把握でき、進捗状況の管理にも役立ちます。視覚的にわかりやすいよう、項目ごとに色分けをしたり、講師名をプルダウンリストから選択できるようにしたりするなどの工夫も有効です。これにより、受講者も自身のスケジュールを把握しやすくなり、研修への参加意識を高めることにもつながります。
研修の具体的な時間配分例
研修のタイムスケジュールを具体的に設定する際には、受講者の集中力を維持し、学習効果を最大化するための工夫が必要です。一般的な集中持続時間は90分が限界とされており、1時間から1時間半ごとに20分程度の休憩を挟むことが推奨されています。午前中に座学を2セッション、午後に実技演習を2セッションといった構成が考えられます。各セッション内でも、導入、講義、演習、質疑応答といった流れで時間配分を細かく設定し、適度に受講者が主体的に取り組める時間を設けることが重要です。
具体的なタイムスケジュール例を下記にまとめます。
9:00~9:30 | オープニングと研修概要説明 |
9:30~10:30 | ビジネスマナー講習(座学) |
10:30~10:45 | 休憩 |
10:45~12:00 | ビジネスマナーの練習(実技) |
12:00~13:00 | 昼休み |
演習の時間配分は、研修講師と相談しながら決定し、複数日にわたる研修の場合は、日ごとに詳細なタイムスケジュールを作成することで、研修が計画通りに進みやすくなります。
研修スケジュールの立て方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
↓
研修スケジュールの立て方|手順やポイントをわかりやすく解説
研修スケジュール作成時の注意点

研修スケジュールを作成する際には、研修の効果を最大限に引き出し、円滑な運営を行うためにいくつかの注意点があります。
ここでは、研修スケジュール作成時の注意点について解説します。
詰め込みすぎず余裕をもたせる
研修スケジュールを作成する際、最も重要な注意点の一つは、内容を詰め込みすぎず、余裕をもたせることです。研修効果を最大化するためには、受講者が集中力を維持できるようなタイムスケジュールを組むことが不可欠です。
人間が集中できる時間は一般的に90分が限度と言われているため、長時間座学が続く場合は、最低でも90分以内に一度は休憩時間を確保し、リフレッシュできる時間を設けるようにしましょう。例えば、50分研修して10分休憩を挟むといった方法も有効です。また、休憩以外にも、身体を動かすようなアクティビティや、グループワークなど、座学以外の要素を取り入れることで、受講者の集中力を維持しやすくなります。無理に短期間で多くの内容を消化しようとすると、受講者が内容についていけなくなり、学習効果が低下するだけでなく、モチベーションの低下や疲労の蓄積につながる可能性もあります。そのため、各セッションの間に適切な休憩時間を設定し、質疑応答やディスカッションの時間を十分に確保するなど、ゆとりを持ったタイムスケジュールを心がけましょう。
社外研修の日程を優先的に確保する
研修スケジュールを立てる際、社内研修と社外研修の両方を組み込む場合は、社外研修の日程を優先的に確保することが重要です。
社外研修は、外部の専門機関が提供しているため、あらかじめ日程が決まっていることが多く、自社の都合に合わせて柔軟に調整することが難しい傾向にあります。先に社内研修の日程を固めてから社外研修を組み込もうとすると、希望する社外研修の日程が合わず、結果的に社内研修の日程変更が必要になるなど、スケジュール作成が煩雑になる可能性があります。そのため、まずは受講させたい社外研修の開催日程を確認し、それに合わせて全体の研修スケジュールを組み立てるのが効率的です。外部講師を招く場合も同様に、講師の空き状況を確認し、早めに日程を確定させることで、その後のスケジュール調整をスムーズに進めることができます。
基礎的な内容の研修を優先する
研修スケジュールを作成する際、新人など未経験者を対象とする場合は、基礎的な内容の研修を優先して序盤に組み込むことが非常に重要です。例えば、新入社員研修では、ビジネスマナーや企業文化、業界知識といった、その後の業務や専門的な学習の土台となる部分から始めるべきです。基礎がしっかりと身についていなければ、応用的な内容に進んでも理解が追いつかず、研修効果が薄れてしまう可能性があります。基礎的な内容を早期に習得することで、受講者は安心して次のステップに進むことができ、学習の定着率も向上します。また、基本的なスキルを習得した上で、徐々に専門的な内容や実践的な演習へと移行する段階的なスケジュールを組むことで、受講者の理解度とモチベーションを維持しやすくなります。
振り返りの機会を設ける
研修スケジュールにおいて、座学や演習だけでなく、研修の最後に必ず振り返りの機会を設けることが重要です。振り返りの時間は、受講者が研修で学んだ内容を整理し、知識やスキルを定着させるために不可欠な要素となります。単に情報をインプットするだけでなく、学んだことを自身の言葉でアウトプットしたり、グループで共有したりすることで、理解を深めることができます。また、振り返りの時間には、研修内容が業務にどう活かせるか、今後どのような行動変容を起こすべきかを具体的に考える機会も含まれます。例えば、研修後に報告書やレポートの作成を義務付けることで、受講者は研修内容を再度整理し、実務への適用を具体的に検討する機会を得られます。これにより、研修の学びが単なる知識習得で終わらず、実際の業務に結びつく行動へとつながる可能性が高まります。さらに、振り返りの内容をアンケートなどで収集することで、研修の課題点や改善点も明確になり、次回の研修企画に活かす貴重なデータを得ることもできます。
研修スケジュールのテンプレート作成方法
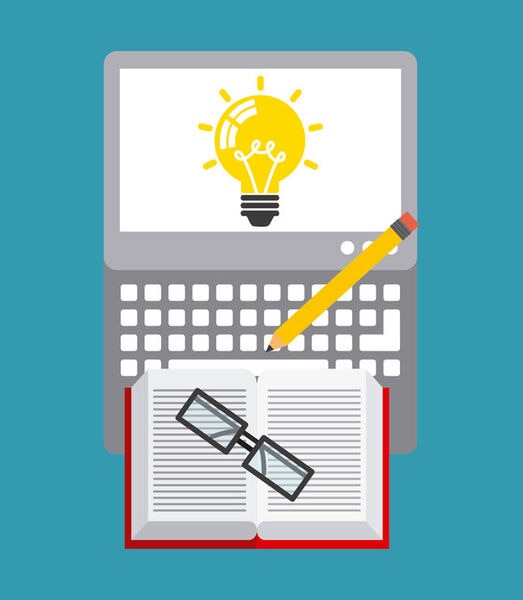
研修スケジュールを効率的に作成するには、テンプレートの活用が非常に有効です。テンプレートを利用することで、一からスケジュール表を作成する手間を省き、項目漏れを防ぎながら、誰にでもわかりやすいフォーマットで情報を整理できます。特に、無料配布されているテンプレートも多く存在するため、コストを抑えつつ質の高いスケジュール作成が可能です。ここでは、Excel、ガントチャート、Googleスプレッドシートといった主要なツールを使ったテンプレート作成方法について解説します。
Excelを活用して作成する
研修スケジュールを効率的に作成する上で、Excelは非常に汎用性の高いツールです。多くの企業で日常的に使用されており、既にある程度Excelの操作に慣れている担当者であれば、スムーズにスケジュール表を作成できます。Excelでテンプレートを作成する際は、日付、時間帯、研修内容、講師、場所などの項目を列に設定し、行に時間軸を設定する基本的な表形式がわかりやすいでしょう。
下記のようなイメージです。
日付 | 時間帯 | 研修内容 | 講師 | 場所 |
4/10 | 9:00~10:00 | 理念研修 | 社長 | A会議室 |
10:00~12:00 | 個人情報研修 | JS部 | A会議室 |
例えば、Microsoft Officeの公式サイトでは、「行程管理表(業務・スケジュール)」といった無料のテンプレートが提供されており、これらを活用することで、1日単位の細かなタイムスケジュールから月間・年間の大まかなスケジュールまで、幅広く対応できます。また、項目ごとに色分けをしたり、講師名をプルダウンリストから選択できるように設定したりするなど、見やすさや入力の手間を減らすカスタマイズを施すことで、より使いやすい研修スケジュールを構築可能です。
一度汎用的なエクセルテンプレートを作成しておけば、今後の研修計画にも繰り返し活用でき、大幅な工数削減につながります。
ガントチャートを用いて作成する
研修スケジュールの作成において、ガントチャートは特に長期的な研修や複数のタスクが並行して進む場合に非常に有効なツールです。ガントチャートはプロジェクト管理によく用いられる手法で、研修期間全体を横軸で示し、各研修項目や準備タスクを縦軸にリスト化します。それぞれのタスクの開始日、終了日、期間をバーで視覚的に表示することで、研修全体の流れや各項目の関連性、進捗状況を一目で把握できるようになります。ExcelやGoogleスプレッドシートには、ガントチャートのテンプレートが用意されていることが多く、これらを活用することで一から作成する手間を省けます。
例えば、パワーポイントでガントチャートを作成することも可能で、視覚的にわかりやすく資料を作成したい場合に適しています。ガントチャートを活用することで、必要なリソースの割り当てや進捗のモニタリングも効率的に行えるため、研修の管理能力が向上し、予期せぬ中断を最小限に抑えることに貢献します。
Googleスプレッドシートで管理する
Googleスプレッドシートは研修スケジュールを管理するための便利なツールであり、チームでの共同作業においてその真価を発揮します。Excelと同様に表計算ソフトとしての基本的な機能に加え、クラウド上でリアルタイムでの共同編集が可能な点が大きなメリットです。これにより、研修スケジュールに変更があった場合でも、関係者全員が常に最新の情報を共有でき、情報伝達のタイムラグによるミスを防ぐことができます。
また、Googleスプレッドシートは無料で利用でき、専用のソフトウェアをインストールする必要がないため、コストを抑えつつ手軽に導入可能です。テンプレートギャラリーにはガントチャートなど、スケジュール管理に適したテンプレートも用意されており、これらを活用することで効率的にスケジュール表を作成できます。開始日を設定するだけでカレンダーが自動生成されたり、担当者を設定すると自動で色分けされたりするなど、視覚的なわかりやすさを向上させる機能も充実しています。インターネットに接続していればどこからでもアクセスできるため、リモート環境での研修運営や、複数の拠点で連携しながら研修を進める場合にも非常に有効です。
研修スケジュールのテンプレ例

研修スケジュールは、対象者や研修期間によって様々な形式が考えられます。例えば、新入社員研修のように数日から数週間にわたるもの、あるいは特定のスキル習得を目的とした1日限りの集中研修などがあります。テンプレート例としては、縦軸に時間、横軸に日付を取り、各セルに研修内容や担当者、場所を記載するシンプルな表形式が一般的です。
より詳細な情報が必要な場合は、備考欄を設けて準備品や注意事項などを追記すると良いでしょう。長期研修では、ガントチャートのように各タスクの期間をバーで示す形式が全体像を把握しやすく、進捗管理にも役立ちます。これらのテンプレートは、ExcelやGoogleスプレッドシートで簡単に作成でき、オンラインで無料配布されているものも多数存在します。自社の研修目的や規模に合わせて、最適なテンプレートを選び、必要に応じてカスタマイズすることで、効率的かつ効果的な研修スケジュールを作成することが可能になります。
ご参考に、テンプレート例を以下にいくつかご紹介します。
社員研修スケジュール(テンプレ例)
①1日研修(例:新入社員研修)
時間 | 内容 | 担当 |
09:30 - 09:45 | 開会挨拶・オリエンテーション | 人事部 |
09:45 - 10:30 | 会社概要・経営方針説明 | 経営陣 |
10:30 - 10:45 | 休憩 | - |
10:45 - 12:00 | 就業規則・社内ルール | 総務部 |
12:00 - 13:00 | 昼食 | - |
13:00 - 14:30 | ビジネスマナー講座 | 外部講師 |
14:30 - 14:45 | 休憩 | - |
14:45 - 16:15 | コンプライアンス基礎 | 法務部 |
16:15 - 16:45 | 研修内容の振り返り・質疑応答 | 人事部 |
16:45 - 17:00 | 閉会挨拶・アンケート記入 | 人事部 |
②2日間研修(例:階層別研修・管理職向け)
1日目
時間 | 内容 | 担当 |
09:30 - 10:00 | 開会・目的共有 | 人事部 |
10:00 - 12:00 | リーダーシップ理論と実践 | 外部講師 |
12:00 - 13:00 | 昼食 | - |
13:00 - 15:00 | 部下育成・評価のポイント | 人事部 |
15:00 - 15:15 | 休憩 | - |
15:15 - 17:00 | ケーススタディ(グループ討議 | ファシリテーター |
2日目
時間 | 内容 | 担当 |
09:30 - 10:00 | 開会・目的共有 | 人事部 |
10:00 - 12:00 | リーダーシップ理論と実践 | 外部講師 |
12:00 - 13:00 | 昼食 | - |
13:00 - 15:00 | 部下育成・評価のポイント | 人事部 |
15:00 - 15:15 | 休憩 | - |
15:15 - 17:00 | ケーススタディ(グループ討議) | ファシリテーター |
社内研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
社内研修に、eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
研修プログラムの作成に利用できるコンテンツを多数ご用意しているほか、自社の歴史や理念などを盛り込んだ自社のオリジナルで作成したコンテンツを搭載することも可能です。
使いやすく管理しやすいテスト機能を搭載しており、学んだ知識の定着もはかれます。
また、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただければ、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
コンテンツには、新人社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定できるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ご興味がおありの場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。