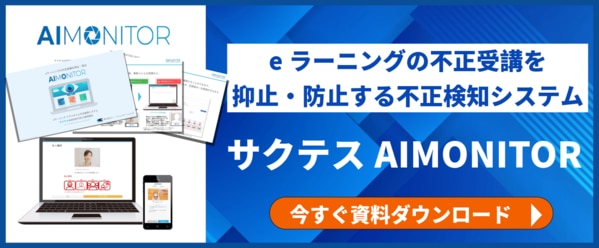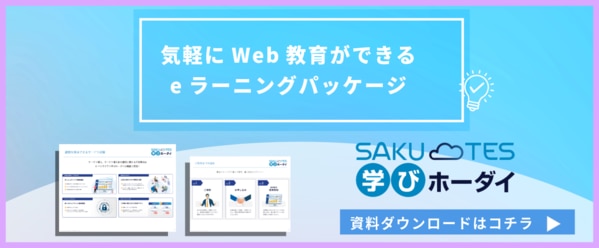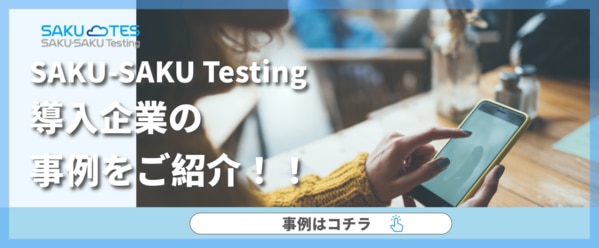人事評価研修とは?目的・メリット・カリキュラムをご紹介

人事評価制度は、従業員の成長を促し、組織の成果を最大化するための重要な仕組みです。しかし、その制度を有効に機能させるためには、評価者や被評価者が制度を正しく理解し、適切に運用するスキルを身につける必要があります。そこで重要となるのが人事評価研修です。本記事では、人事評価研修の目的、メリット、具体的な内容、実施形式、成功させるためのポイント、導入を検討すべき状況、研修を提供している機関について解説します。
目次[非表示]
- 1.人事評価研修の概要
- 1.1.人事評価研修とは
- 1.2.人事評価研修の実施状況
- 1.3.人事評価研修が不可欠な理由
- 2.人事評価研修の目的
- 2.1.評価に必要な知識の習得
- 2.2.適切な評価スキルの向上
- 2.3.評価者としての役割認識の強化
- 2.4.効果的なフィードバックの実践
- 3.人事評価研修を受ける対象者
- 3.1.管理職
- 3.2.人事担当者
- 3.3.経営幹部
- 3.4.評価される立場の人(被評価者)
- 3.5.人事評価研修を受ける対象者や役割、目的
- 4.人事評価研修で習得する内容
- 4.1.人事評価の基本的な理解
- 4.2.目標設定の方法論
- 4.3.公正な評価の実践
- 4.4.面談を通じた評価の伝達方法
- 5.人事評価研修の実施形式
- 5.1.ロールプレイングによる演習
- 5.2.集合形式での実施
- 5.3.eラーニングの活用
- 5.4.人事評価研修の形式ごとの比較表
- 6.人事評価研修を成功させるポイント
- 6.1.実践的なプログラムの導入
- 6.2.定期的な効果測定と改善
- 7.人事評価研修の導入メリット
- 7.1.評価者間の連携強化
- 7.2.人事評価制度の実効性向上
- 7.3.人材育成の促進
- 7.4.組織全体の成果向上
- 8.人事評価研修の実施を検討すべき企業
- 8.1.人事制度が機能不全を起こしている
- 8.2.目標設定や面談に課題がある
- 8.3.評価者のスキルレベルが低い
- 9.人事評価研修を提供している機関
- 10.人事評価研修のオンライン化をご検討の担当者様は「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
人事評価研修の概要

ここでは、人事評価研修の定義やなぜ必要なのかについて解説します。
人事評価研修とは
人事評価研修は、主に評価者が人事評価制度を正確に理解し、公正かつ適切に評価を実施できるようになることを目的とした研修です。評価者研修や考課者研修とも呼ばれ、企業によってはセミナー形式で実施されることもあります。研修内容は多岐にわたり、単に評価方法を学ぶだけでなく、人事評価制度の意義や目的、評価基準の理解、そして被評価者への効果的なフィードバック方法なども含まれます。外部の研修機関に依頼する場合、講師派遣という形で実施されることもあります。インソースのような研修会社では、自治体や公務員といった特定の組織に向けた専門的なプログラムを提供している場合もあります。
人事評価研修の実施状況
多くの企業が人事評価研修を導入しており、特に評価者を対象とした研修は実施率が高い傾向にあります。ある調査では、評価者訓練を「実施している」企業の割合が7割以上にのぼるという結果も出ています。これは、企業が人事評価を適切に行うことの重要性を認識していることの表れと言えるでしょう。
一方で、評価される側の従業員(被評価者)に対する研修の実施率は、評価者研修と比較すると低い傾向にあります。しかし、評価者と被評価者間の評価に対する認識のズレを埋め、制度への納得感を高めるためには、被評価者研修も同様に重要視されるべきです。
人事評価研修が不可欠な理由
人事評価研修が欠かせないのは、人事制度を形だけのものにせず、実効性のある仕組みとして機能させるためです。適切に運用されない人事評価制度は、従業員の不満や不信感を招き、モチベーションの低下や離職にも繋がりかねません。評価者が評価エラーを防ぎ、公平かつ客観的な評価を行うためには、評価者研修による知識とスキルの習得が不可欠です。また、人事評価は単に優劣をつけるだけでなく、従業員の成長を支援し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げるためのマネジメントツールでもあります。適切な目標設定やフィードバックの方法を学ぶことは、労務管理の観点からも重要であり、従業員との信頼関係構築にも寄与します。
人事評価研修の目的

ここでは人事評価研修の目的について解説します。
評価に必要な知識の習得
人事評価研修における重要な目的の一つは、評価者が人事評価に必要な幅広い知識を習得することです。これには、自社の人事評価制度の構造、評価項目とその定義、評価基準の正確な理解が含まれます。また、評価エラーと呼ばれる、評価者の主観や偏見による評価の歪みを防ぐための知識も不可欠です。人事労務に関する基本的な知識や、労務管理の観点から評価結果がどのように活用されるかを知ることも、評価の重要性を認識し、より責任感をもって評価に取り組むことに繋がります。
適切な評価スキルの向上
人事評価研修の主要な目的は、評価者が適切な評価スキルを習得し、向上させることです。具体的には、設定された目標に対する達成度を客観的に判断する能力、職務行動や能力の発揮度を評価基準に照らして適切に評価するスキルなどが含まれます。研修では、これらのスキルを効果的に身につけるために、ケーススタディや演習が取り入れられることがあります。評価者自身の評価スキルが向上することで、より公平で納得感のある評価が実現し、被評価者の成長や組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。
評価者としての役割認識の強化
人事評価研修は、評価者が単に制度に基づいて評価を行うだけでなく、人事評価者としての責任と役割を自覚し、高い意識をもつことを目的としています。評価が被評価者のキャリアやモチベーションに大きな影響を与えることを理解し、公正かつ誠実な姿勢で評価に臨むことの重要性を学びます。評価者は、評価結果を通じて被評価者の成長を支援し、組織全体の目標達成に貢献する役割を担っているという意識を醸成することが、人事評価制度をより効果的に機能させるために不可欠です。
効果的なフィードバックの実践
人事評価研修では、評価者が被評価者に対して効果的なフィードバックを行うスキルの習得も重要な目的としています。評価結果を単に伝えるだけでなく、評価の根拠を具体的に説明し、被評価者の良かった点や改善すべき点を明確に伝える方法を学びます。また、一方的な通達ではなく、被評価者の自己評価も踏まえながら対話し、今後の目標設定や成長に向けた具体的な行動計画を共に考える面談スキルも習得します。適切なフィードバックは、被評価者の納得感を高め、モチベーション向上や主体的な成長を促す上で、マネジメントにおける重要な要素となります。
人事評価研修を受ける対象者

これまで人事評価研修の内容を解説してきましたが、この章では、その研修を受けるべき対象者について見ていきます。
管理職
管理職は、人事評価研修、特に評価者研修の主要な対象者です。彼らは部下の目標設定、日々の業務におけるマネジメント、そして期末の評価とフィードバックを担うため、人事評価制度の正確な理解と適切な評価スキルが不可欠です。研修を通じて、公正な評価基準の適用方法、評価エラーの防止策、効果的なフィードバック面談の進め方などを習得します。管理職の評価スキル向上は、部下のモチベーションや成長に直結し、チームひいては組織全体のパフォーマンス向上に大きく貢献します。人事評価者としての自覚とスキルを高めることが期待されます。
人事担当者
人事担当者も人事評価研修の重要な対象者です。人事担当者は人事評価制度の設計、運用、管理に携わるため、制度全体の目的や仕組み、そして運用上の留意点について深く理解する必要があります。研修を通じて、人事評価が賃金や配置といった人事労務管理とどのように連携するのか、また、評価結果をどのように人材育成や組織開発に活用していくかといった知識を習得します。法改正への対応や、評価制度に関する従業員からの問い合わせへの適切な対応能力を高める上でも、人事評価研修は有益です。労務管理の専門知識と併せて、より実効性のある人事評価制度の運用を目指します。
経営幹部
経営層も人事評価研修の対象となることがあります。経営層は、人事評価制度が企業の経営戦略やビジョンとどのように連携し、組織全体の成果最大化に貢献するかを理解する必要があります。研修を通じて、人事評価制度が単なる評価ツールではなく、組織文化の醸成や変革を推進する力をもつことを認識し、戦略的な人事施策として位置づける視点を養います。また、評価結果を経営判断にどのように活用するか、優秀な人材の確保・育成にどのように繋げるかといった、より高次の視点での人事評価の意義を理解することが求められます。
評価される立場の人(被評価者)
近年では、評価される立場にある一般社員を対象とした被評価者研修も注目されています。被評価者研修の目的は、従業員が自社の人事評価制度について正しく理解し、自身の評価がどのように行われるのか、評価結果が自身のキャリアや待遇にどう影響するのかを知ることです。また、評価に対して一方的に受け身になるのではなく、自身の目標設定を適切に行い、期中の進捗を管理し、評価面談で自身の成果や課題を効果的に伝えるスキルを身につけることも目指します。被評価者が評価制度への理解を深めることは、評価者との間の認識のギャップを減らし、評価に対する納得感を高めることに繋がります。自治体や公務員でも、同様の被評価者向け研修が実施される場合があります。
人事評価研修を受ける対象者や役割、目的
対象者ごとに以下のように表にまとめました。
項目 | 管理職 | 人事担当者 | 経営幹部 | 一般社員 |
主な対象 | 課長・部長クラス | 人事企画・制度運用・労務管理など | CEO・役員・部門長など | 評価される立場の一般社員 |
主な役割 | -部下の目標設定支援- 業務マネジメント -評価・フィードバック | -制度設計・運用・管理- 評価結果の分析・活用 -社内説明・問合せ対応 | -組織方向と制度整合性確保 -戦略的活用・経営判断への反映 | -目標達成に向けた行動 -面談時の説明・自己管理 |
研修で学ぶこと | -評価制度の理解- 公正な基準と適用方法- 評価エラー防止 -フィードバック面談 |
-実務と法対応 | -評価制度と経営戦略の接続- 組織文化と変革視点 -人材発掘・戦略的人事 | -評価制度の理解 -目標設定・進捗管理 -面談での説明力 |
目的・期待される効果 |
-評価の質向上 -部下の成長促進 | -制度運用の的確性向上- 従業員の納得感向上 -人事施策との連携強化 -戦略的人材マネジメント | -人事制度を経営の柱に -組織成果の最大化 -人材投資の最適化 | -評価者とのギャップ解消 -主体的な評価への関与 -キャリア意識向上 |
導入実績例 | 企業全般 | 企業・人事部門 | 経営層向けプログラム | 自治体、公務員組織など |
人事評価研修で習得する内容

ここでは、研修で身につけるべき人事評価の具体的なポイントをご紹介します。
人事評価の基本的な理解
人事評価研修では、まず人事評価の基本的な理解を深めることから始まります。これには、人事評価制度がなぜ必要なのか、どのような目的で行われるのかといった意義の部分に加え、自社の人事評価制度がどのような構成要素(等級制度、評価制度、報酬制度など)から成り立っているのかを把握することが含まれます。また、能力評価、業績評価、情意評価といった評価種類の違いや、それぞれの評価項目がもつ意味、評価フローの流れについても学びます。人事労務の観点から、評価が従業員の処遇や配置にどう影響するのかを理解することも、人事評価の重要性を認識する上で不可欠です。
目標設定の方法論
人事評価制度において、適切な目標設定は評価の質を左右する重要な要素です。研修では、効果的な目標設定の方法論を体系的に学びます。SMART原則に代表される具体的な目標設定のフレームワークや、個人の目標が組織全体の目標とどのように連携するのかを理解します。また、部下の能力や経験レベルに合わせた目標設定のサポート方法、期中の進捗確認や軌道修正のポイント、そして挑戦的な目標設定を促すための関わり方についても習得します。適切な目標設定は、従業員のモチベーションを高め、マネジメントの質を向上させることに繋がります。人事評価制度を運用する上で欠かせないスキルの一つです。
公正な評価の実践
人事評価研修において最も実践が重視される内容の一つが、公正な評価を行うためのスキルの習得です。評価者の主観や感情に左右されず、設定された評価基準に基づいて客観的に評価することの重要性を学びます。評価エラー(ハロー効果、寛大化傾向、中心化傾向など)の種類とその防止策について理解し、実際の評価場面で意識的に排除できるよう訓練します。複数の評価者間で評価の目線を合わせるための摺り合わせ方法や、評価の根拠を明確にするための記録の取り方なども習得します。評価者研修を通じて、評価者間の評価のバラつきをなくし、被評価者にとって納得性の高い評価を実現することを目指します。
面談を通じた評価の伝達方法
人事評価面談は、評価結果を被評価者に伝え、今後の成長に繋げるための重要な機会です。研修では、効果的な面談を通じた評価の伝達方法を具体的に学びます。面談の目的や時間配分の設計、話しやすい雰囲気の作り方といった準備段階から、評価結果の説明方法、被評価者の自己評価や意見の引き出し方、そして今後の目標設定や育成計画に関する対話の進め方まで、一連のプロセスを実践的に習得します。特に、改善点や厳しい評価を伝える際の言葉選びや伝え方には丁寧な指導が行われます。ロールプレイングなどの演習を通じて、自信をもって面談に臨めるスキルを養い、マネジメントにおけるコミュニケーション能力を高めます。
人事評価研修の実施形式

人事評価研修はどのような形式で実施されるかを紹介します。
ロールプレイングによる演習
人事評価研修において、知識の習得だけでなく実践的なスキルを身につける上で非常に有効なのが、ロールプレイングによる演習です。実際の評価面談の場面を想定し、評価者役と被評価者役に分かれて具体的なやり取りを行います。これにより、評価結果の伝え方、フィードバックの際の言葉選び、被評価者からの質問への対応など、座学だけでは得られない実践的な感覚を養うことができます。他の参加者からのフィードバックを受けることで、自身の課題に気づき、改善に繋げることが可能です。特に面談スキルやフィードバック能力の向上を目指す研修では、欠かせない演習形式と言えます。
集合形式での実施
人事評価研修の伝統的な実施形式の一つが、集合形式です。研修会場に受講者が一堂に会し、講師による講義やグループワーク、ディスカッションなどを行います。集合形式のメリットは、講師へその場で質問ができたり、他の参加者と意見交換をしたりすることで、理解を深めやすい点にあります。また、グループ演習などを通じて、実践的なスキルを身につける機会も多くあります。特に、評価者間の目線合わせや、自社の人事評価制度に関する共通認識を醸成することを目的とした研修に適しています。セミナーとして開催されることもあります。
eラーニングの活用
近年、働き方の多様化や効率的な研修実施のニーズから、eラーニングを活用した人事評価研修が増加しています。eラーニングでは、PCやスマートフォン、タブレットなどを用いて、時間や場所を選ばずに自分のペースで学習を進めることができます。動画コンテンツやインタラクティブな教材を活用することで、分かりやすく体系的に知識を習得することが可能です。特に、人事評価制度の基本的な知識や評価基準の理解といったインプット中心の内容に適しています。eラーニングシステムやツールを導入することで、多数の対象者に対して効率的に研修を実施でき、進捗管理も容易になります。
eラー二ングシステムに「SAKU-SAKU Testing」がおすすめ
イー・コミュニケーションズのeラーニングシステム「SAKU-SAKU Testing」を活用いただけば、人事評価制度の研修が簡単に行えます。
管理画面から進捗管理も簡単にでき、管理者・受講者ともに使いやすいシステムです。
人事評価研修の形式ごとの比較表
以下は実施形式ごとの特徴を表にまとめたものです。
実施形式/演習形式 | ロールプレイング | 集合形式 | eラーニング |
目的 | 実践的な評価面談スキルの習得 | -評価者間の目線合わせ- 制度への共通理解の醸成 | -評価制度の基本理解- 評価基準などのインプット |
内容 | -評価者役・被評価者役に分かれて演習- 評価結果の伝え方やフィードバックの言葉選び -質問対応の練習 | -講師による講義 -グループワーク -ディスカッション | -動画教材やインタラクティブコンテンツによる学習 |
期待できる効果/メリット | -実践的感覚の養成- 面談・フィードバックスキル向上 -他参加者からのフィードバックで課題発見 | -講師への直接質問が可能 -参加者同士の意見交換 | -多人数に一斉実施が可能- 場所・時間を問わない -進捗管理がしやすい |
学習環境・ | 会場や研修室での対面演習 | 研修会場に集合して実施 | PC・スマートフォン・タブレット等を使用し、いつでもどこでも学習可能 |
適した内容 | 面談・フィードバックなどの実践スキル強化 | 評価制度の共通理解、他者視点の学習 | 制度理解、評価基準、考え方などのインプット重視の内容 |
備考・ | 他参加者のロール観察も学びになる | セミナー形式での実施もあり | 働き方の多様化に対応した学習手段として拡大中 |
人事評価研修を成功させるポイント
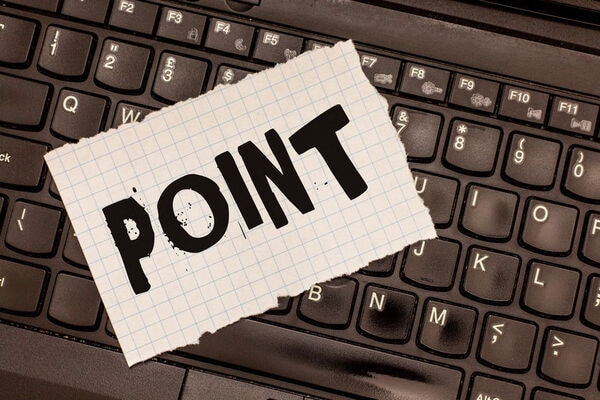
人事評価研修を成功させるにはいくつかのポイントがあります。ここでは、成功ポイントについて解説します。
実践的なプログラムの導入
人事評価研修を成功させるためには、理論だけでなく、実際の評価業務にすぐに活かせる実践的なプログラムを導入することが非常に重要です。単なる講義形式に留まらず、具体的な評価事例を用いたケーススタディや、実際の面談を想定したロールプレイングといった演習を豊富に取り入れるべきです。これにより、受講者は学んだ知識をどのように活用するのかを具体的にイメージし、実践的なスキルを効果的に習得することができます。特に、評価基準の解釈やフィードバックの方法など、実際の判断やコミュニケーションが求められる場面を想定した演習は、研修効果を大きく高めます。
定期的な効果測定と改善
人事評価研修は一度実施して終わりではなく、その効果を定期的に測定し、必要に応じて研修内容や方法を改善していく継続的な取り組みが重要です。研修参加者の理解度やスキルの定着度を確認するためのテストやアンケートを実施したり、実際の評価結果の分布や被評価者からのフィードバックを分析したりすることで、研修効果を測定します。これらの結果に基づき、研修プログラムの改善点や新たな課題を特定し、次回の研修に反映させます。人事評価制度全体の運用状況や組織の目標達成度と照らし合わせながら効果測定を行うことで、より戦略的な研修計画を立てることが可能となり、評価者のスキルアップや組織全体の成果向上に繋がります。スケジュールに組み込み、スキルマップと連動させることも有効です。
人事評価研修の導入メリット

ここでは、人事評価研修導入のメリットについて解説します。
評価者間の連携強化
人事評価研修は、以下のような効果を通じて、評価者間の連携や共通認識の形成に大きく寄与します。
- 評価者間の交流・意見交換の場を提供
- 異なる部署・階層の評価者が一堂に会することで、部署を超えたつながりが生まれる
- 評価制度や評価基準に関する共通理解が深まる
- グレーゾーンの判断や基準の解釈について議論できる
- 評価のばらつきが起きやすい曖昧な領域について、実例を交えた意見交換ができる
- 共通認識をもつことで、「目線合わせ」が実現する
- 評価の一貫性が向上
- 部署ごとの基準の違いや個人差を減らし、全社的に整合性のある評価が可能になる
- 評価者ネットワークの構築が可能
- 研修を通じて評価者同士がつながり、日常的な情報交換や相談がしやすくなる
- 評価業務における連携や相互支援が活性化される
人事評価制度の実効性向上
人事評価研修は、策定された評価制度を実際に機能させるために欠かせない取り組みです。どれほど精密に設計された制度でも、評価者がその趣旨や運用方法を正しく理解していなければ、制度は形式だけのものになってしまいます。
研修では、制度の目的や評価基準、評価プロセスについてしっかりと学ぶことで、評価者が公平で一貫性のある評価を行えるようになります。これにより、制度に対する信頼性が高まり、社員の納得感も得られるようになります。
また、研修を通じて得た知識は、評価結果を人材育成や配置、報酬などの施策に適切に結びつける際にも役立ちます。評価が単なる点数付けで終わるのではなく、組織全体の人事戦略と連動して活用されるようになるのです。
さらに、外部の評価ツールや支援サービスをうまく活用することで、制度運用の効率を高めながら、制度の実効性もさらに向上させることができます。評価者が制度を正しく理解し、実践する力を身につけることで、人事評価制度はようやく「使える仕組み」として組織に根付きます。
人材育成の促進
人事評価は、過去の成果を測るだけでなく、従業員のこれからの成長を後押しするための大切な人材育成の仕組みでもあります。その役割を十分に果たすためには、評価を行う側が正しい知識とスキルをもっていることが必要です。
人事評価研修では、評価者が評価結果をもとに、部下の強みや課題を把握し、具体的な改善策や育成計画を一緒に考える力を養います。こうしたスキルを身につけることで、評価は単なる点数づけではなく、部下の成長を支える対話の機会になります。
特に、適切なフィードバックを行うことによって、被評価者は自分の立ち位置を客観的に理解でき、前向きな気持ちでスキルアップに取り組むようになります。また、評価結果をキャリアパスや能力開発プランと結びつけることで、計画的かつ戦略的な人材育成が可能になります。
このように、人事評価研修によって評価スキルが向上すれば、社員一人ひとりの意欲や成長を促すだけでなく、組織全体のエンゲージメントの向上や、優秀な人材の定着にもつながっていきます。最終的には、組織の採用力や人材の質そのものを高める効果が期待できるのです。
組織全体の成果向上
人事評価研修は、最終的に組織全体の成果を高めることに大きく貢献します。まず、公正で納得感のある評価が行われることで、従業員のモチベーションが高まり、仕事への意欲やエンゲージメントが向上します。その結果として、生産性の向上にもつながります。
さらに、評価結果をもとに行う人材育成や適切な人員配置は、組織の力を最大限に引き出すために欠かせません。評価者である管理職が研修を通じてマネジメントスキルを高めることで、部下との信頼関係も深まり、チームとしての結束力が強くなります。これにより、職場全体のコミュニケーションが活性化し、課題に対して協力しながら解決できる体制が整っていきます。
また、人事評価制度が組織の目指す方向や戦略としっかり連動し、正しく運用されていることで、組織は環境の変化にも柔軟に対応しながら、高い成果を持続的に出し続けることが可能になります。人事評価研修は、そのための基盤づくりとして非常に重要な役割を果たします。
人事評価研修の実施を検討すべき企業

ここでは人事評価研修を取り入れるべき企業とはどのような企業か、詳しく見ていきます。
人事制度が機能不全を起こしている
もし貴社の人事評価制度が期待通りに機能していない、あるいは従業員から不満の声が多く聞かれるといった状況であれば、人事評価研修の実施を真剣に検討する必要があります。例えば、評価結果が従業員の納得感に繋がっていなかったり、評価者によって評価基準の解釈や運用に大きなバラつきが生じていたりする場合、制度そのものに問題がある可能性に加え、評価者のスキル不足が原因であることも考えられます。人事評価研修は、評価者が制度の目的や評価基準を正しく理解し、公正な評価を行うための知識とスキルを習得する機会を提供し、人事評価制度の実効性を取り戻す一助となります。
目標設定や面談に課題がある
従業員の目標設定が曖昧で成果に繋がりにくい、あるいは人事評価面談が形骸化しており、従業員の成長やモチベーション向上に繋がっていないといった課題がある場合も、人事評価研修の導入を検討すべきサインです。適切な目標設定や効果的な面談は、マネジメントにおいて非常に重要な要素であり、これらのスキルは評価者研修を通じて体系的に学ぶことができます。研修では、目標設定の具体的な方法論や、被評価者の状況に合わせた効果的なコミュニケーション、フィードバックのスキルなどを習得し、目標設定や面談の質を向上させることで、従業員のエンゲージメントを高め、パフォーマンス向上に繋げることが期待できます。
評価者のスキルレベルが低い
評価者である管理職やリーダー層の評価スキルにばらつきがあったり、全体的にスキルレベルが低いと感じられる場合、人事評価研修の実施は喫緊の課題と言えます。評価スキルが低いままでは、公正な評価が難しく、従業員の不満や不信感を招く可能性があります。評価者研修は、評価に必要な知識(評価基準の理解、評価エラーの防止など)に加え、目標設定、評価、フィードバックといった一連のプロセスを適切に進めるための実践的なスキルを習得する機会を提供します。評価者全体のスキルアップを図ることで、組織全体の評価の質を高め、人事評価制度への信頼性を向上させることができます。
人事評価研修を提供している機関

ここでは人事評価研修を提供している機関を特徴と共にご紹介します。
提供機関 | 特徴 | 適している企業・ニーズ例 |
社会保険労務士事務所 | ・労務管理や法令に即した実務的な内容 | ・制度運用の適法性 |
コンサルティング企業 | ・経営戦略や組織課題に基づいたカスタマイズ | ・評価制度と組織戦略を連携させたい企業 |
一般財団法人 | ・公共性が高く、特定分野に特化した研修もあり | ・公平性や社会的視点を重視する団体・公共部門や関連業界に所属する組織 |
学校法人 | ・理論に基づいたアカデミックな内容・eラーニングにも対応可能・最新研究や理論に触れられる | ・体系的に学びたい企業・最新の理論やトレンドを取り入れたい企業 |
人事評価研修のオンライン化をご検討の担当者様は「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
社員教育にイー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、教育プラットフォームとして活用することが可能です。
また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。