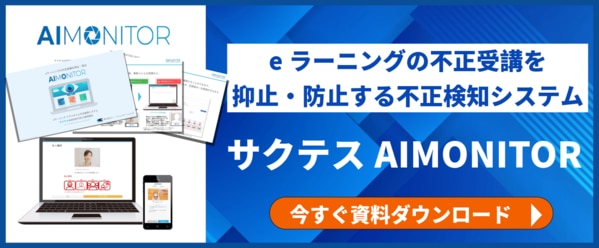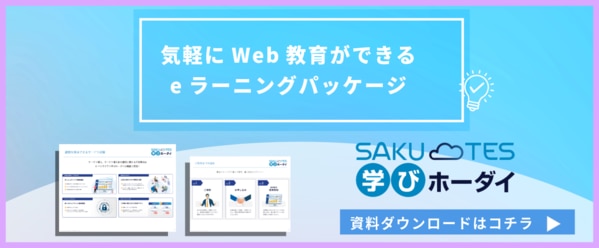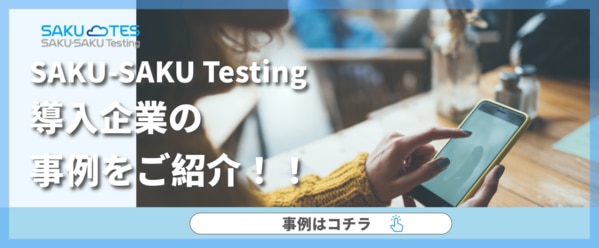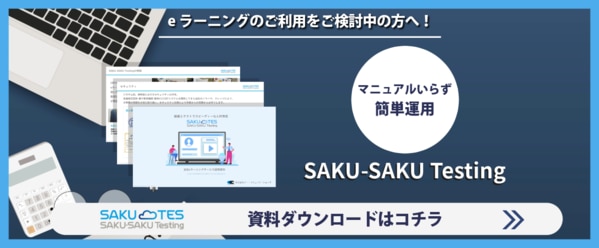ティーチングとは?コーチングとの違いや効果的な使い分けを解説

新人育成や部下育成に携わるマネージャー層やリーダー層にとって、ティーチングとコーチングは重要な人材育成の手法です。しかし、それぞれの明確な違いや具体的な使い分けについて、十分に理解できていないケースも少なくありません。本記事では、ティーチングとコーチングの違い、それぞれのメリット・デメリット、そして具体的な使い分けの場面や効果的な実施方法について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.ティーチングとは
- 2.コーチングとは
- 3.ティーチングとコーチングの違い
- 4.ティーチングの利点と課題
- 5.コーチングの利点と課題
- 6.ティーチングが有効な場面
- 6.1.経験の浅い社員の教育
- 6.2.緊急性の高い業務への対応
- 7.コーチングが有効な場面
- 7.1.自己成長を促したい場合
- 7.2.自主性を引き出したい場合
- 8.ティーチングをより効果的に行う方法
- 8.1.具体的な指導の実施
- 8.2.継続的なフィードバック
- 9.コーチングの効果を高める方法
- 9.1.目標設定と期間の明確化
- 9.2.自発的な思考の促進
- 10.まとめ
- 11.社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ
ティーチングとは
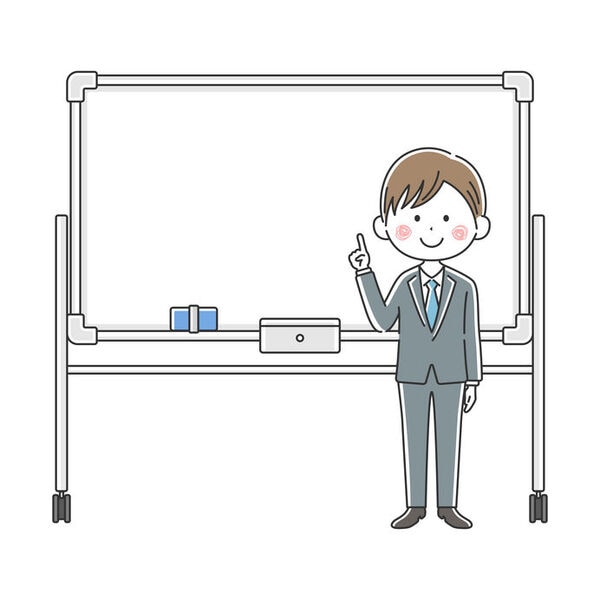
ティーチングとは、指導者自身がもつ知識、スキル、経験、心構えを相手に直接教える指導法を指します。学校教育における教師から生徒への指導のように、明確な答えや解決策を提示し、受講者がそれを習得することで、特定の目標達成や課題解決を目指すものです。
この指導法は、特に新入社員や経験の浅い社員に対し、業務に必要な基礎知識や手順、会社のルールなどを効率的に習得させる際に有効な手段として用いられます。ティーチングは、指導される側の知識やスキルが不足している場合に、短期間でのレベルアップを可能にする指導法であり、その即効性が大きな特徴です。
コーチングとは

コーチングとは、コーチと支援対象者が対等なパートナーシップを築き、対話や問いかけを通じて、対象者自身が内側にある答えや可能性を見つけ出し、自律的な成長を促進する人材育成の基本手法です。
コーチは直接的なアドバイスや解決策を教えるのではなく、質問を投げかけ、傾聴することで、対象者が自身の思考を深め、新たな気づきを得られるようにサポートします。
一例として、「あなたはどうしたいですか?」「そのために何ができますか?」といった問いかけを通じて、対象者が主体的に目標設定や課題解決に取り組むことを促します。このプロセスにより、対象者は自ら考えて行動する習慣を身につけ、潜在能力を最大限に引き出すことが期待されます。コーチングは、特に自己成長への意欲が高い人や、自力で問題解決能力を向上させたい場合に有効な方法とされています。
ティーチングとコーチングの違い

ティーチングとコーチングはどちらも人材育成の手法ですが、そのアプローチ、目的、そして求められるスキルにおいて明確な違いがあります。ティーチングとコーチングは、対象者や状況に応じて適切に使い分けることで、より効果的な人材育成が可能となります。
ゴール
ティーチングの目的は指導者がもっている知識やスキルを相手に伝え特定の問題解決や目標達成を短期間で実現させることにあります。
例えば新しいシステムの使い方や業務の手順など明確な答えがある事柄について指導者が具体的な方法を教えることで相手が迅速にその知識やスキルを習得し課題を解決することを目指します。これに対してコーチングの目的は対象者自身が答えを見つけ出し自らの力で成長していくことを促進することです。コーチは質問や対話を通じて相手の思考を深め潜在能力を引き出すことで長期的な視点での自律的な成長を支援します。
つまりティーチングは答えを教えることで短期的な成果を追求するのに対しコーチングは答えを導き出す手助けをすることで対象者の主体的な成長と中長期的なパフォーマンス向上を目指す点に違いがあります。
取り組み方
ティーチングとコーチングでは、指導の取り組み方に大きな違いがあります。
ティーチングは、指導者が一方的に知識やスキルを伝える「指示型」の指導方法です。具体的には、指導者が模範を示したり、手順を詳細に説明したりすることで、受講者が正確にそれを再現できるように促します。
具体的には、ビジネスマナー研修や新しいツールの操作説明など、明確な答えや定まった手順がある場合に効果的です。この方法は、短期間で大人数に一貫した情報を伝えるのに適しており、効率的な知識伝達が可能です。
一方、コーチングは「支援型」の指導方法で、コーチと対象者が対等な関係で対話を進めます。コーチは質問を投げかけ、対象者が自ら考え、行動計画を立てるプロセスをサポートします。
例を挙げると、部下が新しい企画を立案する際に、コーチが「どのような目標を達成したいか」「そのために何が必要か」といった質問をすることで、部下自身が思考を深め、自律的に解決策を見つける手助けをします。このように、ティーチングが「教える」ことに重点を置くのに対し、コーチングは「引き出す」ことに重点を置き、対象者の主体性を尊重する指導法という点で、根本的な方法が異なります。
求められるスキル
ティーチングとコーチングでは、指導者に求められるスキルが大きく異なります。
ティーチングにおいては、指導内容に関する専門知識や経験が最も重要です。正確かつ分かりやすく情報を伝える説明力や、複雑な内容を分解して順序立てて教える構成力が求められます。また、相手の理解度を確認しながら進める確認力も不可欠です。指導者は、自身がもつ知識やノウハウを体系的に整理し、相手が短時間で効率的に習得できるよう工夫するスキルが求められます。
一方、コーチングにおいては、相手の考えや感情を引き出す傾聴力と質問力が非常に重要です。コーチは相手の言葉だけでなく、非言語的なメッセージにも耳を傾け、深いレベルで理解しようと努めます。そして、相手の気づきを促すようなオープンな質問を投げかけ、自発的な思考を促すスキルが求められます。さらに、相手の成長や努力を認め、肯定的なフィードバックを与える承認力も不可欠です。
このように、ティーチングが知識伝達のスキルを重視するのに対し、コーチングは相手の内面を引き出し、自律的な成長をサポートするコミュニケーションスキルを重視するという違いがあります。
ティーチングの利点と課題

ティーチングには、その即効性や効率性という大きなメリットがある一方で、指導される側の主体性や思考力を阻害する可能性といった課題も存在します。これらの利点と課題を理解することで、ティーチングをより効果的に活用できるようになります。
ティーチングの利点
ティーチングのメリットは、表の3点が挙げられます。
メリット | 内容 | 具体例 |
即効性・効率性が高い | 短時間で必要な知識やスキルを効率よく伝えられる。緊急時や基本知識の習得に適している。 | ・新入社員の電話応対指導 |
大人数への教育が可能 | 講義形式での実施により、多人数に同時に教えることができ、教育コストの削減にもつながる。 | ・ビジネスマナー研修 |
共通認識の形成に効果的 | 全員が同じ内容を同じ方法で学ぶことで、業務における認識のズレを防ぎ、チームや組織全体の生産性向上に貢献する。 | ・営業ツールの使い方 |
これらのメリットは、特に時間やリソースが限られているビジネスの現場において、人材育成を効率的に進める上で大きな強みとなります。
ティーチングの課題
ティーチングには下表のように課題も存在します。
課題 | 内容 | 具体例・影響 |
指導者の知識に依存する | 指導者が持つ知識・経験の範囲内でしか教えられないため、限界がある。特に新しい問題には対応しづらい。 | ・新たなトラブルに対して指導者が適切な解決策を示せない |
部下の自立性が育ちにくい | 一方的に答えを与えることで、部下が自分で考える機会を失い、指示待ちになりがち。 | ・課題解決能力や改善提案力が育たない |
モチベーションの低下につながる | 常に「教えられる側」でいることに不満を感じたり、意見が尊重されないと感じたりすることで、学習意欲や業務意欲が下がる可能性がある。 | ・経験のある部下が成長機会を感じられず不満を持つ |
これらの課題を認識し、ティーチングを補完する他の育成手法と組み合わせることが重要です。
コーチングの利点と課題

コーチングは、対象者の自律的な成長を促し、潜在能力を引き出すという大きなメリットをもつ一方で、成果が出るまでに時間がかかる点や、コーチ自身のスキルが重要になる点などの課題も存在します。これらの利点と課題を理解することは、効果的な人材育成戦略を構築する上で不可欠です。
コーチングの利点
コーチングのメリットは多岐にわたります。
メリット | 内容 | 具体例・効果 |
主体的な成長を促進 | 答えを与えるのではなく対話を通じて気づきを促し、自ら考え行動する力を育てる。 | ・プロジェクトの課題に対し、部下が自分で解決策を導き出す |
潜在能力や可能性を引き出せる | 部下の隠れた強みや才能を引き出し、自己肯定感や挑戦意欲を高める。 | ・自分の得意分野に気づき、自信を持って行動するようになる |
問題解決力・思考力の向上 | 論理的思考や多角的視点を持ち、課題を分析・解決する力を育てる。 | ・将来的な課題にも応用できるスキルが身につく |
信頼関係の構築・コミュニケーション活性化 | 傾聴と対話を重ねることで、上司と部下の信頼関係が深まり、心理的安全性が高まる。 | ・部下が安心して悩みや意見を話せる |
これらのメリットは、組織全体の生産性向上や、自律性の高い人材の育成に大きく貢献します。
コーチングの課題
コーチングには、いくつかの課題も存在します。
課題 | 内容 | 具体例・影響 |
成果が出るまでに時間がかかる | 自発的な気づきと行動を促すプロセスのため、即効性に欠け、短期的な目標達成には不向きな場合がある。 | ・緊急対応が必要な場面では効果が薄く、ティーチングの方が適している |
高度なスキルが必要 | コーチングには傾聴力・質問力・共感力などの高度なコミュニケーションスキルが必要であり、未熟なコーチでは効果が出にくい。 | ・スキル不足のコーチが行うと、部下が不信感を抱いたり、コーチングが逆効果になる可能性も |
一度に多くの人を育成できない | 原則1対1で行うため、複数の部下を同時に指導することが難しく、コーチ側の時間的・精神的負担が大きくなる。 | ・人数が多いと対応が追いつかず、指導の質が低下したり、コーチ自身が疲弊したりする |
これらの課題を理解し、コーチングを導入する際には、目的や対象者の状況を考慮し、他の育成手法とのバランスを検討することが重要です。
ティーチングが有効な場面

ティーチングは、知識や経験が不足している対象者に対して、明確な情報やスキルを効率的に伝える必要がある場合に有効です。具体的なケースを見ていきましょう。
経験の浅い社員の教育
経験の浅い社員や新入社員の教育において、ティーチングは非常に有効な指導方法です。彼らは業務に関する基礎的な知識やスキルが不足しているため、まずは明確な答えや具体的な手順を教えることが重要となります。
代表的なものとしては、会社のビジネスマナー、社内システムの操作方法、基本的な営業トークのスクリプト、安全衛生に関するルールなど、誰もが共通して身につけるべき知識や技術は、ティーチングによる指導が適しています。このような研修では、指導者が一方的に情報を伝えるだけでなく、具体的な事例を交えたり、実践的な演習を取り入れたりする指導法を用いることで、受講者の理解を深めることができます。
また、複数人を対象とした集合研修や座学形式の指導においても、ティーチングは効率的に多くの社員に共通の知識を習得させるのに役立ちます。このように、経験の浅い社員に対しては、まず土台となる知識とスキルをティーチングでしっかりと構築することが、その後の自律的な成長を促す上で不可欠なステップとなるのです。
緊急性の高い業務への対応
緊急性の高い業務への対応は、ティーチングが特に有効な場面の一つです。
例えば、顧客からのクレーム対応、システムトラブル発生時の初動、あるいは予期せぬ事故発生時の緊急措置など、迅速かつ正確な判断と行動が求められる状況では、部下が自ら考えて最適な答えを導き出す時間を十分に取ることができません。このような場合、経験豊富な上司やリーダーが、これまでの経験に基づいた明確な解決策や手順を具体的に指導することで、部下は迷うことなく、迅速に適切な行動をとることができます。ティーチングによって、必要な知識やノウハウを短時間で習得させ、緊急事態への対応能力を高めることが可能です。また、事前にマニュアルを整備し、その内容をティーチングで徹底することも、緊急時の混乱を最小限に抑え、組織全体の対応力を向上させる上で非常に重要です。このケースでは、思考を促すコーチングよりも、直接的に「何をすべきか」を教えるティーチングの方が、事態の早期収束と被害の最小化に直結すると言えるでしょう。
コーチングが有効な場面

コーチングは対象者がすでに一定の知識や経験をもちさらなる成長や自律性を引き出したい場合に特に有効な手法です具体的なケースを見ていきましょう。
自己成長を促したい場合
部下やメンバーが、自身のキャリアやスキルについて深く考え、自己成長を自律的に促したいと考えている場合、コーチングが非常に有効な手法となります。このケースでは、彼らはすでに基本的な業務知識や経験を一定程度もち合わせており、外部からの指示ではなく、自身の内側から答えを見つけることを求めていることが多いです。コーチは、具体的な課題や目標設定のサポートから始め、部下自身が「何を達成したいのか」「そのためにはどのような強みや資源を活用できるのか」といった問いを通じて、自らの潜在能力や可能性を最大限に引き出す力を養うことを支援します。
例えば、新しい役割への挑戦、リーダーシップ能力の向上、あるいは仕事における新たな価値観の発見など、明確な正解がない中で、部下自身が主体的に思考し、行動計画を立てるプロセスをコーチがサポートすることで、内発的なモチベーションが高まり、持続的な成長へとつながります。このような状況で一方的なティーチングを行うと、部下の自律的な思考を妨げ、成長機会を奪ってしまう可能性があるため、コーチングのアプローチがより効果的と言えるでしょう。
自主性を引き出したい場合
部下の自主性を引き出したい場合、コーチングが有効なアプローチとなります。特に、経験を積んだ部下や、課題解決能力を向上させたい部下に対しては、一方的に答えを教えるティーチングでは限界があります。コーチングでは、コーチが問いかけを通じて部下自身の内省を促し、「あなたはどうしたいのか」「そのために何ができるのか」といった質問を繰り返すことで、部下自身が課題の本質を理解し、自力で解決策を導き出す力を養います。
一例として挙げられるのが、新しいプロジェクトの企画立案や、困難な顧客との交渉など、定型的な答えがない状況において、コーチが「どのような情報が必要か」「誰に協力を求めるか」といった具体的な行動を促す質問をすることで、部下は自ら考え、行動する習慣を身につけます。これにより、指示待ちではなく、自ら率先して行動し、問題解決に取り組む自律的な人材へと成長することが期待されます。
コーチングは、部下がもっている能力やアイデアを引き出し、主体的な行動を促すことで、長期的な視点での成長と組織への貢献を可能にします。
ティーチングをより効果的に行う方法

ティーチングは、適切な方法で実施することでその効果を最大限に高めることができます。一方的な情報伝達に終わらせず、相手の理解を促す工夫が重要です。
具体的な指導の実施
ティーチングをより効果的に行うには、具体的な指導法を実践することが重要です。
- 教える内容をできる限り言語化する
●抽象的な概念や属人的な技術でも、明確な言葉で説明する。
●相手がイメージしやすいように、わかりやすい表現を心がける。
→例:「簡潔に書く」ではなく「結論→根拠→考察の順で、一文は30文字以内が目安」な ど具体的に伝える。 - 具体例や手本を交える
●指導内容に関連した実例やケーススタディを提示する。
●実際の業務を想定した例を使うことで理解が深まる。 - 実践的なトレーニングを取り入れる
●座学だけでなく、以下のような実践形式も活用する:
→ロールプレイング(例:報告の練習、接客応対の練習)
→OJT(On-the-Job Training:実務を通じた指導)
●現場に即した知識・スキルが定着しやすくなる。
これらの具体的な指導法を実践することで、ティーチングの効果を飛躍的に高めることが可能となります。
継続的なフィードバック
ティーチングの効果を高めるには、継続的なフィードバックが不可欠です。指導者が一方的に教えるだけでなく、指導を受けた側が内容を理解し、実践できているかを確認し、改善点があれば具体的に伝えることが重要です。具体的には、新しい業務の手順を教えた後、実際に業務に取り組む様子を観察し、良い点や改善すべき点をその場で伝える、あるいは定期的な進捗確認の場を設けて、疑問点や課題を一緒に解決していくといった方法があります。フィードバックは、「できていない点」を指摘するだけでなく、「できている点」も具体的に褒めることで、相手のモチベーションを維持し、自信を育むことにつながります。
また、フィードバックは、教えっぱなしにせず、相手が理解した内容を自身の言葉で説明してもらうなど、アウトプットの機会を設けることで、より定着を促すことができます。これにより、教わった内容が知識としてだけでなく、行動として定着し、次のステップへとつながる土台を築くことが可能となるのです。継続的なフィードバックは、ティーチングを単なる知識伝達で終わらせず、実践的なスキル習得と成長へとつなげる上で非常に重要な要素と言えるでしょう。
コーチングの効果を高める方法

コーチングは、適切に実施することで、部下の自律的な成長と潜在能力の開花を促す強力なツールとなります。効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な方法があります。
目標設定と期間の明確化
コーチングの効果を最大限に高めるためには、まず目標設定と期間を明確にすることが重要です。
- 目標は具体的・測定可能にする
- 抽象的な表現は避け、誰が見ても成果が判断できるように設定する。
- 例:「営業成績を上げたい」ではなく →「3ヶ月で新規顧客を5件獲得、売上を10%向上させる」
- 期限(達成までの期間)を明確にする
- 目標に「いつまでに達成するか」を加えることで、行動計画を立てやすくなる。
- 締切があることで、モチベーションの維持や行動のスピードアップにもつながる。
- 目標設定はコーチと対象者で共有・合意する
- 何を目指すのか、方向性を明確にし、認識のズレをなくす。
- コーチと対象者が同じゴールを見据えることで、サポートが効果的になる。
- 本人が“本当に達成したい”と思える目標にする
- 外から与えられた目標ではなく、本人が主体的にやりたいと感じる目標であることが重要。
- コーチは対話を通じて、内発的動機に基づいた目標を引き出す役割を担う。
- 現実的かつ挑戦的な目標に調整する
- 現状から乖離しすぎないが、少し努力が必要なレベルに設定することで成長を促す。
明確な目標と期間を設定することで、コーチングセッションの方向性が定まり、対象者の主体的な行動を促し、着実に成果へと結びつけることが可能となります。
自発的な思考の促進
コーチングの効果を最大限に高めるためには、対象者の自発的な思考を促進することが不可欠です。コーチは、単に質問を投げかけるだけでなく、対象者が自身の内面と深く向き合い、これまでの経験や知識を総動員して、自ら答えを導き出す力を養うことを重視します。このプロセスにおいて、コーチはオープンな質問を活用しながら、対象者が多角的な視点から物事を捉え、思考を深めることを促します。
部下が業務上の課題に直面しているようなケースでは、すぐに解決策を提示するのではなく、「この課題の根本原因は何だと考えますか?」「過去の経験で似たような状況はありましたか?」「もし仮に解決できたとしたら、どのような状態になりますか?」といった問いを投げかけます。これにより、部下は自力で問題の構造を分析し、潜在的な解決策を発見する力を養うことができます。また、コーチは部下の発言を傾聴し、その思考プロセスを承認することで、部下が安心して自分の考えを表現できる安全な場を提供します。
このような環境は、部下が自信をもって自発的に思考し、行動に移すための重要な土台となるのです。
まとめ

本記事では、ティーチングとコーチングの使い分けについて解説してきました。以下に、これまでの内容を簡単にまとめます。
ティーチングとコーチング
観点 | ティーチング(Teaching) | コーチング(Coaching) |
目的 | 知識・スキルを教えること | 本人の気づき・成長を促すこと |
対象者 | 初学者・未経験者など | 一定の経験がある人・自走できる人 |
アプローチ | 指示・説明・指導型 | 傾聴・質問・支援型 |
主な役割 | 教える人(先生)が主導 | 対話で引き出す(伴走者的) |
コミュニケーション | 一方向が中心(教える→学ぶ) | 双方向(対話を通じて気づきを得る) |
効果 | 短期的な知識習得に有効 | 長期的な成長や自律的な行動に有効 |
想定シーン | 研修、講義、マニュアル指導など | 部下育成、目標達成支援、1on1など |
例 | 「これはこうします」「覚えてください」 | 「どう考えますか?」「あなたならどうしますか?」 |
ティーチングとコーチングには、それぞれの強みがあります。
知識をしっかり伝えたい場面ではティーチング、自分で考え行動してもらいたい場面ではコーチング、のように相手や状況に応じて使い分けることで、より効果的なコミュニケーションや育成につながります。
大切なのは、相手にとって何が必要かを見極め、適切なアプローチを選ぶことです。ぜひ日々の関わりの中で、両方の手法を意識的に活用してみてください。
社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ
社員教育にイー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、教育プラットフォームとして活用することが可能です。
また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
興味をおもちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。