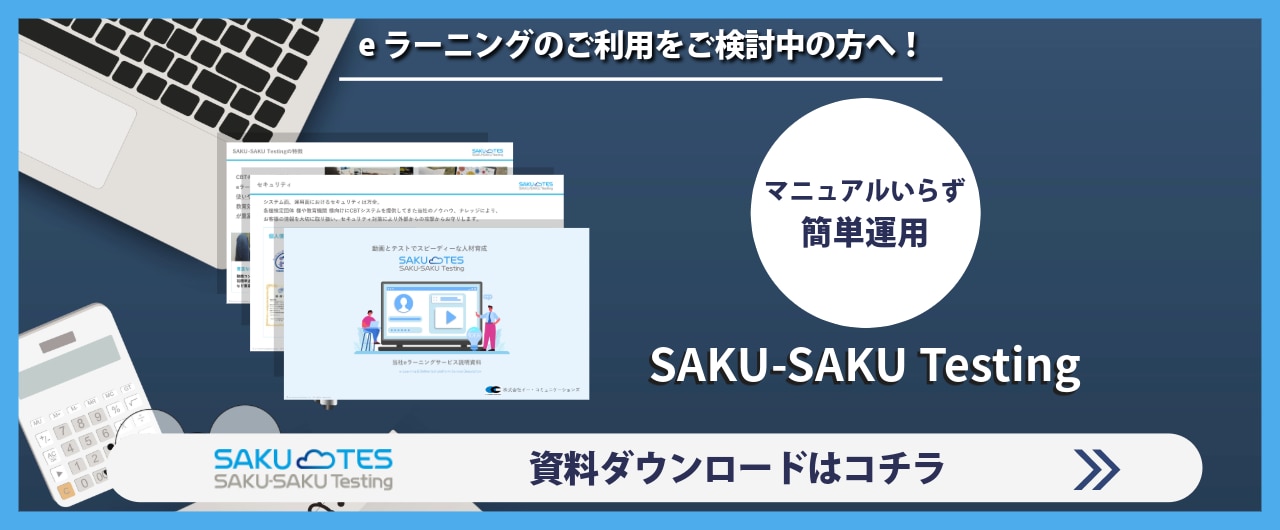タックマンモデルとは?チームビルディングの具体的手法を紹介

チームのパフォーマンスが上がらない、メンバー間の対立が絶えないなど、チーム運営に課題を感じているリーダーは少なくありません。
そうした課題の解決に役立つのが、チームの成長段階を理論的に示した「タックマンモデル」です。
このモデルを理解することで、チームが今どの段階にいるのかを客観的に把握し、次のステップに進むための具体的な施策を打つことが可能になります。
本記事では、タックマンモデルの5つの段階、導入のメリット、特に困難な「混乱期」の乗り越え方、そして各段階でリーダーがとるべき行動について解説します。
目次[非表示]
- 1.そもそもタックマンモデルとは?チームの成長段階を示す理論
- 2.チームが成熟していく5つのプロセス【タックマンモデル】
- 2.1.第1段階「形成期」(Forming):メンバーがお互いを探り合う時期
- 2.2.第2段階「混乱期」(Storming):意見の対立が起こりやすい時期
- 2.3.第3段階「統一期」(Norming):チームのルールや役割が定まる時期
- 2.4.第4段階「機能期」(Performing):チームとして成果を最大化できる時期
- 2.5.第5段階「散会期」(Adjourning):プロジェクト完了とチーム解散の時期
- 3.タックマンモデルをチームビルディングに導入する3つのメリット
- 4.チームの成長に不可欠な「混乱期」を乗り越える方法
- 5.各段階でリーダーが実践すべき具体的な行動
- 5.1.形成期:心理的安全性を確保し、交流を促す
- 5.2.混乱期:対立を恐れず、議論をファシリテートする
- 5.3.統一期:メンバーの役割を明確にし、ルールを確立する
- 5.4.機能期:メンバーに権限を委譲し、自律性を尊重する
- 6.まとめ
- 7.リーダー育成にeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
そもそもタックマンモデルとは?チームの成長段階を示す理論

タックマンモデルとは、1965年に心理学者のブルース・タックマンが提唱した、チームが結成されてから目標を達成し解散するまでの成長プロセスを示した理論です。
このモデルでは、チームは「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」「散会期」という5つの段階を経て成熟していくとされています。
チームが現在どの発展段階にあるかを客観的に把握し、各段階で起こりうる課題を予測して適切な対策を講じるためのフレームワークとして、多くの組織のチームビルディングで活用されています。
5つの成長段階
第一段階 | 形成期 |
第二段階 | 混乱期 |
第三段階 | 統一期 |
第四段階 | 機能期 |
第五段階 | 散会期 |
チームが成熟していく5つのプロセス【タックマンモデル】

タックマンモデルでは、チームの成長プロセスを5段階で定義しています。
チームは「形成期」から始まり、対立が生じる「混乱期」を経て、次第に「統一期」「機能期」へと成熟していきます。
そして、最終的にプロジェクトの完了とともに「散会期」を迎えます。
これらの段階を順番に経ていくのが一般的ですが、各段階を通過するのに要する期間はチームの状況によって異なり、時には前の段階へ逆戻りすることもあります。
ここでは、具体的な5つのプロセスを解説していきます。
第1段階「形成期」(Forming):メンバーがお互いを探り合う時期
形成期は、チームが結成された直後の段階です。
メンバーは互いのことをまだよく知らず、不安や緊張感を抱えているため、遠慮がちで表面的なコミュニケーションが多くなります。
この時期は、リーダーの指示や判断に依存する傾向が強く、メンバーは自発的に行動するよりも指示を待つことがほとんどです。
チームの目標や個々の役割についても理解が浅く、手探りの状態で業務を進めています。
メンバーはまだ「個」として存在しており、チームとしての一体感はほとんどありません。
この形成期では、まずはお互いを知り、関係性を構築することが主な課題となります。
第2段階「混乱期」(Storming):意見の対立が起こりやすい時期
混乱期は、ストーミングとも呼ばれ、チームの成長過程で最も困難な時期とされています。
メンバー間の緊張がほぐれ、それぞれの価値観や仕事の進め方に対する意見を主張し始めることで、対立や衝突が頻繁に起こるようになります。
チームの目標や進め方に対する不満が噴出し、議論が紛糾したり、人間関係が悪化したりすることもあります。
その結果、チームのパフォーマンスは一時的に低下する傾向が見られます。
しかし、この混乱期は、メンバーが本音でぶつかり合い、相互理解を深めるために不可欠なプロセスであり、これを乗り越えることでチームはより強固になります。
第3段階「統一期」(Norming):チームのルールや役割が定まる時期
混乱期での対立を経て、チームは統一期へと移行します。
この段階では、メンバー間の対立が収束し、お互いの価値観や考え方を尊重し合う姿勢が生まれます。
チーム共通の目標が明確に共有され、それを達成するためのルールや規範が確立されていきます。
メンバーそれぞれの役割と責任が明確になり、協力体制が構築されることで、チームとしての一体感が生まれます。
リーダーシップのあり方も変化し、リーダー主導からメンバーの自律性を重んじるスタイルへと移行していきます。
コミュニケーションも活発になり、チームは安定した状態となります。
第4段階「機能期」(Performing):チームとして成果を最大化できる時期
機能期は、チームが最も成熟し、高いパフォーマンスを発揮できる段階です。
メンバーはチームの目標と自身の役割を完全に理解し、自律的に行動します。
リーダーの細かい指示がなくても、メンバー同士が協力し、課題解決に向けて主体的に動くことが可能です。
お互いの強みと弱みを補い合い、相乗効果が生まれることで、個人の能力の総和を大きく超える成果を生み出します。
チーム内に信頼関係が構築されており、建設的な意見交換が活発に行われます。
この機能期にあるチームは、安定して高い成果を出し続けることができます。
第5段階「散会期」(Adjourning):プロジェクト完了とチーム解散の時期
散会期は、プロジェクトの終了や目標の達成により、チームがその役割を終えて解散する段階です。
この時期、メンバーは目標達成への満足感や達成感を共有する一方で、共に活動してきたチームやメンバーとの別れに対して、寂しさや喪失感を抱くこともあります。
この段階では、プロジェクト全体の振り返りを行い、得られた成果や学び、個々の成長などを確認し合うことが重要です。
活動を通じて得た知識や経験を形式知化し、組織の資産として次につなげる役割も担っています。
散会期を適切に経験することで、メンバーは次の活動へ前向きな気持ちで進むことができます。
タックマンモデルをチームビルディングに導入する3つのメリット

タックマンモデルをチームビルディングのフレームワークとして導入することは、理論を学ぶだけでなく、実践的なメリットをもたらします。
チームが成長する過程を地図のように示すこのモデルを活用することで、リーダーやメンバーは自分たちの現在地を把握し、進むべき方向を見定めることが可能になります。
実際のチーム運営の事例においても、タックマンモデルを共通言語とすることで、多くの課題解決の糸口が見つかっています。
ここでは、具体的な3つのメリットについて紹介します。
チームの現状を客観的に把握できる
タックマンモデルを導入する最大のメリットの一つは、チームの状態を客観的に評価できる点です。
チーム運営がうまくいかないと感じる時、その原因が個人の能力や人間関係にあると考えがちですが、モデルに照らし合わせることで、それがチームの成長過程における自然な現象であると理解できます。
「最近、意見の衝突が多い」という状況も、「チームが混乱期に入った証拠」と捉えれば、冷静に対処法を検討できます。
このように、漠然とした問題意識を構造的に理解し、感情的な対立を避けて、建設的な議論の土台を築くための共通認識をもつことができます。
次のステップに進むための課題が明確になる
チームの現在地がタックマンモデルのどの段階にあるかを特定できると、次に目指すべきステップと、そのために乗り越えるべき課題が明確になります。
例を挙げると、まだメンバーが互いに遠慮している「形成期」であれば、相互理解を促進するためのコミュニケーション機会を増やすことが課題となります。
一方、意見対立が激化している「混乱期」であれば、対立を建設的な議論へと導くルール作りや、共通目標の再設定が課題です。
このように、各段階特有の課題を事前に予測し、的を絞った対策を講じられるため、チームの成長を効果的に促進できます。
メンバー間の相互理解を促進する
タックマンモデルをチーム全体で共有することは、メンバー間の相互理解を深める上で非常に有効です。
チームが経験している対立や停滞が、特定の個人の問題ではなく、チームが成長するために必要なプロセスの一部であるという共通認識が生まれます。
これにより、メンバーは現在の状況を前向きに捉え、安心して本音を交わしやすくなります。
例えば、混乱期において「これは成長痛だ」と全員が理解していれば、対立を恐れず、より良い結論を導くための議論に集中できます。
チームビルディングを目的とした研修でゲームなどを通じてこのモデルを学ぶことも、相互理解を促す良い機会となります。
チームの成長に不可欠な「混乱期」を乗り越える方法

タックマンモデルの5段階において、多くのチームが最も困難を感じ、停滞しやすいのが「混乱期」です。
メンバー間の意見の対立が激化し、時には感情的な衝突に発展することもあるため、この時期を乗り越えられずに機能不全に陥るチームも少なくありません。
しかし、この混乱期は、メンバーが本音で向き合い、チームとしての一体感を醸成するために不可欠なプロセスです。
ここでは、この重要な時期を建設的に乗り越え、チームを次のステージへと導くための具体的な方法を解説します。
混乱期はチームの成長痛と捉える
混乱期を乗り越えるための第一歩は、この時期を「チームの成長痛」として認識することです。
意見の対立や衝突は、メンバーがチームの目標達成に対して真剣に向き合いはじめた証拠であり、決してネガティブな現象ではありません。
むしろ、このプロセスを避けて表面的な調和を保とうとすると、本質的な課題が解決されず、チームは成熟できません。
リーダーとメンバーが共に「混乱期は成長のために必要な段階である」という共通認識をもつことで、対立を前向きに受け止め、建設的な議論へとつなげる心構えができます。
この認識の共有が、困難な時期を乗り越えるための精神的な基盤となります。
チーム共通の目標を改めて設定する
混乱期における意見の対立は、多くの場合、目標に対する認識のズレや、個々の価値観の違いから生じます。
そのため、一度立ち止まり、チーム共通の目標をメンバー全員で再確認・再設定するプロセスが非常に有効です。
ワークショップなどを通じて、「このチームは何を成し遂げるために存在するのか」「最終的なゴールは何か」を改めて議論し、全員が納得できる形で言語化します。
共通の目指す先が明確になることで、個人的な意見の対立から解放され、目標達成のために何をすべきかという建設的な視点に議論をシフトさせることができます。
これにより、チームは再び一つの方向へ向かって進む力を得られます。
メンバー同士が本音で話せる場を設ける
混乱期の対立を建設的なものにするためには、メンバーが安心して本音を打ち明けられる「心理的安全性」が確保された場が不可欠です。
リーダーは、定期的な1on1ミーティングや、第三者を交えたファシリテーション付きの会議など、意図的に本音で対話できる機会を設けなければなりません。
また、業務から離れて相互理解を深めるためのワークショップや、チームビルディングを目的としたゲーム形式のイベントを実施することも効果的です。
こうした場で互いの考えや背景を理解し合うことで、意見の対立が個人的な攻撃ではなく、チームをより良くするための協力的なプロセスへと変わっていきます。
各段階でリーダーが実践すべき具体的な行動

タックマンモデルのプロセスを円滑に進め、チームの成長を最大化するためには、各段階の特性に応じたリーダーの関与が不可欠です。
チームの状態によって、求められるリーダーシップのスタイルは大きく異なります。
形成期には方向性を示す強いリーダーが求められる一方、機能期にはメンバーの自律性を尊重する支援者としての役割が重要になります。
リーダーはチームの成長段階を正確に見極め、自らの行動を柔軟に変化させていくことが求められます。
ここでは、各段階でリーダーが実践すべき具体的な行動を解説します。
形成期:心理的安全性を確保し、交流を促す
形成期においてリーダーが最も注力すべきは、メンバーが安心して発言・行動できる心理的安全性の高い環境を作ることです。
メンバーはまだ互いを信頼しておらず、不安を抱えているため、リーダーが率先してコミュニケーションのハブとなる必要があります。
具体的には、自己紹介や相互理解を深めるワークショップの企画、定期的なミーティングでの積極的な声かけ、チームの目標やビジョンの明確な提示などが挙げられます。
この段階では、メンバーが安心してチームに馴染めるよう、リーダーが方向性を示し、支援する姿勢を見せることが重要です。
混乱期:対立を恐れず、議論をファシリテートする
混乱期では、リーダーは意見の対立を恐れず、むしろそれをチーム成長の機会と捉える姿勢が求められます。
対立を無理に抑え込むのではなく、すべての意見が尊重される場を作り、建設的な議論へと導くファシリテーターとしての役割を担います。
感情的な応酬にならないよう、議論のルールを定めたり、論点を整理したりすることが重要です。
また、対立の根底にある価値観の違いをメンバーが理解し合えるよう対話を促し、チーム共通の目標に立ち返ることを働きかけます。
リーダー自身が冷静さを保ち、対立を乗り越えるプロセスを導くことが必要です。
統一期:メンバーの役割を明確にし、ルールを確立する
混乱期を経て合意形成が進む統一期において、リーダーの役割は、チームとしての規範やルールを確立し、定着させることです。
議論を通じて生まれた共通認識を、具体的な行動基準や業務プロセスに落とし込む支援を行います。
メンバーそれぞれの強みや意向を踏まえながら、個々の役割と責任範囲を明確にすることで、自律的な協業体制の基盤を築きます。
この時期、リーダーは指示命令するのではなく、メンバーの意見を積極的に取り入れ、チームが自らルールを作り上げていくプロセスをサポートする姿勢が求められます。
機能期:メンバーに権限を委譲し、自律性を尊重する
チームが機能期に入ると、リーダーは主役の座をメンバーに譲り、支援役に徹することが求められます。
マイクロマネジメントは避け、業務遂行に関する裁量権や意思決定の権限をメンバーへ委譲します。
リーダーの主な役割は、メンバーがパフォーマンスを最大限に発揮できるよう、外部との交渉やリソース確保といった環境整備に注力することです。
また、チームの自律性を尊重しつつも、目標達成に向けた軌道修正が必要な場合には適切なフィードバックを行い、チーム全体のさらなる成長を後押しします。
まとめ

タックマンモデルは、チームが結成から解散に至るまでの自然な成長過程を可視化し、各段階でとるべき行動を示唆する有効なフレームワークです。
このモデルを理解し活用することで、リーダーやメンバーはチームの現状を客観的に把握し、直面する課題に対して的確に対処できるようになります。
特に、多くのチームが困難を感じる混乱期を、成長に必要なプロセスと捉えて建設的に乗り越えることが、高い成果を生み出すチームへの鍵となります。
効果的なチームビルディングを進める上で、このモデルは共通言語として機能し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。
リーダー育成にeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
リーダー育成は企業の成長に欠かせない重要な取り組みです。
しかし、多忙な業務の中で効率的に学びの機会を提供するのは容易ではありません。
ここで注目されるのが「eラーニング」の活用です。
eラーニングは、時間や場所を問わず学べる柔軟性が魅力です。
リーダーに必要なスキルや知識を体系的に学べる講座が豊富なうえ、進捗の管理や効果測定が簡単にでき、人材育成の成果を可視化できます。
イーコミュニケーションズのeラーニングシステム「SAKU-SAKU Testing」では自社で作成したリーダー育成用のコンテンツを搭載して研修を行うことも可能です。
また、「SAKU-SAKU Testing」と共に利用できる、リーダー育成用コンテンツ「ビジネスマネジメント」もご用意しております。
「ビジネスマネジメント」では、「管理職の基本」から「マーケティング」「人材育成」などリーダーとなる方に知っておいてほしい11コースがあり、1本あたりの平均時間5分の動画と確認問題によって構成されています。
短いスキマ時間で効率的に知識を定着させることができることが特長です。
これからのリーダー育成には、業務効率化を高めつつ人材育成をしていくことが求められます。