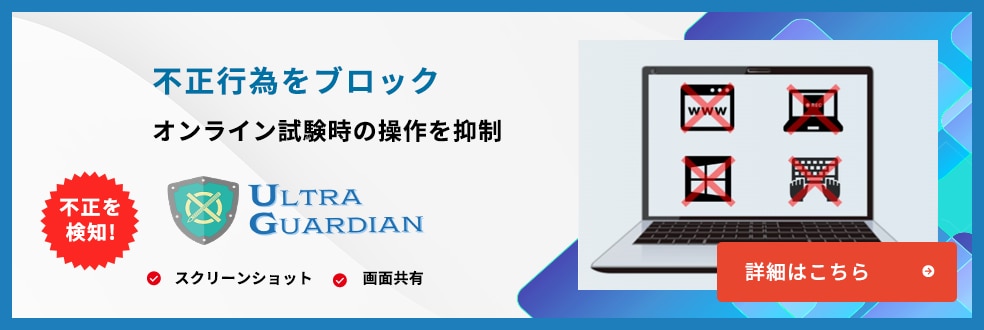司法試験がパソコン受験へ 試験はどう変わる?対策や注意点を紹介
司法試験は2026年実施の試験から紙での筆記試験からパソコンでの受験になると発表されました。
そこでこの記事では、司法試験に関わる専門学校・予備校などの事務局の方に向けて、司法試験CBT化(パソコン受験)に関して現段階でわかっている内容をまとめ、現在紙試験で行っている模試等をCBT化する場合の導入方法やポイントをご紹介します。
目次[非表示]
- 1.司法試験におけるパソコン受験(CBT化)はいつから?
- 2.2026年司法試験CBT化(パソコン受験)へ向けた現状のまとめ
- 2.1.2023年4月1日「司法試験等デジタル化推進企画係」を設立
- 2.2.2025年度から出願手続きのオンライン化・手数料のキャッシュレス化を予定
- 2.3.法務省指定の「CBTテストセンター」で集合形式にて実施予定
- 2.4.使用するパソコンのスペック・文字入力等について
- 3.CBTシステム体験版の利用方法
- 4.司法試験のCBT化(パソコン受験)による注意点
- 5.司法試験のCBT化(パソコン受験)への対策
- 5.1.タイピング力の強化
- 5.2.答案構成のスキルを磨く
- 5.3.時間配分を考えておく
- 5.4.CBT方式で模擬試験を受ける
- 6.司法試験の模擬試験をCBT化(パソコン受験)する際の手順・注意点
- 7.司法試験の模擬試験のCBT化ならイー・コミュニケーションズにご相談ください
司法試験におけるパソコン受験(CBT化)はいつから?
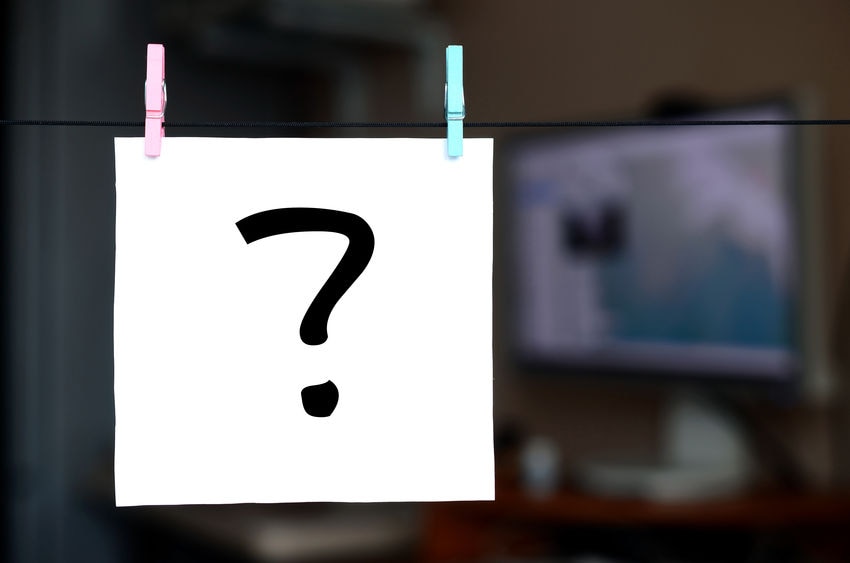
法務省は、2026年(令和8年)の論文式試験から、司法試験でパソコン受験(CBT方式)を導入する予定です。これにより、これまでの紙媒体での筆記試験から、全国の試験会場に設置されたパソコンで解答する形式へと全面的に移行します。
CBT化の主な目的は、試験運営の効率化と受験生の負担軽減です。手書き答案による採点時間の長期化や公平性の課題を解決し、採点業務の迅速化と採点基準の均一化を図ることが期待されています。
出典:法務省|司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化に関する質疑について
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00425.html
2026年司法試験CBT化(パソコン受験)へ向けた現状のまとめ

現時点(2025年9月)でわかっている司法試験CBT化(パソコン受験)へ向けた内容を解説します。
2023年4月1日「司法試験等デジタル化推進企画係」を設立
法務省では、2023年4月1日に省内に「司法試験等デジタル化推進企画係」を設立しました。2026年の司法試験のCBT化開始を目標に準備を進めています。
出典:日経クロステック(2023/7/4)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/08188/
2025年度から出願手続きのオンライン化・手数料のキャッシュレス化を予定
司法試験のデジタル化推進に伴い、出願手続きや受験票、成績通知書の交付といった事務手続きのオンライン化が2025年(令和7年度)から段階的に導入される予定です。
また、受験手数料の支払いについては、2026年(令和8年度)よりキャッシュレス決済が利用可能となる見込みです。
出典:法務省大臣官房人事課|司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について
https://www.moj.go.jp/content/001422584.pdf
法務省指定の「CBTテストセンター」で集合形式にて実施予定
2026年から実施予定のパソコン受験での司法試験は、司法試験委員会(法務省)指定の「CBTテストセンター」を会場として集合形式で実施し、同センターに設置されているパソコン等を使用することが予定されています。
また、CBT方式を導入する司法試験(短答式試験、論文式試験)、司法試験予備試験(論文式試験)のそれぞれにおいて、問題文の紙媒体での配布は行われず、答案構成用紙は配布する(メモ用紙は持ち帰り可)予定としています。
使用するパソコンのスペック・文字入力等について
司法試験のCBT方式では、OSにWindows 11 Pro、メモリは8GB以上のパソコンが使用される予定です。画面解像度は1920x1080ピクセル以上、モニターサイズは23インチ以上を基準とし、周辺機器としてテンキー付きの日本語配列キーボード、USB接続の光学式マウスが用意されます。
文字入力は「日本語Microsoft IME」を使用しますが、予測変換機能は利用できない見込みです。編集機能はコピー&ペーストなどが可能で、一部のキーボードショートカットも使用できますが、インデントや禁則処理といった書式設定機能は利用できない見込みとなっています。
出典:法務省|司法試験等のCBT(Computer Based Testing)方式の導入に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/content/001437905.pdf
CBTシステム体験版の利用方法
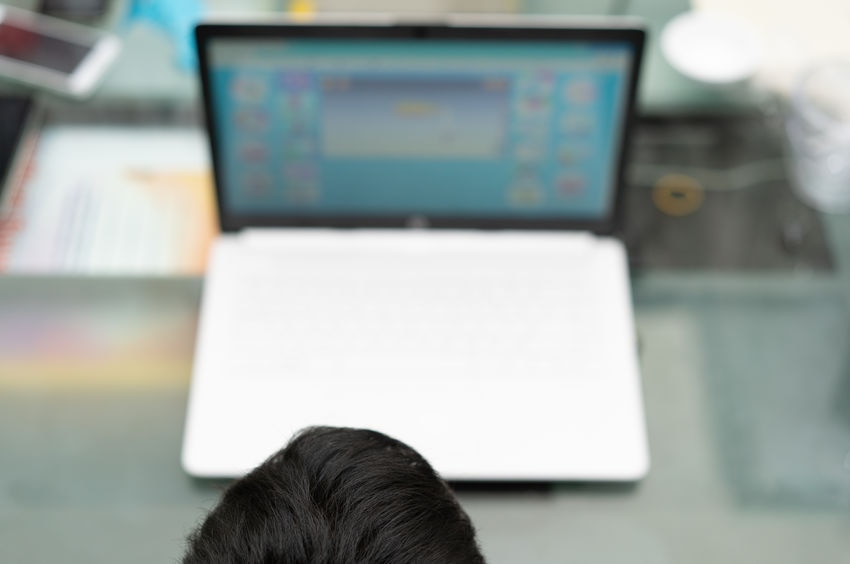
法務省は、受験生がCBT方式の試験に円滑に対応できるよう、司法試験CBTシステムの体験版を公開しています。
この体験版は、法務省のウェブサイトから誰でもアクセスして利用することが可能です。
※以下よりダウンロード可能です
法務省|司法試験等CBTシステム(体験版)
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00238.html
実際の試験で使われるシステムと同様の画面構成や操作感を試すことができ、解答の入力、文字の装飾、見直し機能などを事前に確認できます。
本番で戸惑うことがないよう、操作方法に慣れておくだけでなく、自分なりの使い方や答案作成のシミュレーションを行うために、積極的に活用することが推奨されます。
短答式・論文式別に操作マニュアルが用意されているため、あわせてチェックすると良いでしょう。
・司法試験等CBTシステム体験版操作マニュアル <R7.8版> 【短答式試験】
https://www.moj.go.jp/content/001437908.pdf
・司法試験等CBTシステム体験版操作マニュアル <R7.8版> 【論文式試験】
https://www.moj.go.jp/content/001437909.pdf
司法試験のCBT化(パソコン受験)による注意点

現状の司法試験は3日間の論文式試験と1日の短答式試験となっており、論文式試験では3日間で約4万字を記述する必要があります。CBT化(パソコン受験)により手書きの負担から解放されますが、CBT化による課題もありそうです。現状考えられる課題についてまとめます。
タイピング速度によって解答時間の差が生まれる
現状の司法試験の答案用紙はA4で横書き23行です。1枚びっしりうめると650字~700字くらいの文字量です。
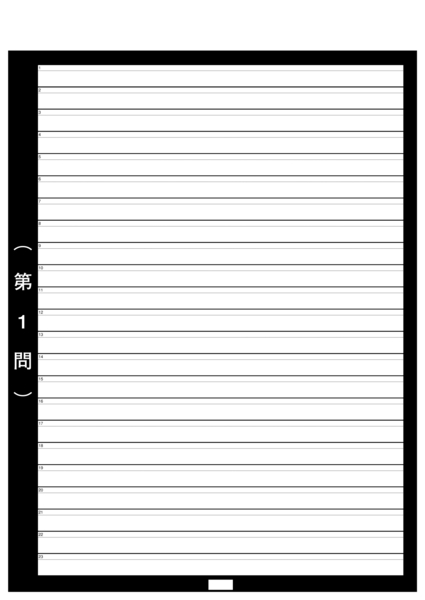
法務省「令和4年(2022年)司法試験 論文式試験答案用紙」
https://www.moj.go.jp/content/001371994.pdf
必須科目は1問について表紙を除いて8枚、選択科目は1問について4枚が配布されます。必須科目は平均5枚以上を書くとされています。一般的な社会人の1分間の平均タイピング文字数は60文字で、5枚分の3500文字をタイピングすると約58分かかることになるでしょう。
現状、解答時間は1問120分となっていますので、タイピングが速ければ速いほど、記述時間を短縮し、答案構成に時間を使うことができます。
このようにタイピングの速さによって解答時間に差が生まれますので、タイピングが速い人が有利になり、遅い人には不利になるでしょう。
答案構成がおざなりになる
パソコンでの受験では、文章を書いたり消したりする作業が簡単にできるため、答案構成をおざなりにし、とりあえず書き始めてしまうことが考えられます。
パソコンでの受験になっても、全体の構成を考えてから書き始めたほうが、理論構成がしっかりした答案を書くことができるので、答案構成は必要です。
試験問題や採点方法が変更になる可能性がある
従来の司法試験が手書き方式だったのに対し、パソコン方式(CBT方式)に変わることで、試験問題の傾向や採点方法も変わる可能性があります。
タイピングによる答案作成の高速化に伴い、出題問題数が増加する可能性や、より深い思考力を問う問題が出される可能性が想定されます。
また、答案のデジタル化によって、採点基準や評価方法そのものが見直されることもあり得ます。
司法試験のCBT化(パソコン受験)への対策

司法試験のCBT化に関して、まだ具体的なことはわかっていませんが、現時点でできる対策について解説します。
タイピング力の強化
CBT化により、タイピング力によって解答時間に差が生まれることがわかりました。今すぐにできる対策として、タイピング力の強化が考えられます。
速く正確に打つことを心がけ、タイピングで不利にならないように備えることが大切です。
答案構成のスキルを磨く
答案構成は問題文を読み、論点を考え、解答に書くべき内容を洗い出し、答案の構成を決定する、答案の設計図を作るような作業です。現状の紙の試験で行っていることですが、CBT化する際にも問題形式が大きく変わらない限り、答案構成が必要になります。
そのため、答案構成のスキルを磨くことで、論理立ったしっかりとした構成で記述をすることができます。
時間配分を考えておく
CBT化によって、答案作成にかかる時間が手書きの時と変わるため、時間配分の見直しが必須です。タイピング速度が上がれば、記述に要する時間は短縮される可能性がありますが、その分、問題文の読解や答案構成にじっくり時間をかける戦略も考えられます。
一方で、パソコン操作に慣れていない場合は、想定外のところで時間をロスするかもしれません。
模擬試験などを通じて、自分自身のタイピング速度や思考のペースを把握し、「問題把握・答案構成・執筆・見直し」の各工程に何分ずつ割り当てるか、最適なバランスを見つけ出す訓練が必要です。
CBT方式で模擬試験を受ける
CBT化への対策の一つは、CBT形式での模擬試験を経験することです。実際の試験環境に近い状況で問題を解くことで、多くの気づきを得られます。
パソコンの画面で長時間、集中して長文を読み書きすることに慣れるだけでなく、時間配分や疲労の度合い、答案構成の具体的な方法などを実践的に確認できます。
各予備校などが提供するCBT模試を積極的に活用し、本番のシミュレーションを重ねることで、技術的な操作への不安を解消し、精神的な余裕をもって本番に臨むことができます。
司法試験の模擬試験をCBT化(パソコン受験)する際の手順・注意点

司法試験がCBT化すると、現状行っている模擬試験もCBT化したほうがいいのではないかとお考えの専門学校・予備校などの事務局の方もおられると思います。
そこで、ここでは紙試験で行っている模擬試験をCBT化する際の手順をご紹介します。
今回はとくに、CBTサービスを提供している会社に依頼して導入する方法について解説します。依頼する会社によって手順が異なる場合がありますので、実際に導入時には導入手順をしっかり把握してください。
手順としては以下の4つステップで進めていきます。
- ヒアリング(自社-依頼会社)
- 要件定義(依頼会社)
- 設計・開発(依頼会社)
- 運用開始(自社)
それぞれの手順についてみていきましょう。
①ヒアリング
CBT化するにあたって、まずは、依頼会社が自社の現状について詳細のヒアリング調査を行います。現状の紙試験で抱えている課題はもちろん、司法試験CBT化に向けて必要な項目の洗い出しをするなど、CBT化に関わるさまざまな事項について依頼会社と細かくすりあわせを行っていくフェーズです。
②要件定義
ヒアリングが終わったら、試験仕様に関する要件定義を依頼会社が行います。現状実施している試験をベースとして、具体的な内容を詰めていくフェーズです。
決めるべき内容としては、具体的に以下のようなものがあります。
・問題数
・試験時間
・出題形式(〇×選択式/複数選択式/記述式など )
・問題の難易度・分類
・合格点
③設計・開発
要件定義に則り、依頼会社が試験問題を規定のフォーマットに落とし込んで設計・開発を行います。受け入れの際には、CBTシステムとしてニーズをしっかり満たしているかどうかを確認する必要があります。
題の内容や妥当性はもちろん、フォーマットや出題文の表現、類似問題はないか、難易度が極端に異なる問題はないかなどを細かく確認しましょう。
④運用開始
完成したCBTに問題がなければ、実際に運用開始となります。リリース後も、依頼会社のカスタマーサポートなどと連携して運用していく必要があります。
運用を開始してから重視しなければならないポイントが、成績と受験者情報の管理です。受験者ごとの合否はもちろん、受験者の属性や点数ごとのサマリーの抽出、問題ごとの正答率や解答時間なども確認ができると、傾向と対策の分析に役立ちます。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。
↓↓
CBT試験とは?ほかの試験との違いやメリット、導入方法を徹底解説
司法試験の模擬試験のCBT化ならイー・コミュニケーションズにご相談ください
弊社は試験配信の運用実績が豊富で、毎年100万人規模の試験を安定稼働させています。絶対評価・相対評価など評価機能を選ぶことができ、柔軟な運用が可能です。
さらに設問や個人情報の流出を防ぐセキュリティの高い仕様で、大規模な同時受験も問題ありません。試験中はオフラインにすることも可能で、サーバーの負担を心配する必要もありません。
また、数々の業種でさまざまな形式の試験を実施してきたので、コンサルティングから支援が可能です。そしてテスト分析による問題の精査・ブラッシュアップも伴走支援させていただきます。受験者の管理もしやすい工夫がなされています。
導入を決定していなくても、ご興味がおありでしたら、まずは「お問い合わせ」からご連絡ください。
もちろんご質問だけでも結構です。ご要望をお伺いしつつベストなご提案をさせていただきます。