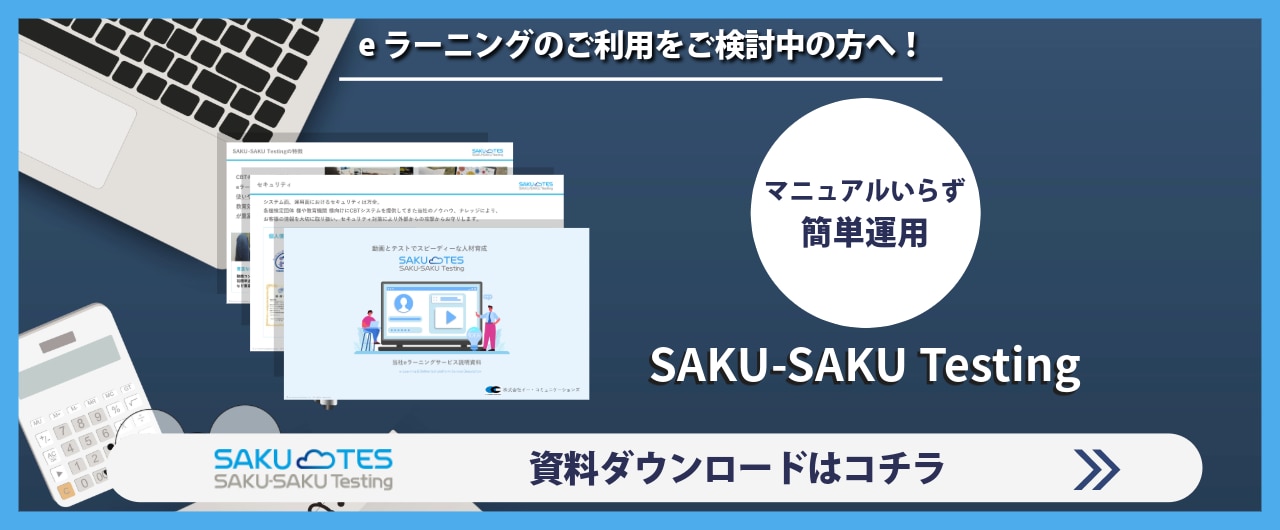管理職研修が意味ないと言われる5つの原因|目的の見直しで変わる改善策

多くの企業で実施される管理職研修ですが、「時間とコストをかけたのに効果が見えない」「結局何も変わらない」といった声が聞かれることがあります。
研修が無駄だったと感じられる背景には、企画や運営における明確な理由が存在します。
研修が意味ないものに終わるか、組織の成長を促す投資となるかは、その目的をいかに明確にし、受講者や組織の現状に即した設計ができるかにかかっています。
本記事では、管理職研修が形骸化する原因を分析し、その改善策を解説します。
▼資料ダウンロード:管理職に知っておいてほしい11コースのeラーニングコンテンツ
目次[非表示]
- 1.管理職研修が「意味ない」で終わってしまう5つの原因
- 1.1.① 研修の目的が曖昧で受講者と共有できていない
- 1.2.② 研修内容が古く、現場の実態とかけ離れている
- 1.3.③講義を聞くだけで、実践的なスキルが身につかない
- 1.4.④ 研修後のフォローアップがなく、学びが継続しない
- 1.5.⑤受講者本人が「やらされ感」で参加している
- 2.そもそも管理職研修はなぜ必要なのか?本来の目的を再確認
- 3.「意味ない研修」を「価値ある投資」に変える5つの改善策
- 3.1.①自社の課題から逆算して研修のゴールを設定する
- 3.2.②受講者のレベルや課題に合わせたプログラムを設計する
- 3.3.③アウトプット中心の演習で「できる」状態を目指す
- 3.4.④研修後の行動計画を立て、上司も巻き込み実践を促す
- 3.5.⑤研修の重要性を事前に伝え、参加意欲を高める
- 4.【目的別】効果的な管理職研修の主な種類
- 5.まとめ
- 6.管理職向けのeラーニングに「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
管理職研修が「意味ない」で終わってしまう5つの原因

管理職研修が期待された効果を発揮せず、「意味ない」という評価で終わってしまう背景には、いくつかの共通した原因が存在します。
これらの原因は、研修の企画段階から実施後まで、さまざまなプロセスに潜んでいます。自社の研修がうまくいかないと感じる場合、まずはこれらの典型的な課題に当てはまっていないかを確認し、問題の所在を特定することが改善の第一歩となります。
ここでは、研修が失敗に終わる主な5つの原因を掘り下げていきます。
① 研修の目的が曖昧で受講者と共有できていない
管理職研修の目的が「管理職としての自覚を促す」といった抽象的なレベルに留まっている場合、受講者は研修で何を学ぶべきかを具体的に理解できません。
企業側が研修を通じてどのような能力を身につけ、どのような行動変容を期待しているのかが明確に定義されていないと、研修内容は散漫になり、受講者の学習意欲も低下します。
例えば、「部下の主体性を引き出すためのコーチングスキルを習得する」というように、研修後に達成すべきゴールを具体的かつ行動レベルで設定し、それを事前に受講者と共有することが不可欠です。
目的が共有されて初めて、受講者は研修を自分事として捉え、主体的に学ぶ姿勢をもつことができます。
② 研修内容が古く、現場の実態とかけ離れている
過去の成功体験に基づいた精神論や、変化の激しい現代のビジネス環境にそぐわない古い理論をベースにした管理職研修の内容では、受講者は実践の場で活用できません。
特に、働き方の多様化やリモートワークの普及、コンプライアンス意識の高まりなど、管理職が直面する課題は年々複雑化しています。
研修内容がこうした現場の実態から乖離していると、受講者は「理想論ばかりで役に立たない」と感じてしまいます。
自社の置かれた状況や、管理職が実際に抱えている悩みに寄り添った、実践的で最新の内容にアップデートし続けることが、研修の価値を高める上で必要です。
③講義を聞くだけで、実践的なスキルが身につかない
講師の話を一方的に聞く座学中心の研修では、知識として「知っている」状態にはなっても、スキルとして「できる」状態にはなりません。
管理職に求められるのは、知識そのものではなく、現場で部下やチームを動かす実践的なスキルです。そのためには、インプットだけでなくアウトプットの機会を豊富に盛り込んだカリキュラム設計が求められます。
部下との面談を想定したロールプレイングや、自部署の課題解決策を議論するグループワークなどを通じて、学んだことをその場で試行錯誤する経験が、スキルの定着と行動変容を促します。
知識偏重のカリキュラムを見直し、演習の比重を高めるべきです。
④ 研修後のフォローアップがなく、学びが継続しない
研修が単発のイベントで終わり、その後のフォローアップがなければ、学習した内容は時間とともに忘れ去られます。研修直後は意欲が高まっていても、日々の業務に追われるうちに、意識や行動は元に戻ってしまうことが少なくありません。
研修の成果を持続させるためには、学びを現場で実践し、定着させるための仕組みが必要です。
例えば、数ヶ月後にフォローアップ研修を実施して実践状況を振り返ったり、研修で立てた行動計画の進捗を上司と共有する場を設けたりすることが有効です。
計画的かつ適切な頻度でのフォローがなければ、研修の効果は限定的なものに終わります。
⑤受講者本人が「やらされ感」で参加している
研修の効果を大きく左右するのが、受講者本人の参加意欲です。
会社からの指示で義務的に参加しているだけで、本人が研修の必要性を感じていない場合、学習効果は著しく低下します。この「やらされ感」のマインドは、研修内容が自身の課題解決やキャリア形成にどう結びつくのかを理解できていないことに起因します。
なぜ今この研修が必要なのか、その背景にある組織の課題や本人への期待を事前に丁寧に伝えることが重要です。
研修を受けることのメリットを本人が納得して初めて、主体的な学習姿勢が生まれ、研修内容の吸収率も高まります。
そもそも管理職研修はなぜ必要なのか?本来の目的を再確認

管理職研修が「意味ない」と批判される一方で、組織運営におけるその重要性は揺るぎません。
多くの従業員は、専門スキルをもつプレイヤーとしては優秀でも、マネージャーとして必要なスキルを自然に身につけているわけではありません。この役割転換を円滑に進め、組織全体のパフォーマンスを向上させるために、管理職研修の必要性があります。
ここでは、研修が果たすべき本来の目的を3つの観点から再確認し、その本質的な価値を見つめ直します。
組織全体の生産性を向上させるため
管理職のマネジメント能力は、担当するチームや部署の業績、ひいては組織全体の生産性に直接的な影響を及ぼします。優れた管理職は、明確な目標を設定し、部下一人ひとりの能力や意欲を引き出し、チームとして最大の成果を創出する役割を担います。
管理職研修は、目標管理、業務の進捗管理、人材育成、チームビルディングといったマネジメントの基本スキルを体系的に提供します。
これらのスキルを習得した管理職が増えることで、各部署の運営が効率化され、結果として企業全体の生産性向上につながるのです。
時代の変化に対応できるリーダーを育成するため
現代のビジネス環境は、グローバル化、デジタル化、価値観の多様化など、目まぐるしく変化しています。このような状況下で管理職に求められるのは、単なる業務遂行の管理者ではなく、変化を捉え、組織を導くリーダーシップです。
特に、ハラスメント防止や適切な労務管理といったコンプライアンス遵守は、組織のリスク管理において極めて重要です。法改正や社会情勢の変化に対応した知識を継続的にアップデートしなければ、厳しい経営環境を乗り切ることはできません。
管理職研修は、こうした時代の要請に応えられるリーダーを育成するための不可欠な機会となります。
管理職の育成に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
↓
管理職に求められるスキルと育成のポイント:組織成果につなげる実践ガイド
経営層と現場をつなぐパイプ役を担うため
管理職は、経営層が示すビジョンや戦略を現場の従業員に具体的に伝え、日々の業務に落とし込むという重要な役割を担います。同時に、現場で起きている問題や従業員の意見を吸い上げ、経営層にフィードバックするパイプ役でもあります。
この双方向のコミュニケーションが円滑に行われることで、組織の一体感が高まり、戦略の実行力も向上します。
研修という共通のテーマを通じて、自社の経営方針や全社的な課題への理解を深めることは、管理職が経営視点と現場視点の双方を併せもち、組織の中核として機能するための土台を築く上で効果的です。
管理職研修については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
↓
管理職研修とは?種類や内容・目的別プログラム例まで詳しく紹介
「意味ない研修」を「価値ある投資」に変える5つの改善策

管理職研修を形骸化させず、組織の成長につながる「価値ある投資」へと転換するためには、具体的な改善策が必要です。研修が意味ないと言われる原因を解消し、効果を最大化するためのポイントは、企画から実施、そしてフォローアップまで一貫しています。
ここでは、すぐに実践できるおすすめの改善策を5つに絞って具体的に解説します。これらの視点を取り入れることで、研修の質は大きく向上するはずです。
①自社の課題から逆算して研修のゴールを設定する
効果的な研修を企画する上で最も重要なのは、出発点を自社の具体的な課題に置くことです。
- 「若手社員の離職率が高い」など、自社の具体的な課題を明確にし、その解決のために管理職に求められるスキルや行動を分析します。
- 「研修終了後、部下との1on1ミーティングを月1回実施し、キャリア開発を支援できる状態になる」のように、具体的で測定可能な行動レベルでゴールを設定します。
課題から逆算してゴールを定めることで、研修プログラムの軸が明確になり、内容の取捨選択も容易になります。
②受講者のレベルや課題に合わせたプログラムを設計する
新任管理職、中堅管理職、上級管理職では、直面している課題や求められる役割が大きく異なります。そのため、全管理職に同じ内容の研修を一律で実施しても、十分な効果は期待できません。受講者の階層や役職、経験年数に応じて、研修の難易度や内容をカスタマイズすることが不可欠です。
事前にアンケートやヒアリングを実施し、受講者がどのような点に悩んでいるのか、どのようなスキルを求めているのかを把握した上でカリキュラムを設計することで、学習効果と満足度を高めることができます。
③アウトプット中心の演習で「できる」状態を目指す
研修の成果を現場での行動変容につなげるためには、知識のインプットに加えて、実践的なアウトプットの機会を豊富に設けることが極めて重要です。学んだ理論やスキルをその場で実際に使ってみることで、理解が深まり、スキルとして定着します。
例えば、困難な状況にある部下への対応を想定したケーススタディや、自部署の業務改善計画を立案し発表するグループワークなどが有効です。
講師からの一方的な講義時間を減らし、受講者が主体的に考え、話し、行動する演習中心のプログラムにすることで、「知っている」から「できる」への移行を促します。
④研修後の行動計画を立て、上司も巻き込み実践を促す
研修で得た学びを一時的なもので終わらせず、現場で継続的に実践させるためには、研修後の仕組みづくりが不可欠です。研修の最後に、学んだことを自身の業務にどう活かすか、具体的な行動計画(アクションプラン)を受講者自身に作成させます。
さらに、その計画を本人の上司にも共有し、定期的な面談などで進捗を確認し、フィードバックを行う体制を整えます。
上司が部下の成長を支援する役割を担うことで、職場全体で学びを実践する文化が醸成され、研修効果の定着が促進されるマネジメントが実現します。
⑤研修の重要性を事前に伝え、参加意欲を高める
受講者の学習効果は、研修に臨むマインドに大きく左右されます。
「やらされ感」を払拭し、主体的な参加を促すためには、事前の動機付けが鍵となります。
なぜ会社としてこの研修を実施するのか、その背景にある課題意識や管理職に対する期待を、経営層や人事責任者から直接伝える機会を設けることが有効です。
また、この研修で得られるスキルが、受講者自身の市場価値向上やキャリアプランにどう貢献するのかを具体的に示すことで、研修を「自分事」として捉えるようになります。
丁寧な事前説明を通じて、受講者の学習意欲を高める働きかけが重要です。
【目的別】効果的な管理職研修の主な種類

一口に管理職研修といっても、その対象者や目的によって内容は多岐にわたります。
自社の育成課題に最適な研修を選ぶためには、どのような種類があるのかを把握することが重要です。新任、中堅、そして将来の候補者といった階層ごとに、求められるスキルや視点は異なります。
ここでは、代表的な3つの階層別に、効果的な研修の目的と内容を解説します。
新任管理職向け|マネジメントの基礎を学ぶ
- 目的:プレイヤーからチーム全体の成果を最大化する役割への意識転換
- 内容:目標設定、業務管理、部下指導、労務管理といったマネジメントの基本知識とスキル、効果的なコミュニケーション方法、チームビルディングの初歩
これまで自己の業務遂行に集中してきた人材が、組織を動かす側に立つための第一歩を支援します。
中堅・上級管理職向け|組織開発や部下育成スキルを強化する
管理職として一定の経験を積んだ中堅・上級管理職には、より高度なスキルが求められます。
- 目的:担当部署の業績向上に加え、組織全体の課題解決や変革をリードする能力の強化
- 内容:組織開発、戦略的人材育成、次世代リーダーの選抜・育成、コーチングやメンタリングなどの高度な部下育成手法
自身のマネジメントスタイルを客観的に見つめ直し、コーチングやメンタリングなどの高度な部下育成手法を学ぶことで、組織に良い影響を与える変革の担い手としての能力を強化します。
管理職候補者向け|次世代リーダーとしての視座を高める
将来の組織を担うリーダー候補を選抜し、早期から育成するための研修です。
- 目的:将来の組織を担うリーダー候補として、経営者的な視点やリーダーシップマインドの醸成
- 内容:経営戦略、財務状況、市場環境などのマクロな情報インプット、全社的な視点から事業課題を考える訓練、異業種交流や経営幹部との対話
異業種交流や経営幹部との対話などを通じて、自身の専門領域を超えた広い視野を獲得し、将来の経営幹部としての当事者意識を高めるマインドセットを形成します。
まとめ

管理職研修を「意味ない」ものにしないためには、目的の明確化、内容の最新化、実践機会の増加、継続的なフォローアップ、そして受講者の参加意欲向上という5つの原因と改善策に体系的に取り組むことが不可欠です。研修を単発の施策ではなく、人材育成戦略の一環としてデザインすることで、組織の成長につながる「価値ある投資」へと転換できます。
研修を単発の施策ではなく、人材育成戦略の一環として体系的にデザインする視点が、その成否を分けます。
管理職向けのeラーニングに「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
管理職向けのeラーニングには、弊社のeラーニングコンテンツ「ビジネスマネジメント」をぜひご活用ください。
「管理職の基本」から「マーケティング」「人材育成」など管理職の方やマネージャー候補の人材向けに、管理職に知っておいてほしい11コースをご用意しております。管理職にマネジメント・経営目線の能力を身につけさせたい、管理職候補の人材に管理職としての能力を身につけさせたいとお考えの企業様におすすめです。
例えば、プロジェクトマネジメントを学ぶコンテンツでは、「プロジェクトマネジメントとは」から始まり「プロジェクトの終了」まで主に7つのコンテンツがあります。業務の確実な遂行の責任をもつ管理職として、必要な行動を学ぶことが可能なため、マネジメントスキル向上におすすめのコンテンツです。
また、人材育成を学ぶコンテンツでは、「人的資本経営」「モティベーションマネジメント」「パフォーマンスマネジメント」「メンバーの状況に応じた対応」「評価とフィードバック」「アンコンシャスバイアス」「1on1コミュニケーション」などがあります。
メンバーの協働を促し、チームを活性化する管理職として、リーダーとしての行動を学ぶことが可能なため、部下育成スキルを養いたい時や評価スキル向上を目指す際におすすめのコンテンツです。
さらに、コンプライアンスを学ぶコンテンツでは、「コンプライアンスの重要性」「労働基準法と労務管理」「情報セキュリティの重要性」「コンプライアンス違反を防ぐ行動」などがあります。組織の規律を守る管理職として、コンプライアンスの重要性と具体的な行動を学ぶことが可能なため、労務管理の基礎構築におすすめのコンテンツです。
「SAKU-SAKU Testing」は、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。