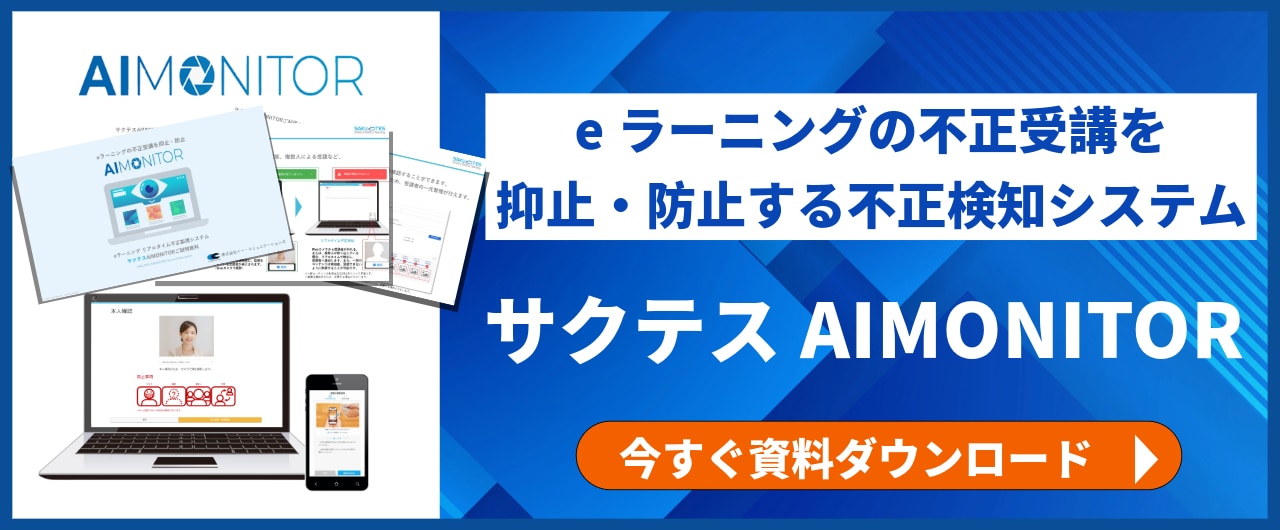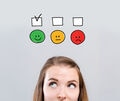企業内大学とは?作り方のポイントと成功事例を紹介

企業が自社内に教育機関を設立し、従業員の能力開発やキャリア形成を支援する企業内大学は、現代のビジネス環境においてその重要性を増しています。
変化の激しい時代に対応できる人材を育成するため、多くの企業が導入を検討している企業内大学ですが、その概要や設立・運用には具体的な理解が欠かせません。
本記事では、企業内大学の概要からそのメリット・デメリット、設立手順、そして具体的な成功事例について解説します。
目次[非表示]
- 1.企業内大学の概要
- 1.1.企業内大学の定義
- 1.2.企業内大学の歴史
- 1.3.一般的な社内研修との違い
- 2.企業内大学のメリット
- 3.企業内大学の懸念点
- 4.企業内大学の設立手順
- 4.1.STEP1:目的とコンセプトの明確化
- 4.2.STEP2:学習対象者の設定
- 4.3.STEP3:教育ニーズの把握
- 4.4.STEP4:カリキュラムの設計
- 4.5.STEP5:運用体制の構築
- 4.6.STEP6:効果測定
- 4.7.カリキュラムの目標設定
- 4.8.対象範囲の拡大
- 4.9.専門講師の育成
- 4.10.多様な学習形式の導入
- 4.11.組織文化との連携
- 5.企業内大学の事例
- 5.1.国内企業の事例
- 5.1.1.1. ソニーグループ
- 5.1.2.2. ソフトバンク
- 5.1.3.3. コカ・コーラボトラーズジャパン
- 5.1.4.4. その他事例
- 5.2.海外企業の事例
- 5.2.1.1. マクドナルド
- 5.2.2.2. GE(ゼネラル・エレクトリック)
- 5.2.3.3. モトローラ
- 6.企業内大学にeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
企業内大学の概要

企業内大学とは、企業が従業員向けに社内に設置する研修制度の一つです。従業員が自身の目標やキャリアプランに合わせて必要な講座を選択し、受講できる点が特徴です。
企業によっては、「カレッジ」「アカデミー」「経営塾」といった独自の名称を用いることもあります。
企業内大学とは、単なるスキル習得の場に留まらず、企業のビジョンや経営戦略を浸透させ、組織全体の方向性を明確にする役割も担っています。また、昨今のDXやAIの普及に伴い、企業は人材育成のあり方を再構築する必要に迫られており、企業内大学はその解決策の一つとして注目されています。
企業内大学の定義
企業内大学とは、企業が従業員の学習ニーズに応えるために、社内に開設する教育機関を指します。
一般的には、通常の大学のように必修科目と選択科目が設けられており、従業員は自身の目標やキャリアプランに合わせて、これらの講座を選択して受講できます。これは、公的に認められた大学とは異なり、あくまで企業内の研修制度の一環として位置づけられます。従業員が自主的に学ぶ場を提供する制度であり、業務に必要な知識や技術だけでなく、キャリアアップや専門性の深化を目的とした学習機会も提供します。
企業内大学はコーポレートユニバーシティ(CU)と呼ばれることもあり、企業によっては独自の名称を使用するケースも見られます。企業内大学は、人材育成だけでなく、組織の理念や目標を教育プログラムに組み込み、社員に浸透させることで、一体感や共通認識を醸成し、組織全体の方向性を明確にする役割ももっています。
企業内大学の歴史
企業内大学の歴史は古く、1950年代にアメリカの主要企業が開設したのが始まりとされています。アメリカで最初の企業内大学と言われるのは、1953年にゼネラル・エレクトリック社(GE)がクロトンビルに設立したリーダー研修センター(現在のJohnF.WelchLeadershipCenter)です。また、マクドナルド社の「ハンバーガー大学」なども初期の成功事例として知られており、これらの成功によって多くの企業が企業内大学の設立に注目するようになりました。
日本では2000年以降に大手企業を中心に企業内大学が次々と発足し、ソニーやトヨタ、富士通、損保ジャパン、ニチレイ、資生堂などがその存在を公にしました。従来の企業内大学は、幹部候補生の育成や次世代リーダーの輩出を主な目的としていましたが、近年ではリスキリングやキャリア別の能力開発など、目的が拡大しています。これは、グローバル化や少子化による人材獲得競争の激化、DXの加速、そしてテレワークの普及といった社会環境の変化に対応するための動きであるといえます。
一般的な社内研修との違い
企業内大学とは、一般的な社内研修と比較して、いくつかの明確な違いがあります。
違いを表でまとめると以下のとおりです。
項目 | 社内研修 | 企業内大学 |
|---|---|---|
目的 | 業務に必要な基礎スキル習得(例:ビジネスマナー、ITリテラシー) | キャリアアップ、次世代リーダー育成、経営戦略に沿った人材育成 |
学習 | 業務に直結する知識・スキルが中心 | 語学、ビジネススキル、専門知識など幅広く、自己啓発やキャリア形成にも対応 |
受講スタイル | 人事部や上司の指示で受講するケースが多い | 自発的に受講を選択し、主体的に学習できる |
講師 | 人事担当者や社内上司 | 社内外の専門家、現役経営陣、経験豊富な社員など多彩 |
学習姿勢 | 「やらされている感」をもちやすい | 自主性・主体性を重視し、実践的で前向きな学習につながる |
目指す成果 | 即戦力としてのスキル強化 | 長期的な人材育成・企業文化の浸透・組織の持続的成長 |
企業内大学のメリット

企業内大学を導入することで、企業と従業員双方に多くのメリットが生まれます。
企業にとっては、自社の経営戦略に合致した人材を計画的かつ体系的に育成できる点が大きなメリットです。これにより、組織全体の競争力強化や持続的な成長を促進できます。
一方、従業員にとっては、個人のキャリアアップやスキルアップの機会が拡大し、自己成長を実感できる場となります。
ここでは、企業側のメリットと従業員側のメリットを詳しく解説していきます。
企業側のメリット
第一に、自社の経営戦略に合致した人材を計画的に育成できる点です。
企業内大学では、企業のビジョンやミッション、価値観を教育プログラムに組み込むことで、社員全体がこれらを共有し、理解を深めることが可能です。これにより、組織の一体感が醸成され、目標達成に向けた取り組みが加速します。
第二に、ナレッジ共有と人材育成の強化に有効であることです。社内の優秀な人材が講師を務めることで、企業独自の技術やノウハウを体系的に伝承し、組織全体の知識レベルの底上げを図ることができます。
また、次世代リーダーの育成にも力を入れることができ、経営層が講師として登壇することで、外部講師ではカバーしきれない自社の理念や将来のビジョンを踏まえた教育が実現します。
第三に、優秀な人材の採用活動における強力なアピールポイントとなることです。人手不足が深刻化する中で、企業内大学のように従業員の成長を支援する教育制度は、求職者にとって大きな魅力となります。
最後に、従業員のエンゲージメント向上と離職防止にもつながります。企業が従業員のスキルアップやキャリアアップを支援する姿勢を示すことで、従業員は会社への愛着や信頼感を高め、離職率の低下にも貢献します。
企業側のメリットまとめ
□経営戦略に合致した人材育成
□ナレッジ共有と人材育成の強化
□次世代リーダー育成
□採用活動でのアピール効果
□従業員エンゲージメント向上と離職防止
従業員側のメリット
企業内大学は、従業員側にも多くのメリットをもたらします。
まず、スキル向上とキャリアアップの機会が拡大する点です。企業内大学では、語学やビジネススキル、専門知識など、多種多様な講座の中から興味のある内容を自由に選択して受講できます。これらの講座は、職種や業務内容を問わず選択できる場合が多く、無料で受講できるケースも少なくありません。これにより、従業員は自身のキャリアプランに合わせて、必要な知識やスキルを習得し、自己成長を促進できます。
また、自己啓発の手段としても幅広く活用できるため、将来のキャリア形成に向けた継続的な学習が可能です。
次に、エンゲージメントの向上と離職防止につながることも大きなメリットです。企業が従業員の成長を積極的に支援する姿勢は、従業員の会社への貢献意欲を高め、会社への愛着や信頼感を醸成します。従業員は「会社が自分の成長を支援してくれる」と感じることで、モチベーション高く業務に取り組むことができ、結果として離職率の低下にもつながると考えられます。さらに、企業内大学を通じて、部署や役職を超えた社内コミュニケーションが活性化し、新たな人的ネットワークの形成にも寄与する可能性もあります。
従業員側のメリットまとめ
□スキル向上とキャリアアップの機会拡大
□自己啓発と継続学習の促進
□エンゲージメント向上と離職防止
□社内コミュニケーションの活性化
企業内大学の懸念点
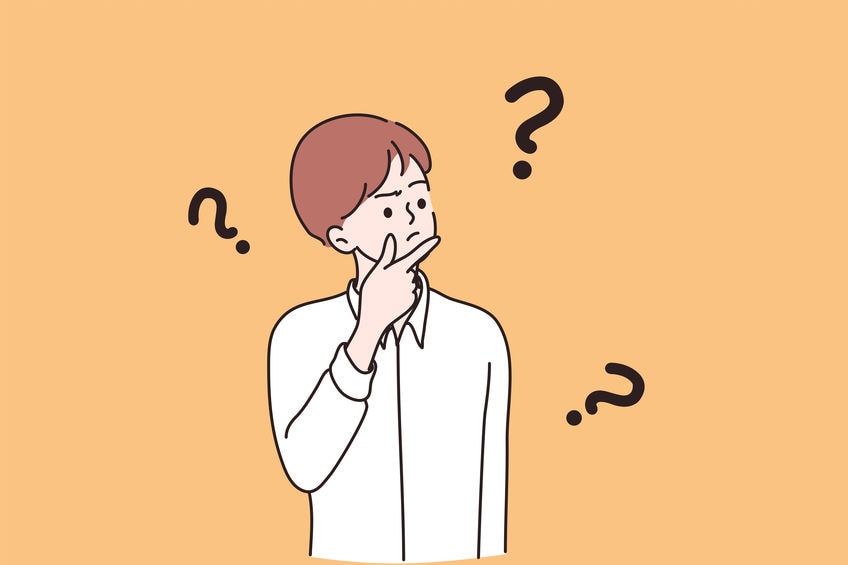
企業内大学の導入は多くのメリットをもたらしますが、一方でいくつかの懸念点も存在します。導入と運用のコスト、講師選定の難しさ、そして仕組み構築の複雑さなどが挙げられます。これらのデメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることが、企業内大学を成功させる鍵となります。
ここでは、コストと講師選定という2つの課題について解説します。
導入と運用のコスト
企業内大学の導入と運用にはかなりのコストがかかるというデメリットがあります。
まず設立時には教育コンテンツの開発費用、学習管理システムの導入費用、専用施設の確保費用など初期投資が必要となります。継続的な運用においても講師への謝礼、教材費、システム維持費、そして運営に携わる人員の人件費などさまざまなコストが発生します。
特に企業内大学は長期的な人材育成を目的としているため設立後も継続的にプログラムを充実させ運用規模を拡大していくとさらにコストが増加する可能性があります。そのため費用対効果を十分に計算し経営資源をどこまで費やすかを緻密に計画しておくことが重要です。また企業内大学では社員のニーズに合わせて幅広いコースを用意することがあり、これに伴い仕組みの構築が複雑化し受講履歴の管理など運営に伴う業務が煩雑になることも懸念点として挙げられます。
講師選定の課題
企業内大学を運営する上で、講師選定は大きな課題の一つとなります。
社内講師を起用する場合、専門知識や実務経験が豊富であることはもちろん、教育スキルや指導力も求められます。しかし、全ての分野において適切な社内講師を見つけることは容易ではありません。
特に、経営戦略や次世代リーダーシップといった高度なテーマの場合、適切な人材が社内に不足しているケースも考えられます。また、現役の社員が講師を兼務する場合、通常業務との両立が難しく、講師側の負担が大きくなる可能性もデメリットとして挙げられます。外部講師を招く場合も、費用が高額になることや、自社の企業文化やニーズに完全に合致する講師を見つけるのが難しいといった課題があります。さらに、講師の質が受講者の学習効果に直結するため、継続的な講師の育成や評価体制の構築も重要です。これにより、講師の質を維持・向上させ、受講者の満足度を高める必要があります。
企業内大学の設立手順

企業内大学を設立する際には、明確な目的設定から始まり、学習対象者の設定、教育ニーズの把握、カリキュラム設計、運用体制の構築、そして効果測定まで、体系的な手順を踏むことが重要です。
これらのステップを順に解説していきます。
STEP1:目的とコンセプトの明確化
企業内大学を設立する最初の重要なステップは、目的とコンセプトを明確にすることです。まず、自社のビジョンや経営戦略、事業戦略を踏まえ、「どのような人材を育成したいのか」「企業内大学を通じてどのような結果を得たいのか」を具体的に検討しましょう。これが、企業内大学のプログラム内容や運用の方向性を決定する土台となります。
例えば、次世代リーダーの育成、特定の専門スキルをもつ人材の養成、あるいは全従業員のエンゲージメント向上といった目的が考えられます。目的を明確にする際は、現状の経営課題、部署ごとの人材の過不足、優秀な従業員の特徴など、多方面から自社の状況を分析することが不可欠です。次に、企業内大学のコンセプトを設定します。コンセプトとは、企業内大学がどのような価値を提供し、どのような学習体験を創出するのかという根本的な考え方です。これは企業の価値観やビジョンを反映し、社員一人ひとりの成長と組織の発展を促進するものでなければなりません。
例えば、「継続的な学びと成長を支援する場」「組織の理念と戦略を共有する場」といったコンセプトが考えられます。目的とコンセプトを明確にすることで、企業内大学の方向性が定まり、効果的な教育プログラムの設計につながります。
STEP2:学習対象者の設定
企業内大学を設立する上で、次に重要なステップは学習対象者を明確にすることです。企業内大学の受講対象者は、パート・アルバイト従業員を含む全従業員とするのが理想的です。特に採用難が続く現在、内部人材のスキルアップは企業の競争力強化に直結するため、できるだけ多くの従業員を対象とすることで、企業全体のスキルレベルの底上げが期待できます。しかし、企業内大学設立の目的によっては、特定の階層や職種に絞って対象者を選定するケースもあります。
例えば、「優秀な従業員を集めて経営人材を育成したい」「若手のDX人材を増やしたい」といった目的がある場合は、受講者を選抜・限定したり、公募制としたりすることも有効な方法です。
対象者を設定する際には、目的で定めた「どのような人材を育成したいのか」という点と密接に連携させる必要があります。対象者のニーズやレベルに合わせたカリキュラムを設計することで、より効果的な学習成果を生み出すことが可能になります。
STEP3:教育ニーズの把握
企業内大学の設立手順において、目的とコンセプト、学習対象者を明確にした後は、組織内の教育ニーズを詳細に把握することが不可欠です。
このステップでは、従業員が現在どのような知識やスキルをもっており、今後どのような能力を身につける必要があるのかを分析します。具体的には、従業員の知識レベルやスキルを調査し、自社の社員に不足している知識やスキル、そして今後強化すべき点を明確にしていきます。アンケート調査、ヒアリング、スキルマップの活用、人事評価データ、業務分析などを通じて、現状の課題を特定することが有効です。例えば、DX推進のためにデジタルスキルが不足している、次世代リーダー候補のマネジメント能力を強化する必要がある、といった具体的なニーズを洗い出します。
現状の課題を把握することで、企業内大学で取り組むべきカリキュラムの内容が具体的に見えてきます。また、従業員が何を学びたいと考えているのか、どのような学習方法を望んでいるのかといった、従業員側の学習意欲やニーズも把握することで、より実践的で魅力的なカリキュラムを設計し、受講者のモチベーションを高めることにもつながります。
STEP4:カリキュラムの設計
企業内大学の成功には、効果的なカリキュラムの設計が不可欠です。教育ニーズの把握で洗い出した課題や目的に基づき、具体的な学習内容と形式を決定します。
カリキュラムは、企業の戦略的なニーズに合わせてカスタマイズされることが多く、経営学、リーダーシップ、専門技術など、多岐にわたるテーマを盛り込むことが可能です。単に知識を詰め込むだけでなく、実践的なスキル習得を重視した内容にするべきです。例えば、ケーススタディやグループワーク、ロールプレイングなど、受講者が能動的に参加できる学習形式を取り入れることで、理解度と定着度を高めることができます。また、オンライン学習やeラーニング、集合研修、OJT(On-the-JobTraining)など、多様な学習形式を組み合わせることで、従業員の学習スタイルやスケジュールに合わせた柔軟な学びを提供することも重要です。
カリキュラム設計においては、学習内容だけでなく、学習期間、評価方法、修了要件なども具体的に定める必要があります。また、受講者が目標を持って意欲的に学習に取り組めるよう、カリキュラムとキャリアアップ支援の体制を連動させることも効果的です。
例えば、カリキュラム修了後のキャリアパスを明確に示したり、上司が部下の学習進捗を把握し、個別のアドバイスを行えるような仕組みを構築したりすることが考えられます。
STEP5:運用体制の構築
企業内大学を効果的に機能させるためには、堅固な運用体制の構築が不可欠です。このステップでは、企業内大学を誰がどのように運営していくのかを具体的に定めます。具体的には、以下の項目を決定していく必要があります。まず、運営組織の設置です。人事部内に専門チームを設けるのか、独立した部署として企業内大学を位置づけるのかを検討します。特に、企業内大学は一般的な社内研修とは異なる目的を持つため、人事部とは別の組織で運営されることも少なくありません。次に、教育を担当する講師陣の選定と育成です。社内講師を活用する場合は、その選定基準や育成プログラムを策定します。外部講師を招く場合は、その選定プロセスや契約条件を明確にします。また、受講者の募集方法、受講管理、学習進捗の把握、質問対応など、日常的な運営業務に関するルールやフローを確立することも重要です。学習管理システム(LMS)などのツールを導入することで、これらの運用業務を効率化し、受講履歴や学習進捗の管理を容易にすることができます。さらに、企業内大学を社内外に広く周知するための広報戦略や、受講後のフィードバックを収集し、カリキュラムや運用方法を改善していくための体制も整える必要があります。運用の継続性を確保するためには、定期的な見直しと改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが重要です。
STEP6:効果測定
企業内大学を設立し、運用を開始したら、その効果を適切に測定することが不可欠です。効果測定の方法を事前に確立することで、企業内大学が目的を達成しているか、投資に見合う成果を出しているかを評価し、今後の改善につなげることができます。効果測定の指標としては、まず受講者の学習状況や満足度が挙げられます。
例えば、講座の受講率、修了率、テストの成績、アンケートによる満足度調査などが考えられます。
次に、学習成果が業務にどう活かされているかを測定することも重要です。これには、受講後の業務パフォーマンスの変化、スキルレベルの向上、プロジェクトへの貢献度などを評価します。
具体的な指標としては、売上向上、コスト削減、顧客満足度向上といった業績への貢献度や、離職率の低下、エンゲージメントの向上なども重要な指標となり得ます。
また、長期的な視点では、次世代リーダーの輩出数や、特定の専門分野における人材の質的な変化なども評価対象となります。効果測定の結果を定期的に分析し、カリキュラムの内容や運用方法を継続的に改善していくPDCAサイクルを回すことで、企業内大学の価値を最大化していくことができます。
企業内大学設立のSTEPをまとめると以下のとおりです。
STEP1:目的とコンセプトの明確化
育成したい人材像・期待する成果を定義
ビジョン・経営戦略との整合性を確認
「継続的学びの場」「理念共有の場」などのコンセプトを設定
STEP2:学習対象者の設定
全従業員を対象/特定階層に絞るかを決定
公募制・選抜制の導入も検討
目的に沿った対象者を明確化
STEP3:教育ニーズの把握
社員のスキル現状を調査(アンケート、スキルマップ、人事評価など)
不足スキルや強化ポイントを特定(例:DXスキル、リーダーシップ)
学習意欲・希望内容を把握しカリキュラム設計へ反映
STEP4:カリキュラムの設計
目的・ニーズに基づいた学習テーマを設定
実践重視(ケーススタディ・グループワーク・ロールプレイ)
学習形式の多様化(集合研修/eラーニング/OJT)
学習期間・評価方法・修了要件を明確化
キャリア支援と連動させモチベーションを高める
STEP5:運用体制の構築
運営組織の決定(人事部内チーム/独立組織)
講師の選定(社内講師・外部講師の基準と育成)
受講管理・進捗把握・質問対応の仕組み整備
LMS導入による効率化
広報・フィードバック収集・改善体制を確立
PDCAサイクルで継続的に改善
STEP6:効果測定
受講率・修了率・満足度・テスト成績
業務成果との連動(売上・コスト削減・顧客満足度向上)
離職率低下・エンゲージメント向上など人事指標
長期的にはリーダー輩出数や人材の質的変化を評価
定期的な分析→カリキュラム・運用改善
企業内大学設立の重要ポイント

企業内大学を成功させるためには、設立手順に加え、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。カリキュラムの目標設定の明確化、対象範囲の拡大、専門講師の育成、多様な学習形式の導入、そして組織文化との連携などが大切です。
ここでは、設立における重要ポイントについて解説します。
カリキュラムの目標設定
企業内大学のカリキュラムを設計する上で、それぞれの講座に明確な目標を設定することが極めて重要です。
単に講座を多数用意するだけでは、受講者が何を学び、どのように業務に活かせば良いのかが不明瞭になり、効果的なスキルアップやキャリアアップにつながらない可能性があります。カリキュラムの目標設定においては、その講義を通じて何を身につけてほしいのか、どのような能力を向上させたいのかを具体的に定義し、受講者にも明確に伝えることが求められます。
例えば、「この講座を修了すれば、〇〇のスキルを習得し、△△の業務を効率的に遂行できるようになる」といった具体的な目標を設定することで、受講者は目的意識をもって学習に取り組むことができます。また、設定した目標は、企業全体の経営戦略や人材育成計画と連携している必要があります。企業の求める人材像や、今後必要となるスキルセットをカリキュラムの目標に落とし込むことで、企業内大学が組織の成長に直結する効果的な人材育成の場となります。さらに、目標達成度を測るための評価基準も同時に設定することで、受講者の学習成果を可視化し、カリキュラムの改善にも役立てることが可能になります。
対象範囲の拡大
企業内大学の対象範囲を拡大することは、企業にとって重要な戦略的意義をもちます。従来の企業内大学が、次世代リーダー候補など一部の選抜された従業員を主な対象としていたのに対し、近年では正社員だけでなく派遣社員やパートを含む全従業員を対象とすることが推奨されています。この対象範囲の拡大は、単に福利厚生の一環として学習機会を提供するだけでなく、企業全体の競争力強化に直結します。人手不足が続く現代において、外部から優秀な人材を確保することが難しい状況にあるため、社内のあらゆる従業員のスキルを底上げし、戦力化することが重要です。全ての従業員に学びの場を提供し、自己研鑽の機会を用意することで、組織全体のスキルアップにつながり、生産性の向上が期待できます。また、企業理念や企業としてのビジョンを全従業員と共有できるため、企業に対する理解度も高まり、組織の一体感を醸成する効果もあります。対象範囲を拡大することで、従業員の学習意欲の向上やエンゲージメントの強化にもつながり、結果として離職防止にも寄与すると考えられます。
専門講師の育成
企業内大学の質を高める上で、専門講師の育成は極めて重要な要素です。特に、企業独自の技術やノウハウを伝承するカリキュラムにおいては、社内から専門知識と実務経験を兼ね備えた人材を講師として育成することが不可欠となります。専門講師の育成には、まず講師としてのスキルを向上させるための研修プログラムを設けることが挙げられます。
具体的には、効果的なプレゼンテーション方法、受講者を引き付けるファシリテーションスキル、教材作成のノウハウなどを習得させる研修を実施することが考えられます。また、講師を務める社員のモチベーションを維持・向上させるためのインセンティブ設計も重要です。
例えば、講師としての評価を人事処遇や評価制度と連動させたり、講師活動をキャリアパスの一つとして位置づけたりすることで、社員が積極的に講師を務める動機付けとなるでしょう。
さらに、講師間で情報共有や意見交換ができるコミュニティを形成し、互いに学び合う機会を提供することも有効です。
専門講師の育成は、企業内大学の独自性を高め、他社にはないオリジナルカリキュラムの実現を可能にするだけでなく、社員間のコミュニケーションを活性化し、組織全体の学習文化を醸成する上でも重要な役割を担います。
多様な学習形式の導入
企業内大学をより効果的なものにするためには、多様な学習形式を導入することが重要です。
従業員の学習スタイルやライフスタイルは多岐にわたるため、一つの形式に限定せず、様々な選択肢を提供することで、より多くの従業員が学びやすい環境を構築できます。
例えば、従来の集合研修に加えて、eラーニングやオンライン学習システム(LMS)の活用は、時間や場所の制約を受けずに学習できるため、テレワークが普及した現代において特に有効です。これにより、従業員は自分のペースで学習を進めることができ、多忙な業務の中でも自己啓発の時間を確保しやすくなります。
また、実践的な学びを重視するためには、OJT(On-the-JobTraining)やプロジェクトベースの学習も重要です。実際の業務を通してスキルを習得し、課題解決に取り組むことで、より実用的な能力が身につきます。
さらに、ケーススタディやグループディスカッション、ロールプレイングなど、受講者が能動的に参加できるインタラクティブな形式を取り入れることで、理解度を深め、実践力を養うことができます。異業種交流講座や外部教育機関への派遣なども、社外の知見を取り入れ、視野を広げる機会となります。多様な学習形式を組み合わせることで、従業員の学習意欲を喚起し、それぞれのニーズに合った最適な学習体験を提供することが可能となります。
eラーニングやオンライン学習システム(LMS)の導入をご検討の際は、イー・コミュニケーションズの「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、自社の動画や資料、問題を搭載したオリジナル研修が簡単に実施できます。企業内大学の学習形式の一つとして、「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。
組織文化との連携
企業内大学の成功には、単なる研修制度としてではなく、組織文化と密接に連携させることが不可欠です。
企業内大学は、組織の理念や目標を教育プログラムに組み込み、社員に浸透させることで、一体感や共通認識を醸成し、組織全体の方向性を明確にし、目標達成に向けた取り組みを加速させます。これは「学習する組織」「共感する組織」「自走する組織」といった、組織開発において目指す状態の実現に寄与します。
具体的には、企業トップ自身が講師として参加し、ビジョンや価値観、戦略を直接伝えることで、それらがより具体的かつ実感をもって社員に伝わります。
また、経営陣が研修への参加を推奨し、実際の業績に結びつける例を示すことで、社員の参加意欲を引き出すことができます。企業内大学を通じて、従業員が教え合い、学び合う文化を醸成することも重要です。社員が自身のスキルや経験を共有する場を設けることで、組織全体のナレッジマネジメントが促進され、イノベーション創出の土台となります。
さらに、企業内大学を人事評価やキャリアアップ支援の仕組みと連携させることで、学習成果が正当に評価され、従業員の学習モチベーションを継続的に高めることにもつながります。組織文化と企業内大学が連携することで、企業は持続的な成長戦略を支える強固な人材基盤を築くことができるでしょう。
企業内大学の事例

多くの企業が企業内大学を導入し、人材育成の成果を上げています。国内企業ではソニー、ソフトバンク、コカ・コーラボトラーズジャパンなどが、海外企業ではマクドナルドなどが有名です。これらの事例は、企業内大学がどのように機能し、どのような成果をもたらすのかを具体的に示しています。
国内企業の事例
まずは、国内企業の事例をまとめます。
1. ソニーグループ
ソニーユニバーシティ(2000年設立)
・国内の企業内大学の先駆け。
・部長級・課長級・係長級の3階層に分けて、半年間のリーダーシップ教育を実施。
・経営陣や社外有識者が講師を務め、国際的な人材育成にも注力(受講者の約7割が海外勤務者)。
ものづくり総合大学(SGMO)
・技術の伝承に特化。
・「第10回日本HRチャレンジ大賞」を受賞。
2. ソフトバンク
ソフトバンクユニバーシティ
・次世代リーダーの育成や全社員の能力開発を推進。
・グループ全体の成長戦略に直結する教育体系を構築。
3. コカ・コーラボトラーズジャパン
コカ・コーラユニバーシティジャパン
・若手リーダーの育成に特化。
・グローバルブランドとしての経営理念と実務スキルを融合。
4. その他事例
資生堂
明治安田生命(MYユニバーシティ)
ヤマハミュージックジャパン(ヤマハミュージックアカデミー)
→ 各社が自社の事業戦略に直結するテーマを掲げて企業内大学を運営。
海外企業の事例
次に、海外企業の事例についてまとめます。
1. マクドナルド
ハンバーガー大学(1961年設立)
・世界で最も有名な企業内大学のひとつ。
・レストランマネジメントや接客スキルを中心に教育。
・常に最新の教育理論を取り入れ、実践的なスキル習得を重視。
・世界中の従業員が受講し、グローバル標準を確立。
2. GE(ゼネラル・エレクトリック)
クロトンビル経営開発研究所
・1950年代設立。
・世界的に有名な経営者教育の拠点。
・次世代リーダー育成と企業理念の浸透を推進。
3. モトローラ
モトローラユニバーシティ
・技術革新と人材開発を結びつける場。
・長期的な人材戦略の中核として機能。
海外企業の企業内大学は「単なる教育機関」ではなく、企業理念・戦略・組織文化を体現し、持続的成長を支えるインフラの役割を果たしています。
企業内大学にeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
忙しい社会人の学びには、eラーニングの活用がおすすめです。イー・コミュニケーションズの「SAKU-SAKU Testing」は、資料や動画、テストなどのコンテンツが配信でき、受講者の好きなタイミングで学習してもらえます。そのため企業側は会場の確保や設営、講師などの準備が不要になります。
コンテンツの受講状況や学習データ、結果などをリアルタイムで管理でき、採点の効率化やフィードバックも容易に行えます。
ぜひ、企業内大学に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。