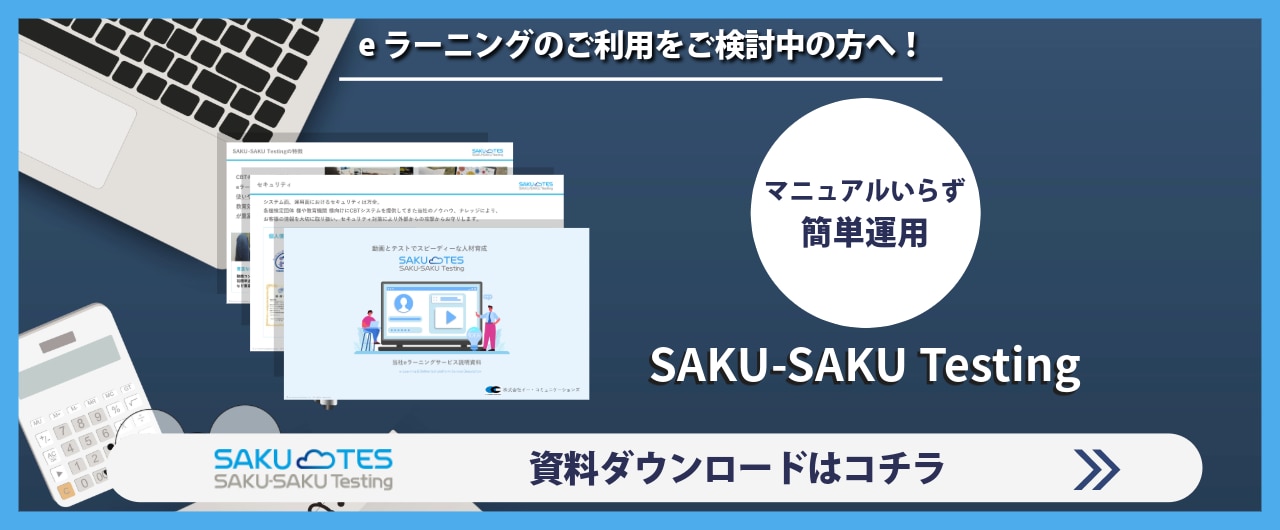取適法とは?下請法との違いや企業が押さえるべきポイントを解説

2026年1月に施行される「取適法(中小受託取引適正化法)」は、従来の下請法を改正し、中小企業との取引をより公平・透明にするための法律です。
企業の人事部・人材教育担当者は、契約や発注業務の適正化に向けて早めに理解を深め、社内での対応体制を整えることが大切です。
本記事では、取適法の概要や改正ポイント、実務上の対応策を、担当者の方にも分かりやすく解説します。
▼資料ダウンロード:2026年施行「取適法」対策ガイド
目次[非表示]
- 1.この記事の監修者
- 2.取適法とは
- 2.1.施行日と適用対象
- 3.取適法の目的
- 3.1.不当な価格決定を防ぐ
- 3.2.支払い条件の見直し
- 3.3.保護対象の拡大
- 4.取適法で変わる下請法からの主要な改正点
- 4.1.法律名・用語の変更
- 4.1.1.変更内容
- 4.2.適用対象の拡大:取引範囲
- 4.2.1.運送委託も規制対象に
- 4.3.適用対象の拡大:事業者
- 4.3.1.具体的な適用基準
- 4.4.新たに禁止される行為
- 4.4.1.約束手形による支払いの原則禁止
- 4.4.2.協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 4.5.面的執行の拡大
- 4.6.その他の重要な改正点
- 5.発注者(委託事業者)に課される義務
- 6.企業が今から準備すべきこと
- 6.1.自社取引関係の総点検
- 6.2.契約書・発注書フォーマットの見直し
- 6.3.社内規程の整備と担当者への周知
- 6.4.下請法から取適法への移行準備
- 7.取適法違反時のペナルティ
- 7.1.行政指導・指導・勧告の範囲
- 7.2.面的執行・罰則の内容
- 8.まとめ
- 8.1.関連サービス
この記事の監修者

浅見 隆行
アサミ経営法律事務所 弁護士
企業危機管理を中心に、会社法・企業コンプライアンス、危機管理広報、情報管理を中心に取り扱う。
取適法とは

取適法は、正式名称を「中小受託取引適正化法」といい、従来の下請法を改正して新たに制定された法律です。
中小企業との取引をより公正かつ透明に行うことを目的としており、名称や用語の見直し、対象となる取引の拡大、禁止行為の追加などが盛り込まれています。
適用対象となる取引は、従来の下請法では「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つでしたが、取適法では「特定運送委託」が加わり5種類となりました(製造委託の対象も「金型以外の型・治具等の製造委託」まで含まれるように拡大しました)。
対象事業者も資本金だけでなく従業員数による基準が追加されました。
また、協議なしの一方的な代金決定や手形払いなど、従来は明確でなかった禁止規定が新設・強化され、企業には実務上の対応が求められます。
取適法が制定された背景には、中小企業を取り巻く取引環境の課題があります。原材料費やエネルギーコストの上昇分が発注者に十分反映されず、受注する中小事業者がコストを自社で負担せざるを得ない状況も見られました。その結果、利益確保や従業員への賃上げの原資が十分に確保しにくいケースもありました。
取適法は、こうした状況を改善し、中小事業者が適正な価格で取引できる仕組みを定着させることで、事業運営を安定させる環境を整えるものです。
企業は契約や発注業務のルールを早めに確認・整備し、変更点に対応することが重要です。
施行日と適用対象
取適法は、2026年1月1日から施行されます。
適用対象は中小企業との委託取引全般で、特に以下の取引が含まれます。
製造委託・修理委託
情報成果物作成委託(プログラムや文書など)
役務提供委託(運送、倉庫保管、情報処理など)
- 特定運送委託(改正により新設)
自社がどの取引に該当するのか、あらかじめ確認しておくことが大切です。対象の範囲を把握しておくことで、施行後に慌てずに対応できます。
取適法の目的

取適法(中小受託取引適正化法)は、中小企業や個人事業主が不利な条件を押し付けられず、適正な価格で安心して取引できる環境を整えることを目的とした法律です。
ここでは、具体的な狙いを整理します。
不当な価格決定を防ぐ
従来は、発注者が理由を示さずに価格を据え置いたり減額したりするケースもありました。
取適法では、中小企業が不当な理由で一方的に条件を決められないよう、ルールを明確化しています。
これにより、受託側も利益を確保しやすくなり、賃上げや設備投資など、事業運営の安定につなげやすくなります。
支払い条件の見直し
中小企業の資金繰りを圧迫してきた約束手形や長期の支払サイトといった慣行について、取適法では見直しを促しています。
代金の支払を確実かつ迅速に行う仕組みを整えることで、受託側も安定した資金管理ができ、安心して業務に取り組める環境が整います。
保護対象の拡大
従来の下請法では、資本金の基準によって一部の中小企業しか保護されませんでした。
取適法では「従業員数」を新たな判断基準として加え、個人事業主や小規模事業者も対象に含めています。
これにより、より多くの中小事業者が公平な条件のもとで契約できるようになります。
取適法で変わる下請法からの主要な改正点

取適法(中小受託取引適正化法)の施行により、これまでの下請法から、法律名や用語の変更、適用対象の拡大、禁止行為の追加など、企業の契約・発注業務に直接影響する改正が行われました。
ここでは、分かりやすく主要な変更点と実務上のポイントを整理します。
法律名・用語の変更
今回の改正では、法律名や主要用語が刷新されました。従来の「親事業者」「下請事業者」という上下関係をイメージさせる呼び方から、対等な関係を前提とした名称に変更となっています。
変更内容
区分 | 改正前 | 改正後 |
法律の正式名称 | 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
通称 | 下請法 | 取適法(とりてきほう) |
委託側 | 親事業者 | 委託事業者 |
受託側 | 下請事業者 | 中小受託事業者 |
支払い対象 | 下請代金 | 製造委託等代金 |
適用対象の拡大:取引範囲
運送委託も規制対象に
従来の下請法では、対象となる取引は製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4種類に限定されていました。
今回の改正では、この枠を拡大し、従来の4類型に加え、以下の取引も適用対象となります。
特定運送委託
- 製造・販売などに付随する荷主から運送事業者への運送委託
- 荷待ちや荷役作業の無償強制など、物流業界の不適切な慣行も規制対象
- 適正な運賃や手数料の支払いを確保し、受託者が不利益を被らないことを目的
金型以外の型・治具等の製造委託
- 従来の金型に加え、木型、樹脂型、ジグなど特殊な型や治具も対象
- 特定製品専用の型や治具を無償で使用させたり保管させたりする行為の是正
- 適正な対価の支払いを促すことで、公正な取引関係を確保
適用対象の拡大:事業者
従来の「資本金」基準だけでなく、「常時使用する従業員数」も新基準として追加されました。これにより、資本金が小さくても事業規模の大きい企業が規制対象外になることを防ぎます。
具体的な適用基準
製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)発注側(委託事業者)
受託側(中小受託事業者)
資本金3億円超
資本金1,000万円超3億円以下
従業員300人超
資本金3億円以下
資本金1,000万円以下
従業員300人以下
「情報成果物作成委託」「役務提供委託」
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)発注側(委託事業者)
受託側(中小受託事業者)
資本金5,000万円超
資本金1,000万円超5,000万円以下
従業員100人超
資本金5,000万円以下
資本金1,000万円以下
従業員100人以下
新たに禁止される行為
約束手形による支払いの原則禁止
従来、中小企業への支払いには約束手形が用いられることが多く、受託側の資金繰りを圧迫していました。取適法では、原則として約束手形による支払いを禁止し、支払期日までに中小受託事業者が代金の満額を確実に受け取れる仕組みを義務付けています。
<禁止される具体例>
割引料や手数料を負担させ、代金の満額を受け取れない支払い方法
電子記録債権やファクタリングを利用した場合で、代金満額を期日までに受け取れない方法
協議に応じない一方的な代金決定の禁止
原材料費や労務費の高騰などがあっても、委託事業者が製造委託等代金の価格を一方的に決めたり、受託側からの値上げ要請の協議を無視して価格を一方的に据え置く行為は、取適法で禁止されています。
これは単に価格の維持を防ぐだけでなく、交渉プロセスそのものの適正化を目的としています。
<禁止される行為の例>
正当な理由なく値上げ要請の協議を拒否、申し入れを無視する
協議開始を遅らせる条件付き要求
具体的理由なく価格を据え置く
委託事業者には、単に価格を決定するのではなく、受託事業者との協議に積極的かつ誠実に対応する姿勢が求められます。
面的執行の拡大
違反行為の監督体制も強化されました。従来は公正取引委員会や中小企業庁が中心でしたが、取適法では事業所管省庁(例:国土交通省など)も、違反行為に対して指導・助言を行うことが可能となります。
これにより、行政間の情報連携が強化され、業界ごとの専門性を活かした監督・指導が行いやすくなります。
その他の重要な改正点
これまでご紹介した主要な改正点に加え、取適法にはその他にもいくつかの重要な変更があります。主なポイントは以下の通りです。
発注書面の電子交付が容易に
従来は相手方の承諾が必要でしたが、取適法では原則として承諾なしで電子交付が可能となり、契約手続きの効率化が図れます。遅延利息の適用範囲拡大
支払遅延だけでなく、不当な代金減額にも年率14.6%の遅延利息支払い義務が課されるため、受託事業者の権利保護がより確実になります。
出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法ガイドブック」
出典:公正取引委員会「取適法リーフレット」
出典:公正取引委員会「改正法条文」
▼資料ダウンロード:2026年施行「取適法」対策ガイド
発注者(委託事業者)に課される義務

取適法では、発注者(委託事業者)に対して具体的な義務が定められています。契約や発注の透明性を確保することで、中小事業者との取引を公正に進め、トラブルや法的リスクを未然に防ぐことが目的です。
ここでは、発注者に課される主な4つの義務を解説します。
書類作成・保存義務
発注者は、契約書や発注書、支払関連書類など、取引に関する重要書類を作成し、一定期間保存する義務があります。
これにより、契約内容や取引条件を後から確認できるようにし、トラブル発生時に証拠として活用可能です。社内での書類管理フローの整備も必須となります。
発注内容の明示義務
契約や発注時には、以下の内容を明確に伝える必要があります。
取引の目的・範囲
発注金額や算定方法
納期・成果物の要件
これにより、中小事業者が不利な条件で契約することを防ぎ、双方の合意に基づいた公正な取引が実現します。取適法では、書類作成・保存義務、発注内容の明示義務に違反した場合に、刑事罰が課されることになりました。
支払期日の設定義務
取適法では、支払期日(物品・役務提供を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内)を明確に定めることが義務付けられています。
明確な期日設定により、取引先への支払遅延を防ぎ、財務管理の透明性も向上します。また、期日管理を社内で徹底することで、契約トラブルのリスクも低減されます。
遅延利息の支払義務
万が一、支払が期日までに行われなかった場合は、遅延利息(年利14.6%)を支払う義務があります。
遅延利息の設定は契約書で明示することが推奨され、未払いによる中小事業者への不利益を回避できます。これにより、取引関係の信頼性維持にもつながります。
企業が今から準備すべきこと

取適法の施行までに、企業が事前に準備を進めることは非常に大切です。社内の取引管理や契約フローを整理し、担当者への教育を徹底することで、施行後もスムーズに対応できます。
早めの対応が、法令遵守と取引関係の安定につながります。ここでは、具体的に準備しておきたい項目を整理します。
自社取引関係の総点検
まず、自社が関わるすべての取引を洗い出し、対象となる中小事業者や契約内容を確認します。
チェックポイントは以下です。
契約先の事業規模(資本金・従業員数)
対象となる取引の種類(製造・修理・情報成果物作成・役務提供・特定運送)
契約条件や支払方法の透明性
総点検を行うことで、取適法の適用対象かどうかを把握し、必要な改善点を早期に特定できます。
契約書・発注書フォーマットの見直し
契約書や発注書の内容も、取適法に対応する形に見直す必要があります。
具体的には以下の対応が求められます。
発注条件・支払期日・遅延利息の明示
協議なしの一方的な価格変更や手形払いを禁止する条項の追加
契約内容の保存期間や管理体制の明確化
フォーマットの統一は、社内の契約管理の効率化にもつながります。
- 契約書作成や支払条件の確認方法
- 一方的な価格決定や不当な負担の禁止
- 違反時のリスクや遅延利息の理解
社内規程の整備と担当者への周知
社内規程やマニュアルも、取適法に沿った内容に更新する必要があります。
さらに、契約・発注担当者への周知徹底が不可欠です。
社内マニュアルの改訂
研修内容の更新:従来のコンプライアンス研修や業務研修の内容を見直し、取適法対応のポイントを盛り込む
- 契約書作成や支払条件の確認方法
- 一方的な価格決定や不当な負担の禁止
- 違反時のリスクや遅延利息の理解
社内研修・eラーニングを活用して担当者教育を徹底
これにより、現場担当者の認識不足による違反リスクを防ぎ、社内全体で法令遵守体制を強化できます。
下請法から取適法への移行準備
既存の下請法対応フローを取適法に移行する作業も必要です。
既存契約の見直し・必要に応じた修正
契約管理システムや帳票のアップデート
担当者向けガイドラインの改訂
早めに移行準備を進めることで、施行直後の混乱を避けることができます。
取適法違反時のペナルティ

取適法に違反した場合、企業には行政上および法的なペナルティが科されます。違反内容によっては、企業の信用低下や取引停止リスクにもつながるため、事前の遵守体制の整備が不可欠です。ここでは、具体的な行政措置と罰則内容を整理します。
行政指導・指導・勧告の範囲
取適法違反が疑われる場合、まず行政庁は指導・助言や勧告を行います。具体的には以下の内容です。
違反行為の是正指導
契約内容や支払条件の改善勧告
取引先への影響を最小限に抑える対応策の提示
行政指導・勧告は、企業に対して違反行為の認識を促し、改善を促すための初期段階の措置です。なお、勧告は公表されます。
無視や改善不履行が続く場合、さらに強力な行政措置(排除措置命令、課徴金)が適用されます。
面的執行・罰則の内容
取適法では、重大または繰り返しの違反に対して「面的執行」と呼ばれる強制措置が可能です。具体的には以下の内容が含まれます。
違反行為の停止命令
違反内容の公表
必要に応じた罰金・過料の適用
面的執行は、企業の社会的信用に直接影響するため、早期の違反是正が重要です。また、罰則のリスクを避けるためにも、日頃から社内フローや契約管理の遵守状況を確認することが求められます。
▼資料ダウンロード:2026年施行「取適法」対策ガイド
まとめ
取適法(中小受託取引適正化法)は、2026年1月施行に向けて、企業が中小事業者との取引をより公平・透明に進めるための重要な法律です。契約や発注業務のルール、禁止行為の整理、社内規程や教育体制の整備など、早めに確認・準備を進めることが求められます。施行直前になって慌てることのないよう、今のうちから社内フローや契約管理のチェックを行い、必要な改善を進めておくことが重要です。
こうしたタイミングで、社内のコンプライアンス教育も見直してみてはいかがでしょうか。
イー・コミュニケーションズの「弁護士が解説 よくわかる企業のコンプライアンス講座」 は、弁護士によるわかりやすい解説動画と確認テストで、企業内のコンプライアンス教育を手軽に実施できるeラーニングコンテンツです。
24テーマから必要な内容だけを選んで受講できるため、自社の実務に合わせた効率的な教育が可能です。
取適法の施行に合わせた内容更新も予定しており、今のタイミングで研修コンテンツを見直すことで、社内の法令遵守体制をより確実なものにできます。契約や発注フローの整備とあわせて、教育面でも準備を進め、安心して施行を迎えましょう。
▼関連記事:コンプライアンス研修とは?目的・内容・効果的な実施方法を解説
関連サービス
SAKU-SAKU Testing:誰でも簡単に直感で操作できるシステムで、知識習得に高い効果のあるeラーニングプラットフォームです。受講者の受講状況やテスト結果をリアルタイムで管理することも可能です。
サクテス学びホーダイ:100本を超える動画と3,000問以上のビジネス問題を含むコンテンツパッケージで、すぐにWeb教育をスタートできます。