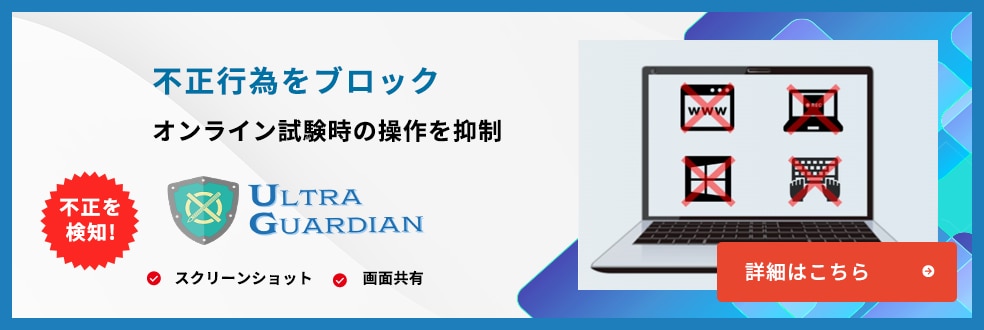論述試験の作成方法|論述式テストと選択式テストの違いと作成のポイント
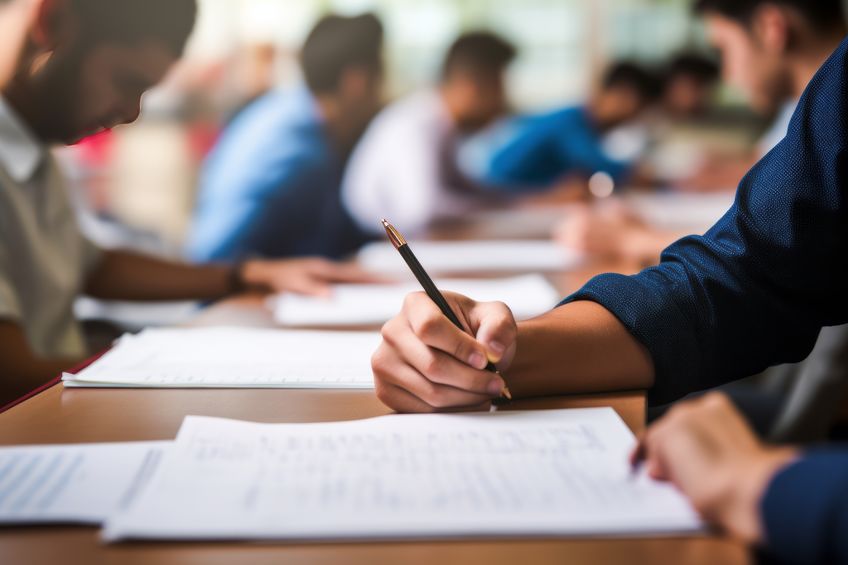
検定や国家試験、社内試験などで論述試験の作成を担当される方、そして効率的な試験運営を目指しオンライン化を検討されている方へ向けて、本記事では論述式テストと選択式テストの違い、論述試験の具体的な作成ポイント、さらにはオンライン化における注意点と効率化のヒントについて解説します。
目次[非表示]
- 1.論述式と選択式の比較
- 1.1.論述式試験の形式
- 1.2.選択式試験の形式
- 1.3.論述式と選択式の比較表
- 2.論述試験作成のステップ
- 2.1.目的を明確にする
- 2.2.出題の意図を明確にする
- 2.3.評価基準の設定
- 3.論述試験の問題作成のポイント
- 3.1.具体的でわかりやすい背景設定
- 3.2.条件と視点を明示
- 3.3.多様な解答を許容する設計
- 3.4.分量と時間配分の明示
- 3.5.評価項目との直結
- 4.論述試験の良い設問の型
- 5.採点基準(ルーブリック)の設計
- 5.1.採点者間でブレない基準を作る
- 5.2.評価軸の例
- 6.試行と改善
- 7.論述試験をオンラインで行う場合のポイント
- 8.オンラインテストにイー・コミュニケーションズの「MASTER CBT PLUS」をご活用ください
論述式と選択式の比較
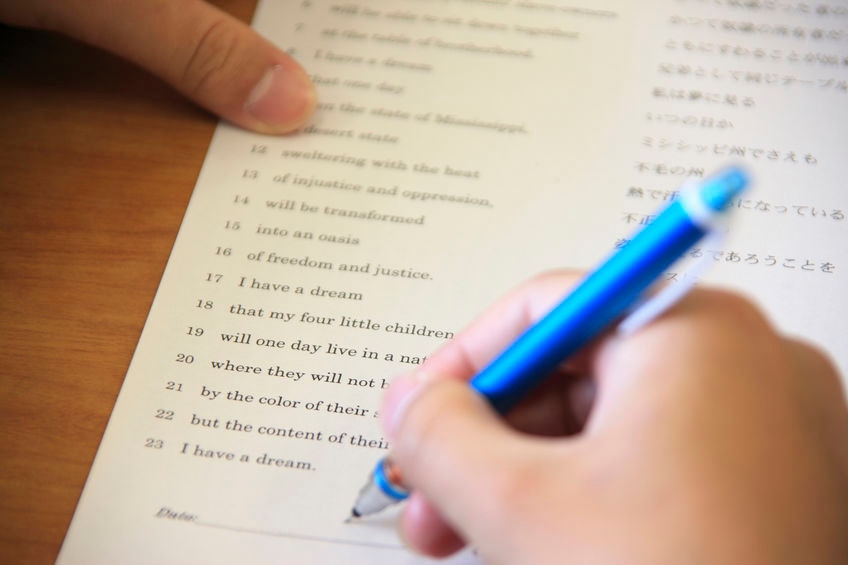
試験形式は大きく分けて論述式と選択式の2つがあり、それぞれに異なる特徴と目的が存在します。
ここでは、それぞれの特徴を解説します。
論述式試験の形式
論述式試験は、問いに対して自分の考えを文章でまとめて答える方式です。大学の期末試験などでよく使われており、知識をただ覚えているかどうかだけでなく、それを整理してわかりやすく表現する力も問われます。例えば「〜について論ぜよ」といった形の問題が典型的です。採点のときには、必要なキーワードが入っているか、論理がしっかりしているか、読みやすい文章になっているかなどが重視されます。
例として、明治大学では「問題理解力」「説得力」「構成力」「文章力」「知識力」といった観点で評価されるとされています。
選択式試験の形式
選択式試験は、用意された選択肢の中から正しい答えを選ぶ方式です。
短い時間で多くの問題を解けるため、広い範囲の知識や理解度を効率よく確かめるのに向いています。出題形式には、正しいか誤りかを答える正誤問題、いくつかの選択肢から選ぶ多肢選択問題、穴埋め形式の問題などがあります。
論述式と選択式の比較表
両者の違いを表にまとめると以下の通りです。
試験形式 | 特徴 | 評価される | 出題形式の例 | 評価方法・採点基準 / 活用場面 |
|---|---|---|---|---|
論述式 | ・問いに対して自分の考えを一定の文字量で記述する形式 ・大学の期末試験などで多く用いられる | ・知識の有無だけでなく整理力 ・テーマ理解度 ・論理的思考力と表現力 | ・「〜について論ぜよ」といった自由記述型 | ・キーワードの有無 ・論理の一貫性 ・文章の読みやすさ ・特にキーワードや論理展開を重視 |
選択式 | ・提示された選択肢から正解を選ぶ形式 ・短時間で多くの問題を処理できる | ・広範な知識の有無や理解度 ・効率的な情報処理能力 | ・正誤問題 ・多肢選択問題 ・穴埋め問題 | ・短時間で多くの知識を確認する場合に有効 ・広い範囲を効率的に評価したい場合に活用 |
論述試験作成のステップ

論述試験の作成において、目的と出題の意図を明確にすることは、試験の質と評価の妥当性を確保する上で不可欠です。
次に、評価基準を具体的に設定し、採点における客観性と公平性を保つための準備が必要です。
ここでは、作成の際のステップについてまとめます。
目的を明確にする
論述試験を作成する上で最も重要なのは、試験の目的を明確にすることです。
どのような能力や知識を受験者に身につけてほしいのか、試験を通じて何を評価したいのかを具体的に設定する必要があります。
例えば、単なる知識の有無を問うだけでなく、その知識を応用する思考力、問題解決能力、あるいは論理的な構成力や表現力を評価したいのかといった点を明確にします。目的が明確であれば、それに合致した適切な問題を作成でき、また、後述する評価基準の設定も容易になります。受験者の思考力や表現力を総合的に測定したいのであれば論述式が適していますが、短時間で広範な知識を問う場合は選択式が優れています。試験の形式がもつ特性を理解し、測りたい能力に最適な形式を選ぶことが、効果的な論述試験作成の第一歩です。
出題の意図を明確にする
出題の意図を明確にすることは、論述試験の質を高める上で非常に重要です。設問文では、受験者に何を問いたいのか、どのような視点から記述してほしいのかを具体的に示す必要があります。
例えば、「〇〇について論ぜよ」という形式の問題であっても、そのテーマが何を意味するのか、どのような側面について記述を求めているのかを具体的に示し、曖昧さを排除することが大切です。これにより、受験者は出題者の意図を正確に理解し、的外れな解答を防ぐことができるでしょう。出題の意図が不明確だと、受験者が意図を読み取れず、出題者の求める解答から大きくずれてしまう可能性があります。
また、採点者間での評価のブレを防ぐためにも、採点基準が出題の意図と合致するように事前に説明し、採点者間で議論を行うことが望ましいです。明確な出題意図は、質の高い解答を引き出し、採点の公平性を保つための基盤となります。
評価基準の設定
評価基準の設定は、論述試験の採点における公平性と客観性を担保するために不可欠です。採点基準を明確にすることで、採点者間のブレを最小限に抑え、受験者にとっても何が評価されるのかが明確になります。
例えば、評価項目としては「問題理解力」「説得力」「構成力」「文章力」「知識力」などが挙げられます。これらの項目それぞれについて、具体的な評価のレベルを設定することが重要です。
例えば、「知識力」であれば「キーワードが網羅されているか」「専門用語が正確に使用されているか」といった細分化された採点基準を設けることが考えられます。また、採点時に各項目に点数を割り振ることで、総合的な評価だけでなく、各能力の到達度を具体的に示すことが可能です。採点者が複数いる場合は、事前に採点基準に関する詳細な説明と議論を行い、採点の練習を重ねることで、採点者の頭の中にある基準が出題の意図と合致するように調整することが望ましいです。これにより、異なる採点者が同じ解答を採点しても、一貫した結果が得られやすくなり、試験の信頼性が向上します。
論述試験の問題作成のポイント

論述試験の問題作成においては、受験者がその意図を正確に理解し、自身の能力を最大限に発揮できるような工夫が必要です。背景設定の具体性、条件と視点の明確化、多様な解答の許容、分量と時間配分の明示、そして評価項目との直結がその鍵となります。
具体的でわかりやすい背景設定
論述試験の問題を作成する際、受験者がスムーズに思考を開始し、本質的な解答に集中できるように、具体的でわかりやすい背景設定をすることが重要です。
漠然とした問いではなく、具体的な事例や状況を提示することで、受験者は問題の意図を正確に把握しやすくなります。
例えば、「地球温暖化について論ぜよ」といった抽象的な問いよりも、「ある地域の工場排水による河川汚染が地域住民の健康に与える影響について、あなたの考えを述べなさい」といった具体的なケースを設定することで、受験者は問題意識をもち、論点を絞りやすくなるでしょう。背景設定には、図や表などの非言語テキストや、データを用いることも有効です。これにより、多角的な視点から情報を読み解く力を問うことも可能になります。具体的でわかりやすい背景設定は、受験者がもつ知識を現実の問題に結びつけ、応用力を試すための土台となります。
条件と視点を明示
論述試験の設問では、受験者がどのように書き、どのような視点で記述すべきかを明確にすることが重要です。
例えば、「〇〇の観点から論述しなさい」や「△△の立場から記述しなさい」といった具体的な条件や視点を提示することで、受験者は解答の方向性を見失わずにすみます。漠然とした設問では、受験者が何を求められているのか判断に迷い、的外れな解答をしてしまう可能性があります。明確な条件と視点の提示は、受験者が自身のもつ知識や思考力を効果的に記述する手助けとなり、採点者にとっても評価がしやすくなるメリットがあります。
例えば、問題文に「背景の説明:必要に応じて簡単な定義や歴史的背景を述べる」といった書き方のヒントを含めることも有効です。
また、論述の構成として「序論・本論・結論」の型を示すことで、論理的な記述を促すことができます。
多様な解答を許容する設計
論述試験の設問は、単一の正解を求めるのではなく、受験者の多様な視点や独自の考察を許容する設計が望ましいです。そうすることで、受験者は自らの考えを自由に記述でき、より深い思考力を測ることができます。
例えば、「〇〇について、あなたの考えを記述しなさい」という形式であれば、異なるアプローチや結論であっても、論理的かつ説得力のある記述であれば高く評価されるように採点基準を設定します。このような設計は、単なる知識の暗記に留まらない、真の理解と応用力を測ることに繋がります。ただし、多様な解答を許容するといっても、論点が不明確になったり、採点基準が曖昧になったりしないよう、設問の意図や評価のポイントは明確にしておく必要があります。
また、想定する解答の文字数を明確に示し、文字数制限の中で論理的に記述できるかどうかも評価のポイントになります。文字数については、解答欄1行あたりの文字数の目安を40字前後とし、採点者が読みやすい適切な文字の大きさになるように配慮を促すことも重要です。このような配慮は、受験者が時間配分を計画し、与えられた制約の中で最大限のパフォーマンスを発揮する手助けとなります。
分量と時間配分の明示
論述試験において、受験者が効率的に解答を進めるためには、問題の分量と適切な時間配分を明示することが非常に重要です。
例えば、「500字以内で述べなさい」といった明確な文字数制限を設けることで、受験者は解答の構成や内容の取捨選択を計画的に行えます。
また、試験時間全体のうち、各設問に割り当てる推奨時間を提示することで、受験者は時間切れによる未完成な解答を防ぎ、すべての問題に均等に取り組むことが可能になります。
特に論述試験に苦手意識をもつ受験者は、文章の構成を練るのに時間がかかる傾向があるため、最低でも10分程度の構成を練る時間を確保するよう促すことも有効です。これは、単なる暗記力だけでなく、限られた時間の中で情報を整理し、論理的に思考し、表現する能力を測ることに繋がります。分量と時間配分の明示は、受験者の負担を軽減し、本来の思考力や表現力を正しく評価するための基盤となります。
評価項目との直結
論述試験の問題作成において、設問が直接的に評価項目と結びついていることは、採点の公平性と受験者の解答の方向性を明確にする上で不可欠です。設問が評価したい能力や知識と直結していれば、採点者はより客観的に評価を下すことができ、受験者も何が評価されるのかを理解して解答を作成できます。
例えば、論理的思考力を評価したいのであれば、「主張とその根拠を明確に示しなさい」といった設問にすることで、直接的にその能力を問うことができます。知識の応用力を評価したいのであれば、「具体的な事例を挙げ、その問題を解決するための方法を考察しなさい」といった問いが考えられます。
評価項目と設問を明確に紐づけることで、受験者は評価されるポイントを意識した記述が可能となり、採点者は設定した評価基準に基づき、一貫した採点を行うことができます。これは、試験の妥当性を高め、受験者にとっても納得感のある結果を提供する上で非常に重要です。
論述試験の良い設問の型
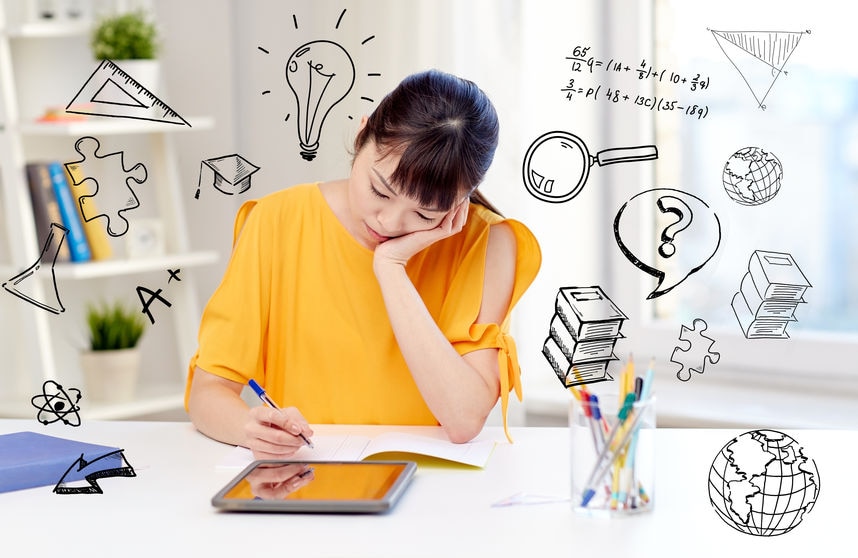
論述試験における良い設問には、典型的な型がいくつかあります。それぞれが特定の思考力や表現力を引き出すために有効であり、評価したい能力に応じて適切に使い分けることが重要です。代表的な型としては、事例分析型、立場選択型、説明型が挙げられます。
事例分析型
事例分析型は、具体的な事例や状況を提示し、それを分析させる設問形式です。この型は、受験者の実践的な思考力や問題解決能力を評価するのに適しています。
目的
与えられた情報を整理し、論理的に考察した上で、問題点の抽出や解決策の提示ができるかを測る。
設問例
「A社が直面しているXという問題について、その原因を分析し、具体的な解決策を提案しなさい。」
作問上のポイント
・分析対象が具体的であること。
・解答に複数の切り口があり、思考の深さを比較できること。
・事実やデータを根拠として使わせる余地を設けること。
立場選択型
立場選択型は、複数の異なる立場や意見を提示し、その中から一つを選び、その理由を説明させる設問形式です。この型は、受験者の批判的思考力や説得力を評価するのに有効です。
目的
多様な視点を踏まえつつ、自分の立場を明確にし、論理的に主張を展開できるかを測る。
設問例
「環境保護と経済発展のどちらを優先すべきか、立場を選び、その理由を論じなさい。」
作問上のポイント
・複数の立場が成立するように問題を設定すること。
・メリット・デメリットの双方に触れられる構造にすること。
・反対意見への言及を促すことで、より説得力のある解答を引き出すこと。
説明型
説明型は、特定の概念や理論、現象について、その意味や仕組みを分かりやすく記述させる設問形式です。この型は、受験者の知識の正確さや理解度、さらに他者にわかりやすく伝える力を評価するのに適しています。
目的
単なる暗記ではなく、概念や因果関係を整理し、体系的に説明できるかを測る。
設問例
・「〇〇の法則について、具体例を挙げながら説明しなさい。」
・「△△という資格の重要性について、その社会的背景を踏まえて述べなさい。」
作問上のポイント
・専門用語を正しく使いつつ、理解しやすい表現を引き出せる設問にすること。
・抽象的な概念に対して具体例を交えた説明を促すこと。
・単なる用語列挙ではなく、因果関係や背景を踏まえた論述を評価できるようにすること。
採点基準(ルーブリック)の設計
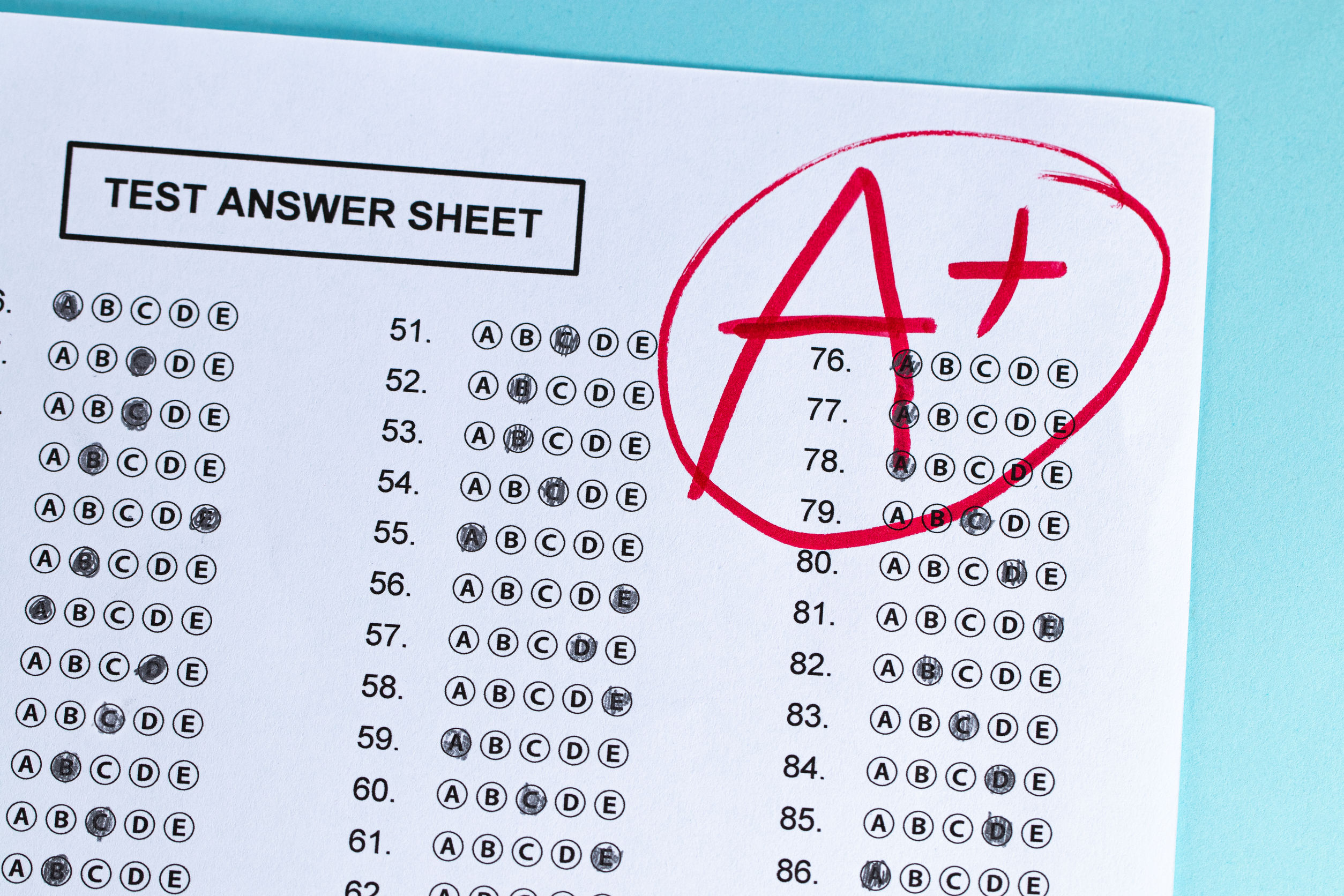
採点基準であるルーブリックの設計は、論述試験の評価における客観性と透明性を高める上で極めて重要です。
採点者間のブレをなくし、公正な評価を行うためには、詳細で具体的な基準を設ける必要があります。また、受験者に対しても、何がどのように評価されるのかを明確に提示することで、学習目標の明確化と自己評価能力の向上を促します。
ここでは、採点基準の設計について解説します。
採点者間でブレない基準を作る
採点者間で評価のブレが生じないように、詳細かつ具体的な採点基準を策定し、それを採点者全員で共有し、理解を深める必要があります。
具体的には、ルーブリックを作成し、各評価項目について複数の段階を設定し、それぞれの段階でどのような記述が求められるのかを明確に記述します。
例えば、文章構成の項目であれば、「論理的破綻がなく、主張と根拠が明確に示されている」といった最上位の評価から、「主張が不明確で、論理の飛躍が見られる」といった下位の評価まで、具体例を交えながら定義します。
また、採点者全員で事前に採点の練習を行い、模範解答や過去の解答例を用いて、実際に採点を行いながら基準の解釈について議論する場を設けることも有効です。これにより、個々の採点者の主観による評価のばらつきをおさえ、安定した採点結果を得ることが可能になります。さらに、同じ採点者が同じ解答を採点しても、まったく同じ結果にならないことも起こり得るため、複数の採点者が採点し、その結果を比較検討することで、より信頼性の高い評価を実現できます。
評価軸の例
代表的な評価軸としては、以下のような項目が考えられます。
問題理解力:設問の意図を正確に把握し、求められている論点に沿った解答をしているか
知識力:関連するキーワードや専門用語が適切に使用されているか、提示されたデータや情報を正確に理解しているか
構成力:序論・本論・結論といった論理的な構成が明確であるか、段落間の接続が自然であるか
説得力:主張が明確で、その根拠が具体的かつ論理的に示されているか、読者に納得感を与える内容であるか
文章力:誤字脱字がないか、適切な語彙や表現が用いられているか、一文の長さが適切で読みやすいか
これらの評価軸ごとに、例えば5段階や7段階といった具体的なレベルを設定し、それぞれのレベルに達している解答の特徴を記述することで、採点者はより正確で一貫した採点を行うことが可能になります。
試行と改善

論述試験の品質を向上させるためには、作成した問題を一度で終わらせるのではなく、試行と改善のサイクルを回すことが重要です。
プレテストを実施し、その結果からフィードバックを得て、問題を修正することで、より効果的で公平な試験へと進化させることができます。
ここでは、試行と改善のプロセスを解説します。
プレテストの実施
論述試験の品質と妥当性を高めるためには、本番実施前にプレテストを実施することが有効です。プレテストを行うことで、作成した問題文の不明瞭な点や、想定外の解釈がないかを確認できます。また、設問の難易度や解答に要する時間の妥当性を検証し、実際の試験時間内に受験者が無理なく解答できるかを判断する重要な機会となります。
さらに、採点基準が適切に機能するか、採点者間で評価のブレが生じないかを確認する上でも役立ちます。プレテストの受験者には、本番の受験者層に近い属性の協力を仰ぎ、客観的なフィードバックを得ることが望ましいです。実施後には、受験者の解答内容や、解答にかかった時間、問題に対する感想などを丁寧に収集し、改善点を見つけ出すための貴重なデータとして活用します。この段階で問題の調整を行うことで、本番試験の信頼性と公平性を大きく向上させることが可能となります。
フィードバック
プレテスト実施後のフィードバックは、論述試験の質を高める上で不可欠なプロセスです。受験者からのフィードバック、そして採点者からのフィードバックの両方を収集し、分析することが重要になります。
受験者からは、問題文のわかりやすさ、時間配分の適切さ、設問の意図の理解度などについて意見を募ります。これにより、受験者が問題に対してどのように感じたか、どこでつまずいたかといった具体的な情報を得ることができます。
一方、採点者からは、採点基準の曖昧さ、採点のしやすさ、解答の傾向などについて意見を求めます。これにより、採点基準の改善点や、採点者間のブレを減らすための具体的な方策を見出すことが可能になります。
フィードバックの収集方法としては、アンケート調査、ヒアリング、または採点者会議での議論などが考えられます。収集したフィードバックは、具体的な改善策を検討するための貴重な情報源となり、論述試験の精度向上に直結します。
修正
プレテストで得られたフィードバックに基づき、論述試験の問題や採点基準を修正する作業は、試験の質を最終的に高める上で極めて重要です。
修正の際には、まずフィードバックを具体的に分析し、どのような問題点があったのかを特定します。
例えば、問題文が曖昧で受験者の解釈が分かれたのであれば、表現をより明確に改善します。解答に時間がかかりすぎたという意見が多ければ、設問の分量を見直すか、試験時間を調整することを検討します。
また、採点者間で評価に大きなブレがあった場合は、ルーブリックの記述をより具体的にしたり、採点者向けのガイドラインを充実させたりするなど、採点基準そのものを見直す必要があります。修正作業は一度で完了するとは限らず、場合によっては再度プレテストを実施し、さらなるフィードバックを得て修正を繰り返すことで、より精度の高い論述試験へと磨き上げていきます。
この継続的な改善プロセスが、受験者にとって公平で、かつ目的を達成できる試験の実現に繋がります。
論述試験をオンラインで行う場合のポイント

従来は紙での実施が多かった論述試験も、司法試験のCBT化などの影響もあり、オンラインで実施するパターンが増えています。
論述試験をオンラインで実施する場合、従来の紙媒体での試験とは異なる様々な課題が生じます。
特に、受験環境の統一、厳密な時間管理、そして不正防止策の徹底は、試験の公平性と信頼性を保つ上で重要なポイントとなります。
さらに、採点効率化のためのシステム導入や、受験者への適切なサポート体制も考慮する必要があります。
入力環境の統一
オンラインで論述試験を実施する際、受験者の入力環境をできる限り統一することは、公平な試験条件を確保するために重要です。
使用するデバイス(PC、タブレット)、ブラウザ、OSのバージョンなどを事前に指定し、推奨環境を明確に提示することが望ましいでしょう。これにより、特定の環境でのみ発生する不具合や、入力方式の違いによる有利不利を防ぐことができます。
また、日本語入力システム(IME)の設定についても、推奨される設定や注意点を事前に周知することで、文字入力に関するトラブルを未然に防ぎます。
テストプラットフォームによっては、受験者が別のアプリケーションに切り替えたり、他のウィンドウを開くのを制限できる機能もあります。このような機能は、不正行為の防止にもつながり、公平な入力環境の維持に貢献します。
試験前にテスト環境での動作確認を促す機会を設けることで、受験者が本番で安心して試験に臨めるようサポートすることも大切です。
制限時間管理
オンラインでの論述試験における制限時間管理は、試験の公平性を保ち、受験者のパフォーマンスを適切に評価するために重要です。システム上で試験の開始と終了を明確にし、厳格な時間制限を設ける必要があります。
試験時間が終了したら自動的に解答ができなくなる設定にすることで、時間外の解答を防ぎ、すべての受験者に平等な条件を提供できます。また、試験中に残り時間をリアルタイムで表示する機能や、時間切れが近づいた際に警告を表示する機能は、受験者が時間配分を意識し、効率的に解答を進める上で役立ちます。
試験のセクションごとに制限時間を設定することも、受験者が計画的に解答を進める手助けとなります。オンライン試験では、受験者の自宅環境によって通信速度などに差が生じる可能性も考慮し、システムの安定性や遅延対策も合わせて講じることが望ましいでしょう。これにより、技術的な問題が受験者の時間管理に影響を与えることを最小限に抑えられます。
不正防止策
オンライン論述試験における不正防止策は、試験の信頼性と公平性を確保する上で重要な課題の一つです。自宅など遠隔地で受験する場合、受験者にとって不正がしやすい環境となるため、多角的な対策が求められます。
具体的には、AIによる不正検知やWebカメラを使った有人監視が効果的です。例えば、PCのカメラを利用して受験中の様子を録画し、試験後にAIや監督員が不審な行動がないか確認する方法が挙げられます。顔認証技術を導入し、なりすまし受験を防ぐための本人確認を行うことも可能です。
また、試験中の画面共有や、指定されたアプリケーション以外の起動を制限するシステムの利用も有効な手段です。問題の流出を防ぐために、ランダム出題や問題文のコピー貼り付けを制限する機能も有用です。
さらに、受験者に対して不正行為に対する厳格な処分を事前に周知し、不正を行わないよう心理的な抑止力を働かせることも重要です。これらの対策を組み合わせることで、オンライン環境下での不正行為のリスクを最小限に抑え、公正な試験運営を目指すことができます。
イー・コミュニケーションズが提供する「ULTRA GUARDIAN」は、オンライン試験実施時に、受験操作の制御や、表示制御、遠隔操作検知など、あらゆる不正行為を防止できるWindowsアプリケーションです。受験画面上に最前面でフルスクリーン表示にすることで、他のウィンドウやアプリケーションを起動することができません。
また、リモート監視サービスの「Remote Testing」をご活用いただければ、自宅でも厳正・厳格な試験が実現できます。Webカメラで受験者を録画し、録画された動画をAIが自動解析、不正と思われる挙動を検知するなど、受験時の不正抑止・防止が可能です。
採点効率化
オンライン論述試験の導入は、採点業務の劇的な効率化を可能にします。従来の紙媒体での試験では、答案用紙の回収、仕分け、手作業による採点と集計に多大な時間と労力がかかっていました。
しかし、オンライン化された試験システムでは、解答がデジタルデータとして保存されるため、採点者は場所を選ばずに採点作業を進めることができます。多くのオンライン試験システムは、記述式問題にも対応したデジタル採点機能を備えています。
また、キーワードの自動検出や、類似表現のパターンマッチングなど、AIを活用した自動採点システムも登場しており、採点基準に沿った客観的な評価と採点時間の短縮を実現します。複数の採点者が関わる場合でも、システム上で採点結果を一元管理し、採点者間のブレを自動で検知・調整する機能もあります。
受験者サポート
オンライン論述試験を円滑に実施するためには、受験者への適切なサポート体制を構築することが不可欠です。オンライン試験に不慣れな受験者や、技術的なトラブルに直面した受験者が安心して試験に臨めるよう、事前に十分な情報提供と問い合わせ窓口の設置が必要です。
具体的には、試験システムの操作方法に関する詳細なマニュアルやQ&Aサイトを用意し、よくある質問とその解決策を提示します。また、試験当日には、リアルタイムで対応できる技術サポート窓口(電話、チャットなど)を設置し、緊急時のトラブルに迅速に対応できる体制を整えることが重要です。
試験開始前の接続テストやシステム動作確認の機会を提供することで、受験者が自身の環境で問題なく試験を受けられるかを確認できるようにします。さらに、予期せぬシステム障害や通信トラブルが発生した場合の対応方針(再試験の実施、時間延長など)を事前に明確に伝え、受験者の不安を軽減することも大切です。
手厚い受験者サポートは、試験の公平性を保つだけでなく、受験者の満足度向上にも繋がります。
オンラインテストにイー・コミュニケーションズの「MASTER CBT PLUS」をご活用ください
論述試験を含むオンラインテストには、CBTシステムの「MASTER CBT PLUS」がおすすめです。ブラウザベースで動作をするエンジンのため、アプリケーションのインストールは不要です。PCやスマートフォン、タブレットなどの受験端末とインターネット回線のみで受験できるため、場所と時間を問わず、オンラインテストの実施が可能です。
また、「MASTER CBT PLUS」と連携して使用できるリモート監視サービスの「Remote Testing」や操作制御アプリケーションの「ULTRA GUARDIAN」を導入いただくことで、自宅でもセキュアな環境で試験を実施することが可能です。
ご興味がおありの場合は、お気軽にお問い合わせください。