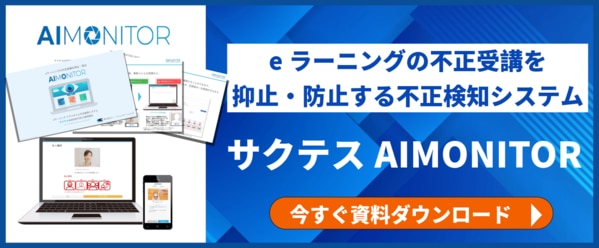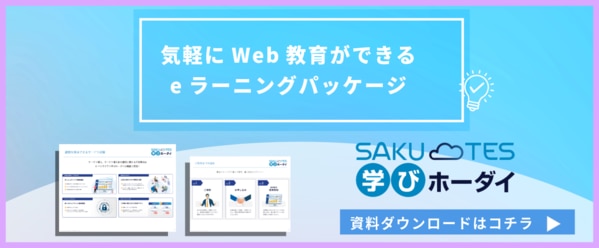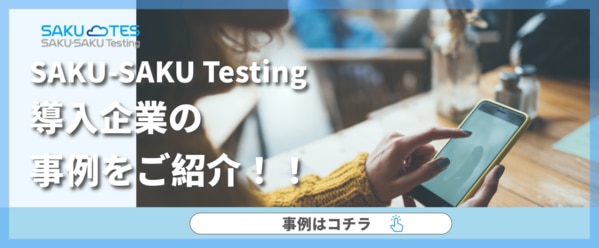傾聴力とは?ビジネスでの活用法と能力を高める方法

傾聴力とは、単に相手の話を聞くだけではなく、相手の言葉に耳を傾け、真意を理解しようとする姿勢を指します。このスキルは、良好なコミュニケーションを築き、信頼関係を深める上で欠かせません。
本記事では、傾聴力の定義や重要性を始め、高い傾聴力を身につけるための具体的なテクニックやトレーニング方法、ビジネスシーンにおける活用例などを紹介します。
目次[非表示]
- 1.傾聴力の基本的な理解
- 1.1.傾聴力の定義と重要性
- 1.2.「聞く」「聴く」「訊く」の使い分け
- 2.傾聴力が高い人の特徴
- 2.1.話を最後まできちんと聴く
- 2.2.相手の気持ちをくみ取ろうとする
- 2.3.相づちや言い換えを使って理解を確認する
- 2.4.自分の意見を押しつけない
- 2.5.本当の問題に気づける
- 2.6.自然な質問で会話を深める
- 3.傾聴力がもたらすメリット
- 3.1.個人にとってのメリット
- 3.2.組織にとってのメリット
- 4.傾聴力の種類と心がけ
- 4.1.傾聴力の主な種類
- 4.1.1. ① 受容的傾聴
- 4.1.2.② 反映的傾聴
- 4.1.3.③ 積極的傾聴=アクティブリスニング
- 4.2.傾聴力を発揮するための「3つの心がけ」
- 5.傾聴力を高めるトレーニングやロールプレイング
- 6.傾聴力を高めるためトレーニング
- 6.1.日常で意識するトレーニング
- 6.2.ロールプレイングの活用
- 6.2.1.1. 役割を決める
- 6.2.2.2. テーマを決める
- 6.2.3.3. 実施(5〜10分)
- 6.2.4.4. フィードバックタイム
- 7.傾聴力の活用
- 7.1.営業活動での傾聴力
- 7.2.1on1ミーティングでの活用
- 7.3.チーム内コミュニケーション
- 7.4.リーダー・マネジメント層に求められる傾聴力
- 7.5.その他のビジネスシーン
- 8.スピードが求められる現代でもできる傾聴のポイント
- 9.傾聴力を実践する際の留意点
- 9.1.傾聴を妨げる行動をしない
- 9.2.継続的に取り組む
- 10.傾聴力の評価方法
- 10.1.1. 基本姿勢の評価
- 10.2.2. アクティブリスニングの評価
- 10.3.3. 共感と公平性の評価
- 11.社員のスキルアップにeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
傾聴力の基本的な理解

傾聴力は、ビジネスシーンで欠かせないコミュニケーションスキルの一つです。単に相手の話を聞くだけでなく、深く理解し、適切に対応する能力を指します。以下では、傾聴力の定義や重要性、そして実践的なテクニックについて詳しく解説していきます。
傾聴力の定義と重要性
傾聴力とは、他者の話を深く理解し、共感をもって受け止める能力のことです。
単に言葉を「聞く」だけでなく、相手の感情や意図を察知し適切に反応する「聴く」力が求められます。傾聴力が向上すると、コミュニケーションの質を大きく向上させて相互理解が進みます。
相手の話を受け止めるだけでなく、その奥にある思いや意図に目を向ける姿勢こそが、傾聴力の本質です。信頼関係を築き、円滑なコミュニケーションを実現するために欠かせないスキルです。経済産業省が提唱する「人生100年時代の社会人基礎力」の一つとしても位置づけられており、ビジネスにおいて不可欠な能力と考えられています。
「聞く」「聴く」「訊く」の使い分け
日本語の「きく」には、3つの漢字があります。それぞれ少しずつ意味が違います。
- 「聞く」は、ただ音が耳に入ってくること。たとえば、電車の音や周りの会話が自然に聞こえるようなときに使います。
- 「聴く」は、相手の話にしっかり耳を傾けて、内容だけでなく気持ちまで理解しようとすることです。自分から進んで聴こうとする姿勢が大切になります。
→ 「傾聴力」とは、この「聴く」の力のことを指します。 - 「訊く」は、何かをたずねたり、知らないことを質問したりするときに使います。
傾聴力では、「聴く」こと――。相手の話に心を向けて理解しようとすることがとても大切です。
傾聴力が高い人の特徴

傾聴力に優れた人は、人間関係を円滑に保ち、ビジネスシーンでも大きな成果を生み出します。
ここでは、傾聴力が高い人の具体的な特徴を詳しく見ていきます。
話を最後まできちんと聴く
相手の話を途中でさえぎらず、真剣に最後まで耳を傾けます。これによって、話す人は安心して自分の気持ちや考えを伝えることができます。
相手の気持ちをくみ取ろうとする
言葉だけでなく、表情や声の調子、身ぶりなどから、相手の本当の気持ちや考えを読み取ろうとします。
相づちや言い換えを使って理解を確認する
うなずいたり、「つまり○○ということですね」と言い換えて確認したりして、相手が話しやすい空気をつくります。
自分の意見を押しつけない
すぐにアドバイスをしたり自分の考えを言ったりせず、まずは相手の立場や気持ちを大切にします。
本当の問題に気づける
相手の話の中から、表に出ていない根本的な問題や解決のヒントを見つけるのが得意です。
自然な質問で会話を深める
相手が話しやすくなるような質問を投げかけて、対話を深めることができます。
傾聴力がもたらすメリット

人の話をきちんと聴ける力は、信頼や成果につながる多くのメリットが得られます。ここでは個人と組織、それぞれにもたらすメリットを見ていきます。
個人にとってのメリット
- 信頼されやすくなる
相手の話をしっかり聴くことで、「この人はちゃんと話を聴いてくれる」と思われ、信頼関係が生まれます。 - 人間関係がスムーズになる
人の気持ちや考えを理解できるようになるので、関係が良くなり、トラブルも減ります。 - 問題解決がうまくなる
相手の本当の悩みや課題に気づけるようになり、的確な対応ができるようになります。 - 新しいアイデアが生まれる
いろんな人の考えを受け入れられるようになるため、発想の幅が広がります。
組織にとってのメリット
- チームの雰囲気がよくなる
メンバー同士がしっかり話を聴き合うことで、信頼関係ができ、協力しやすくなります。 - 働きやすい職場になる
お互いの話を丁寧に聞ける環境があると、安心して仕事ができるようになります。 - お客様との関係も良くなる
お客様の本当のニーズを聴き出すことができるようになり、信頼され、ビジネスにもつながります。 - 早めのサポートができる
部下や同僚の悩みに早く気づけるので、適切なサポートができ、結果として離職の防止やモチベーション向上につながります。
このように、「よく聴く力」=傾聴力は、仕事にも人間関係にも良い影響をたくさんもたらします。
傾聴力の種類と心がけ

傾聴力は単に「聞く」だけではなく、より深いレベルで相手を理解しようとする能動的なプロセスです。そのため、いくつかの種類に分類され、効果的に実践するためには特定の要素が不可欠となります。ここでは、傾聴力の主な種類と、それに必要な要素について詳しく解説します。
傾聴力の主な種類
傾聴力にはいくつかの種類があります。心理学やコミュニケーションスキルの分野でよく使われる代表的な3つをご紹介します。
① 受容的傾聴
→ 「そのまま受け入れる聴き方」
相手の話を評価したり、すぐにアドバイスしたりせず、まずは「うんうん」と静かにしっかり受け止める姿勢です。
話し手は「この人には安心して話せる」と感じます。
② 反映的傾聴
→ 「聞いたことを伝え返す聴き方」
相手が話した内容や気持ちを、「〇〇と言いたいんですね」「そう思ったんですね」などと、言葉にして返すことで、「ちゃんと聴いてくれている」と伝える方法です。
「バックトラッキング(繰り返し)」や「言い換え(パラフレーズ)」が含まれます。
③ 積極的傾聴=アクティブリスニング
→ 「関わりながら聴く聴き方」
ただ黙って聞くだけでなく、相づちや質問を交えて、相手の話をもっと深く理解しようとする聴き方です。
「どう感じたんですか?」「そのとき何があったんですか?」など、会話を深めるやり取りをします。
この方法は、心理学者のカール・ロジャースが広めたもので、カウンセリングでも使われています。
傾聴力を発揮するための「3つの心がけ」
これはアメリカの心理学者「カール・ロジャース」が提唱したもので、信頼される聴き手になるための基本です。
① 共感的理解とは「相手の気持ちになって考えること」です。
相手の話を「自分だったらどう感じるかな?」と相手の立場に立って、心の中を想像して聴くことです。
ただ「かわいそう」と思うのではなく、「この人は今、こんな気持ちかもしれない」と本気で寄り添う姿勢が大切です。
② 無条件の肯定的関心とは「相手をそのまま受け入れること」です。
相手が何を話しても、否定したり、評価したりせず、「この人の話をちゃんと聴こう」という気持ちで聴くことです。
自分の好みや考えを押しつけず、相手に安心して話してもらうことを大事にします。
③ 自己一致とは 「自分に正直でいること」です。
聴いている自分自身が、気持ちをごまかさず、本音で相手と向き合うことです。
わからないときは無理にわかったふりをせず、「ちょっとわかりにくかったので、もう一度教えてください」と正直に言えることも含まれます。
この3つは、どれもバラバラではなく、お互いにつながって、相手に安心感と信頼感を与える聴き方になります。
傾聴をより深くするために、とても大切な考え方です。
傾聴力を高めるトレーニングやロールプレイング

傾聴力を高めるためトレーニング
傾聴力は意識することで誰でも伸ばすことができます。ここでは、その力を高めるために役立つ日常で意識するトレーニングとロールプレイングをご紹介します。
日常で意識するトレーニング
傾聴のスキル | 説明 | ポイント・注意点 |
アクティブリスニング(積極的傾聴) | 単に聞くだけでなく、理解を深めるために積極的に関わる姿勢。適切な相槌や繰り返し、要約を含む。 | 相手の話をしっかり受け止める姿勢が重要。 |
バックトラッキング(繰り返し) | 相手の言葉を繰り返して確認し、理解していることを示す。 | 過剰にならず、自然に行うことがポイント。 |
ミラーリング | 相手の表情・しぐさ・声のトーンを自然に真似ることで安心感を与える。 | やりすぎると不自然になるので注意。 |
ペーシング | 会話のテンポやリズムを相手に合わせることでスムーズなコミュニケーションを促す。 | 相手に合わせすぎて自分を見失わないように注意。 |
オープンクエスチョン | 「はい」「いいえ」では答えられない質問で、相手に自由に話してもらう。 | 適切なタイミングで質問することが効果的。 |
沈黙 | 相手が考えたり感情を整理するための時間を与える。 | 不安にならず、自然な間として受け入れること。 |
これらのテクニックを意識的に繰り返すことで、傾聴スキルを向上させることができます。
ロールプレイングの活用
傾聴力を高めるロールプレイングは、実践的な練習を通してスキルを身につける有効な方法です。以下に、効果的なロールプレイングの流れと例をご紹介します。
1. 役割を決める
- 話し手(スピーカー):話題について自由に話す。
- 聞き手(リスナー):傾聴のテクニックを意識して話を聴く。
- (※オブザーバーをつけると客観的なフィードバックが可能)
2. テーマを決める
例えば以下のような例があります。
- 「最近仕事で困っていること」
- 「学生時代に一番頑張ったこと」
- 「最近嬉しかったこと/悲しかったこと」
3. 実施(5〜10分)
- 話し手が自由に話す
- 聞き手は傾聴の技術を使いながら聴く
聞き手は以下を意識して実践します。
- 相手の話を遮らない
- あいづちやうなずきで関心を示す
- 内容を要約・確認する
- 感情に共感する言葉をかける
- ノンバーバル(表情・姿勢)も活用する
4. フィードバックタイム
- 話し手:話しやすかったか?理解されていると感じたか?
- 聞き手:自分ができた点・難しかった点
- オブザーバー(いれば):良かった点・改善点を指摘
ロールプレイでは「アドバイスをしない」「評価をしない」「話を奪わない」ことが基本です。あくまで「聴くこと」に徹する練習です。
傾聴力の活用

傾聴力は、さまざまな場面で活用できる汎用性の高いスキルです。
単に情報を得るだけでなく、相手との信頼関係を構築し、問題解決や目標達成に繋げるために重要な役割を果たします。ここでは、具体的なビジネスシーンでの傾聴力の応用例と、他のスキルとの組み合わせによる効果について解説します。
営業活動での傾聴力
顧客の話に丁寧に耳を傾け、ニーズや課題を深く理解することで、より的確な提案が可能
→顧客の信頼を得て、契約獲得や継続的な関係構築につながります。
1on1ミーティングでの活用
部下の声に真摯に耳を傾けることで、悩みや目標を把握し、適切な育成やサポートが可能
→部下のモチベーション向上や成長促進となります。
チーム内コミュニケーション
メンバーの意見を尊重し、多様な視点を受け入れる
→チームワークが強化され、課題解決や意思決定の質が向上します。
リーダー・マネジメント層に求められる傾聴力
部下やチームメンバーとの信頼関係構築やエンゲージメント向上、チームのパフォーマンスを最大化させます。
その他のビジネスシーン
- 接客業・コンサルティング:顧客の要望や状況を正確に把握し、的確な対応を行うために必要。
- 採用面接:候補者の話し方や内容から潜在能力や適性を見極める際に活用。
このように、傾聴力は職種や役職に関わらず、あらゆるビジネスシーンで求められる基本的かつ重要なスキルと言えます。
スピードが求められる現代でもできる傾聴のポイント

「じっくり話を聴く=時間がかかる」と思われるかもしれませんが、相手との信頼関係を築く最短ルートになることも多いです。ここでは傾聴のポイントや意味を説明します。
1. 傾聴は「長時間聞くこと」ではなく「質の高い聴き方」
- 傾聴はただ長く話を聞くことではなく、短い時間でも集中して相手の話の本質を理解すること。
- 時間が限られていても、ポイントを押さえた聴き方をすることで効果的に傾聴できます。
2. 傾聴はコミュニケーションの効率化につながる
- 初めに相手の話をしっかり聴くことで、誤解や手戻りを防ぎ、結果的に時間の節約になります。
- スピーディーに正確な理解ができるため、無駄なやり取りが減ります。
3. 短時間でもできる傾聴のテクニックがある
- 要点を繰り返す「バックトラッキング」や、簡潔な「オープンクエスチョン」を使えば、素早く相手の本音や重要ポイントを引き出せます。
- 「沈黙の間」も1〜2秒の短いタイミングで効果的に使えます。
傾聴力を実践する際の留意点

傾聴力を伸ばすことは、ビジネスの場で多くのメリットをもたらします。ただし、スキルを身につけるには、意識すべき注意点もいくつかあります。うっかり傾聴を妨げてしまう行動に気をつけながら、日々意識して取り組むことが大切です。ここでは、聴く力を高める際に気をつけたいポイントを解説します。
傾聴を妨げる行動をしない
- 話を途中でさえぎらない
相手の話が終わる前に自分の意見やアドバイスを話し始めると、相手は「ちゃんと聞いてもらえていない」と感じてしまいます。 - 話を否定したり評価をしない
「それは違う」「そんなことはダメだ」と否定すると、相手は安心して本音を話せなくなります。 - スマホや他の作業をしながら聞かない(ながら聞きはしない)
スマホを見たり他のことをしながら話を聞くのは、相手に対する敬意が伝わらず、真剣に聞いている感じがしません。 - 言葉の表面だけを捉えない
相手の気持ちや考えの裏側まで理解しようとせず、ただ言われたことだけを受け取ると、本当の意図がつかめません。 - 急いで問題を解決しようとしない
相手が話し終わる前に解決策を出してしまうと、話すチャンスを奪い、相手の気持ちを十分に理解できません。
これらの行動に無意識のうちに陥っていないか、常に自己チェックを行うことが大切です。
継続的に取り組む
傾聴力は、一度身につければそれで終わりではなく、継続的な取り組みによって維持・向上させていく必要があります。
日々の業務やプライベートでのコミュニケーションにおいて、意識的に傾聴を実践することが重要です。会話の際に、相手の話に真剣に耳を傾ける、適切な相槌を打つ、相手の言葉を要約して返すといった基本的なテクニックを意識的に使うことから始められます。また、自分の傾聴の質についてフィードバックを求めることも有効です。同僚や信頼できる相手に、自分の話の聞き方について率直な意見をもらうことで、自身の課題や改善点に気づくことができます。傾聴は継続的な努力によって磨かれるスキルであり、日々の意識と実践がその向上に不可欠です。
傾聴力の評価方法

ビジネスシーンにおいて傾聴力は重要なスキルであると認識されており、企業は従業員の傾聴力を評価し、育成するためのさまざまな取り組みを行っています。
傾聴力を可視化し、計画的に能力向上を図ることは、組織全体のコミュニケーション活性化やパフォーマンス向上に繋がります。ここでは、傾聴力の評価方法について解説します。
1. 基本姿勢の評価
相手の話を遮らず、最後まで聴く姿勢が傾聴の出発点です。表情やうなずき、声のトーンなどの非言語行動を含め、話し手に安心感を与えられているかを確認します。また、適切なタイミングで相槌を打ち、「聞いている」というメッセージを伝えられているかも重要です。
2. アクティブリスニングの評価
話の要点を正しく捉えるために、質問や要約で理解を確認する姿勢を評価します。これにより、情報の取りこぼしを防ぐだけでなく、話し手に対して関心と理解を示せているかが測定できます。さらに、質問の質(オープン/クローズド)や要約の的確さも評価ポイントとなります。
3. 共感と公平性の評価
相手の立場や感情に寄り添い、共感的に受け止めているかを観察します。同時に、自分の先入観や価値観で判断せず、公平かつ客観的に話を受け止めているかも確認します。共感的理解と公平性のバランスが取れていることが、質の高い傾聴を示す指標です。
社員のスキルアップにeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
本記事では、聴く力の重要性や、その実践方法についてご紹介しました。
近年では、傾聴力向上に注力する企業が増えており、組織全体でその価値を共有することが求められています。
まずは、その重要性を社員全体で共通認識として持つことがスタートです。
そのためには、研修やセミナーを通じて、基本的な考え方から実践的なコミュニケーション技術までを無理なく学べる機会をつくることが大切です。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、自社の動画を搭載したオリジナル研修が簡単に実施できます。
ぜひ動画研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。
また、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。