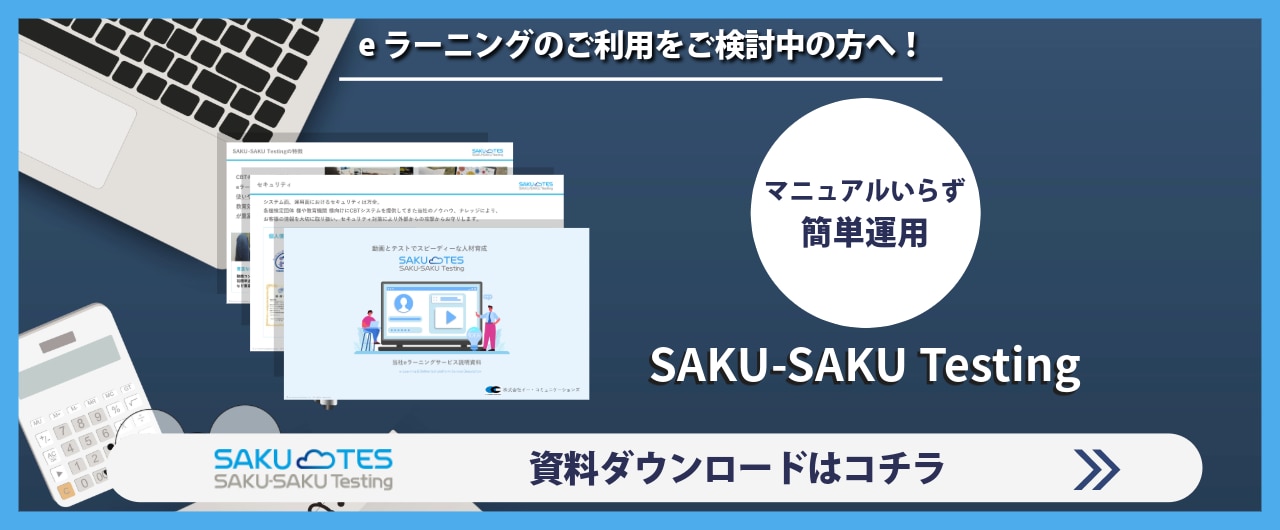オンデマンド研修とは?メリット・デメリットや成功のコツを徹底解説
研修のオンライン化が進む中、多くの企業が注目しているのが「オンデマンド研修」です。オンデマンド研修とは、従業員が自分のスケジュールに合わせて受講できる柔軟な研修形式のことです。
そこで今回は、オンデマンド研修の導入がはじめてという方でも効果的な成果を出す研修のコツをお伝えします。
従業員のスキルアップと組織の成長を実現するための効果的なアプローチにお役立てください。
目次[非表示]
- 1.オンデマンド研修とは
- 2.オンデマンド研修のメリット
- 2.1.【受講者メリット】時間や場所を選ばず、自分のペースで学習できる
- 2.2.【受講者メリット】繰り返し学習による知識の定着と理解度の向上
- 2.3.【管理者メリット】コスト削減と研修品質の均一化
- 2.4.【管理者メリット】学習進捗の可視化と管理負担の軽減
- 3.オンデマンド研修のデメリットと注意点
- 3.1.一方通行になりがちなコミュニケーション
- 3.2.受講強制力の弱さ
- 3.3.システム環境・インターネット接続への依存性
- 4.オンデマンド研修の効果最大化のためのポイント
- 5.オンデマンド研修が効果を発揮するケース
- 6.失敗しない!オンデマンド研修導入のステップ
- 6.1.ステップ1:目的設定と管理ルールの構築
- 6.2.ステップ2:飽きさせない動画教材の作成
- 6.3.ステップ3:LMSなどのプラットフォーム選定
- 6.4.ステップ4:進捗管理、効果測定、フィードバックの実施
- 7.オンデマンド研修に必要なツール(LMS)
- 8.オンデマンド研修にイー・コミュニケーションズのSAKU-SAKU Testing をご活用ください
オンデマンド研修とは

オンデマンド研修とは、「利用者の要望に応じて提供される」という意味を持つオンデマンド(On Demand)の名の通り、受講者が好きなタイミングと場所で学習できる研修形態です。
具体的には、事前に収録・制作された動画やスライドなどの学習コンテンツを、インターネットを通じてオンラインで配信し、受講者がPCやスマートフォンから視聴しながら学ぶ形式を指します。
この形式の最大の利点は、受講者が時間や場所に縛られず、自身のスケジュールに合わせて研修を受けられる利便性の高さにあります。
また、学習内容を何度でも繰り返し確認できるため、理解度や学習スピードに応じた柔軟な学習が可能です。
オンデマンド研修は、eラーニング(電子的な手段を用いた学習方法)の主要な形態の一つです。
近年、動画配信機能を備えたLMS(学習管理システム)などのeラーニングシステムを活用してオンデマンド研修を実施する企業が増加しており、LMSを用いることで研修データの詳細な管理や効果測定が容易となっています。
リアルタイム研修(ライブ配信型)との違いを比較

オンラインで実施される研修には、オンデマンド研修の他にリアルタイム研修(ライブ配信型研修)があります。
この二つは、学習の進め方とコミュニケーションの形態が大きく異なります。
リアルタイム研修は、Web会議システムなどを使い、講師の授業に受講者が同時に参加する形式で、対面研修をオンライン上に置き換えたものといえます。
この形式は、講師や参加者同士がリアルタイムで直接的にディスカッションや質疑応答ができる点がメリットです。しかし、受講日時は固定されるため、スケジュール調整が必要であり、内容の振り返りや復習が困難になる場合があります。
一方、オンデマンド研修は、いつでもどこでも自分の都合の良い時間に受講できる反面、講師とのやり取りはメールや掲示板など間接的になり、タイムラグが生じます。
ただし、一度制作したコンテンツは繰り返し利用できるため、学習内容の定着を促進できます。研修の目的やニーズに応じて、この両者を適切に選択、または組み合わせて活用することが重要です。
企業研修においてオンデマンド形式が注目される理由

近年、企業研修においてオンデマンド形式が急速に普及し、注目を集めている背景には、社会や働き方の大きな変化があります。
まず、働き方の多様化が挙げられます。テレワークの普及や、事業のグローバル化、地方への拠点分散などの要因により、従業員が特定の時間に一堂に会して研修を受ける従来の集合研修の実施が困難なケースが増加しました。
オンデマンド研修は、勤務場所や時間の影響を受けずに効率的に実施できるため、この課題を解決する有力な代替手段となっています。
また、社会全体のDX化やテクノロジーの進化も普及を後押ししています。高速インターネットやクラウド技術の進歩により、大容量の動画教材をオンラインで容易に利用できるようになり、コンテンツ制作や配信にかかるコストも減少しました。
さらに、LMSなどのプラットフォームの進化により、学習進捗をデータに基づいて管理・改善できるようになり、データドリブンな人材育成が実現可能になったことも、導入が増えている大きな理由です。
オンデマンド研修のメリット

オンデマンド研修は、研修を受ける従業員(受講者)と、研修を提供する企業(管理者・教育担当者)の双方に多くの利点をもたらします。
【受講者メリット】時間や場所を選ばず、自分のペースで学習できる
受講者にとって最大のメリットは、学習の柔軟性です。
オンデマンド研修は、PC、スマートフォン、タブレットなどのデバイスさえあれば、自宅、職場、出張先といった場所を問わず、好きなタイミングで学習が可能です。忙しいビジネスパーソンにとって、日中の業務に追われまとまった時間を確保しづらくても、通勤時間や業務の隙間時間などを活用して学習を進めることができるため、継続的な学習が促進されます。
この柔軟性が、業務スケジュールに無理なく組み込まれ、結果としてパフォーマンスの向上につながります。
【受講者メリット】繰り返し学習による知識の定着と理解度の向上
オンデマンド研修は、個々人の理解度や学習スピードに合わせた学習を可能にします。
集合研修では生じがちな「わからないまま進んでしまう」という問題は、オンデマンド研修では解消されます。録画されたコンテンツは何度でも見返すことができ、特に専門的な用語が多い研修や難易度の高い内容の場合、重要な部分を繰り返し確認できる環境は、理解度に大きな差を生む要因となります。
この反復学習の優位性により、受講者は納得や確信を得ながら確実にスキルを習得でき、知識の定着を促進します。
【管理者メリット】コスト削減と研修品質の均一化
管理者側の大きなメリットは、コストと労力の削減です。
従来の集合研修で必要だった会場費、受講者の交通費・宿泊費、印刷物の準備、および実施の都度発生する講師の人件費などが大幅に削減されます。一度教材を作成すれば繰り返し利用できるため、再度の提供にかかる追加コストを抑えられ、高いコストパフォーマンスを発揮します。
また、研修品質の均一化も実現します。
オンデマンド研修では、最も指導スキルの高い講師による授業を収録し、その高品質なコンテンツをすべての従業員に均等に配信できます。これにより、講師による指導力の差で研修効果にばらつきが生じることなく、全社的に一貫した知識とスキルを提供することが可能です。
【管理者メリット】学習進捗の可視化と管理負担の軽減
オンデマンド研修では、LMS(学習管理システム)の活用により、受講者管理の効率化が図れます。LMSを使えば、受講者一人ひとりの視聴状況、学習履歴、理解度テストの結果などがデジタル上で自動的に収集・記録されます。
これにより、管理側は「どの社員が、どの程度の理解度で学んでいるのか」をリアルタイムで把握できるようになり、学習進捗の可視化が容易になります。
また、集合研修で必要だったスケジュール調整や出欠確認などのアナログな手間が削減され、研修担当者の管理負担が大幅に軽減されます。教育担当者は、浮いたリソースを研修内容の質の向上や、データに基づいた戦略的な人材育成に注力できるようになります。
オンデマンド研修のデメリットと注意点

オンデマンド研修は柔軟性やコスト面で優れている一方で、非対面形式特有のデメリットや、運用上の注意点が存在します。
これらの課題を事前に把握し、対策を講じることが、導入失敗を防ぐ鍵となります。
一方通行になりがちなコミュニケーション
オンデマンド研修は、事前に収録された教材を視聴する形式のため、リアルタイムでのコミュニケーションが難しいという課題があります。
受講者は学習中に疑問が生じても、その場で講師に直接質問したり、即時のフィードバックを得たりすることができません。このため、疑問点が未解消のまま残ってしまい、学習効果が薄れる可能性があります。
また、講師側も受講者の表情や態度を直接把握できないため、理解度を測ることが難しくなります。さらに、集合研修で見られた受講者同士の雑談や意見交換を通じた「新たな気づき」や「チームワークの醸成」といった交流の機会が生まれにくいという難点もあります。
受講強制力の弱さ
オンデマンド研修の大きなメリットである「いつでも受講できる」という自由度の高さは、裏を返せば「いつまでも受講しない」というデメリットにつながる可能性があります。
受講スケジュールや学習の進捗が受講者自身の自己管理能力に委ねられるため、モチベーションが続かなかったり、受講を先延ばしにしたりするケースが頻発する懸念があります。集合研修やリアルタイム研修のように日時が固定されていると強制力が働きますが、オンデマンドでは受講者が主体的に取り組む意欲がなければ、学習進度が停滞し、結果として研修の修了率が低下するリスクがあります。
企業が研修成果を確実に測りたい場合、フォローアップの仕組みを整えることが不可欠です。
システム環境・インターネット接続への依存性
オンデマンド研修は、オンラインでの動画配信が前提となるため、システム環境とインターネット接続への依存性が注意点となります。
受講者が利用するPCやタブレットなどの端末が古い場合や、ネットワーク障害、回線が不安定である場合、肝心な研修動画がスムーズに再生できないというトラブルが生じる可能性があります。
これにより、学習スケジュールが大きく乱れたり、受講者体験が悪化したりすることが懸念されます。従来の集合研修では考慮不要だった、こうしたトラブルシューティングや受講環境の整備に、時間やコストを割く必要が出てきます。
オンデマンド研修の効果最大化のためのポイント

オンデマンド研修のデメリットを解消し、高い学習効果を確実にするためには、運用面および教材面で戦略的な工夫を凝らすことが成功の鍵となります。
受講者のモチベーションを維持する仕組みづくり
自由度の高さゆえに生じるモチベーション低下を避けるためには、受講者が自律的に学習を進められる仕組みを構築することが不可欠です。
まず、研修の目的、具体的な学習目標、明確な受講期限、そして進捗報告の方法などのルールを定め、社内に周知徹底します。
また、受講した努力や成果を人事評価と連携させるなど、取り組みが企業内で評価される仕組みを構築することも、学習意欲を持続させる上で大切です。進捗が遅れている受講者には、自動リマインドメールや上司からの定期的なフィードバックを行うことも有効な対策となります。
疑問解消や交流の機会を設ける工夫
オンデマンド研修では、受講者が一方通行に学習するだけになりやすい点が課題です。これを補うためには、運営側が意識的に交流や質問の場を設ける必要があります。
例えば、受講期間中に定期的なオンラインQ&Aセッションを設ければ、直接講師に質問でき、理解の抜け漏れを防げます。さらに、受講者から寄せられた質問を整理してFAQとして共有すれば、同じ疑問を持つ人にも役立ちます。
また、学習内容をテーマにしたディスカッション会や小グループでの意見交換の場を設けることも効果的です。
こうした仕組みにより、受講者同士の交流や「教え合い」が生まれ、孤立感を防ぎつつモチベーション維持にもつながります。
高品質な教材の用意と、動画以外のコンテンツの活用
研修効果を最大化するためには、教材そのものの品質が鍵となります。受講者が「スキルが伸びる」「仕事に役立つ」と感じるような、有益で実践的な内容を盛り込むことが大前提です。
また、長時間の動画視聴による集中力低下を防ぐため、受講者を飽きさせない工夫が求められます。具体的には、コンテンツを短い単位に分割するマイクロラーニング化や、ストーリー性を持たせた構成が効果的です。
さらに、理解度を客観的に確認するために定期的なテストを実施すると、受講者は緊張感を持ちながら学習でき、知識の定着にもつながります。
加えて、動画だけに頼らず、テキスト資料や課題提出を組み合わせることで学習の幅を広げることができます。アウトプットを伴う演習やロールプレイを取り入れると、知識を「使えるスキル」へと転換しやすくなります。
こうした多様なコンテンツ活用により、能動的な学習姿勢を引き出し、学習効果を一層高められます。
オンデマンド研修が効果を発揮するケース

オンデマンド研修の強みを理解することで、どのような研修内容や受講者層に対して最も効果を発揮するのかが明確になります。
オンデマンド研修が向いている研修内容(知識定着・事前学習など)
オンデマンド研修が特に高い効果を発揮するのは、主に知識のインプットや定着を目的とした研修です。
具体的には、資料や動画をベースにした講義形式の学習や、コンプライアンス、情報セキュリティ、製品知識、業界知識など、コミュニケーションを主目的としない座学中心の内容です。
また、内容が複雑で難易度が高く、一度では理解しにくい研修内容も、繰り返し学習できるオンデマンド形式に適しています。
さらに、時間的な制約がある受講者が多い場合にも最適です。営業担当者のように外出が多くスケジュールの都合がつきにくい社員や、シフト制で勤務時間がバラバラな職場など、全員が一斉に集まることが困難なケースでは、自分の都合の良いタイミングで手軽に研修を受けられる点は大きなメリットとなります。
オンデマンド研修の重要な活用法として、リアルタイム研修や集合研修の「事前学習」としての役割もあります。基礎知識をオンデマンドで事前に習得しておくことで、その後の対面研修の質を高めることができます。
リアルタイム研修(集合研修)の実施が推奨されるケース
オンデマンド研修は万能ではなく、リアルタイム形式や集合形式のほうが適しているケースも存在します。
それは、インタラクティブ性(双方向性)を重視したい場合です。ディスカッション、ワークショップ、グループ活動、ロールプレイングなど、受講者同士の議論や情報交換が不可欠な研修内容には、その場での質問やフィードバックが可能なリアルタイム研修が適しています。特に、コミュニケーションスキルやマネジメントスキルといった実践的なスキルを養うためには、対話と即時的なフィードバックが不可欠です。
また、プロジェクトの立ち上げ時など、特定の時期までに全員が必ず内容を理解し終えなければならないという強制力が必要な場合も、日時が固定されるリアルタイム研修が有効です。
研修の目的や内容に応じて、これらの形式を使い分ける、あるいは組み合わせることが最も効果的です。
失敗しない!オンデマンド研修導入のステップ

オンデマンド研修を導入し、継続的に成果を出すためには、場当たり的な準備ではなく、戦略的なステップを踏むことが重要です。
ステップ1:目的設定と管理ルールの構築
まずは研修の目的を明確にし、対象者を定めます。「どのスキルを習得させたいのか」「どのような成果を期待するのか」を言語化し、ゴールを共有しましょう。
また、オンデマンド研修では受講が自主性に委ねられるため、学習目標や期限、評価基準を定めることが欠かせません。進捗報告の方法を整備し、全員に周知することで受講者の主体性を引き出します。
ステップ2:飽きさせない動画教材の作成
研修の中心は動画教材です。長時間の一方的な説明は集中力を損なうため、映像や音声を工夫し、クイズやミニテストを挟むと効果的です。
教材の制作は、内製化すれば自社の実情を反映しやすくコストも抑えられますが、専門知識やリソースが必要です。
一方、外部発注ではプロ品質の教材を得られ、既存の汎用コンテンツを活用すれば即時性もあります。リアルタイム研修を録画して再利用する方法も有効です。
ステップ3:LMSなどのプラットフォーム選定
教材が完成したら、配信と管理のためのプラットフォームを選びます。単なる動画配信ではなく、進捗や理解度を管理できるLMS(学習管理システム)が最適です。
プラットフォームを選定する際は、受講者の学習環境(スマホやタブレットからの利用可否など)を考慮し、システムが教材のサイズやボリュームに適しているかを確認することが大切です。
ステップ4:進捗管理、効果測定、フィードバックの実施
オンデマンド研修は実施して終わりではなく、継続的な進捗管理と学習効果の測定が不可欠です。
受講状況やテスト結果を追跡し、必要に応じてフィードバックや質疑応答を行いましょう。アンケートで受講者の声を集め、成果や課題を把握することも有効です。蓄積したデータを基に教材を改善し、PDCAサイクルを回すことで、研修効果を継続的に高められます。
オンデマンド研修に必要なツール(LMS)

オンデマンド研修を効果的かつ安全に実施するためには、適切な配信環境の整備が不可欠です。
LMS(学習管理システム)の主要機能と選定基準
オンデマンド研修の中核となるのがLMS(Learning Management System:学習管理システム)です。
LMSは、単に動画を配信するだけでなく、社内教育に必要な多岐にわたる機能を一元的に備えたプラットフォームです。
主要機能としては、コンテンツの搭載・管理、受講者の進捗状況の追跡、理解度確認テストの作成と実施、成績や学習履歴の管理などが挙げられます。これらの機能により、教育担当者は効率的かつ正確なデータ管理が可能となり、受講者へのきめ細やかなフォローアップや研修の改善に役立てることができます。
選定基準としては、直感的な操作性で管理者が簡単にコンテンツを搭載できるか、受講状況やテスト結果をリアルタイムで可視化・管理できるか、そしてセキュリティ対策が堅牢であるか、さらにスマートフォンやタブレットからの利用が可能か、といった点が重要です。
YouTubeなど、他の配信手段の適性
動画の配信手段としてYouTubeなどの一般公開プラットフォームを用いることも考えられますが、研修用途にはあまり推奨されません。
その主な理由として、セキュリティの懸念が挙げられます。
研修内容によっては社外秘の情報を含む場合があり、不特定多数がアクセス可能なYouTubeの機能では、セキュリティに配慮した配信に適さない場合があります。
また、YouTubeには、受講者の実施状況を把握したり、理解度をテストで計測したりする管理機能がないため、研修効果の測定や進捗管理が非常に困難になります。
オンデマンド研修にイー・コミュニケーションズのSAKU-SAKU Testing をご活用ください
オンデマンド研修を導入したいとお考えの企業様は、イー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご検討くださいませ。
SAKU-SAKU Testingは、知識の定着にテストを用いる「テストエデュケーション」で学習ができ、知識習得に高い効果が望めます。また同時に、誰でも簡単に直感で操作できるシステムにより、研修の実施から受講まで、効率的な運用を実現しています。受講者の受講状況やテスト結果をリアルタイムで管理することも可能です。
自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
お気軽にお問い合わせください。