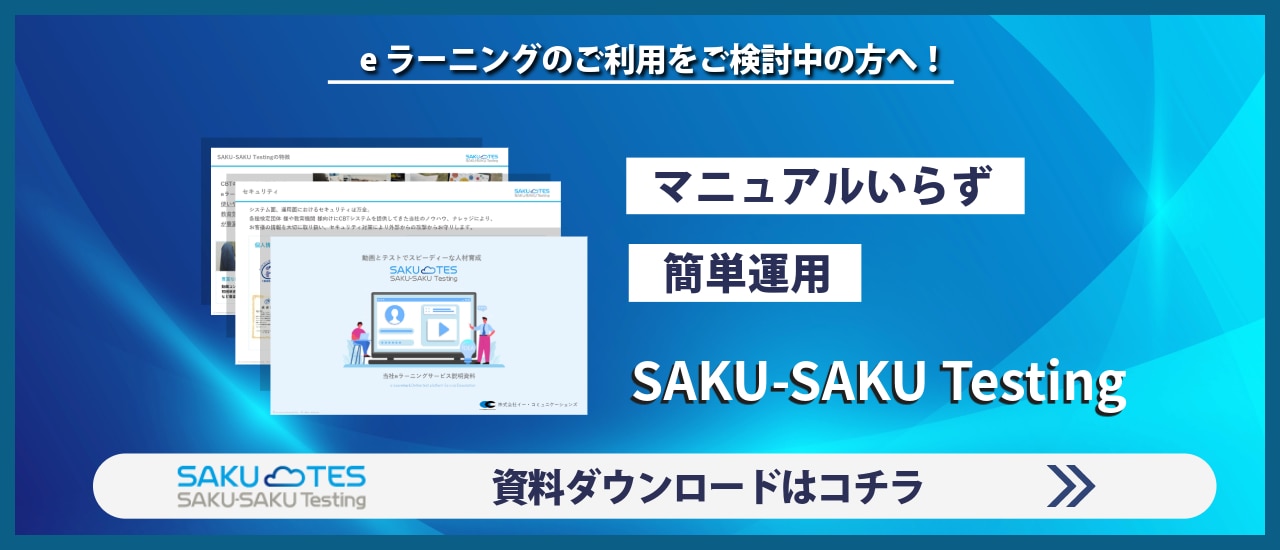役員研修で行うべき内容は?目的と成功のポイントを解説

コーポレートガバナンス・コードの2021年改訂により取締役・監査役に対するトレーニングの開示が明示され、上場企業では役員研修の実施が求められるようになりました。しかし、取締役や監査役、社外取締役も参加するとなると予定をおさえるのに一苦労です。本記事では役員研修をどのように行うべきか検討されている総務・人事担当者向けに、役員研修に盛り込む内容や成功のポイント等を解説していきます。
▼資料ダウンロード:eラーニングコンテンツ「取締役・監査役トレーニング」
目次[非表示]
- 1.役員研修とは
- 2.役員研修の目的
- 2.1.企業の経営理念をあらためて理解する
- 2.2.業績を上げる
- 2.3.経営者の負担軽減
- 2.4.役員のスキル向上
- 3.役員研修に盛り込む内容
- 3.1.経営判断と戦略思考
- 3.2.コーポレートガバナンスと法的責任
- 3.3.リスクマネジメントと危機対応
- 3.4.人的資本経営と組織マネジメント
- 3.5.デジタルセキュリティと知的財産管理
- 4.役員研修の形態
- 4.1.社内実施型(内製研修)
- 4.2.外部プログラムへの参加
- 4.3.公開講座・セミナー
- 4.4.コーチング・メンタリング
- 4.5.eラーニング
- 5.役員研修の設計方法
- 5.1.求められる役員像の明確化
- 5.2.現状把握と課題抽出
- 5.3.プログラム設計
- 5.4.実行と評価
- 6.役員研修成功のポイント
- 6.1.目的を明確にする
- 6.2.受講者に合わせて内容を設計する
- 6.3.実践的なディスカッションやケーススタディを取り入れる
- 6.4.アフターフォローを行う
- 6.5.継続的にアップデートする仕組みを作る
- 7.効果的・効率的に役員研修を行いたい担当者様は「取締役・監査役トレーニング」をご検討ください。
役員研修とは

役員研修は役員を対象に行うもので、管理職研修とも異なります。その定義と必要性について見ていきましょう。
役員の定義
会社法における役員とは、取締役、会計参与、監査役と定められています。(会社法第329条)
役員とは経営に大きく携わり、使用者の管理監督を行う人材をさします。そのため使用者に雇用される労働者である管理職とは根本的に立場が異なります。
出典:e-Govポータル「会社法」第三百二十九条(デジタル庁)
役員研修の対象
一般的に「役員研修」と呼ばれるものは、法律上の役員(取締役・監査役など)だけでなく、経営に深く関与する 取締役や執行役員 を対象とすることが多いです。
また、社外取締役や監査役を含めることで、経営方針やガバナンスに対する共通認識を高められます。さらに、将来的に役員就任が見込まれる幹部層を対象にする企業もあり、短期的な経営強化と長期的なリーダー育成の両面で実施されるケースが増えています。
役員研修の必要性
企業の成長に役員研修は不可欠です。なぜなら役員は企業の責任者であり、大勢の部下の上に立って先導する立場だからです。
役員は企業経営の中枢を担うため、専門知識や判断力を欠くと企業全体に影響を及ぼすリスクがあります。研修を通じて経営やガバナンスに関する知識を補い、リーダーシップや戦略的思考を磨くことが重要です。
さらに、上場企業においては「コーポレートガバナンス・コード」の改訂により、取締役・監査役への研修方針を開示することが求められており、制度面からも役員研修の実施が必要とされています。
原則4-14②「上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。」
出典:「コーポレートガバナンス・コード~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」(株式会社東京証券取引所)
役員研修の目的

役員研修の目的は大きく4つあります。それぞれ解説していきます。
企業の経営理念をあらためて理解する
まずは自社の経営理念、ミッション・ビジョンをあらためて理解し、役員としての正しいかじ取りをする必要があります。どうしても社員との心理的距離が生じてしまうため、交流は困難になりがちですが、その中で企業の目標達成のためにはどのように振舞うことが正しいのかを学びます。
業績を上げる
次に役員研修には、会社の業績を上げる目的もあります。役員は経営に大きく関わる幹部であり、事業運営への影響力は大きいです。研修で会得したスキルや知識は、経営の成果に直結することが多々あり、役員の能力が企業の業績を左右する可能性が大いにあるのです。
経営者の負担軽減
3つ目に経営者の負担を軽減するという目的があります。役員が経営幹部として十分なスキルを持っていれば、経営者の負担を軽減することができ、逆に能力不足だと負担が大きくなります。経営者にすべての判断を委ねるのではなく、役員が右腕として一緒にマネジメントを行えれば、経営者は中長期的な経営戦略を立てることができるなど、ゆとりが生まれ、企業にとって最善の選択をすることができるでしょう。
役員のスキル向上
最後は役員のスキル向上の目的のためです。役員は会社経営に携わるため、役員研によって求められるスキルを高める必要があります。このような研修は不定期開催ではなく、定期的に行い、役員候補の能力も伸ばしておきましょう。将来役員の中から経営者になる人がでるかもしれないため常に資質を高めておくことが重要です。
役員研修に盛り込む内容

役員研修では、会社経営に直結する知識やスキルを体系的に習得することが求められます。単に制度や規則を理解するだけでなく、役員として組織全体を導く判断力・責任感・実行力を養う必要があります。以下では、研修に盛り込むべき5つの主要領域を整理します。
経営判断と戦略思考
役員は、日々の経営課題から将来の企業価値を左右する意思決定まで担います。そのためには、法的責任を踏まえたうえで、短期的な収益と長期的な成長のバランスをとる力が不可欠です。
具体的なテーマ例
- 経営判断原則の習得
- 不確実性下での意思決定プロセス
- 事業ポートフォリオの再構築やM&A戦略
コーポレートガバナンスと法的責任
持続可能な経営の基盤はガバナンスです。取締役会が機能不全に陥ると、重大な経営リスクを招く可能性があります。役員は自らの法的責任を正しく理解し、監督・監査機能を発揮する必要があります。
具体的なテーマ例
- 取締役・監査役の責任範囲
- 内部統制システムの構築
- コンプライアンス経営と企業倫理
▶関連記事:コーポレートガバナンスとは?意味・目的・強化施策を解説
リスクマネジメントと危機対応
経営には常にリスクが伴います。情報漏えいや不祥事が発生した場合、役員の初動対応が企業存続を左右しかねません。想定外の事態にも冷静に対処できる備えが求められます。
具体的なテーマ例
- 内部通報制度の運用方法
- 危機管理広報の基本
- レピュテーションリスク管理
人的資本経営と組織マネジメント
人材は最大の経営資源であり、役員には「人を活かす視点」が求められます。法令遵守にとどまらず、従業員の多様性を尊重し、健全な職場環境をつくることが企業価値につながります。
具体的なテーマ例
- ダイバーシティ推進の仕組み
- ハラスメント防止策
- 働き方改革の推進
デジタルセキュリティと知的財産管理
デジタル化の進展に伴い、情報セキュリティは経営リスクの中心となっています。サイバー攻撃や情報漏えいは企業の信用を一瞬で失墜させるため、役員自身が理解を持つことが不可欠です。
具体的なテーマ例
- 個人情報保護体制の整備
- サイバー攻撃への備え
- DX推進に伴うセキュリティ課題
役員研修の形態

役員研修にはさまざまな実施形態があり、それぞれにメリットと課題があります。
役員層は時間的制約が大きく、研修効果を業務に直結させる必要があるため、最適な方法を選択することが重要です。ここでは代表的な形態を紹介します。
社内実施型(内製研修)
自社に講師を招いて行う研修や、経営層向けに独自に設計したプログラムを用いた研修です。自社の実情や戦略に即した内容にできる点が強みです。一方で、講師の選定やプログラム設計に手間やコストがかかる場合があります。
外部プログラムへの参加
研修会社や教育機関が提供する役員向けプログラムに参加する形式です。他社の役員との交流やディスカッションを通じて、新たな視点やベストプラクティスを学べるのが特徴です。泊まり込みの合宿形式や短期集中型プログラムも多く、非日常的な環境で経営課題に向き合える機会となります。
公開講座・セミナー
単発で参加できる公開型の講座やセミナーも役員研修の一つです。最新の経営理論や事例を短時間でインプットできるため、忙しい役員でも取り入れやすい方法です。ただし、断片的な学びにとどまりやすいため、継続的な研修と組み合わせることが望ましいでしょう。
コーチング・メンタリング
役員個人に対して専門家が伴走する形式です。特定の経営課題やリーダーシップの強化など、個別のニーズに応じた支援が可能です。信頼関係を構築しながら、自らの思考や行動を深く見直すきっかけとなります。
eラーニング
動画教材やオンライン講座を通じて学ぶ自己学習型の研修です。時間や場所を選ばず受講できるため、多忙な役員にとって最も導入しやすい方法のひとつです。加えて、最新の経営理論や事例をタイムリーに取り入れやすく、繰り返し学習することで知識を定着させることができます。
一方で、実践的なアウトプット機会は限られるため、集合研修やコーチングと組み合わせることで、より効果的な研修体系を構築できます。
〈事例〉役員研修でeラーニング「取締役・監査役トレーニング」を導入
役員研修の設計方法

役員研修を成功させるためには、場当たり的な計画ではなく、戦略的かつ体系的な設計プロセスを経ることが不可欠です。
まず自社が求める理想の役員像を具体的に描き、現状とのギャップを正確に分析することから始めます。
その上で、抽出された課題を解決するための最適なプログラムを設計し、実行後はその効果を評価して次へと繋げるという一連の流れを確立することが、研修の質を高める上で重要です。
求められる役員像の明確化
効果的な研修プログラムを設計するための出発点は、自社の経営戦略やビジョンを踏まえ、「どのような役員を育成したいのか」という理想像を具体的に定義することです。
例えば、グローバル市場への展開を加速させるために、異文化理解力とリーダーシップに長けた役員が必要なのか、あるいは新規事業を創出するために、革新的な発想と実行力をもつ役員が求められるのかなど、企業の置かれた状況によって理想像は異なります。
この役員像が、研修の目的設定から内容選定に至るまでのすべてのプロセスにおける判断基準となります。
現状把握と課題抽出
次に、定義した理想の役員像と、現在の役員たちの能力や意識との間に存在するギャップを客観的に把握します。
このプロセスでは、アセスメントツールの活用、上司や部下、同僚からの多面的な評価(360度評価)、あるいは経営トップや本人へのインタビューなどが有効な手段となります。
ここで明らかになった「理想と現状の差」こそが、研修で取り組むべき具体的な課題です。課題を正確に特定することなく進めると、研修内容が実態と乖離し、効果の薄いものになってしまうため、慎重な分析が求められます。
プログラム設計
抽出された課題を解決するために、研修の具体的な中身を設計していきます。
研修の目標、対象者、期間、予算などを考慮しながら、最適なテーマ、講師、教材、実施形式(集合研修、eラーニング、コーチングなど)を決定します。
知識のインプットを目的とする講義形式だけでなく、より実践的なスキル習得を目指すケーススタディ、参加者同士の議論を促すグループワーク、現実の経営課題に取り組むアクションラーニングなど、目的に応じて多様な手法を組み合わせることが効果を高める鍵となります。
常に課題解決に繋がるかという視点でプログラムを構築することが重要です。
実行と評価
設計したプログラムに沿って研修を実施した後は、その効果を必ず評価し、次回の改善に繋げることが不可欠です。
評価の視点としては、研修直後のアンケートで測定する「満足度」や「理解度」だけでなく、一定期間が経過した後に、研修で学んだことが実務でどの程度活かされているかという「行動変容」や、それが業績にどう貢献したかという「成果」のレベルまで測定することが理想です。
この評価結果をフィードバックし、PDCAサイクルを回していくことで、研修プログラムはより洗練され、組織の成長に貢献するものへと進化していきます。
役員研修成功のポイント

役員研修を効果的に実施するためには、単に知識を習得するだけでなく、経営層としての視座を高め、実践に活かせる学びを設計することが重要です。
ここでは、役員研修を成功に導くためのポイントを整理します。
目的を明確にする
役員研修は「形式的に受講すること」が目的ではなく、企業や受講者にとってどのような価値を生むのかを明確にする必要があります。研修を通じて身につけたい能力や期待される行動変容を具体化し、研修後にどのように成果を活用するかをあらかじめ描いておくと効果的です。
また、コーポレートガバナンス・コードでも「上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針を開示すべき」とされており、目的設定は企業の説明責任にも直結します。
受講者に合わせて内容を設計する
役員といっても立場や経験はさまざまです。全員が同じ知識を必要としているわけではありません。経営フェーズや事業課題に応じて、テーマを柔軟に設計することが大切です。
たとえば、グローバル展開を進める企業では国際法務や異文化マネジメントを、DXを推進している企業ではデジタル戦略やサイバーセキュリティを重点的に取り上げるなど、自社の状況に即した内容にすることで実効性が高まります。
実践的なディスカッションやケーススタディを取り入れる
役員研修では、知識のインプットにとどまらず、意思決定力やリーダーシップを磨くことが重要です。そのため、講義形式だけでなく、ディスカッションやケーススタディを組み合わせると効果的です。
たとえば、過去の不祥事対応をケースに危機管理広報をシミュレーションする、M&Aの成功・失敗事例を議論するなど、実務に直結した演習を行うことで学びが深まります。
アフターフォローを行う
研修は受講した時点で完結するものではありません。知識を現場で活かし定着させるには、フォローアップが不可欠です。一定期間後に再度確認の機会を設けたり、学んだ内容を実務で試す場を提供することで、学習効果が持続します。
特に役員はフィードバックを得にくい立場にあるため、研修終了後のチェックや振り返りがより重要になります。
継続的にアップデートする仕組みを作る
役員研修は単発で終えるのではなく、制度として継続的に実施することが望ましいです。社会環境や法規制は常に変化しており、人的資本経営、サステナビリティ、AI活用など新たなテーマも次々と登場します。定期的に内容をアップデートし、最新の知識と視点を持ち続けることが企業の競争力強化につながります。
効果的・効率的に役員研修を行いたい担当者様は「取締役・監査役トレーニング」をご検討ください。
eラーニングプラットフォーム「SUKU-SUKU Testing」では、役員研修として利用できるコンテンツ「取締役・監査役トレーニング」をご用意しています。
「取締役・監査役が知っておくべき基礎知識」「人事労務」「情報セキュリティ」「危機管理」の4つのカテゴリーがあり、役員研修でおさえるべき内容を網羅しています。
5~15分の動画と確認問題でスキマ時間で効率的に知識を定着させることができます。
管理用画面から受講状況やテスト結果が簡単に確認でき、グループ会社の役員や社外取締役の受講も簡単に管理ができます。
それぞれのカテゴリー受講後に行う総復習テストでは、結果をレーダーチャートで表示し、スキルを可視化することが可能です。
役員研修にぜひ「取締役・監査役トレーニング」をご活用ください。
▼資料ダウンロード:eラーニングコンテンツ「取締役・監査役トレーニング」