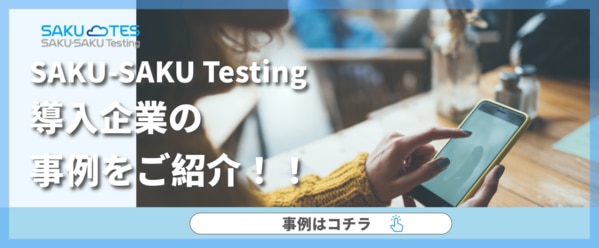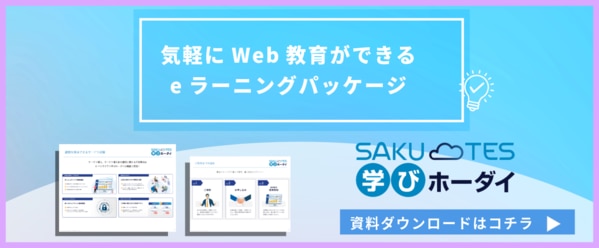ミッショングレード制度(役割等級制度)とは?メリットやデメリット、導入手順を解説

企業における人事制度は、組織の運営や従業員のやる気に大きな影響を与える重要な仕組みです。その中でも近年注目されているのが「ミッショングレード制度(役割等級制度)」です。この制度は、従来の年功序列型の評価方法を見直し、成果や役割を重視した柔軟な評価システムとして多くの企業で導入が進められています。
導入を検討している企業が理解しておくべきポイントや、それによって得られるメリット・注意すべきデメリットを知ることで、より効果的な運用が可能になります。
本記事は、ミッショングレード制度の基本的な概要から、そのメリット・デメリット、導入手順について解説します。
目次[非表示]
- 1.ミッショングレード制度とは
- 1.1.ミッショングレード制度の概要
- 1.2.他の等級制度との違い
- 2.ミッショングレード制度の仕組み
- 3.ミッショングレード制度のメリット
- 3.1.評価基準が合理的になる
- 3.2.社員の主体性が向上する
- 3.3.業務目標に向けた取り組みを促進する
- 4.ミッショングレード制度のデメリット
- 4.1.降格や降給に伴う不満の発生
- 4.2.制度運用が難しい
- 4.3.評価基準のあいまいさに伴う課題
- 5.ミッショングレード制度の導入手順
- 5.1.STEP1:制度の方向性を決める
- 5.2.STEP2:役割定義書の作成
- 5.2.1.営業マネージャー
- 5.2.2.ソフトウェアエンジニア
- 5.2.3.人事担当者
- 5.3.STEP3:社内への周知手続き
- 6.ミッショングレード制度の導入事例
- 7.昇格・昇進試験や受講必須の教育にイー・コミュニケーションズの「サクテスAIMONITOR」がおすすめ
ミッショングレード制度とは

ミッショングレード制とは、従業員の役割や業務を基に評価を行う新しい人事制度の一つです。ここでは、ミッショングレード制度の概要や他の等級制度との違いを解説します。
ミッショングレード制度の概要
ミッショングレード制度は年功や職歴にとらわれず、与えられたミッションに対して達成した成果を重視する点が主要な特徴となっています。ミッショングレード制度では、社員は自身に与えられた役割に基づいて明確な評価を受け、その成果に応じて報酬やキャリアが決定します。また、この仕組みにより従業員が自分の成長を実感しやすくなり、それがスキルや能力の向上に向けたモチベーションの向上にもつながります。さらに、透明性の高い評価基準が採用されるため、社員間で公平性を感じられる職場環境が整備されやすくなる点も魅力です。
他の等級制度との違い
ミッショングレード制度は、従来の職能資格制度や職務等級制度とは異なる評価基準を採用しています。職能資格制度は在籍年数や経験に基づいて評価されることが多く、従業員の成長が企業内の既定の枠組みに左右されやすいのが特徴です。
一方で、職務等級制度は業務内容や職務そのものの評価を重視しますが、実績や成果を正確に評価するには詳細で煩雑な分析が求められる課題があります。これに対し、ミッショングレード制度はジョブ型の働き方を基盤とし、役割(ミッション)を明確に設定したうえで個々の社員の目標達成への取り組みを評価の中心に据えています。この評価方法により、社員は自らのミッションの達成に集中でき、業務パフォーマンスの向上が期待できます。また、役割が明確化されることで、組織としての効率化も促進され、時代に即した柔軟な働き方を実現する基盤となっています。
ミッショングレード制度の仕組み

ミッショングレード制度は、社員が担う役割やその成果に基づいて評価を行い、報酬やキャリアパスを決定します。この評価方法では、役割の責任や業務の難易度、目標達成度が特に重視されます。
ここではミッショングレード制度における給与の決定方法や昇給・降給、昇格・降格の仕組みについて解説します。
給与の決定方法
ミッショングレード制度における給与の決定方法は、役割の重要性や業務の難易度に応じて柔軟かつ適切に設定されます。ミッショングレード制度では、各従業員に対して役割に基づいた明確な期待値が設定され、その期待に応じて給与が決定されます。これにより、役職だけでなく、実際の仕事内容や責任範囲に基づいて公平な報酬が支払われる仕組みを構築しています。また、業務内容や役割に変更が生じた場合には、従業員との話し合いを通じて役割を見直し、必要に応じて給与の調整も行われます。このプロセスは、従業員にとって納得感のある透明性の高い給与体系を実現するとともに、企業全体での公平性を保つ重要な要素となっています。
昇給と降給の仕組み
ミッショングレード制度では、昇給が行われる際には、役割に対する期待値が高まった場合が主な要因となります。従業員は通常、給与改定におけるミッショングレードの見直しが行われることにより、業務上のミッションを成功裏に達成した結果として昇給の機会を得ます。その際には、パフォーマンスの評価も重要な要素となります。従業員の取り組みが明確な成果につながることで、昇給の可能性が高まり、同時にモチベーションの向上にもつながります。このプロセスを通じて、会社としても更なる成長が期待されます。
一方、降給の仕組みについても、役割の重要性が低下した場合や成果が十分でない場合に該当する可能性があります。降給は給与テーブルやミッショングレードの再評価が実施される際に考慮される場合が多く、特に人事異動のタイミングでその判断が行われます。この過程では、従業員に対して十分な理由が説明されることが一般的であり、透明性と公平性を確保する取り組みがなされています。評価基準が明確であるため、組織全体でルールに基づいた実行が可能となる環境が整えられています。
昇格と降格の仕組み
昇格は、従業員が新たな役割を果たすために必要な条件をクリアした際に実施される重要なプロセスです。具体的には、明確な業績向上の実績や新たなスキル・能力の習得が求められ、これにより職場での責任が増すことが一般的です。これは、従業員にとって大きなモチベーションとなり、キャリア発展の機会を提供する要素でもあります。特に、ミッショングレードやジョブ型の雇用制度を採用している企業では、昇格基準が透明化されており、組織全体のパフォーマンスを底上げする要因となっています。
一方で降格は、従業員の業務パフォーマンスが期待される基準に届かない場合や適材適所を考慮する必要がある場合に発生します。この際、従業員の適性や職務能力を再評価し、新たな配置の検討が進められます。適切な配置転換により、従業員自身の能力をより活かせる可能性が広がります。ミッショングレードを基盤とした制度はこれらの昇格・降格の基準を明確に定義しており、ジョブ型雇用との相性も良いため、柔軟で公平な人材運用を実現する仕組みとなっています。
ミッショングレード制度のメリット

ミッショングレード制度には企業や社員にとって多くのメリットがあります。
ここでは、メリットについて解説します。
評価基準が合理的になる
従来の年功序列や経験年数に依存した評価方法に比べ、ミッショングレード制度は客観的な指標をもとに評価を行うため、合理的で一貫性のある評価基準が確立されています。このミッショングレード制度では、社員の成果が具体的に数値や実績として測定されるため、評価の透明性が向上し、従業員にとって納得感のある評価環境が実現します。
さらに、社員が果たした役割の重要性や達成したミッションごとに着目することで、公平性が高い評価が行われます。この仕組みは、評価の過程における曖昧さを排除し、従業員に明確で具体的なフィードバックを提供することを可能にします。ミッショングレード制度を導入することで、組織内のモチベーションを向上させ、パフォーマンスの向上を促進する効果が期待されます。
社員の主体性が向上する
ミッショングレード制度では、各従業員が自らの役割に責任をもつことが期待され、役割に対する意識が自然と高まります。この仕組みは、従業員が自発的な行動を取る促進剤となり、主体性をもつことで業務に対する積極的な姿勢が生まれやすくなります。
特に、ミッショングレードに基づく評価制度を導入することにより、個々の業績が明確に結果へ反映される仕組みが整っているため、社員は自分の努力や成果が正当に認められるという実感を持ちやすくなります。
そのため、社員一人ひとりが自身の成長やスキル向上に対して積極的に取り組む姿勢を強め、学びや能力開発への意欲が促進されます。また、ミッショングレード制度を活用することで、主体性を持つ社員の増加が期待され、個人のパフォーマンスだけでなく、チーム全体の士気や協力体制の向上にも繋がります。このような相乗効果は、最終的に企業全体の生産性向上や業績拡大にも良い影響を及ぼす重要な要素となります。
業務目標に向けた取り組みを促進する
ミッショングレード制度は、業務目標に対して明確な目標設定を可能にする仕組みであり、従業員の行動を具体的に導きます。それぞれの役割に応じた目標が設定され、個々のミッションが明示されることで、社員は自身の役割を認識し、自らのミッション達成に向けた努力をしやすくなります。
さらに、目標が明確であることにより、各社員が何に優先的に取り組むべきかが理解でき、効率的な業務遂行が促進されます。
ミッショングレード制度のデメリット

ミッショングレード制度にはいくつかのデメリットも存在します。
ここでは、デメリットについて解説します。
降格や降給に伴う不満の発生
降格や降給は、従業員にとって非常に敏感な問題であり、これに伴うデメリットは無視できません。
特に、自信をもって取り組んできた業務が十分に評価されていないと感じると、モチベーションが著しく低下する可能性があります。また、給与が減少することで、経済的な負担や生活面での不安が増すこともあります。このような状況は、職場環境に悪影響を与え、チーム全体のパフォーマンス低下を招く要因となり得ます。そして、変化に適応できない従業員が離職を検討することもあり、人材流出が組織の安定性や成長に障害をもたらす可能性があります。降格や降給への対応は、個々の従業員の心情やキャリア形成を考慮しながら進めることが重要です。
制度運用が難しい
ミッショングレード制度の運用には、難しい面が多々あります。まず、役割に基づく正確な評価を行うためには、明確で適切な指標や基準の設定が不可欠です。しかし、これには専門的な知識や経験が必要とされ、多くの場合、企業にとって大きな負担となります。
また、評価の透明性や公平性を保つことは制度の信頼性を確保するために非常に重要ですが、そのためには運用プロセスを定期的かつ慎重に見直す必要があります。このような見直し作業には多くの労力が伴い、さらに評価基準の変更や調整が周知徹底されない場合には、社内での混乱や不満が生じるリスクもあります。結果として、ミッショングレード制度を効果的に運用することは決して簡単ではなく、そのプロセスにおける課題がデメリットとなることが多いのです。
評価基準のあいまいさに伴う課題
評価基準があいまいである場合、従業員は自分がどのように評価されたか理解しにくくなるというデメリットがあります。明確な評価基準が定められていないことで、従業員は自己改善に向けた具体的な方向性を見失い、結果的に目標達成意欲が低下する可能性があります。また、曖昧な基準は人事異動や昇進における不公平感を引き起こし、不満を生む要因になるというさらなるデメリットも存在します。
このような状況が続くと、社員は評価の透明性や一貫性を感じられず、企業全体への信頼感が損なわれる事態に発展することも考えられます。
その結果、従業員の士気低下や離職率の上昇といった深刻な問題につながる可能性があります。これらのデメリットを解消するためには、各役職に合わせた明確で具体的な評価基準を設定し、従業員に対して定期的なフィードバックを行うことが求められます。これにより、企業文化の透明性を高め、社員のモチベーションを維持することが可能となるでしょう。
ミッショングレード制度の導入手順

ミッショングレード制度を導入する際は、緻密な計画と段階的な実施が重要です。
ここでは、導入手順について解説します。
STEP1:制度の方向性を決める
まずは、制度の方向性を決めます。役割を明確化することにより、従業員は自らの職務に対する理解を深め、どのようにパフォーマンスを向上させるべきかを具体的に考えるきっかけとなります。また、ミッショングレード制度を通じて職務の重要性が可視化されることで、組織全体での役割分担がより一層明確になり、生産性や業務効率を高める効果が期待できます。
STEP2:役割定義書の作成
役割定義書は、ミッショングレード制度の基盤として非常に重要な文書です。この書類には、各役職に期待される業務内容や成果目標を具体的かつ明確に記載します。
役割等級数の設定は、役割定義書の中で重要な要素です。各役職に応じた等級を定めることで、それぞれの役割に対する責任や期待が明確になります。特にミッショングレードの考え方を取り入れることで、役割や職務の価値がより具体化され、各従業員に対して明確な目標が示されます。
役割定義書の構成要素は以下の表の通りです。
項目 | 内容 |
職種・職位名 | 例:営業マネージャー、開発リーダーなど |
所属部門 | 所属チームや部署の名称 |
ミッション(存在意義) | このポジションが組織において担うべき目的 |
主要業務(職務内容) | 日常的・定常的に行う業務の詳細 |
成果責任(KPI・KGI) | 期待される成果や目標指標(売上、品質、納期など) |
意思決定権限 | どの範囲の判断・決裁を任されているか |
求められるスキル・行動特性 | 技術的スキル、リーダーシップ、課題解決力など |
グレード要件 | 該当する等級に必要な条件や期待水準 |
役割定義書の職種別のサンプルをご紹介します。
営業マネージャー
項目 | 内容 |
職種・職位名 | 営業マネージャー(Bグレード) |
所属部門 | 営業第1課 |
ミッション | 顧客課題を解決する提案営業を通じて、持続的な売上成長を実現する |
主要業務 | チームメンバーの営業活動支援と指導- 商談戦略の立案- 売上・利益の進捗管理 |
成果責任 | 月間売上1,000万円以上- 商談数15件以上/月- メンバーの成約率改善 |
意思決定範囲 | 案件の優先度設定、提案内容の最終確認 |
必須スキル | 法人営業経験5年以上- マネジメント経験1年以上 |
等級要件 | Bグレード:リーダーシップ・戦略立案能力必須 |
ソフトウェアエンジニア
項目 | 内容 |
職種・職位名 | ソフトウェアエンジニア(Cグレード) |
所属部門 | プロダクト開発部 |
ミッション | 顧客価値の高いシステムを安定的・迅速に開発・提供する |
主要業務 | Webアプリの設計・実装- コードレビュー- 障害対応とパフォーマンス改善 |
成果責任 | 月次開発完了率90%以上- 障害件数月1件未満 |
意思決定範囲 | 実装方式の選定、技術的アーキテクチャの提案 |
必須スキル | React/Node.jsなどの経験- Git運用経験 |
等級要件 | Cグレード:実装・設計の主担当経験あり |
人事担当者
項目 | 内容 |
職種・職位名 | 人事ビジネスパートナー(HRBP) |
所属部門 | 人事部門/事業部門 |
ミッション | 担当部門の組織成長と人材活用を人事戦略で支援する |
主要業務 | 組織課題の特定と人事施策立案- 評価運用・タレントマネジメント支援 |
成果責任 | 離職率改善(前年比-5%)- 年間施策実施率100% |
意思決定範囲 | 担当組織内の配置案、評価運用方式 |
必須スキル | 人事経験3年以上- 組織コンサルの素養 |
等級要件 | B~Cグレード:施策立案と推進力をもつこと |
STEP3:社内への周知手続き
ミッショングレード制度の導入に際して、社内への周知手続きは極めて重要です。周知が適切に行われることで、従業員の理解や支持を高め、スムーズな導入と制度の定着が期待できます。
まず、ミッショングレード制度の目的、意義、そして導入による具体的なメリットを従業員に明確に伝えることが必要です。そのために、視覚的にわかりやすい資料の準備や、制度の概要を簡潔に説明するツールの活用が効果的です。また、説明会やワークショップを開催し、従業員が質問や意見を直接共有できる場を設けることも欠かせません。これにより、制度に対する納得感と理解が深まります。
さらに、現場のフィードバックを制度運用に反映させることが、従業員との信頼関係を強化するポイントとなります。例えば、匿名で意見を集める仕組みを導入したり、各チームや部門ごとにディスカッションの場を定期的に設けることが有益です。従業員が自分の意見や疑問を自由に発信できる環境を整えることで、ミッショングレード制度に対する関与意識を高められます。
また、制度導入後も継続的なフォローと情報共有を行うことが重要です。例えば、定期的にプロセスや成果を振り返るレポートを作成し、社内ネットワークやミーティングで広く共有することで、従業員の関心を維持できます。さらに、ミッショングレード制度の実施によって達成された成功事例を紹介することで、従業員のモチベーション向上や制度へのさらなる理解促進にもつながるでしょう。このように、全社的な取り組みを通じて、ミッショングレード制度が組織文化に根付いていく基盤を築くことが可能です。
ミッショングレード制度の導入事例

多くの企業がミッショングレード制度を導入し、その成果を実感しています。
ここでは、導入している企業の事例をご紹介します。
ソフトバンク株式会社
2005年に新人事制度の一環として導入。年齢や在籍年数によらず、社員の志と実力で登用することで、優秀な人材獲得に成功。
株式会社日立製作所
グローバル化に伴い、全世界共通のミッショングレード制を採用。職務の役割や職責を全世界統一的に評価することで、給与テーブルに多様性が生まれ、業務に柔軟に対応できるようになった。
ソニー株式会社
事業のグローバル化に伴い、世界基準でミッショングレード制を採用。役割をインディビジュアルコントリビューター等級群とマネジメント等級群に分け、シームレスに行き来できる体系。
株式会社ココナラ
社員の主体性と助け合いの文化を重視し、ミッショングレード制を導入。4つのグレードに分け、マネジメントかスペシャリストの道を選べる仕組み。
株式会社クボタ
職種ごとに3つのコースを設定し、コースごとに等級を規定。業績貢献度に応じて進級し、能力や意欲に基づいたコース変更も可能。「適材適所」「機会均等」を実現しています。
カゴメ株式会社
従来の「年功型」から「職務型」の役割等級制度への移行を進行中。各ポジションごとのミッション・アカウンタビリティと処遇の関係性の可視化や、社員の納得感の醸成とモチベーションの向上を目指しています。
昇格・昇進試験や受講必須の教育にイー・コミュニケーションズの「サクテスAIMONITOR」がおすすめ
社内の昇給・昇格試験や必ず受けなければいけない教育の実施等にイー・コミュニケーションズの「サクテスAIMONITOR」がおすすめです。
「サクテスAIMONITOR」はeラーニングやテスト実施時の不正を抑止・防止する不正検知システムです。
受ける前の本人認証や受講時(試験時)の不正をリアルタイムで検知し、受講コンテンツの停止など、制御を行います。
受講端末のカメラで監視し、「受講者が動画を見ずに離席している」「受講者が入れ替わっている」「受講者以外も受講している」「受講者が寝ている」「関係ない他のアプリケーションを開いている」などの挙動を検知し、アラートを出したりコンテンツを停止するなど、不正を検知するAI×クラウドサービスです。
興味がおありの場合は、お気軽にお問い合わせください。