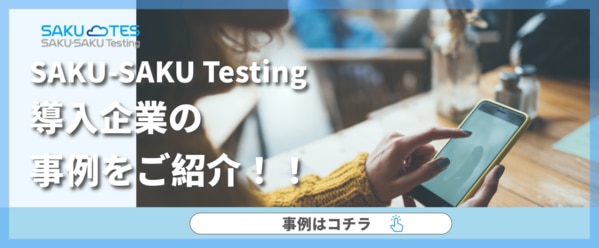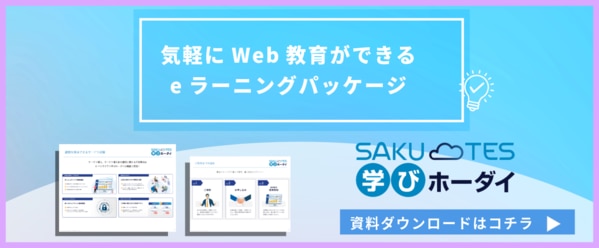人間関係構築力が求められるワケとは?社会人に必要な理由と向上のコツ

社会人において人間関係構築力とは、円滑な職場のコミュニケーションや信頼関係を築き、仕事の効率やチームの生産性を高める重要なスキルです。人間関係構築力があることで、さまざまな価値観や考え方をもつ人々が集まる現代の職場環境で、他者と良好な関係を保ちながら協力し合うことが可能になります。
この記事では人間関係構築力が必要な理由や向上のコツを解説します。
目次[非表示]
- 1.人間関係構築力とは
- 1.1.人間関係構築力の意味
- 1.2.人間関係構築力の主な要素
- 2.職場で人間関係構築力が重要視される理由
- 3.仕事における人間関係構築力を磨くメリット
- 3.1.コミュニケーションの観点
- 3.2.チームワークの観点
- 3.3.生産性の観点
- 3.4.モチベーションの観点
- 3.5.リーダーシップの観点
- 3.6.顧客対応の観点
- 3.7.キャリア形成の観点
- 4.人間関係構築力が不足している職場で起こりがちな課題
- 4.1.コミュニケーション面の停滞
- 4.2.チームワークの弱体化
- 4.3.生産性の低下
- 4.4.モチベーションとエンゲージメントの低下
- 4.5.リーダーシップとマネジメントの難航
- 4.6.顧客・取引先への影響
- 4.7.組織コストの増大
- 5.人間関係構築力が高い人・不足している人の特徴
- 5.1.人間関係構築力が高い人の特徴
- 5.2.人間関係構築が不足している人の特徴
- 6.人間関係構築力を高める方法
- 6.1.人間関係構築力を高めるステップ
- 6.1.1.ステップ①自分を知る ― コミュニケーションの癖を可視化する
- 6.1.2.ステップ②相手の視点を尊重する ― 傾聴と興味を持った関わり
- 6.1.3.ステップ③感情を整える ― 冷静さを保ち信頼を積み上げる
- 6.1.4.実践ステップ(チェックリスト)
- 6.2.コミュニケーション技術とテクニック
- 6.3.職場で使える具体例
- 6.3.1.アイスブレイクの導入
- 6.3.2.キャリブレーションで気配り
- 6.4.研修やセミナーの参加
- 7.まとめ
- 8.社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ
人間関係構築力とは

人間関係構築力とは、職場や日常生活の中で他者と良好な関係を築き、信頼を育むための能力のことを指します。
意味や要素を詳しく見ていきましょう。
人間関係構築力の意味
人間関係構築力とは、他者との信頼関係や良好なコミュニケーションの基盤をつくり上げる力を指します。その意味は、単なる言葉のやり取りだけではなく、相手の立場や気持ちを深く理解し、相互に納得し合える関係性を創出することにあります。人間関係構築力の本質は、お互いを尊重する姿勢にあり、こうした態度が真の信頼関係を生み出します。また、人間関係構築力は困難な状況でも周囲と協力し合い、柔軟に対応できる力も含んでいます。さらに、人間関係構築力とはEQ(心の知能指数)と深い関係があり、感情のコントロールや他者理解のスキルもその一部です。このように、人間関係構築力の意味は、単なるコミュニケーション能力にとどまらず、感情や信頼、相手への思いやりをもち、豊かな人間性を発揮することまで含まれると言えるでしょう。
人間関係構築力の主な要素
人間関係構築力は、さまざまな要素やスキルによって支えられています。特に重要となる要素は、質問力、傾聴力、共感力、平等性、実行力の5つです。
質問力 | 相手の考えや背景、状況を深く探る | 適切な質問を用いることで円滑なコミュニケーションが可能 |
傾聴力 | 相手の話にしっかり耳を傾け言葉や気持ちを受け止める | 相手との信頼関係を築く |
共感力 | 相手の立場に自分を置き換えて理解し、気持ちに寄り添う | 人間関係を深める |
平等性 | ・相手の立場や状況に左右されず公平に接する | 継続的な信頼関係を築く |
実行力 | 約束を守り、言動に責任をもって行動する | 相手からの信頼を得る |
これらの要素とスキルをバランスよく身につけることで、良好な人間関係を築く基盤となります。
職場で人間関係構築力が重要視される理由
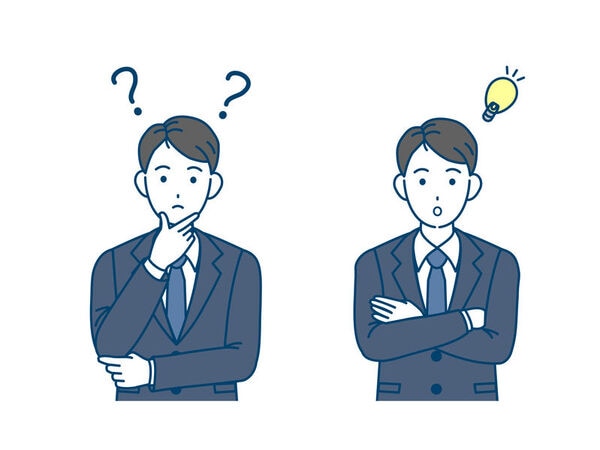
職場内でも商談先でも、成果を左右するのは結局「人と人とのつながり」。ここでは、人間関係構築力が重要視される理由を3つの観点でまとめました。
① 社内の空気を良くし、仕事を回しやすくする
信頼がベースにあるチームでは、相談や情報共有が滞りません。問題が起きても「言いづらいから先送り」がなくなり、素早く協力体制を敷けます。役職や部署が違っても“壁”が低ければ、進行中のプロジェクトが滑らかに動き、余計なロスタイムを減らせます。
② 組織全体のアウトプットを底上げする
互いを理解し合う関係性が築けていると、アイデアの提案や改善提案が活発化。小さな工夫が連鎖し、業務フローは常にアップデートされ続けます。その結果、個々の能力の総和以上の成果が生まれ、生産性の高い組織へと進化していきます。
③ 顧客・取引先と長期的なパートナーシップを結ぶ
クライアントの課題やニーズを的確に捉え、タイムリーに応えるためには、土台にある「信頼される関係」が大切です。対話を重ねて相手の視点に立つことで、要望を先回りした提案が可能になり、トラブル対応でも安心感を提供できます。こうして築いた信頼は、新規案件の紹介や継続発注という形で返ってきます。
仕事における人間関係構築力を磨くメリット

仕事において人間関係構築力を磨くことには大きなメリットがあります。
ここでは、7つの観点からメリットについてご紹介します。
コミュニケーションの観点
人間関係構築力が高い職場では、対面・チャット・ドキュメントなど複数チャネルでの情報共有が滞りません。伝達ミスや思い込みによる手戻りが減るため、再作業コストを大幅に削減できます。結果として「言った・言わない」の不毛な議論が消え、議論は本質的な課題解決に集中します。
チームワークの観点
相互理解と信頼があるチームは、業務分担やフォローアップが自然に行われます。メンバー同士で負荷を調整しやすく、締切遅延や属人化リスクを回避できます。そのため、休暇取得や急な欠員が出てもプロジェクト全体のスケジュールが崩れにくくなります。
生産性の観点
良好な関係性があると、改善提案やアイデア出しが活発化し、業務フローが継続的にアップデートされます。小さな工夫の連鎖が組織全体のアウトプット量と質を底上げし、「現状維持」の空気が一掃されます。
モチベーションの観点
心理的安全性が高い環境では、挑戦や学習が促されます。失敗を共有して学ぶ文化が根付くため、メンバーは新しいスキルに積極的に手を伸ばし、キャリアの伸びしろを自ら広げていきます。
リーダーシップの観点
相互信頼を土台にした関係性があると、リーダーはビジョンや目標をスムーズに浸透させられます。巻き込み力が高まり、変革プロジェクトの推進スピードも加速。メンバー側も安心して意見を発し、主体的に動くようになります。
顧客対応の観点
クライアントと深い信頼関係を築けるため、相手の課題やニーズを先読みした提案が可能になります。トラブル時にも迅速かつ誠実に対応でき、顧客満足度が向上。結果として案件継続率や新規紹介が伸び、売上の安定化に寄与します。
キャリア形成の観点
社内外のネットワークが広がり、評価や機会につながります。異動・プロジェクトアサイン・転職時の推薦など、キャリア選択肢が増えるだけでなく、専門領域を超えた知見も得やすくなります。
表でまとめると下記のとおりです。
観点 | 得られるメリット | 具体的な効果例 |
コミュニケーション | 情報共有がスムーズになり、誤解・手戻りが減少 | 口頭だけでなくチャットやドキュメントでの確認が増え、伝達ミスによる再作業コストを削減 |
チームワーク | 協力体制が強化され、業務分担・フォローが円滑に | メンバー間で負荷調整がしやすく、締切遅延や属人化リスクを回避 |
生産性 | 改善提案が活発化し、プロセスが継続的にアップデート | 定期的な振り返りで業務フローが最適化され、アウトプット量と質の両方が向上 |
モチベーション | 職場の心理的安全性が高まり、挑戦や学習が促進 | 「失敗を共有して学ぶ」文化が根付き、新しいスキル習得への意欲が高まる |
リーダーシップ | 相互信頼が土台となり、リーダーの発信力・巻き込み力が向上 | ビジョン・目標が浸透しやすく、変革プロジェクトの推進が加速 |
顧客対応 | クライアントとの信頼関係が深まり、案件継続率が上昇 | ニーズを先読みした提案や迅速なトラブル対応で顧客満足度が向上 |
キャリア形成 | 社内外ネットワークが拡大し、機会や評価につながる | 異動やプロジェクトアサイン、転職時の推薦など、キャリア選択肢が広がる |
人間関係構築力を高めることは、企業の価値向上や競争力の強化といった仕事全体へのメリットにもつながります。
人間関係構築力が不足している職場で起こりがちな課題

人間関係構築力が不足している職場ではさまざまな課題が生じます。
ここでは、どのような課題が生じるかについて解説します。
コミュニケーション面の停滞
- 情報共有の遅延・欠落
重要な連絡が届かず、認識齟齬や手戻りが頻発。
- 「言いづらさ」による問題先送り
ミスや懸念が隠蔽され、発覚した時には損失が拡大しやすい。
チームワークの弱体化
- 協力体制が組めない
個人作業へと閉じこもり、業務負荷が偏る。 - 属人化リスクの増大
ノウハウが共有されず、欠員が出るとプロジェクトがストップ。
生産性の低下
- 改善提案が出にくい
意見を言うハードルが高く、非効率なプロセスが放置される。 - 余計な確認・やり直し
誤解と再作業で、実作業時間が圧迫される。
モチベーションとエンゲージメントの低下
- 心理的安全性の欠如
失敗を恐れる空気が蔓延し、挑戦や学習が止まる。 - 職場ストレスの増大
疎外感や孤立感が離職意向を高める。
リーダーシップとマネジメントの難航
- 方針浸透の停滞
信頼が薄いと目標が腹落ちせず、実行力が伴わない。 - 人材育成の機会損失
メンバーは相談しづらく、成長スピードが遅くなる。
顧客・取引先への影響
- 対応スピードの鈍化
社内連携が取れず、返答やトラブル解決が遅れる。 - 信頼低下による機会損失
顧客満足度が下がり、リピートや紹介が望めなくなる。
組織コストの増大
- 離職率上昇による採用・育成コスト
退職が連鎖し、新人教育に時間と費用がかさむ。 - レピュテーションリスク
「働きにくい職場」の評判が採用難を招く。
人間関係構築力が不足すると、コミュニケーションの断絶から生産性・モチベーションの低下、さらには顧客満足度や企業ブランドの毀損にまで波及します。逆に言えば、この力を高めるだけで多面的な課題の予防・解決が期待できます。
人間関係構築力が高い人・不足している人の特徴

人間関係構築力が高い人・不足している人にはそれぞれ特徴があります。
ここでは、特徴について解説します。
人間関係構築力が高い人の特徴
人間関係づくりが得意な人は、まず相手視点でのコミュニケーションを欠かしません。難しい言葉をかみ砕き、相手の背景や立場に合わせて言葉を選ぶため、誤解が生まれにくいのが特徴です。さらに傾聴姿勢が徹底しており、話の内容だけでなく感情面にもアンテナを張り、うなずきや要約で「理解している」サインを送り続けます。
相手の考えや価値観に共感を示すことにも長けており、違いを尊重しながら自分の意見を提案できるため、対話が対立ではなく協働に向かいやすくなります。フィードバックを伝える際は、先に相手の良い点を認めたうえで具体的な改善策を提示し、「次に何をすればいいか」が明確です。
また、職位や部署の枠を越えてネットワークを自発的に広げるので、情報や協力を得やすい環境を自然に作ります。約束と期限を守り、進捗を細やかに共有するため「この人に任せれば安心」という信頼が蓄積。衝突が起きても感情と事実を切り分けて冷静に合意点を探すため、トラブルが長期化しにくいのも大きな強みです。
自己認識にも優れ、他者からの指摘を成長の材料として受け止め、行動を調整します。その結果、周囲に心理的安全性を提供し、メンバーが安心してアイデアや失敗を共有できる空気を生み出します。人との縁を“点”ではなく“線”で捉え、節目ごとに小さなフォローを重ねて関係を長期的に育てる点も見逃せません。
人間関係構築が不足している人の特徴
一方で、人間関係づくりが苦手な人は自己中心的な伝え方になりがちです。聞き返しや確認を怠り、一方通行で情報を投げるため認識違いが頻発します。話を途中で遮ったり急いで結論づけたりすることが多く、相手は「聞いてもらえていない」と感じやすくなります。
他者の価値観に対しては「それは違う」と否定から入るケースが多く、共感よりも評価が先に立つため心理的距離が広がります。フィードバックも抽象的な批判や感情的な言葉に偏り、相手が防衛的になり行動変容が起こりづらいのが実情です。
ネットワーキングにも消極的で、必要最低限の人としか関わらないため情報や協力を得にくくなります。さらに、報告・連絡・相談が遅れ、期限や約束を軽視する傾向があると、周囲はフォローに追われ信頼貯金が目減りします。
対立が起きた際には感情をコントロールできず、問題を個人攻撃として捉えがちです。自分へのフィードバックにも耳を塞ぎ、防衛的に振る舞うことで成長機会を逃します。ミスに対して厳しく批判するため、周囲は萎縮して沈黙し、心理的安全性が低下。結果として関係は短期的・表面的になり、用事があるときだけ連絡する“利害関係”で終わりやすくなります。
それぞれの特徴を表にまとめると以下のとおりです。
観点 | 人間関係構築力が | 人間関係構築力が |
コミュニケーション | 相手の立場に合わせて言葉を選び、要点を分かりやすく伝える。オープンクエスチョンを多用し、双方向の対話を促す。 | 自分本位の話し方が多く、情報が一方通行。聞き返しや確認を怠り、誤解を招きやすい。 |
傾聴姿勢 | 相手の話を遮らずに最後まで聴き、内容・感情の両面をくみ取る。うなずきや要約で理解を示す。 | 表面だけ聞いて結論を急ぐ。相手の感情を軽視し「聞いていない」と受け取られやすい。 |
共感・理解 | 違う価値観を尊重し、「なるほど、そう考えるのですね」と共感を示す。 | 自分の価値観を基準に評価しがち。「それは違う」と否定から入るため距離が生まれる。 |
フィードバック | ポジティブな点を先に伝えてから改善点を伝える。具体的で行動可能な提案を添える。 | 感情的・抽象的な指摘が多く、相手に萎縮や防衛反応を生じさせる。 |
ネットワーキング | 立場や部署を越えて自発的に交流を広げ、紹介・連携を促進する。 | 必要最低限の人としか関わらず、情報や協力を得にくい。 |
信頼構築 | 約束を守り、進捗をこまめに報告するため「任せても安心」と感じてもらえる。 | 期限を守らない/報告がないため、周囲がフォローに追われる。 |
対立・摩擦への対応 | 事実と感情を切り分け、双方の落としどころを探る。 | 感情的になりやすく、問題を個人攻撃と捉えがち。 |
自己認識 | 自分の強み・弱みを理解し、状況に応じて行動を調整できる。 | フィードバックを受けても自己防衛的になり、成長機会を逃す。 |
心理的安全性の提供 | ミスを責めずに学びへ結びつけるため、周囲が意見を出しやすい。 | 失敗を過度に批判し、周囲が沈黙・保身に走る文化を生む。 |
継続的な関係維持 | 相手の変化や節目(異動・誕生日など)を気に掛け、小さなフォローを続ける。 | 用事があるときだけ連絡し、関係が途切れやすい。 |
両者の違いを意識し、少しずつ「聴く・共感する・確実にフォローする」習慣を身につけることが、人間関係構築力を高める近道です。
人間関係構築力を高める方法
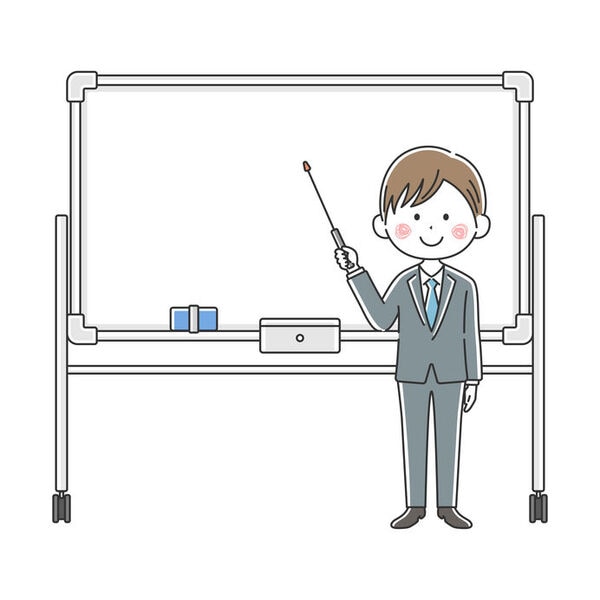
人間関係を築く力は、意識的なトレーニングで着実に伸ばせます。まずステップを整理し、職場で使える具体的なコミュニケーション技術の紹介や研修の利用について等解説します。
人間関係構築力を高めるステップ
「自分を知る → 相手を尊重する → 感情を整える」 という流れで人間関係構築力を高める方法を解説します。
ステップ①自分を知る ― コミュニケーションの癖を可視化する
- 自己診断
日々の会話を振り返り、「話しすぎていないか」「相手の反応を拾えているか」をチェック。 - 改善ポイントの特定
例:説明が長い → 要点を先に述べる/反論が多い → 共感フレーズを先に置く。
ステップ②相手の視点を尊重する ― 傾聴と興味を持った関わり
- 目標を明確に
「プロジェクトを円滑に進めるために相手を理解する」など、対話の目的を先に自覚する。
- 傾聴力の強化
オープンクエスチョンで深掘りし、相手の言葉を要約して返す(バックトラッキング)。
ステップ③感情を整える ― 冷静さを保ち信頼を積み上げる
- 感情のコントロール
深呼吸や一時停止をルーチン化し、反射的な言動を減らす。 - 約束を守る
小さな締切でも厳守し、進捗をこまめに共有することで信頼残高を積み上げる。
実践ステップ(チェックリスト)
- 相手に興味を持つ
仕事以外の話題も交えてアイスブレイク。 - 傾聴する
うなずき・相づち・要約で「理解のサイン」を示す。 - 感情を整える
苛立ちを感じたら 6 秒ルール(6 秒黙る)を適用。 - 約束を守る
期限前にリマインドを自分へセット、完了後は即共有。
コミュニケーション技術とテクニック
コミュニケーションにはさまざまなテクニックがあります。以下に表でまとめました。
テクニック | 概要 | 効果 |
ミラーリング | 相手の仕草・姿勢・言葉選びをさりげなく合わせる | 親近感・安心感を生む |
ペーシング | 話す速度や声のトーンを相手に合わせる | 自然で心地よい会話リズムになる |
バックトラッキング | 相手のキーワードを繰り返し要約 | 「わかってもらえた」の感覚を与える |
キャリブレーション | 相手の微妙な表情・声色を観察し変化を察知 | 適切なタイミングで声かけ・フォローができる |
職場で使える具体例
人間関係構築力を高めるために職場で使える具体例をご紹介します。
アイスブレイクの導入
- 自己紹介ゲーム
新メンバーが加わった日に「好きな映画ベスト3」を共有。 - GOOD & NEW
朝会で「最近良かったこと」と「新しい発見」を30 秒ずつシェア。
キャリブレーションで気配り
- 進捗報告の際、相手の声が沈んでいたら
→「何か壁になっていることがあれば一緒に考えましょう」と提案。
研修やセミナーの参加
人間関係構築力を高めるうえで、研修やセミナーの活用は非常に有効です。これらの研修やセミナーでは、コミュニケーションスキルや信頼関係づくりのための具体的な方法について、体系的かつ実践的に学ぶことができます。
特に、職場で起こりうる実際のシチュエーションを題材にしたケーススタディや、参加者同士のロールプレイを通じて、自分の課題や強みを客観的に把握しやすくなるのが特徴です。また、セミナーや研修での意見交換やフィードバックを受けることで、自身の課題を多角的視点で知ることができ、コミュニケーションスタイルの改善へと繋げることが可能です。このように、研修やセミナーは人間関係構築力を磨くためのアプローチとして、多くの企業で活用されています。
研修で学べるスキルと期待できる効果について表にまとめます。
研修で学べる主なスキル | 具体的なポイント/期待できる効果 |
傾聴力 | 相手の言葉・感情を汲み取る聞き方を体得。対話練習で「うなずき・要約・質問」を繰り返し実践し、信頼感を高める。 |
質問力 | オープンクエスチョン/クローズドクエスチョンの使い分けを学び、相手の本音やニーズを引き出す。 |
共感力 | 「受容→共感→提案」のステップで相手の価値観を尊重しながら関係を深める方法を習得。 |
ラポール形成テクニック | 心理学的手法(ミラーリング・ペーシングなど)で短時間でも安心感を醸成し、協力関係を築く。 |
ストレスマネジメント | 呼吸法・リフレーミングなどで自分の感情を整え、対人トラブルを未然に防止。 |
感情コントロール | 怒りや不安を客観視して言動を選択するトレーニングを行い、冷静なコミュニケーションを実現。 |
実践的ロールプレイ | 実際のビジネスシーンを想定した対話を反復し、身につけたスキルを「使えるレベル」へ昇華。 |
適用範囲 | 職場のチーム運営・顧客対応はもちろん、家庭や友人関係など私生活でも活用可能。 |
まとめ
人間関係構築力は、職場や社会生活において円滑なコミュニケーションを可能にし、信頼関係を育むために欠かせないスキルです。質問力や傾聴力、共感力などの要素が組み合わさり、これらをバランスよく磨くことで良好な関係を築けます。
逆にこの力が不足すると、コミュニケーション不足や誤解が生じ、仕事の効率が落ちるリスクが高まります。
日々の対話の中で意識的にスキルを磨き続けることで確実に向上します。
人間関係構築力の向上は、個人の働きやすさだけでなく、職場全体の環境改善や企業の成長にも大きく貢献します。
社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ
社員教育にイー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、人間関係構築力を育成するための教育プラットフォームとして活用することが可能です。
また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
ご興味がおありの場合はお気軽にお問い合わせください。