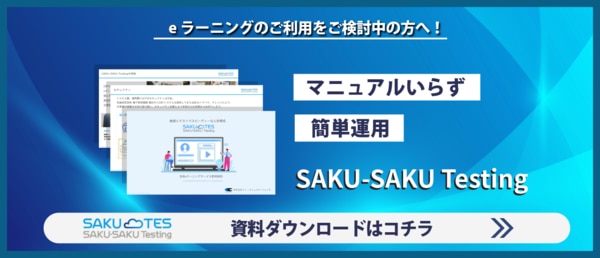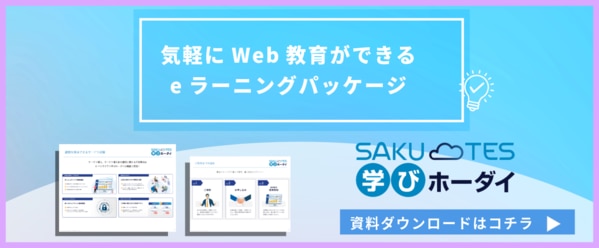DESC法とは?アサーティブコミュニケーションを実践するための活用例を解説

DESC法とは、アサーティブなコミュニケーションを実践するための具体的で効果的な手法です。「Describe(描写する)」「Express(表現する)」「Suggest(提案する)」「Consequences(結果や結論をまとめる)」という4つのステップで構成されています。
DESC法を活用することで、相手との意見交換が円滑になり、誤解を減らしながら双方の理解を深めることができます。
本記事では、DESC法とは何か、また具体的な活用例について解説します。
目次[非表示]
- 1.DESC法とは何か?
- 1.1.DESC法の意味と目的
- 1.2.アサーティブコミュニケーションとの関係
- 1.2.1.アサーティブとは
- 1.2.2.アサーティブコミュニケーションとは
- 2.DESC法の4つのステップと構造
- 2.1.Step 1: Describe(描写する)
- 2.2.Step 2: Express(表現する)
- 2.3.Step 3: Suggest(提案する)
- 2.4.Step 4:Consequences(結果や結論をまとめる)
- 3.DESC法を活用するメリットとその効果
- 3.1.コミュニケーションがスムーズになる
- 3.2.信頼関係を築くことができる
- 3.3.効果的な提案力の向上
- 4.DESC法のデメリットと注意点
- 4.1.適用を誤ると逆効果になる可能性
- 4.2.相手の視点を理解する重要性
- 5.アサーティブコミュニケーションと事例
- 5.1.職場での具体的な活用例
- 5.2.面接や交渉での活用方法
- 6.DESC法とその他の方法との違い
- 6.1.結論を重視するPREP法
- 6.1.1.1. Point(結論・主張)
- 6.1.2.2. Reason(理由・根拠)
- 6.1.3.3. Example(具体例)
- 6.1.4.4. Point(結論の再提示)
- 6.2.聞き手にストレスを感じさせないSDS法
- 6.2.1.S(Simplicity:簡潔さ)
- 6.2.2.D(Directness:直接性)
- 6.2.3.S(Sensitivity:配慮)
- 6.3.それぞれの使い分けのポイント
- 7.まとめと次のステップ
- 7.1.実践するための心得
- 7.2.日常に活用するためのヒント
- 8.社員教育に「SAKU-SAKU Testing」がおすすめ
DESC法とは何か?

DESC(デスク)法とは、人とのコミュニケーションを円滑に進めるため、自分の意見や感情を効果的に伝える手法です。DESC法は、相手を不快にさせず、建設的な対話を促進しながら自らの考えを納得させる力をもつことを目的としています。
ここでは、DESC法の意味や目的について解説します。
DESC法の意味と目的
DESC法とは、「Describe(描写する)」「Express(表現する)」「Suggest(提案する)」「Consequences(結果や結論をまとめる)」の各ステップの頭文字を取ったコミュニケーション手法です。
この手法を用いることで、自分の気持ちや意図を相手に正確かつ効果的に伝えることが可能です。
DESC法は、単なる一方的な意見の押し付けではなく、相手との相互理解を図り、納得を促すプロセスに重きをおいています。特にビジネスの現場では、意見の食い違いや誤解を減らし、建設的な話し合いを行う上で重要な役割を果たします。
この方法は発信者の意図や感情をわかりやすく整理しつつ、相手の反応や立場を尊重する、双方向的でバランスの取れたコミュニケーションスタイルを実現することを目指しています。結果として、関係性の改善や円滑な意思疎通を促進する効果が期待できます。
アサーティブコミュニケーションとの関係
DESC法は、アサーティブコミュニケーションを実践するための具体的な手段の一つです。
アサーティブとは
アサーティブ(Assertive)とは、自分の意見や感情を適切に主張しながらも、相手の考えや感情を尊重し、調和の取れた対話を行う姿勢を指します。
反対に、自分ばかりの主張を押し通す「アグレッシブ(Aggressive)」や、逆に自分の意見を抑え込みすぎる「ノンアサーティブ(Passive)」は、いずれも長期的な人間関係を損ねやすく、問題解決を難しくします。
アサーティブコミュニケーションとは
アサーティブコミュニケーションとは、相手の立場や感情を尊重しながら、自分の意見や気持ちをきちんと伝えるコミュニケーションの取り方です。健全で円滑な人間関係を築くうえで非常に重要です。
DESC法を活用することで、自分の考えをクリアに伝えながらも、相手の立場や感情に配慮したアプローチが可能になります。その結果、相手に受け入れられやすい形で意思を示し、対話の中で双方の信頼関係を深めることができます。このようなアサーティブなコミュニケーション手法は、職場のチームワークや人間関係の向上において大きな効果を発揮します。また、お互いの意見を尊重し合うことで、より建設的で前向きな関係を築く基盤が形成されます。
DESC法の4つのステップと構造

DESC法とは、コミュニケーションを効果的に行うための4つのステップから成り立つ手法です。これらのステップは、関与者全員が理解しやすく、納得できる内容を提供することを目的として設計されています。
ここでは、4つのSTEPを具体的に見ていきます。
Step 1: Describe(描写する)
最初のステップは、Describe(描写する)です。この段階では、相手の行動や状況について、事実に基づいて客観的に伝えることが重要です。
主観的な意見や感情を交えず、単なる事実を示すことで、相手に誤解を与えません。
例えば、具体的な事例を挙げることで、双方がイメージを共有しやすくなります。言葉選びに注意を払い、感情的な表現を避けつつ、冷静に現状を伝える姿勢が求められます。この「描写する」というプロセスは、DESC法とは切り離せない基本的な要素であり、初期段階での信頼や理解を構築するために欠かせません。
このステップが正確に実施されることで、その後の段階に円滑に進むための土台がしっかりと整います。
Step 2: Express(表現する)
次に、Express(表現する)ステップがあります。Express(表現する)では、DESC法とは何かを活用しながら、描写した事実について自分の思いを伝えることが重要です。
このステップにおいて、感情や意見を率直に述べることを重視しますが、相手に無理な圧力を感じさせない形で伝えることが求められます。特に、冷静なトーンを保ちつつ、自分の感情を適切に言語化することで、相手が状況を理解しやすくすることがポイントです。また、相手がどのように受け取るかを常に意識し、自身の態度や言葉遣いに配慮することで、対話がスムーズに進む可能性が高まります。
Step 3: Suggest(提案する)
Step3では、 Suggest(提案する)という段階に進みます。このステップでは、問題解決に向けて、具体的な提案を行うことを目的としています。
提案は、相手が受け入れやすい形で柔軟に示す必要があります。例えば、一方的に結論を押しつけるのではなく、選択肢を提示する方法を取り入れると、相手の意見や感情を尊重しつつ、建設的な話し合いにつなげることができます。
さらに、提案内容を取り入れることで生じる利点や可能性についても触れると、相手がより前向きに考えやすくなるでしょう。このように、相手にも能動的な対応を促せる環境を整えることが、問題解決の成功に一歩近づく鍵となります。
Step 4:Consequences(結果や結論をまとめる)
最後のステップ、Consequences(結果や結論をまとめる)では、相手が提案を受け入れるかどうかを念頭に置いて意思決定を促します。提案の結果や選択肢の可能性についても説明することが求められ、相手が自分で判断できるように道筋を示します。このステップは、相手が選択した結果に対する配慮をもった説明が重要です。相手が提案に対して反応を示すことで、コミュニケーションがさらに深まります。最終的に、このステップが相手との関係を強化する基盤となるのです。
DESC法を活用するメリットとその効果

DESC法を活用することで、さまざまなメリットを得ることができます。特に、コミュニケーションがスムーズになる点が大きな特徴です。相手に伝えたい内容を明確に表現し、効率的に話し合いを進められることで、意見の食い違いや誤解を最小限に抑えることが可能です。その結果、言葉のやり取りが円滑になり、作業やプロジェクトの進捗がよりスピーディーになるというメリットがあります。また、双方の理解を深めるための明確な情報伝達にもつながり、コミュニケーションの質全体を向上させます。このように、DESC法を採用することで、個人やチームの協力がより効果的になり、最終的な成果へと結びつく点が大きな魅力です。
コミュニケーションがスムーズになる
DESC法を活用することで、多くのメリットが得られ、特にコミュニケーションが大幅にスムーズになります。まず事実を客観的に描写することから始め、その後、自分の感情や意見を明確に伝えるステップに進むことで、相手にとっても内容が理解しやすくなり、無用な混乱を避けることができます。この手法は、相手との誤解を減らし、意見交換をより建設的に行う土台を提供します。
さらに、提案や適切な反応を引き出す状況を作り出すことで、双方向の会話が一層活性化されます。こうしたプロセスを通じて、コミュニケーションの質が飛躍的に向上するため、DESC法は効果的な方法として多くのメリットを提供します。
信頼関係を築くことができる
正確な情報のやりとりは、信頼関係を築く上で極めて重要です。DESC法を実践することで、自分の考えを明確に伝えられるようになり、コミュニケーションが円滑になります。
DESC法は相手に自分の意見を理解してもらいやすくし、共感を得られる可能性を高めます。その結果として、信頼関係が強化されるとともに、職場やプライベートでの相互理解が深まり、より良い人間関係を築く基盤を提供します。この信頼関係がもたらすメリットは、お互いに誠意をもって向き合うことでさらに大きくなり、長期的な信頼感が積み重なって関係がより深まります。
効果的な提案力の向上
DESC法を用いることで、効果的な提案力の向上が期待されます。この手法を活用する最大のメリットは、具体的な状況や課題に対して明確に提案を行える点です。自分の意見を整理しつつ、相手の懸念やニーズを的確に把握し、それに適した提案内容を提示できるため、提案が受け入れられやすくなります。
また、提案内容が具体的で説得力をもつことで、合意形成が効率よく進みます。さらに、この手法を身につけることで、コミュニケーションの場面において自信をもって意見を述べることが可能となるため、職場での対話だけでなく、多様な社会的な場面でも応用できるメリットがあります。
DESC法のデメリットと注意点

DESC法を利用する上で注意すべきデメリットも存在します。効果的なコミュニケーションツールである一方で、適用方法を誤ると逆効果となる可能性があります。
ここでは、デメリットと注意点に関して解説します。
適用を誤ると逆効果になる可能性
DESC法は適切に運用しなければ逆効果となる可能性があります。具体的には、自己主張に集中するあまり、相手の気持ちや状況に十分な配慮が欠けると、相手の拒絶反応を引き起こす原因になりかねません。また、提案や意見を伝える際に強い表現を用いることで、信頼関係を損なうリスクも伴います。このようなデメリットを回避するためには、相手の反応を柔軟に受け入れ、会話の流れや状況に適したアプローチを心掛ける必要があります。特に、相手との信頼を築くためには、押し付けるのではなく、相手の立場に寄り添った態度を意識することが大切です。
相手の視点を理解する重要性
相手の視点を理解することは、DESC法を成功させるための重要な要素です。DESC法を活用する際には、相手の感情や状況に対して敏感である必要があります。相手の視点を尊重し、共通点を見つけることで、より建設的な会話が生まれるだけでなく、相互理解を深める土台となります。特に、相手が抱えている不安や疑問に寄り添うことは、コミュニケーションをスムーズに進めるための重要な鍵です。
一方で、相手の視点を無視した場合には、双方の意思疎通がうまくいかず、誤解や対立が生じ、最悪の場合は関係性そのものが損なわれる可能性があります。このようなデメリットを避けるためにも、自己主張だけに偏らず、相手の考えや覚悟を確認し合う姿勢が求められます。その結果として、互いのニーズに応える効果的なコミュニケーションが生まれやすくなるでしょう。
アサーティブコミュニケーションと事例

アサーティブコミュニケーションは、自己表現と他者へのリスペクトを両立させる方法であり、効果的な意思疎通を図るための重要な手法です。このコミュニケーションスタイルを活用することで、職場での同僚とのやり取りや会議、そして採用面接、交渉といった場面でより成功に近づける可能性があります。
ここでは、具体的な活用法について解説します。
職場での具体的な活用例
職場におけるアサーティブコミュニケーションの具体例として、プロジェクトの進行に関する意見交換が挙げられます。例えば、会議中にメンバーが自らのアイデアを提案する際には、事実を基に状況を説明しつつ、感情や意見も適切に表現することで、効果的なコミュニケーションが図れます。このような事例では、他のメンバーも意見を述べやすくなり、結果として建設的な議論が進む環境が整います。さらに、自分が担っている役割や負担感について率直に共有することも、アサーティブな姿勢の具体例です。このプロセスにより、必要なサポートを得られるだけでなく、業務効率の向上やチーム全体の連携強化にも寄与します。
面接や交渉での活用方法
面接や交渉の場でも、アサーティブコミュニケーションは大いに役立ちます。例えば、面接時に自分の経験やスキルをアピールする際、具体的な事例を用いて実績を述べることで、説得力を高めることが可能です。その際、自分の成果や取り組みに対する感情や意欲を表現することで、面接官に自信をもった印象を与えることができます。交渉においても、アサーティブな姿勢で自分の要求を明確に伝えつつ、相手が望む条件や背景を理解しようと努めることで、効果的な合意点を見つけやすくなります。これらの手法を活用することで、面接や交渉といった重要な場面での成果をより高めることが期待できます。
DESC法とその他の方法との違い

コミュニケーション手法にはさまざまな方法が存在しますが、DESC法とは、自分の意見や感情を明確に伝えつつ、相手との関係性を重視した手法です。このDESC法は、自己表現と相手への配慮をバランスよく取り入れており、他のコミュニケーション手法と一線を画しています。一方で、PREP法のように結論を先に述べ、その後に理由や具体例を述べることで論理的かつ簡潔に伝える手法もよく利用されます。また、聞き手への優しさや共感を重視するSDS法など、場面や目的に応じた多様なアプローチが存在します。これらの手法を理解し、適切に使い分けることで、コミュニケーションの効果をより一層高めることができます。
結論を重視するPREP法
PREP法(プレップ)は、結論を先に伝える特徴的な構成で、情報を効果的に伝えるための優れた手法です。この構成は、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(再結論)」の順で進められ、特にビジネスシーンにおいて大きな効果を発揮します。PREP法を活用することで、相手は最初に重要なポイントを把握でき、続く理由や具体例によってその結論を論理的に納得することが可能になります。
この手法を取り入れると、アサーティブなコミュニケーションにおいて、相手が求める情報を簡潔かつわかりやすく伝えることができ、特にプレゼンテーションや議論の場で有用です。また、相手に要点を明確に提示することで時間を有効活用でき、双方の理解を深める結果を生み出します。
PREP法の例とポイントは次の通りです。
1. Point(結論・主張)
まず結論やメインの主張を簡潔に提示します。
例:「私の意見は〇〇です。」「結論としては、△△することを提案します。」
ポイント
話の冒頭で結論を示すことで、聞き手や読み手が「何が言いたいのか」をつかみやすくなります。
長い前置きをせず、まず要点を伝えるのが特徴です。
2. Reason(理由・根拠)
続いて、結論の理由・根拠を説明します。
例:「なぜなら、〇〇というデータが示しているからです。」「この理由は△△という背景があるからです。」
ポイント
データや事例、ロジック(因果関係など)を使って結論を裏付けます。
聞き手が納得できる「理由付け」がポイントです。
3. Example(具体例)
理由を証明・補強するため、具体的な事例やエピソードを挙げます。
例:「たとえば、先月実施したキャンペーンでも〇〇という成果がありました。」「△△という実例からも、この方法が有効だと分かります。」
ポイント
実際に起きたことや、数字を用いたエビデンスを示すと説得力が高まります。
相手がイメージしやすい例を選ぶことで理解を深めやすくなります。
4. Point(結論の再提示)
最後に、もう一度最初に示した結論を繰り返し伝えます。
例:「以上のことから、〇〇するのが最適な方針だと考えます。」「したがって、△△が必要だという結論になります。」
ポイント
最初に提示した結論と合わせて、話をスッキリと締めくくります。
結論を再確認できるため、聞き手の印象に強く残ります。
聞き手にストレスを感じさせないSDS法
SDS(エスディーエス)法は、聞き手の受け取りやすさを重視する手法です。
SDS法という名前のコミュニケーション・フレームワークでは、「Summary(要約)→Detail(詳細)→Summary(要約)」が有名ですが、ここでは、「S(Simplicity:簡潔さ)」「D(Directness:直接性)」「S(Sensitivity:配慮)」の3つを柱としているSDS法をご紹介します。
この手法では、簡潔な言葉で直接的に伝えることが求められ、さらに、相手の状況や感情に配慮しながら分かりやすく話すことを目的としています。
特に、初対面の相手や異なる立場の人とのコミュニケーションにおいて、相手にストレスや負担を感じさせずに説明ができるため、多くの場面で実践しやすい方法です。
SDS法のポイントと効果は次のとおりです。
S(Simplicity:簡潔さ)
ポイント: 伝えたい内容をなるべくシンプルにまとめる。専門用語を過度に使わず、分かりやすい言葉や構成にする。
効果: 情報が整理され、相手が要点を素早く理解しやすくなる。
D(Directness:直接性)
ポイント: 回りくどい表現ではなく、ストレートに要点を伝える。遠回しな言い方や曖昧さを避け、何を求めているのか、何を伝えたいのかをはっきり示す。
効果: 誤解や時間のロスを減らし、迅速な意思疎通や問題解決につなげやすくなる。
S(Sensitivity:配慮)
ポイント: 相手の立場や状況、感情、文化的背景などに配慮しつつ伝える。言葉選びやトーンを意識し、過度に攻撃的にならないようにする。
効果: 良好な人間関係を築きやすくなり、信頼関係の維持や協力を得やすくなる。
それぞれの使い分けのポイント
各手法の使い分けは、目的や状況に応じて行うことが肝要です。たとえば、短い時間で納得を得たい場合にはPREP法が適しており、具体例を示しながら要点を簡潔に伝えることがコツとなります。
一方で、初めての相手に対してはSDS法が効果的で、分かりやすい流れを作ることで相手が安心できる環境を整えることができます。
また、DESC法は感情や相手の視点を重視するため、関係構築が求められる場面で活用するのが理想的です。この場合、相手の意見を尊重しつつ自分の主張を的確に伝えることがポイントです。これらの手法を状況に応じて巧みに取り入れ、コツを押さえた活用を心がけることで、より良好なコミュニケーションが実現できるでしょう。
まとめと次のステップ

DESC法とは、効果的なコミュニケーションを実現するための有力な手法です。この方法を活用することで、相手との対話が円滑になり、建設的な関係性を築けるようになります。「DESC法とは何か」を理解し、実践することにより、特に職場や日常生活におけるコミュニケーション力の向上が期待され、さまざまな場面で役立つスキルと言えるでしょう。今後は、DESC法を学んだ内容をもとに実践し、さらに改善や成長を目指すことが重要です。
実践するための心得
実践するためには、DESC法とはどのようなものかを正しく理解し、それを活用するための基盤を作ることから始めましょう。
DESC法を実践するときには、相手への配慮を忘れず、相手の感情や状況を尊重しながら進めることが求められます。この方法では、自分の意見や感情を率直に伝える一方で、押し付けがましい印象を与えないよう注意することも重要です。コツとしては、共感を示しながら誠実なコミュニケーションを取ることが挙げられます。また、相手がリラックスし、安心感をもてる環境を整えることで、より良い結果を引き出すことができます。
日常に活用するためのヒント
日常生活でDESC法を活用するために、まずは意識的に実践を重ねることが重要です。例えば、日常生活の中で友人や家族との日常的な会話にDESC法を取り入れることで、相手とのコミュニケーションをより円滑にする効果が期待できます。また、積極的にフィードバックを求めることで自身の取り組みを客観的に見直し、スキルを向上させる手助けとなるでしょう。職場内でのミーティングや打ち合わせといった仕事の場面でもこの手法を活用することで、効果を実感しやすく、より自然に身につけることが可能です。こうした取り組みを通じて、場面や状況に応じた柔軟な対応力を養い、日常生活全般で実際に活かせる手法としてDESC法を定着させることが大切です。
社員教育に「SAKU-SAKU Testing」がおすすめ
イー・コミュニケーションズのeラーニングシステム「SAKU-SAKU Testing」を活用した社員教育がおすすめです。
「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、自社独自の社員教育を行うためのプラットフォームとして活用することが可能です。
また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用に加え、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されているものなど、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
ご興味がおありの場合はお気軽にお問い合わせください。