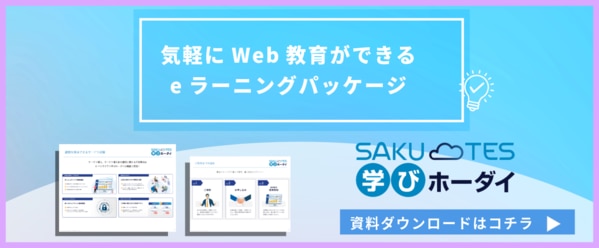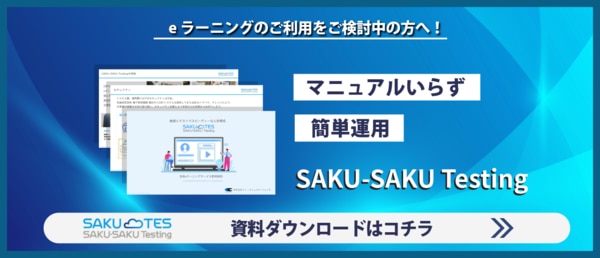コンプライアンスとは?意味・重要性・違反事例・対策までわかりやすく解説

近年、「コンプライアンス」がますます重要視されつつあります。
コンプライアンスは、単なるルールや法律の遵守だけでなく、企業の信頼や働きやすさにも関わる大切な考え方です。
本記事では、身近な違反例やリスク、企業ができる具体的な対策まで、コンプライアンスについてわかりやすく解説します。
初めて学ぶ方も、改めて意識を確認したい方も、ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.コンプライアンスとは?その意味と使い方
- 2.「コンプライアンス」と混同されやすい関連用語
- 3.「なぜ今コンプライアンスが注目されているのか
- 3.1.企業不祥事や法令違反の増加
- 3.2.SNSや情報発信リスクの拡大
- 3.3.社会的信用の重要性と企業価値への影響
- 4.実際に起きているコンプライアンス違反の事例
- 4.1.不正経理・会計不正
- 4.2.労働問題・ハラスメント
- 4.3.情報漏えい・データ管理不備
- 4.4.著作権・知的財産の侵害
- 5.身近な場面で起こるコンプライアンス違反例
- 5.1.備品やデータの持ち出し
- 5.2.SNSでの不適切投稿
- 5.3.勤務時間・出退勤の虚偽申告
- 6.コンプライアンス違反がもたらすリスク
- 6.1.損害賠償・法的責任
- 6.2.社会的信用の失墜
- 6.3.従業員の離職・士気低下
- 6.4.企業価値・ブランドの毀損
- 7.企業が取るべきコンプライアンス対策
- 7.1.マニュアル・社内規程の整備
- 7.2.コンプライアンス研修の実施
- 7.3.相談・内部通報窓口の設置
- 7.4.経営陣のリーダーシップと組織体制づくり
- 7.5.継続的なモニタリングと改善
- 8.コンプライアンス経営を推進するメリット
- 8.1.企業イメージと信頼の向上
- 8.2.従業員のモチベーション・定着率向上
- 8.3.長期的な企業価値の向上
- 9.コンプライアンス研修を行うならイー・コミュニケーションズへ
コンプライアンスとは?その意味と使い方

近年、企業活動のあらゆる場面で「コンプライアンス」という言葉を耳にするようになりました。
もともとは「法令を守る」というシンプルな意味でしたが、現在ではその範囲はより広く、社会全体のルールや企業倫理までも含む重要な概念として位置づけられています。
ここでは、コンプライアンスの基本的な意味と、企業での使われ方・目的について解説します。
本来の意味は「法令遵守」
「コンプライアンス(compliance)」の本来の意味は「法令遵守」です。
企業活動を行ううえで、法律や行政のルールを守ることは最も基本的な義務です。
例えば、労働基準法や個人情報保護法、独占禁止法など、企業は業種や事業形態に応じて多くの法律を遵守する必要があります。
こうした法令を守る姿勢は、単に「罰則を避けるため」のものではありません。
法律を遵守することで、企業は取引先や顧客、従業員といったステークホルダーからの信頼を得られ、健全な経営基盤を築くことができます。
社内規範や企業倫理も含まれる広い概念
もともと「法令遵守」を意味していたコンプライアンスですが、現代ではその範囲が法律以外にも広がっています。
例えば、企業独自の行動規範・就業規則・社内マニュアルといった社内規範、さらに企業が社会の一員として果たすべき「倫理的責任(企業倫理・社会規範)」も”コンプライアンス”の一部として扱われます。
近年では、法令違反をしていなくても「社会的に不適切」と判断され、企業の信用が大きく損なわれるケースも少なくありません。
つまり、コンプライアンスとは「法律を守ること」だけではなく、「社会からの信頼を守る姿勢」と言い換えることができます。
企業におけるコンプライアンスの目的と意義
企業がコンプライアンスを重視する目的は、単なる法令順守ではなく、企業として持続的に成長するための基盤をつくることにあります。
法令や規範を守ることで、以下のようなメリットがあります。
- ステークホルダー(顧客・取引先・株主など)からの信頼の獲得
- 不祥事の予防によるリスク低減
- 企業ブランドやイメージの向上
- 従業員が安心して働ける職場環境の実現
一方で、コンプライアンス違反は企業経営に大きな打撃を与える可能性があります。社会の信頼を損なえば、たとえ法的責任を免れても企業価値が失われることは避けられません。
コンプライアンスの使い方とビジネスシーンでの例
「コンプライアンス」はビジネスシーンでも頻繁に使われる言葉です。会議や社内メール、報道などで以下のように用いられます。
- 「当社ではコンプライアンスを最優先とした経営を徹底しています」
- 「コンプライアンス研修を通じて、従業員一人ひとりの意識を高める」
- 「法令違反や不祥事など、コンプライアンス上のリスクに注意する必要がある」
このように「コンプライアンス」という言葉は、単なるスローガンではなく、企業の方針や行動の根幹を表すキーワードなのです。
特に企業の信頼性が重視される現代では、コンプライアンスを理解し、正しく使えることが組織全体の競争力にもつながります。
「コンプライアンス」と混同されやすい関連用語

コンプライアンスは、法令遵守や企業倫理を守ることを指す言葉ですが、よく混同される概念として「コーポレートガバナンス」や「CSR」、「内部統制」などがあります。
ここでは、関連する用語との違いや関係をわかりやすく整理し、企業活動の中でコンプライアンスがどのような位置づけにあるのかを見ていきます。
コーポレートガバナンスとの違い
コーポレートガバナンスとは、企業が適切に経営判断を行い、株主や関係者の利益を守るための仕組みを指します。
一方でコンプライアンスは「法律や規範を守ること」に焦点を置いた概念です。
簡単に言えば、コンプライアンスは“守るべきルール”に関する行動の基準であり、ガバナンスは“企業の仕組みや意思決定の枠組み”を指します。
つまり、コンプライアンスはガバナンスを支える土台であり、両者は切り離せない関係にあります。
CSR(企業の社会的責任)との違い
CSRとは「Corporate Social Responsibility」の略で、企業が社会や環境に対して果たすべき責任を意味します。
コンプライアンスが法令遵守や社内規範に焦点を当てるのに対し、CSRは社会全体に対する貢献や責任を強調する点が異なります。
例えば、法令違反がなくても、環境保護や地域社会への貢献を怠ればCSR上の問題となります。そのため、コンプライアンスとCSRは密接に関連しつつも、目的と対象範囲がやや異なる概念です。
内部統制・リスクマネジメントとの関係
内部統制とは、企業が業務を適正に行うための仕組みやルールの総称で、業務プロセスや承認フロー、帳簿管理などが含まれます。
リスクマネジメントは、企業活動に潜むさまざまなリスクを特定し、予防・軽減する取り組みです。
コンプライアンスはこの内部統制やリスクマネジメントと密接に関わっており、ルールを守る行動を通じてリスクを最小化する役割を担います。
つまり、コンプライアンスは、内部統制やリスクマネジメントで決められたルールを実際に守る行動のことを指します。企業全体の仕組みを理解するうえでも、重要な役割を果たしています。
「なぜ今コンプライアンスが注目されているのか
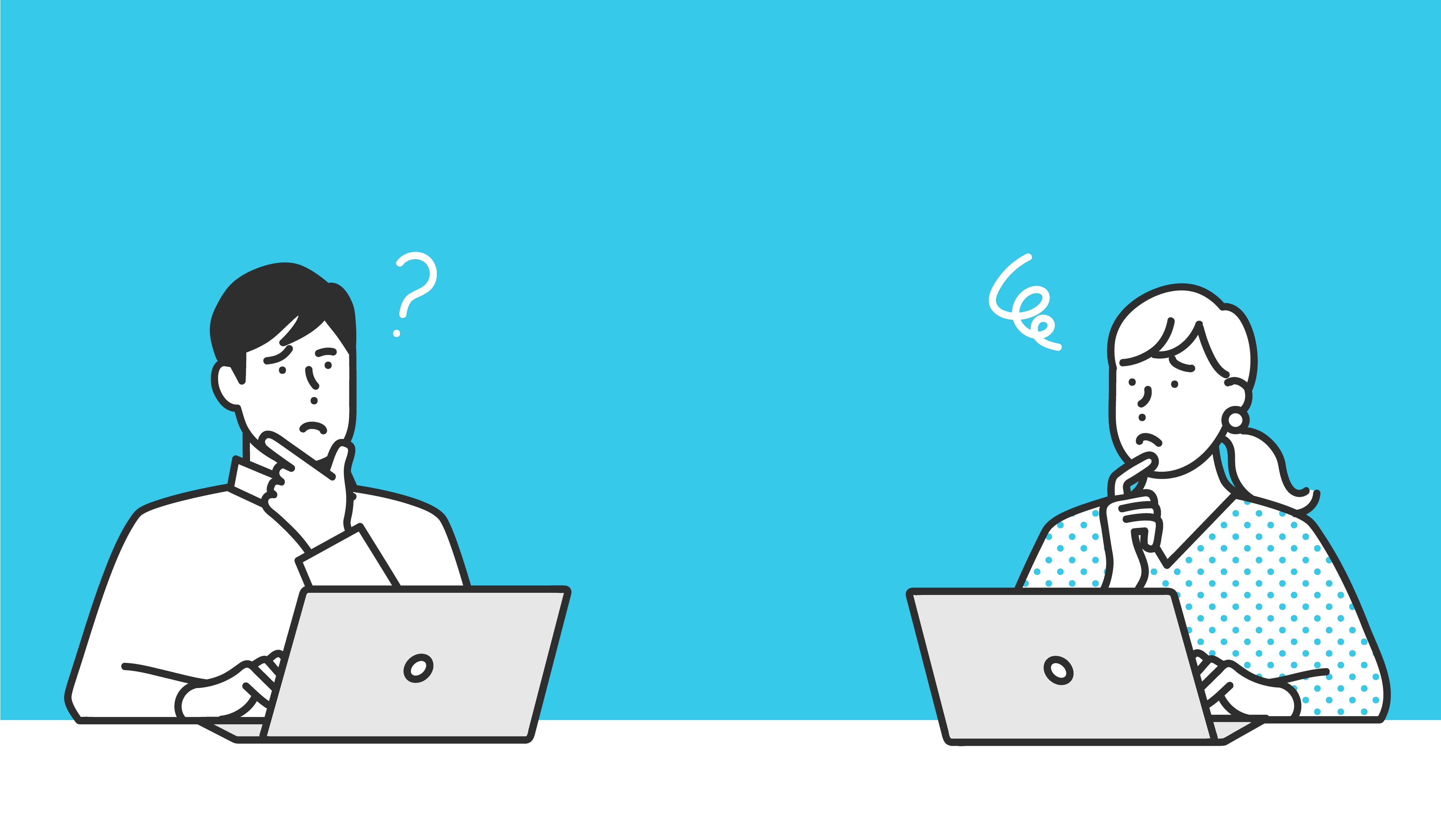
最近では、法令違反や不適切な行為が明るみに出ると、社会的な注目を集め、企業価値やブランドに大きな影響が出てしまいます。そのため、単にルールを守るだけでなく、組織全体でコンプライアンスを徹底することが経営戦略上も重要になっています。
ここでは、なぜコンプライアンスがこれほど注目されるようになったのか、その背景を具体的に解説します。
企業不祥事や法令違反の増加
近年、多くの企業で不正経理や労務問題、情報漏えいなどの不祥事が明るみに出ています。こうした問題は単なる個別のケースではなく、企業文化や組織体制の課題が表れていることも少なくありません。
例えば、架空取引や不正会計などの経理上の不正は、法的な処罰だけでなく企業の評価や信頼にも影響を与える可能性があります。
こうした状況が増える中、企業は事前にリスクを把握し、コンプライアンスを徹底することが求められています。
SNSや情報発信リスクの拡大
インターネットやSNSの普及により、従業員や企業の発信が短時間で広く伝わる時代となりました。些細な発言や投稿が炎上し、社会的信用やブランドに大きな影響を及ぼすことがあります。
企業の公式アカウントだけでなく、社員個人のアカウントによる不適切投稿もリスクの一つです。
そのため、情報発信やコミュニケーションにおけるコンプライアンス意識を組織全体で浸透させることが、企業経営において重要な課題となっています。
社会的信用の重要性と企業価値への影響
企業の社会的信用は、取引先や顧客、投資家からの信頼に直結し、経営の安定や成長にも欠かせません。
コンプライアンス違反が発覚すると、短期的には損害賠償や行政処分のリスクがありますが、長期的にはブランド価値や株価にも影響を及ぼすことがあります。
逆に、従業員教育や規範の遵守を通じてコンプライアンスがしっかり定着すれば、顧客や株主、社会からの信頼が高まり、競争力の強化や持続的な成長につながります。
つまり、コンプライアンスは単なる法令遵守ではなく、企業の未来を支える重要な戦略的要素なのです。
実際に起きているコンプライアンス違反の事例

コンプライアンス違反は、法律や社内規範を守らない行為によって生じます。近年は不正会計や労務問題、情報漏えいなど、さまざまな分野で企業の信用を揺るがす事例が報告されています。
ここでは、特に企業で発生しやすい代表的な違反事例を紹介し、そのリスクの大きさを整理します。
不正経理・会計不正
不正経理や会計不正は、企業にとって非常に大きなリスクです。
具体的には、売上の過大計上や架空取引、費用の水増しなどが挙げられます。こうした行為は、法的な罰則だけでなく、株主や投資家からの信頼の低下や取引先との関係悪化など、長期的な企業価値の損失にもつながります。
企業は会計プロセスの透明化や内部監査の徹底を通じて、こうした不正を未然に防ぐ必要があります。
労働問題・ハラスメント
従業員に対する不当な扱いやハラスメントも、重要なコンプライアンス違反の一つです。
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、長時間労働の強要など、法令違反や社内規範違反に該当する行為は、企業の信用を大きく損ないます。
適切な就業規則の整備、相談窓口の設置、研修の実施によって、従業員が安心して働ける環境を整えることが不可欠です。
情報漏えい・データ管理不備
情報漏えいやデータ管理の不備も、企業にとって深刻なリスクです。顧客情報や社内機密、取引先データなどの漏洩は、法令違反だけでなく社会的信頼の低下にも直結します。
例えば、個人情報保護法に基づく適切な管理が行われていない場合、行政処分や損害賠償のリスクが生じます。
さらに、業務用データの不適切な持ち出しやクラウド管理の不備も、現代の企業で多く見られる問題です。
著作権・知的財産の侵害
著作権や特許、商標などの知的財産権の侵害もコンプライアンス違反に含まれます。
例えば、無断で他社の資料を使用したり、コピー商品を扱ったりすることは法的リスクだけでなく、企業イメージの低下にもつながります。
特にクリエイティブやIT系の企業では、社員一人ひとりの知的財産に対する理解と教育が不可欠です。
適切な権利管理の仕組みを整え、社内でのルール周知を徹底することが求められます。
身近な場面で起こるコンプライアンス違反例

コンプライアンス違反は、企業の経営層や管理部門だけの問題ではありません。実は、日常のちょっとした行動が違反につながることも少なくありません。
ここでは、現場で起こりやすい「身近なコンプライアンス違反」の具体例を紹介し、注意すべきポイントを解説します。
備品やデータの持ち出し
USBメモリや私用パソコンに業務データを保存して持ち出す行為は、意図的でなくても情報漏えいにつながるリスクがあります。
また、会社の備品(文具・機器など)を私的に使用することも、軽微に見えて立派なコンプライアンス違反です。こうした行為を防ぐためには、「会社の資産を個人利用しない」という基本意識を浸透させることが重要です。
データを外部に持ち出す際は、情報セキュリティポリシーに基づいた申請・承認プロセスを必ず経るようにしましょう。
SNSでの不適切投稿
個人のSNSアカウントにおける不用意な投稿も、企業の評判を左右する重大なコンプライアンスリスクです。社内情報や取引先情報、顧客に関する発言などを軽い気持ちで投稿してしまうケースは後を絶ちません。
また、匿名投稿であっても、発言内容や文体から個人や所属企業が特定される場合があります。
企業としては、SNS利用に関するガイドラインの明文化と教育が欠かせません。
社員一人ひとりが「ネット上でも自社の一員である」という意識を持つことが、炎上や信用失墜の防止につながります。
勤務時間・出退勤の虚偽申告
勤務時間や出退勤の虚偽申告も、軽視できないコンプライアンス違反の一つです。
例えば、実際より早く退勤したのに「勤務中」と記録したり、残業をしていないのに時間外労働を申告したりするケースが該当します。
こうした不正は、労働基準法違反や給与の不正受給につながり、懲戒処分の対象にもなり得ます。管理職側も、こうした不正を見逃さず、勤務記録を適正に確認・管理する責任があります。コンプライアンス違反によって発生する法的責任は、企業に直接的な経済的損失をもたらします。
例えば、契約違反や個人情報漏洩、労働法違反などが明らかになると、損害賠償請求や行政処分の対象となる可能性があります。
法的リスクを減らすためには、社内規程やマニュアルの整備、法務チェック体制の強化、定期的な研修が重要です。
社員の「ちょっとくらいなら」という意識の積み重ねが、企業全体の信頼を損なう原因となるため、誠実な労務管理を徹底する必要があります。
コンプライアンス違反がもたらすリスク

コンプライアンス違反は単なるルール違反にとどまらず、企業にさまざまなリスクを引き起こします。法的責任や社会的信用の低下、従業員への影響など、多方面に悪影響が広がるため、違反リスクの理解は経営上欠かせません。
ここでは、主なリスクを具体的に整理します。
損害賠償・法的責任
コンプライアンス違反によって発生する法的責任は、企業に直接的な経済的損失をもたらします。例えば、契約違反や個人情報漏洩、労働法違反などが明らかになると、損害賠償請求や行政処分の対象となる可能性があります。
法的リスクを減らすためには、社内規程やマニュアルの整備、法務チェック体制の強化、定期的な研修が重要です。
社会的信用の失墜
不祥事や違反行為は、メディアやSNSを通じて瞬時に社会へ伝わります。その結果、顧客や取引先、投資家からの信頼を失うだけでなく、企業ブランド自体が損なわれるリスクがあります。
信用の回復には時間がかかり、企業イメージの低下は売上や事業の拡大にも影響を及ぼすことがあります。
従業員の離職・士気低下
コンプライアンス違反が明るみに出ると、従業員の心理的負担が増し、士気の低下や離職率の上昇を招くことがあります。
特にパワハラや不当な業務管理などの内部問題は、社員が安心して働ける環境を損ないます。定期的な研修や相談窓口の設置、透明性の高い社内環境の整備は、従業員の信頼と働きがいを守る上で欠かせません。
企業価値・ブランドの毀損
コンプライアンス違反は、短期的な損害だけでなく、企業価値やブランドの長期的な低下にもつながります。信用の低下による取引停止、投資家からの評価低下、採用面での不利など、多方面に影響が広がります。
過去の不正会計や情報漏えいの事例では、株価下落や企業価値の減少が顕著に見られました。そのため、企業はリスクマネジメントとコンプライアンス体制を統合的に強化し、ブランドと価値を守ることが重要です。
企業が取るべきコンプライアンス対策

コンプライアンス違反を防ぐには、単にルールを設けるだけでは不十分です。
企業全体で意識を浸透させ、実効性のある仕組みと運用を整えることが大切です。
ここでは、具体的な対策を整理します。
マニュアル・社内規程の整備
企業内で守るべきルールや手順を明文化したマニュアルや社内規程の整備は、コンプライアンス対策の基盤です。
業務上の判断基準や手続き、禁止事項を明確にすることで、従業員の行動指針が統一され、違反の未然防止につながります。また、規程は定期的に見直し、最新の法令や社会状況に合わせて更新することが重要です。
マニュアルや規程だけでは十分ではなく、社員一人ひとりが理解し、実践できる状態にすることがポイントです。
コンプライアンス研修の実施
研修は、従業員にコンプライアンスの意義や具体的な対応方法を理解させるだけでなく、組織全体の意識を底上げする役割もあります。
ケーススタディやグループディスカッションを取り入れることで、単なる知識の習得にとどまらず、実務での判断力や対応力を養うことができます。
また、研修を定期的に実施することで、法令改正や新たなリスクへの対応力も強化され、組織全体の安全性と信頼性の向上につながります。
特に新入社員だけでなく、中堅社員や管理職向けの研修も組み合わせることで、階層ごとの意識浸透と実務適用力の向上が期待できます。
相談・内部通報窓口の設置
社員が違反行為や疑わしい行動を気軽に報告できる相談窓口や内部通報制度は、問題を早期に発見・対応するための重要な仕組みです。
匿名での通報や第三者機関の活用など、従業員が安心して利用できる環境を整えることが大切です。
経営陣のリーダーシップと組織体制づくり
コンプライアンスは、経営陣の姿勢や組織文化に大きく影響されます。
トップが明確にコンプライアンスの重要性を示すことで、従業員全体の意識が向上し、実効性のある運用が可能になります。
加えて、コンプライアンス推進部門や責任者を設置し、各部門との連携を強化することで、組織全体で違反防止を徹底できます。
継続的なモニタリングと改善
コンプライアンス対策は、整備して終わりではなく、日常的にモニタリングして改善していくことが重要です。内部監査や定期チェック、ヒヤリハット事例の共有を通じて、現場での問題点や新たなリスクを早期に把握します。
こうしたPDCAサイクルを回すことで、制度や研修の効果を高め、常に実効性のあるコンプライアンス体制を維持することが可能です。
コンプライアンス経営を推進するメリット

コンプライアンス経営とは、法令遵守や企業倫理を重視しながら経営を行う姿勢のことです。これを組織全体で実践することで、企業は単なるリスク回避にとどまらず、持続的な成長や信頼構築にもつなげることができます。
ここでは、具体的なメリットを整理します。
企業イメージと信頼の向上
コンプライアンス経営を徹底することで、取引先や顧客、株主からの信頼が高まります。
法令違反や不正行為が少ない企業は、社会的信用を獲得しやすく、ブランド力の強化にも直結します。
特に近年は、情報公開やCSR活動の透明性が重視されるため、遵守意識の高さは企業イメージ向上の大きな要因となります。
従業員のモチベーション・定着率向上
コンプライアンス経営が浸透した職場では、社員が安心して働ける環境が整います。
不正や不当な圧力が少ない組織は、社員の士気を高め、離職率の低下にもつながります。
また、研修や相談窓口などの取り組みを通じて、社員自身が企業の価値観を理解することで、働きがいの向上も期待できます。
長期的な企業価値の向上
法令遵守や倫理的経営は、企業の長期的な持続可能性を支えます。
コンプライアンス違反による損害や信用低下を未然に防ぐことで、株価や投資家評価の安定、取引先との良好な関係維持につながります。
結果として、短期的な利益追求だけでなく、長期的な企業価値の向上を実現する土台となります。
コンプライアンス研修を行うならイー・コミュニケーションズへ
コンプライアンスは、ステークホルダーや顧客など社外に対しても、また自社で働く従業員に対しても大切なものとなっています。違反があった場合のリスクが大きいため、未然にトラブルを予防することが必要です。
仕組みづくりとともに、管理職や担当者への教育も、全ての従業員への教育もますます必要性が高まっていくと言えるでしょう。
コンプライアンス研修・コンプライアンス学習の導入をご検討中なら、私どもイー・コミュニケーションズにご相談ください。
問題形式で効率よく学べるeラーニングのシステム「SAKU-SAKU Testing」と併用して利用できるコンプライアンス・ハラスメントの基本問題集「コンプライアンス・ハラスメント・情報セキュリティベーシック」をご提供しております。
「コンプライアンス・ハラスメント・情報セキュリティベーシック」 は「コンプライアンス」「ハラスメント」「情報セキュリティ」の3点において、リスクの見える化から教育まで行うことができます。
実際に起こったシーンにおいて正しい行動や考え方を答えさせる「ケース問題」で構成されており、職場ですぐに活用できる知識や考え方が身に付きます。
SAKU-SAKU Testingは問題形式のテストエデュケーションで、アウトプット主体の学習が可能です。
ご質問がおありの場合・ご興味がおありの場合は、ページ右上の「お問い合わせ」よりご連絡いただけます。お気軽にお問い合わせください。
コンプライアンス研修に関するコンテンツ
- 「自社の従業員のハラスメント意識レベルを把握したい」「まずは情報セキュリティに関する知識のベースを揃えたい」といったニーズにこたえ、スピーディーで効果的な教育を実現できるコンテンツパッケージ
- 自社のニーズにあったコンプライアンスコンテンツを選びたいというご担当者におススメ