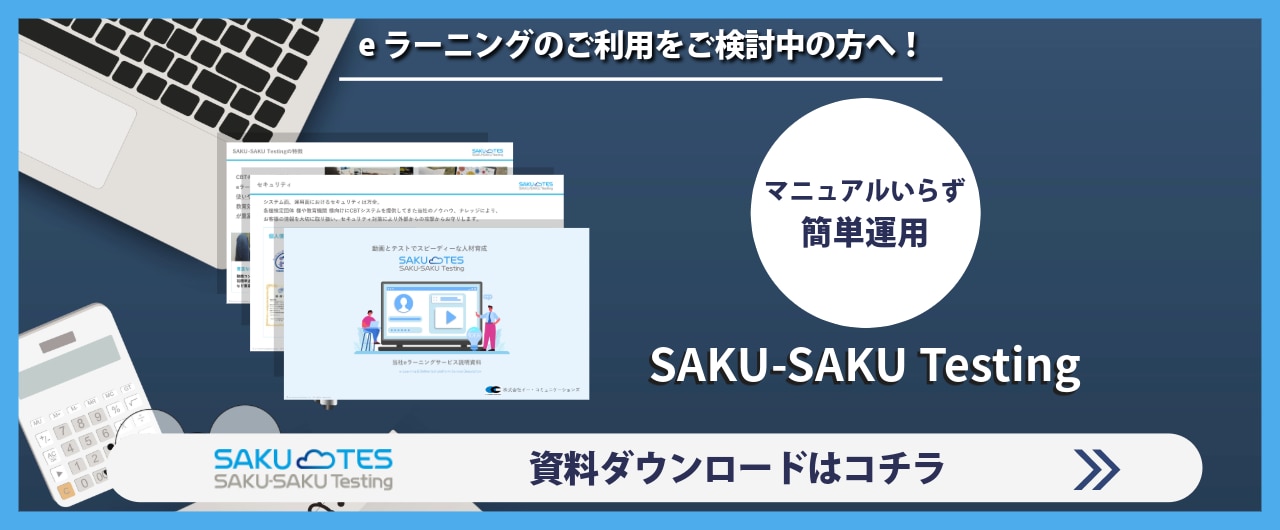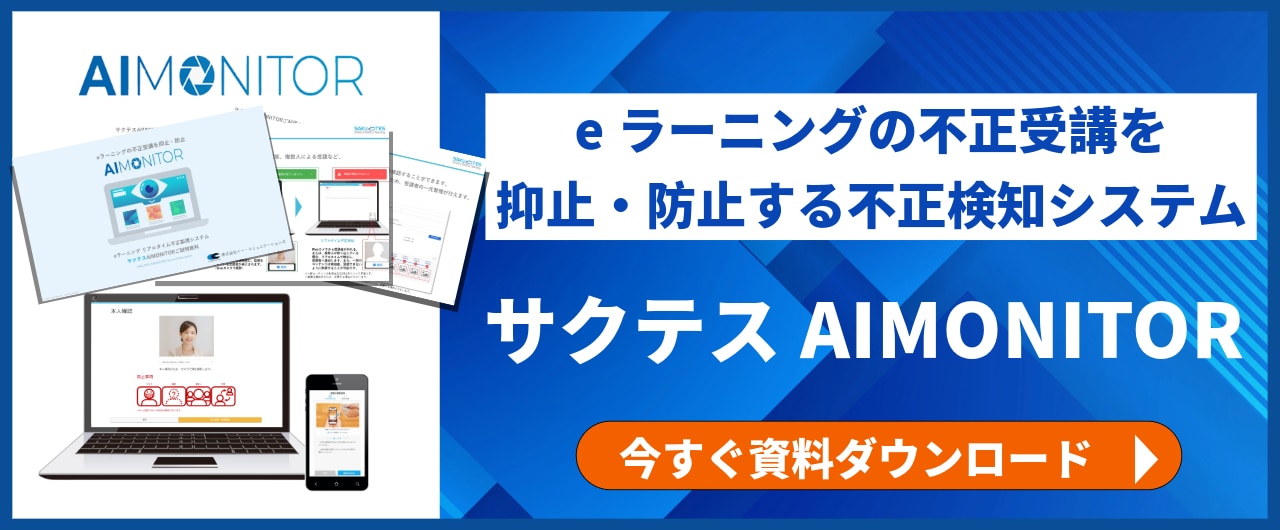アイスブレイクは1分でOK!会議や研修で使える簡単ネタ15選

会議や研修の冒頭、参加者の緊張をほぐして場の雰囲気を良くしたい場面で役立つのがアイスブレイクです。
しかし、準備に時間をかけられないことも少なくありません。
この記事では、わずか1分程度で簡単に実施でき、すぐに場が和むアイスブレイクネタを紹介します。自己紹介系やゲーム系など、状況に合わせて使えるさまざまなネタを取り上げ、成功させるコツも解説します。
目次[非表示]
- 1.アイスブレイクとは?場の空気を和ませるコミュニケーション手法
- 2.1分でアイスブレイクを行う3つのメリット
- 3.【自己紹介系】1分でできる簡単アイスブレイクネタ5選
- 3.1.自己紹介で意外な一面を共有する「実は〇〇です」
- 3.2.ペアで行う「他己紹介」で傾聴力を高める
- 3.3.グループの一体感が生まれる「共通点探しゲーム」
- 3.4.名前と特徴を覚える「積み木自己紹介」
- 3.5.第一印象を伝え合う「印象ゲーム」
- 4.【ゲーム・クイズ系】1分で盛り上がるアイスブレイクネタ5選
- 4.1.体感時間を競う「1分時計チャレンジ」
- 4.2.お題に沿って答える「古今東西ゲーム」
- 4.3.脳の活性化につながる「後出しじゃんけんゲーム」
- 4.4.価値観がわかる「究極の2択クイズ」
- 4.5.連想力を鍛える「ワンワード」
- 5.【オンライン向け】リモートでもできるアイスブレイクネタ5選
- 5.1.バーチャル背景を使って自分の趣味や好きなものを紹介する
- 5.2.チャット機能で「今の気分」を一斉に投稿する
- 5.3.カメラに向かって指を動かす「指体操」
- 5.4.お題に沿ったものを探す「身の回りにあるもの探しゲーム」
- 5.5.スタンプやリアクション機能で気持ちを表現する
- 6.1分アイスブレイクを成功に導く4つのコツ
- 7.アイスブレイクで失敗しないための注意点
- 8.まとめ
- 9.社員のスキルアップ研修にeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
アイスブレイクとは?場の空気を和ませるコミュニケーション手法

アイスブレイクとは、氷を壊すという言葉の通り、会議や研修などで初対面の人同士が集まった際の緊張した雰囲気や心理的な壁を取り除くためのコミュニケーション手法です。
本題に入る前に自己紹介や簡単なゲームなどを取り入れることで、参加者同士の相互理解を促し、コミュニケーションを活性化させる目的があります。
短い時間でリラックスした雰囲気を作り出し、その後の議論や共同作業を円滑に進める土台を築きます。
1分でアイスブレイクを行う3つのメリット

時間をかけずにアイスブレイクを行うことには、多くの利点が存在します。
特に1分という短時間で実施するメリットは、会議や研修の進行を妨げることなく、場の雰囲気を効果的に和ませられる点にあります。
例えば、簡単な自己紹介を取り入れるだけでも、参加者の緊張をほぐし、その後のコミュニケーションを円滑にする効果が期待できます。
ここでは、短時間のアイスブレイクがもたらす具体的な3つのメリットについて解説します。
メリット1:会議や研修の本題にスムーズに入れる
アイスブレイクが長引くと、本来の議題である会議や研修の時間を圧迫してしまう可能性があります。
しかし、実施時間を1分と決めておけば、場の空気を和ませつつも、すぐに本題へと移行できるため、全体の進行がスムーズになります。
短い自己紹介で互いの人となりを少し伝えるだけでも、発言しやすい雰囲気が醸成され、その後の意見交換が活発になる効果が期待できます。
アイスブレイクはあくまで本題を円滑に進めるための準備運動と位置づけ、時間を区切って行うことが重要です。
メリット2:参加者の心理的な負担が少ない
人前で話すことや、注目を浴びることに苦手意識をもつ参加者にとって、長時間にわたるアイスブレイクは大きな心理的負担になり得ます。
その点、1分程度で終わる簡単なものであれば、参加者の抵抗感を和らげ、気軽に参加を促すことが可能です。
特に1対1のペアワークで短い時間お互いのことを伝え合う形式は、大人数の前で一人で長く話すよりもハードルが低いと感じる人が多いです。
全員が安心して参加できる環境を作ることで、アイスブレイク本来の目的を達成しやすくなります。
メリット3:特別な準備が不要ですぐに始められる
1分で実施できるアイスブレイクの多くは、特別な道具や資料を必要としないため、進行役の準備にかかる負担が少ないという利点があります。
例えば、3人程度のグループを作って共通点を探すゲームなどは、口頭での簡単なルール説明だけですぐに始められます。そのため、会議の冒頭や休憩明けなど、場の空気を変えたいと思ったタイミングで気軽に取り入れることが可能です。
準備に手間がかからない手軽さは、アイスブレイクを継続的に活用していく上での大きなメリットとなります。
【自己紹介系】1分でできる簡単アイスブレイクネタ5選

初対面のメンバーが多い場面では、お互いのことを知るきっかけとなる自己紹介系のアイスブレイクが特に有効です。
単に名前や所属を述べるだけでなく、少し工夫を加えることで、参加者の人柄や意外な一面を知ることができます。
これから紹介するネタは、1分という短い時間で実施でき、相互理解を深めるのに役立つものばかりです。
簡単な自己紹介を通じて、その後のコミュニケーションを円滑にする土台を築きます。
自己紹介で意外な一面を共有する「実は〇〇です」
名前や部署名などの基本的な自己紹介に「実は〇〇です」という一言を付け加えて発表してもらうアイスブレイクです。
〇〇には趣味や特技、意外な経歴、最近ハマっていることなど、ポジティブな内容であれば何でも構いません。
この一言があるだけで、その人の個性や人柄を短時間で伝えることができ、聞いている側も親近感を抱きやすくなります。
他の参加者から「詳しく聞きたい」と興味をもたれ、休憩時間などの会話のきっかけが生まれる効果も期待できます。
ペアで行う「他己紹介」で傾聴力を高める
まず2人1組のペアになり、お互いにインタビューをし合います。
インタビューが終わったら、今度は全員の前で、ペアの相手がどのような人物なのかを紹介します。
この「他己紹介」は、相手の話を注意深く聞き、要点をまとめて分かりやすく伝えるスキルが求められるため、傾聴力や要約力のトレーニングにもなります。
自分で自分を紹介するよりも、第三者から紹介されることで、より客観的な人物像が伝わるという面白さもあるネタです。
グループの一体感が生まれる「共通点探しゲーム」
3〜5人のグループに分かれ、制限時間内にメンバー全員に共通する項目をできるだけ多く見つけ出すゲームです。
出身地、好きな食べ物、趣味、血液型など、テーマは何でも構いません。
自分たちだけの共通点を見つけ出す過程で自然と会話が生まれ、一体感が醸成されます。
意外な共通点が見つかったときには、特に大きな盛り上がりを見せるでしょう。
名前と特徴を覚える「積み木自己紹介」
最初の人が「〇〇部の佐藤です。好きな食べ物はカレーです」のように自己紹介をします。
次の人は、前の人の自己紹介を繰り返し、「カレーが好きな佐藤さんの隣の、営業部の鈴木です。趣味は釣りです」と自分の紹介を付け加えます。
これを順番に繰り返していくため、後の人ほど記憶する量が増えて難易度が上がります。
ゲーム感覚で楽しみながら、参加者の名前と特徴を効率的に覚えられるのが特徴で、オンラインの場でも順番を決めれば実施可能です。
第一印象を伝え合う「印象ゲーム」
数人のグループに分かれ、一人の人物をお題として、その人に対するポジティブな第一印象を他のメンバーが順番に伝えていくアイスブレイクです。
「笑顔が素敵」「頼りになりそう」など、あくまで前向きな側面に限定することが、場の雰囲気を良くするうえで重要です。
言われた本人は、自分が他者にどう見られているかを知る良い機会になります。
オンラインで実施する場合は、チャット機能を使い、お題の人にだけメッセージを送る方法も有効です。
【ゲーム・クイズ系】1分で盛り上がるアイスブレイクネタ5選
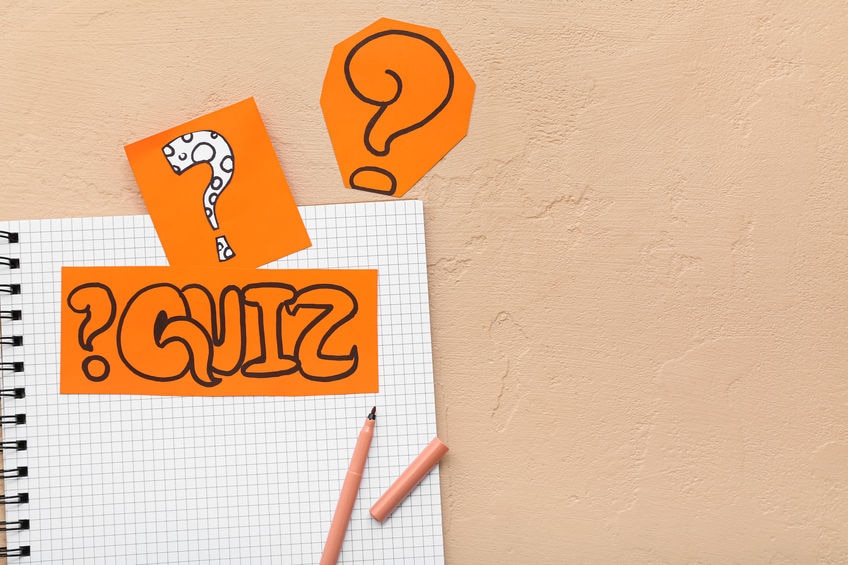
自己紹介だけでなく、もう少しアクティブな要素を取り入れて場を盛り上げたいときには、ゲームやクイズ形式のアイスブレイクが適しています。
簡単なルールで誰もがすぐに参加でき、頭や体を少し使うことで、参加者の緊張を効果的にほぐすことができます。
また、眠気覚ましや集中力を高めるウォーミングアップとしても機能します。
ここで紹介するネタには、オンライン環境でも手軽に実施できるものも含まれています。
体感時間を競う「1分時計チャレンジ」
進行役の「スタート」の合図で、参加者全員に目を閉じてもらい、心の中で時間をカウントしてもらいます。
各自が「1分経った」と思ったタイミングで静かに手を挙げ、実際にストップウォッチで計測している進行役がそのタイムを記録します。
最も1分に近いタイムだった人が勝利するという、非常にシンプルなゲームです。
特別な道具は必要なく、オンラインでも簡単に実施できます。
集中力を高める効果も期待でき、研修や会議を始める前の頭の準備体操として有効です。
お題に沿って答える「古今東西ゲーム」
都道府県の名前、赤いものといったお題を一つ決め、参加者が順番にリズムに合わせて答えを言っていく、誰もが知っているゲームです。
ルール説明がほとんど不要で、すぐに始められる手軽さが魅力です。
既に出た答えを言ったり、答えに詰まったりすると負けとなります。
テンポの良さが場を盛り上げる重要な要素であり、参加者の瞬発力や知識が試されます。
オンラインで実施する際は、発言する順番をあらかじめ決めておくとスムーズに進行します。
脳の活性化につながる「後出しじゃんけんゲーム」
進行役が「じゃんけんポン」の掛け声で手を出した後、参加者は指定された条件の手を後から出すゲームです。
例えば、進行役が「勝ってください」と言ってグーを出した場合、参加者はパーを出さなければなりません。
「負けてください」「あいこにしてください」といった指示もあり、とっさに判断して正しい手を出す必要があるため、脳の良い刺激になります。
会議の冒頭で頭をスッキリさせたい時や、午後の眠気覚ましに最適なネタです。
価値観がわかる「究極の2択クイズ」
もし手に入るなら、時間を止める能力?未来へ行く能力?
食事は一生カレーのみ?一生ラーメンのみ?といった、どちらが正解というわけではない二者択一の質問を投げかけます。
参加者はどちらかを選び、なぜそちらを選んだのか理由を簡単に述べ合います。
この選択とその理由から、個人の価値観や考え方が垣間見え、お互いの内面を知るきっかけになります。
議論が白熱しすぎないよう、理由の発表は1分程度に収めるのがポイントです。
連想力を鍛える「ワンワード」
最初の人がお題となる単語を一つ提示します。例えば「海」というお題が出たら、次の人は「夏」と答え、その次の人は「スイカ」といった具合に前の人が言った単語から連想される言葉を一つだけ答えてつないでいきます。
このゲームは、参加者の発想力や連想力を引き出すのに役立ちます。思いもよらない単語が飛び出すと思わず笑いが起こり、場が和みます。
思考を柔軟にする効果も期待できるため、アイデア出しの会議前などに行うのも良いでしょう。
【オンライン向け】リモートでもできるアイスブレイクネタ5選

リモートワークの普及により、オンラインでの会議や研修が増えています。
対面と比べてコミュニケーションが取りにくく、場の空気が固くなりがちなオンライン環境では、アイスブレイクの重要性が一層高まります。
ここでは、Web会議ツールの機能を活用したり、リモートならではの状況を活かしたりすることで、オンラインでも手軽に実施できて盛り上がるアイスブレイクネタを5つ紹介します。
バーチャル背景を使って自分の趣味や好きなものを紹介する
Web会議ツールのバーチャル背景機能は、アイスブレイクに活用できます。
事前に参加者へ「自分の好きなこと」や「おすすめの場所」などをテーマに、関連する画像を背景に設定しておくよう依頼します。
会議の冒頭で、順番にその背景について説明してもらうことで、自己紹介ができます。
視覚的な情報があるため話が広がりやすく、その人の個性やプライベートな一面を知るきっかけとなり、オンラインでのコミュニケーションの壁を低くします。
チャット機能で「今の気分」を一斉に投稿する
Web会議ツールのチャット機能を利用して、進行役の合図で参加者全員に「今の気分」や「今日の意気込み」などを一斉に投稿してもらう方法です。
短い単語や絵文字だけでも構いません。「楽しみ」「少し緊張しています」といった感情を共有することで、お互いの心理状態を把握しやすくなります。
声を出して発言するのが苦手な人も気軽に参加できるため、一体感が生まれやすいのが特徴です。
場の空気をつかむための簡単なアンケートとしても活用できます。
カメラに向かって指を動かす「指体操」
オンライン会議は長時間同じ姿勢でいることが多いため、体を動かす簡単なアイスブレイクが効果的です。
例えば、進行役の指示に合わせて、左右の手で違う指を順番に折ったり、グーパーを繰り返したりする「指体操」は、座ったままで行えます。
カメラの前で全員が同じ動きをすることで一体感が生まれ、脳の活性化や眠気覚ましにもつながります。
会議の合間のリフレッシュとして取り入れることで、集中力を取り戻すきっかけになります。
お題に沿ったものを探す「身の回りにあるもの探しゲーム」
進行役が「あなたのデスクにあるお気に入りのグッズ」や「緑色のもの」などのお題を出し、参加者はそれに合うものを自宅やオフィスから探してカメラに見せ合うゲームです。
制限時間を1分程度に設定すると、ゲーム性が高まり盛り上がります。
それぞれの個性的なアイテムが登場することで、その人のプライベートな一面や好みが分かり、会話のきっかけになります。
オンラインならではの状況を活かした、手軽で楽しいアイスブレイクです。
スタンプやリアクション機能で気持ちを表現する
Web会議ツールに備わっている、拍手やいいねといったスタンプ機能を活用するアイスブレイクです。
進行役が「今日のランチが楽しみな人は挙手スタンプを押してください」といったお題を出し、参加者は一斉にリアクションで応えます。
言葉を発することなく、瞬時に場の雰囲気や参加者の意向を可視化できます。
操作に慣れることで、会議中の意思表示や相槌としても活用しやすくなり、円滑なコミュニケーションを促進します。
1分アイスブレイクを成功に導く4つのコツ

アイスブレイクは、ただ実施すれば良いというものではなく、やり方によっては逆効果になる可能性も秘めています。
1分という短い時間であっても、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
これから紹介する4つのコツを意識することで、進行役は自信をもって場を和ませ、会議や研修の目的達成に向けた良いスタートを切ることができるようになります。
実施する目的を事前に明確にしておく
アイスブレイクを始める前に、「何のためにこれを行うのか」という目的を進行役自身が明確に理解しておくことが重要です。
例えば、「初対面の参加者の緊張を緩和するため」「これから始まるブレインストーミングのウォーミングアップのため」「チームの一体感を高めるため」といった目的によって、選択すべきネタは異なります。
目的がはっきりしていれば、参加者にもその意図が伝わりやすくなり、より協力的で前向きな雰囲気を作り出せます。
参加者の人数や関係性に合わせたネタを選ぶ
アイスブレイクの成否は、参加者の特性に合ったネタを選べるかにかかっています。
参加者の人数、年齢層、役職、お互いの関係性などを考慮して、最適なものを選びましょう。
例えば、初対面同士であれば自己紹介系、気心の知れたメンバーならゲーム性が高いもの、役職者が多い場では誰もが安心して参加できるシンプルなクイズなどが適しています。
全員が不快な思いをせず、楽しめるような配慮が求められます。
進行役自身が率先して楽しむ姿勢を見せる
場の雰囲気は、進行役の言動に大きく左右されます。
進行役が恥ずかしがったり、義務感から淡々と進めたりすると、その空気は参加者にも伝染し、場が白けてしまう原因になりかねません。
まずは進行役自身が笑顔で、心から楽しむ姿勢を見せることが大切です。
自らがお手本となって積極的に参加し、ポジティブな雰囲気を作り出すことで、参加者も安心してアイスブレイクに参加しやすくなります。
時間をきっちり守り、ダラダラと続けない
「1分でできる」と銘打つからには、時間管理を徹底することが不可欠です。
アイスブレイクが盛り上がったとしても、予定時間を大幅に超えてしまうと、本来の会議や研修の時間が削られてしまいます。
タイマーなどを使って時間を明確に区切り、時間になったらきっぱりと終了して本題に移ることで、場にメリハリが生まれます。
時間を守る姿勢は、その後の会議全体の進行をスムーズにする上でも信頼感につながります。
アイスブレイクで失敗しないための注意点

アイスブレイクは、場の雰囲気を良好にするための強力なツールですが、ネタの選定や進行方法を誤ると、かえって雰囲気を悪化させたり、参加者に不快感を与えたりするリスクがあります。
そうした事態を避けるためには、事前にいくつかの注意点を把握しておくことが重要です。
ここで解説するポイントに配慮することで、誰もが安心して参加できる、安全でポジティブなアイスブレイクを実施できます。
プライベートな内容に踏み込みすぎない
参加者の人柄を知ることはアイスブレイクの一つの目的ですが、プライバシーに関わる領域に踏み込みすぎるお題は避けるべきです。
恋愛、家族、年収、宗教、政治といった個人的でデリケートな話題は、人によっては話したくない内容であり、答えることを強要するとハラスメントと受け取られる可能性もあります。
誰もが安心して話せるよう、趣味や好きな食べ物、出身地など、当たり障りのないテーマ設定を心がけることが大切です。
特定の人だけがわかる内輪ネタは避ける
複数の部署のメンバーや社外の人が参加している場で、一部の社員しかわからないような内輪の話題や専門用語をネタにすることは、避けるべきです。
その話題についていけない参加者は疎外感を覚え、場の一体感を損なう原因となります。
アイスブレイクは、参加者全員が平等に楽しめるものであるべきです。
誰でも理解できる普遍的なテーマや、共通の経験となりうるような内容を選ぶ配慮が求められます。
優劣がつきすぎたり、誰かが恥をかいたりする内容は選ばない
クイズやゲームにおいて、特定の知識や能力によって参加者間に大きな優劣がついてしまう内容は、アイスブレイクには不向きです。
特に、負けた人が大勢の前で恥ずかしい思いをするような罰ゲームなどは避けるべきです。
誰かが失敗したり、できなかったりすることで萎縮してしまい、その後の会議で発言しにくくなる可能性があります。
勝ち負けを決める場合でも、運の要素が強いものにするなど、誰もが後味良く終われるような内容を選びましょう。
まとめ

1分という短い時間で実施できるアイスブレイクは、会議や研修の冒頭で手軽に場の空気を和ませ、コミュニケーションを円滑にするための有効な手法です。
自己紹介系、ゲーム系、オンライン向けなど、多種多様なネタの中から、目的や参加者の状況に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。
成功させるためには、実施目的の明確化、参加者への配慮、進行役自身の楽しむ姿勢、そして時間厳守といったコツを押さえる必要があります。
また、プライベートな内容や内輪ネタを避け、誰もが安心して参加できるような配慮も欠かせません。
社員のスキルアップ研修にeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
社員のスキルアップ研修にeラーニングの活用をご検討の際は、イー・コミュニケーションズの「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、自社の動画を搭載したオリジナル研修が簡単に実施できます。
ぜひ動画研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。
また、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。