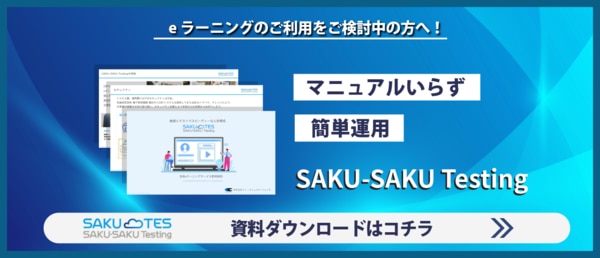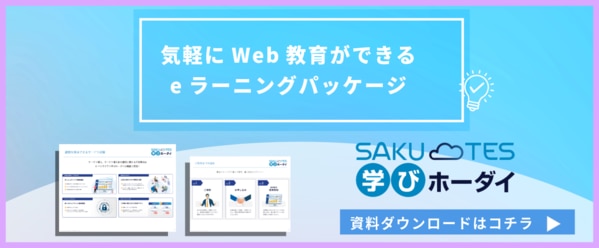人事評価の不満をなくす!不満の原因と解決策をご紹介

いろいろなところで、人事評価への不満をよく耳にします。御社の社内でもそのようなことはないでしょうか?
よく聞く話でよくあることだからといって、放置しておくと危険です。人事評価に関する不満は、人材流出の原因になります。とくに業績のよい社員ほど、評価に不満があると他社へ転職する可能性が高いと言えます。。
この記事では、人事評価の不満を解消する方法についてまとめます。企業のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
▶関連記事:人事評価の項目の決め方と目的、評価基準の具体例のまとめ
▶関連記事:正しい人事評価とは?評価項目ごとに解説します
目次[非表示]
- 1.人事評価とは
- 2.統計から見る人事評価制度への不満
- 3.人事評価への不満を放置するリスク
- 3.1.社員のモチベーション低下
- 3.2.優秀な人材の離職
- 3.3.企業の業績悪化
- 3.4.社員からの不服申し立てや訴訟
- 4.人事評価への不満ポイントと解決策
- 4.1.➀評価の基準が不明瞭
- 4.2.②評価者によって評価に差がある
- 4.3.③評価結果のフィードバック・説明が不十分
- 4.4.④自己評価と上司の評価に差がある
- 4.5.⑤評価が待遇に反映されない
- 5.人事評価の手法
- 5.1.➀MBO(目標管理制度)
- 5.2.②OKR(目標と成果指標)
- 5.3.③コンピテンシー評価
- 5.4.④ノーレイティング
- 5.5.⑤360度評価
- 6.人材育成でお困りの場合はイー・コミュニケーションズにご相談を
人事評価とは

そもそも「人事評価」とは、社員の業績や勤務態度、能力・スキルを評価することです。評価する仕組みは「人事評価制度」といいます。
「人事評価」とよく似た言葉に「人事考課」があります。両者はほぼ同じ意味の言葉です。あまり違いを気にする必要はありません。細かくなりますが両者の違いをいうと、人事評価のほうがやや広い範囲の内容を含みます。「人事考課」は業績などの査定だけを指すことがあるのに対して、「人事評価」は待遇などへの反映や目標設定までより広い意味を指すことがあります。
統計から見る人事評価制度への不満

Adeco Groupが2018年に実施した「『人事評価制度』に関する意識調査」によると、自社の人事評価制度に不満がある人は62.3%という結果となっています。
この調査で分かった人事評価制度の不満の理由の上位5つは下記の通りです。
・評価基準が不明瞭(62.8%)
・評価者の価値観や業務経験によって評価にばらつきが出て、不公平だと感じる(45.2%)
・評価結果のフィードバック、説明が不十分、もしくはそれらの仕組みがない(28.1%)
・自己評価よりも低く評価され、その理由がわからない(22.9%)
・評価結果が昇進、昇格に結びつく制度ではない(21.4%)
この結果から、評価基準がきちんと定められていなかったり、評価者によって評価が変わる、評価内容のフィードバックがなかったり、評価の理由がわからない、評価を得られていても昇進に結びつかなければ、不満につながることがわかります。
人事評価への不満を放置するリスク

社員が抱えている人事評価への不満をそのまま放置してしまうと、企業にとってよくない問題が発生します。
考えられるのは次の4つです。
①社員のモチベーション低下
②優秀な人材の離職
③企業の業績悪化
④社員からの不服申し立てや訴訟
詳しく見ていきましょう。
社員のモチベーション低下
正当な評価がされていないと思っている社員は、まじめに働いても仕方ないと思うようになり、モチベーションが低下します。最低限の仕事だけをするようになり、生産性も低くなります。
優秀な人材の離職
まじめに働いても仕方ないと思うような社員が増えると、組織全体のパフォーマンスが低下します。
すると組織全体の雰囲気が悪くなっていき、そのような雰囲気をいち早く感じ取った優秀な社員から離職していきます。
企業の業績悪化
モチベ―ション低下による生産性の低下や組織全体の雰囲気悪化、優秀な社員の離職により、企業の業績が悪化することも起こりえます。
社員からの不服申し立てや訴訟
低い評価ばかりを受けている社員から、人事評価に関する不服申し立てや訴訟を起こされるケースも考えられます。
特に人事評価により減俸となったり、降格となった場合は可能性が高まります。
人事評価に関して不当な評価をしていないか、法令違反をしていないかなど、企業側もきちんとした体制を構築することが求められます。
人事評価への不満ポイントと解決策

人事評価に社員が不満を感じるケースは多くありますが、社員の納得感が得られるかが重要です。不満を放置すると人材流出や業績悪化につながります。場合によっては訴訟となる可能性もあります。社員の言い分が不当だという場合もありますが、それでも疑問を感じさせない、払拭できる体制作りが大切です。
人事評価について、前述の調査では、社員の77.6%が見直しが必要としながら上司の77.8%が評価は適切だと回答しています。この結果に見られるように、評価する側とされる側の間には認識にズレがあるものと考えるべきです。
前の項目でご紹介した統計結果を参考に、次の5つの不満に対して、原因や解決方法についてまとめます。
①評価の基準が不明瞭
②評価者によって評価に差がある
③評価結果のフィードバック・説明が不十分
④自己評価と上司の評価に差がある
⑤評価が待遇に反映されない
不満は、「評価基準や運用といった査定に対する不満」と「評価に関するコミュニケーション不足に対する不満」、「評価制度の設計に対する不満」に分けられます。
それでは1つずつ見ていきましょう。
➀評価の基準が不明瞭
「評価の基準が不明瞭」は、最も多い不満です。査定は上層部がクローズドな場面で行うことが多いことも背景となっています。
■よくある原因
・評価基準が統一されておらず、個人的なバイアスが加わっている(好き嫌い、先入観、1つの成功・失敗で期間全体を評価してしまうなど)
・評価基準が公開されていない
■対策
・バイアスを排除するルール作り(評価基準の定量化・絶対評価化)とそのルールを守るための評価者の教育
・評価に対する第三者のチェック
・社員への基準の周知
②評価者によって評価に差がある
同じ成績でも評価に差があると不公平感につながります。
また、業務内容・実状を知らない上司が評価する場合は、評価者個人への不信がつのり、仮に定量的・客観的評価だったとしても不満が出る可能性があります。
■おもな原因
・評価者間の評価の基準が揃っていない(全体を厳しく評価する「厳格化傾向」・甘く評価する「寛大化傾向」・平均的に評価する「中央化傾向」など)
・評価者への不信
■対策
・評価項目・評価指標の定量化
・ほかの社員との比較「相対評価」でなく、目標値と比較する「絶対評価」の導入
・評価者を事前に教育(同じ社員を各自評価して、相互の差をチェックするなど)
・評価が出揃ってからの第三者チェック
③評価結果のフィードバック・説明が不十分
書類などで一方的に評価を通知されたり、昇給・昇進のみの結果だけ知らされるため、その評価の根拠がわからず、不満に感じます。
■おもな原因
・フィードバックの仕組み不足
・評価後のコミュニケーション不足
■対策
・日常的なコミュニケーション
・評価体制の見直し
・評価の根拠を伝える場をもつ
④自己評価と上司の評価に差がある
正しく評価されていないという感情は放置すると危険ですが、自己評価が妥当なのかも検証が必要となります。
■原因
・評価者と社員で目標のすり合わせができていないため、達成度に認識のズレがある
・結果をどう評価するかの考え方のズレ
■対策
・期初・目標設定時に、評価者と社員で目標を共有・確認
・自己評価の基準の明文化と社員への周知
・評価は会社への貢献度で決まることの周知
・評価者側の基準の定量化・明文化
・評価者の教育
・360度評価の導入
⑤評価が待遇に反映されない
業績が待遇に反映されない場合は退職につながる可能性があります。成績の良い人ほど流出する可能性が高くなり、企業へのインパクトも大きくなります。
■よくある原因
・「評価機能」と「報酬機能」が連動していない
・評価と報酬の対応がアンバランス
■対策
・評価と報酬をつなげる仕組みづくり
・評価と報酬のバランスの適正化
・評価基準と対応する報酬を明文化して社員に周知
人事評価の手法

人事評価の具体的な手法についてまとめます。評価に対する不満への対策として、評価方法を見直すのも1つの方法です。
ここでは、以下の5つの手法についてまとめます。
・MBO(目標管理制度)
・OKR(目標と成果指標)
・コンピテンシー評価
・ノーレイティング
・360度評価
評価だけを行う手法よりも、人材育成やマネジメントとセット・もしくは育成やマネジメントが中心で評価は付随しているような手法も増えています。
自社で運用しやすいもの、社員の評価への満足度が高まるものを検討しましょう。
それでは1つずつご紹介します。
➀MBO(目標管理制度)
「MBO(目標管理制度)」は、社員が事前に決めた目標に対する達成度合いで評価する手法です。達成度合いに応じて社員をランク付けします。成果主義的と言えます。
目標とその達成度という形で結果が可視化され、評価する側からは評価しやすく、される側は納得しやすいというメリットがあります。
現在の主流となっている手法ですが、基本的に1年とやや長いスパンで考えるため状況の変化が激しい業界ではほかの手法に切り替える例が増えています。
目標の難易度の設定は、本人と企業とで調整しながら適切に設定することが大切です。
②OKR(目標と成果指標)
「OKR(目標と成果指標)」は、アメリカのインテル社で誕生しGoogleなども導入している目標管理手法です。
チームを鼓舞する1つの定性的な「目標」に、個々が複数の定量的な目標「主要な結果」を付随して設定します。1~3か月のスパンで設定・追跡・再評価を行うため、変化のスピードの速い業界で採用されています。
③コンピテンシー評価
「コンピテンシー評価」は、高い業績を上げている社員の行動特性をモデル化し、それを基準に社員を評価する手法です。
基準が明確なので、評価する側は評価しやすくされる側の納得感を感じやすいというメリットがあります。
さらにモデルがはっきりしているので、人材育成もやりやすいこともメリットです。
④ノーレイティング
「ノーレイティング」は、上記MBOに見られるような社員のランク付けを廃止した評価方法です。期間を定めずリアルタイムの目標を設定し、上司とのコミュニケーションを密に取りフィードバック、その都度評価します。
スピーディーな行動と評価が可能で、変化の激しい業界に向いています。しかしコミュニケーションやフィードバックを多く行うため、評価者の負担が大きいというデメリットがあります。
⑤360度評価
「360度評価」は、上司だけでなく同僚や後輩・他部署の社員などさまざまな立場の人も評価を行う手法です。さまざまな視点が加わることで、上司が気づいていなかった側面がわかります。多角的で精度の高い評価が可能となります。
評価に不慣れな人も評価者となるため、思い込みの排除など公平性を確保することが大切です。待遇に反映させるほか、周囲はどんな点を評価しているかを伝えるために活用される例が多くあります。
人材育成でお困りの場合はイー・コミュニケーションズにご相談を
人材育成の一環にeラーニングでの教育がおすすめです。ぜひ私どものeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。知識の定着にテストを用いる「テストエデュケーション」で学習でき、オンライン研修を補完する知識習得に高い効果があります。
教育担当者様の声を反映し、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を実施する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
また、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただければ、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新人社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ぜひ社内教育に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。